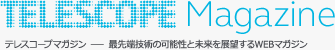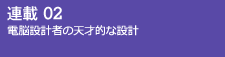|
コンピューターの登場を背景として20世紀末に生まれたメディアアート。東京・初台で1997年に開館し、今年で20周年を迎える「NTTインターコミュニケーション・センター(以下ICC)」は、開館の準備期間を含めれば、メディアアートの草創期から今日に至る流れを見届けてきた存在だ。ICCの主任学芸員として国内外の作家からの信頼も篤い畠中実氏は「ジャンルを逸脱するダイナミズムこそがメディアアートの醍醐味」と語る。今回は、人工知能(以下AI)が生成する言語モデルをビジュアライズした最新作をICCで発表した徳井直生氏を迎え、アートとテクノロジーの関係性について意見を交わした。 |
工学と親和性が高い日本のメディアアート
徳井 ── シンポジウムの席ではよくお話しますが、畠中さんとこうして対談するのは初めての機会ですよね。
畠中 ── 確かにそうです。徳井さんには2004年にICCで開催した「ネクスト:メディア・アートの新世代」展に出展してもらいましたが、その前からのお付き合いです。
徳井 ── 以前から畠中さんに伺いたかったことがあります。そもそも「メディアアート」という言葉自体、海外と日本では解釈が違うと感じるのですが、どう思われますか?
畠中 ── 日本以外ではメディアアートという言葉は正確に意味が通じないので「ニューメディアアート」という呼び方が主流のようです。特に欧米では「アート」という歴史を持った大きなものが確固としてあるんですね。それに対してコンピューターやインターネットなどの新しいメディアを使ったアートである、という風に両者の間には厳格な区別があるように思えます。
海外でもメディアアート事情はそれほど変わりがないとも言えますが、日本の場合は、例えば美術や音楽という文脈だけではなく、技術から発想されたもの、最近ではエンターテインメントの領域など、いろいろな出自を持った人が関わっています。特に、工学部系の人たちが取り組んでいる研究が、メディアアートの文脈に入ることで、研究そのものの性質が変わっていくような、そういうフレキシブルな状況は、ある意味では歓迎すべきことだとも言えます。
徳井 ── ええ。僕らもそうだし、真鍋大度君たちライゾマティクスのメンバーなども、多くが工学系出身ですから。
畠中 ── そういったさまざまな要素を持ったアーティストの活動によって、メディアアートは更新され続けていて、ICCの活動もそうした動きと同期していると思います。
未来を仮定することで、思考が進む
畠中 ── 今年はICCの開館20周年です。企画展「オープンスペース 2017」はICCの活動理念に立ち返って、そのコンセプトをアップデートするようなテーマを考え、「未来の再創造」としました。これは「未来」という概念を考え直そうということですが、僕らが子どもの頃には、21世紀にはいろんな技術が発明されて、社会がすごく豊かになっている、と本でたくさん読んできました。
徳井 ── クルマが空を飛び回っているとか。
畠中 ── ええ。原子力発電などによってエネルギーが生み出され、社会はずっと繁栄する、みたいな未来観がまだ有効だったのですが、現在では、世界のいろんな歪みによって「子どもの頃に読んだ未来と違う」と感じています。
これを続けていったらダメなのではないか、と思わされたのが2011年の震災でした。僕たちが読んできた未来の姿というのは、もう変わってしまったと。それに替わってもっと、2020年以降のサスティナブル(持続可能)な未来を考えなければいけないと思ったんです。
 |