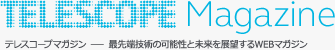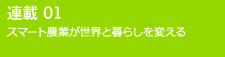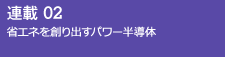|
埋蔵量が限られる石油などの化石燃料に代わり、水素が新たなエネルギー資源として注目されている。中でも水素の化学反応から電力を得られるFCV(燃料電池車)は、水だけしか排出しない究極のエコカーとして期待される。レーシングドライバーとして世界で活躍する佐藤琢磨氏は、来たるべき水素社会にどのような期待を寄せているのか。経済産業省の所轄法人NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)でプロジェクトマネージャーを務める大平英二氏に水素エネルギー普及への道のりを確認しつつ、新時代への夢を共に語り合う。 |
次世代エネルギーの候補として
大平 ── 現在、佐藤さんは日本とアメリカのどちらを拠点に活動されているのですか。
佐藤 ── 北米のインディカー・シリーズに3月から参戦して、この9月にシーズンが終わったところです。今のようなオフの期間は日本で過ごすことが多いですね。この後、来シーズンに向けての準備が始まるとアメリカに戻ります。
大平さんが所属されているのは、日本政府の機関にあたるのですか。
大平 ── ええ。私の所属しているNEDOは、新エネルギーの研究や技術開発を推進する国立研究開発法人です。1980年に設立された背景には第二次オイルショックがあり、太陽光や風力など、石油に替わる新しいエネルギーを普及させようという目的がありました。
国の主導で「将来に向けてこういったエネルギー技術を開発していこう」という目標を、企業や大学の方々と一緒になってやらせていただいています。言うなれば「技術開発のコーディネーター」でしょうか。一つの企業や大学だけでは難しい研究開発テーマについて、様々なメンバーが集まるプロジェクト、すなわち「場」を提供する役目を担っています。
佐藤 ── 新しいエネルギーの1つとして、国が水素に着目しているんですね。
大平 ── ええ。水素エネルギーを担当するのが、私たちのグループです。水素を利用する意義にはいくつかあります。例えば、水素を使うときには、燃やしても何をしても二酸化炭素が出ませんので、地球温暖化対策に貢献する「クリーンなエネルギー」であるという面もその一つです。
佐藤 ── クルマ好きな立場としては、ずっと長くクルマを使っていたいし、クルマのある文化を残したいです。今後、いかに地球とクルマを共存させていけるかに関心があります。
水素は燃料電池として電気を発電するやり方もあるし、燃料として内燃機関*1に使う方法もある。自分でもいつかそういう研究に携わってみたい、という興味がありました。次世代エネルギー源として、水素はすごく可能性を秘めていると感じています。
レースカーと市販車の共通点
佐藤 ── 自動車メーカーがFCV(燃料電池自動車)をずっと研究しているのは僕も知っていました。ただ、先に市場へ出たのはハイブリッドカー、つまり電気モーターのアシストを使った内燃機関のクルマですよね。こんな具合に全部をそっくり切り替えるわけではなく、今までのものの良さを活かしつつ、うまく生活に溶け込んで共存するのがキーポイントだと思うんです。
モータースポーツも純粋な環境問題の観点から見ると、風当たりが強いのは事実です。限られた石油資源を燃やして、ガンガン走って、燃費も悪いというイメージですから。でも、視点を変えると違ったものが見えてきます。
例えば、F1は年に16戦から20戦を隔週で行いますが、各レースの時間はおよそ2時間です。プラクティスやテストも含め、実はあんまり長い時間走っていません。二酸化炭素の排出量だけで比べたら、欧州のフットボールリーグ全体の方が多いという事例研究もあるんです。
大平 ── サッカーは大勢の観客の移動や、スタジアムで使う電気もあるでしょうから。
佐藤 ── 基本的にF1は1戦か2戦を除いて昼間の開催ですしね。これはサッカーの方が環境に悪いと言っているわけではなく、ものの見方を変えると分かることがあるという話です。
そして、今僕が参戦しているインディカーシリーズの場合には、燃料にエタノールというアルコールを使っているんですよ。排ガス規制が日本や欧州よりも厳しい、北米らしい取り組みですね。そういう意味では、モータースポーツの中では最もクリーンなカテゴリーだと言えます。
 |
大平 ── 私もクルマが好きなので、モータースポーツのエンターテインメントとしての魅力は失われてほしくありません。うまく社会に残ってほしいなと思います。
佐藤 ── 僕らドライバーは誰よりも速く走りたいという思いと同時に、見てくれたお客さんが喜んでくれて「楽しかった!!」という思いを共有してもらえれば、エキサイティングなレースをやる意味があります。
エンジニア達もプレッシャーを受けながら、決まった時間の中で限られたリソースを使って結果を出さなきゃいけない。そうした環境の中で人材が育つわけです。現場で鍛えられたその人達が研究所に戻ると、クリーンなエネルギーの研究開発はもちろん、その他、様々な分野で活躍されています。F1でもエンジンがハイブリッド化していますから、今も“走る実験室”*2は生きていますね。
大平 ── やはり技術は繰り返しなんですよね。人を育てる意味でもそうでしょうし。通常使うマシンにはレースで求められるスペックはいらないのでしょうけれども、常に最高値を追及していかないと次に打つ手がなくなってしまう。。
佐藤 ── 1リッターの燃料でどれだけのパワーを生み出せるか、レーシングカーにとって最も大事なことです。パワーを出すためには、燃焼効率が良くないといけません。
一方で、一般車両で燃費のいいエンジンを作る場合にも、燃焼効率が良くないとダメです。不完全燃焼すると有毒ガスも出るし、結果的に燃費も悪くなりますから。一見するとF1と低燃費車は正反対の開発をやっているようで、究極の燃焼効率を目指すという意味では同じなんですね。
[ 脚注 ]
- *1
- 内燃機関: 燃料の燃焼が機関の内部で行われ、燃焼ガスを動作ガスとして熱エネルギーを機械的エネルギーに変える原動機。反対に、燃焼熱を他の媒体(機関の外部)に伝えて作動させる原動機を外燃機関と呼ぶ。
- *2
- 走る実験室: 「レースは走る実験室」とは、本田技研工業(ホンダ)の創業者である故本田宗一郎氏が遺した言葉。自社製品の向上や進化を図るため、レースの厳しい世界に挑んで、その経験を開発に生かすことを旨とした。