JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Interview
- インタビュー
宇宙ビジネスには大きな可能性がある ──
動き出すなら今だ!
- 青木 英剛
- グローバル・ブレイン株式会社 宇宙エバンジェリスト
- 2018.01.31

近年、著しい成長を続ける「宇宙ビジネス」。数年前まではアメリカ発のニュースが時折話題になる程度だったが、最近では日本でもいくつもの宇宙ベンチャー企業が立ち上がり、新聞やテレビで取り上げられることも増えてきた。
はたして宇宙ビジネスとはなにか。参入にはどんな可能性と障壁があるのか。そして私たちにどのような恩恵があるのか、はたまた、私たちが宇宙旅行へ行ける日は来るのか。
東京に拠点を置くベンチャーキャピタルのグローバル・ブレインで、宇宙ビジネスへの投資家として活躍する青木英剛さん。「宇宙エバンジェリスト」の肩書で宇宙の啓蒙活動も行っている青木さんに、宇宙ビジネスがもつ可能性と、現状、そして未来についてお話を伺った。
(インタビュー・文/鳥嶋 真也 撮影/黒滝 千里〈アマナ〉)
大企業の技術者から投資家、宇宙エバンジェリストへ
── 青木さんはどのような経緯で宇宙ビジネスにかかわられるようになったのですか。
私はもともとアメリカの大学と大学院で宇宙工学について学び、アメリカ航空宇宙局(NASA)と共同で研究も行っていました。卒業して日本に帰国した後は、人工衛星の仕事がしたいと思い、国内最大手の三菱電機に入社。宇宙ステーション補給機「こうのとり」など衛星の開発に携わりました。
 |
その後、2011年に三菱電機を辞め、ビジネススクールに通って宇宙ビジネスの研究を行い、経営学修士(MBA)を取得しました。そしてコンサルタントとして、さまざまな企業に宇宙ビジネスのコンサルを行い、いくつかのプロジェクトも実現させています。
時同じくして、日本でも宇宙ベンチャーがいくつか出てきたのですが、どこも非常に苦労していました。そこで、私の持つ技術者としての経験と、ビジネスの知見などをいかして、彼らを支援できないかと考えたんです。そして現在は、グローバル・ブレインで宇宙専門の投資を行っています。
こうした経緯から、私は日本で唯一の「宇宙業界出身のベンチャー・キャピタリスト」として、認めていただいています。
── 「宇宙エバンジェリスト」という素敵な肩書きは、どういった経緯で名乗られるようになったのですか。
コンサルタントをしていたころから、並行して宇宙ビジネスの啓蒙活動も行っていました。多くの人に宇宙を好きになってもらい、ビジネスにつなげていきたいと思い、保育園児から社会人までいろんな人を対象に、さまざまなところで講演をしたり、記事を書いたりしています。
IT業界には、こうした啓蒙活動をする人を指して「エバンジェリスト」(伝道者)という言葉があります。でも宇宙業界にはなかったので、いっそのこと自分がなってしまえと思い、「宇宙エバンジェリスト」と名乗るようになりました。
── 大企業の技術者から投資家へ、というのは、日本ではなかなか思い切った決断だったと思いますが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
三菱電機にいた2000年代後半は、日本の技術系メーカーがことごとく大赤字を出していました。エレクトロニクス産業ではすでに韓国や中国に売上を追い抜かれていました。
これからは技術力だけでは勝てないという思い、そしてそもそも日本の技術系メーカーの多くは、ものづくりにばかり注力しすぎていて、経営面が弱いと感じたことから、経営を学ばねばと思いました。
また、三菱電機にいたころに、オービタル・サイエンシズ社*1(以下オービタル)と共同で働いた経験も大きいです。
オービタルは今から30年前にハーバード大学卒の若者たちが立ち上げた、世界で初めての宇宙ベンチャーと呼べる企業です。このオービタルに、三菱電機から「こうのとり」の技術を販売、輸出することになりました。私たち技術者は会議室に缶詰にされて、オービタルやNASAの技術者たちから「こうのとり」について根掘り葉掘り聞かれ、侃侃諤々の議論をしました。
JAXAから受けた公共事業として「こうのとり」を開発した私たちとは違い、オービタルはなにごとにも積極的で、純粋にビジネスとして宇宙事業をやっているという感じを受けました。
また、NASAとオービタルとの関係も対等で、完全にパートナーという雰囲気でした。日本では、発注側と受注側だと発注側のほうが上で、受注側はぺこぺこするのが当然でした。しかしアメリカでは、受注側も言いたいことは言うし、できないことはできないと言う。彼らのビジネス観、仕事のスピード感、企業の成長の度合いに感銘を受けました。
こうした企業が日本でも生まれないものか、という思いもあり、三菱電機を辞め、経営の勉強をする決心をしたんです。
 |
宇宙ビジネスと他のビジネスの違い
── 宇宙ビジネスのコンサルタント、投資家として活躍される中で、宇宙ビジネスが他の業界と異なると感じられた部分や、宇宙ビジネスならではの特殊性、難しさなどはあるでしょうか。
まず、参入障壁が限りなく高い、ということがあります。
人工衛星もロケットも、宇宙に飛んで行ってしまえば、リバース・エンジニアリング(分解して真似をすること)ができません。他分野なら他社の製品を買ってくればいいのですが、宇宙分野では他社がどういう設計をしているのかがわからないわけです。だから宇宙技術についてわかっている人、企業しか参入できません。
また、宇宙ビジネスを起業するためには、多額の資金が必要です。IT分野なら、数千万から数億円といった少ない投資から始めることもできますが、宇宙業界はまず最初に数十億から100億円を超える資本がないと世界で勝てないというのが現状です。後述するワンウェブ社*2などは、まず1500億円を用意してようやく動き出せました。
さらに、リスクも非常に高いです。ロケットの打ち上げには失敗がつきものですが、1機失敗すると最大100億円近くが吹き飛びます。何回か失敗する覚悟と、それでも続けられる資金が必要です。
そして、成果が出るまでには、時間がかかります。イーロン・マスク氏が立ち上げた宇宙企業であるスペースX社*3も、2002年に設立されてから今の地位を築くまでには長い期間を要しました。宇宙ビジネスで成果を出すには長い時間がかかり、そしてその過程には失敗もつきものだということを、起業家も、そして投資家や支援する国も理解しておく必要があります。
一方、ソフトウェア技術を使ったビジネスの場合は、巨額な資本も必要としませんので、比較的参入障壁は低いと思いますし、今後、新規参入はどんどん増えてくると思います。
宇宙ビジネスのトレンドその1「宇宙ビッグデータ」
── ここからはもう少し細かい、宇宙ビジネスの各分野について伺えればと思います。まず、近年注目されている分野のひとつに「宇宙ビッグデータ」がありますね。
これまで「ビッグデータ」には、膨大な情報データをどう使うかという課題があり、言葉だけがひとり歩きしているような状況でしたが、いよいよマネタイズする段階に入っています。
すでに広告業界では、Webの検索履歴やSNSでの書き込みをもとに広告を出すなどの活用がされています。最近では、家電製品やスマートスピーカーから入手した家の中の情報、さらに監視カメラやドローンが見た情報を活用しようという動きもあります。
そしてそこに加わってくるのが、宇宙の人工衛星から見た情報、いわば最も高い視点から見た情報を活用しようというのが宇宙ビッグデータです。
人工衛星というのは、たとえるなら「宇宙に設置した監視カメラ」です。地球全体の動きを刻一刻と監視し、国境を越えて世界中を見ることできるので、いままでに得られなかったような情報が手に入りますし、地上でデータを延々分析してやっとわかるような情報が、宇宙から見れば瞬時にわかる、ということも起こりえます。
── なぜ、近年になって注目されたり、そうしたビジネスをやろうという企業がいくつも出てきたりしているのでしょうか。
後述する宇宙インターネットなどともかかわってくることですが、電子部品の技術進歩と低コスト化により、高性能な小型衛星が安価に製造できるようになったことが大きいです。
これまで衛星で地球を観測しようとすれば、大型で高価なものが必要でした。それも同じタイプの衛星は1機か2機しか飛んでいないため、撮影したい場所の上空を通過するのは数日おきで、写真1枚の価格も数十万円という状況だったので、ビジネスとして成立していませんでした。
しかし、ベンチャー企業が何十機もの小型衛星を打ち上げて、世界のどこでも高頻度で撮影できるようになり、写真1枚の価格も数百円〜数千円というレベルに下がってきました。こうした宇宙からの情報と、地上やドローンなどの情報を組み合わせたビッグデータが、企業の意思決定などに使えるのではと注目を集めているのです。
── 具体的にはどのような利用法があるのでしょうか。
すでに農業や林業などの一次産業では、生育状況や分布の把握のために使われ始めています。
次の段階として、ヘッジファンドなどが石油の消費量や農作物の育成状況の確認をするために利用しています。これまでは各国が出す統計データを基に投資していたものを、統計データが出る前に宇宙ビッグデータを使って独自に統計データを予測し、先物取引を有利に進めよう、という動きがあるのです。
こうした動きが進めば、他の業界でも利用は進んでいくでしょう。たとえば輸送業であれば、コンテナを積んだ船がいまどこにいるのかがわかりますし、他の企業のコンテナがどういう動きをしているのかもわかります。スーパーマーケットでは、駐車場の混み具合を見ることで、広告や商品を出すタイミングを判断するということもできます。自社の動きを知るだけでなく、競合他社の動きも知り、それをさらに自社の動きにいかす、ということができるわけです。
いずれ、それ以外の業界でも、いままで想像もできなかった使われ方で利用されることになるでしょう。
── ちなみに青木さんも、「アクセルスペース*4」という日本の宇宙ベンチャーに投資しておられますが、同社も宇宙ビッグデータの提供を目指した、地球観測衛星網の構築に挑んでいますね。
アクセルスペースは、超小型衛星開発のパイオニアにして、世界トップレベルの技術をもつ人々によって立ち上げられた企業です。
同社がやろうとしている「AxelGlobe」というサービスは、大量の人工衛星を打ち上げて、地球全体の写真を毎日撮影し、販売しようというものです。アメリカなどにも似た企業はあるのですが、アクセルスペースの衛星には低コストでより高品質な写真を撮れるという強みがあります。
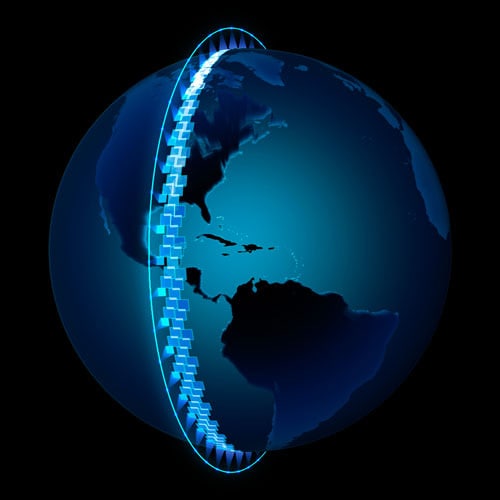 |
また、衛星写真のノウハウのない企業にとっては、ただ写真を受け取ってもそれが何を意味するのかわかりません。そこでアクセルスペースは、写真を撮って販売するだけでなく、AIなどで解析し、その写真からなにがわかるのかという情報も販売しようとしています。
宇宙ビジネスのトレンドその2「宇宙インターネット」
── もうひとつのトレンドとして、衛星を使って世界中にインターネットをつなげようという「宇宙インターネット」がありますね。この分野は今後どのようになっていくのでしょうか。
世界にはインターネットにつながっていない人が、アフリカや南アメリカを中心にまだ40億人――つまり世界の全人口の半分以上もいるといわれています。
こうした地域に住む人々に、衛星を使ってインターネット環境を整備し、情報や教育を提供することで、情報格差や貧富の差を埋めようというのが宇宙インターネットの趣旨です。衛星を使うのには、海底ケーブルや鉄塔などで敷設するより安く済むという理由があります。
いまのところ、一昨年ソフトバンクが投資したことで話題になったワンウェブ社や、スペースX社などが挑んでいます。使える周波数は限られているので、先にインフラを整えた企業が勝つことになるでしょう。
衛星を使って世界中にインターネットを、という構想は90年代からありましたが、多くのプロジェクトが失敗、倒産しました。しかし高性能な小型衛星が安価に造れるようになった現代なら、経済的にペイすると判断されるようになったのです。実際に、ソフトバンクやコカ・コーラ社といった、純粋にビジネスをやっている、つまり経済的にメリットがないと投資しないような企業や投資家が投資しています。
もっとも、衛星が安価になったとはいえ、初期投資は数千億円もかかります。ですが長期的に見れば、大きく期待できる分野だと思います。
── インターネットにつながっていない40億人というのは、あまり豊かではない国に住んでいる方が大半です。そうした人々を対象にして、利益は生まれるものなのでしょうか。
たしかに日本のように、毎月数千円の携帯代を支払うというのは難しいでしょう。そのため、パケットごとに課金するようなビジネスモデルが考えられます。
また、「広告を何本か見たら何時間は無料」といった形態も考えられます。日本でも漫画の配信サイトなどで「広告を見たら1話無料」というようなサービスがありますが、そういったビジネスモデルがそのまま適用できると思います。
とくにワンウェブ社にコカ・コーラ社が出資しているのは、もちろんアフリカなどにインターネットを届けたいというCSR的な取り組みでもあると思いますが、突き詰めればアフリカでコカ・コーラを飲んでほしいという思惑もあると思います。
宇宙ビジネスのトレンドその3「宇宙旅行」
── もうひとつのトレンド、そして昔から多くの人が夢見ていた分野として「宇宙旅行」があります。その現状や、今後の展望はいかがでしょうか。
現在、アメリカのヴァージン・ギャラクティック社*5やブルー・オリジン社*6などが、サブオービタル飛行*7での宇宙旅行を事業化しようと宇宙船の開発を行っており、早ければ今年か来年に宇宙旅行が始まるはずです。
現在の宇宙旅行ビジネスは、民間の航空旅客機の黎明期に似ています。かつて1ドルが360円だった時代、ハワイに行くには数百万円もかかっていました。ですが今は安いときは数万円で行けるようになっています。
宇宙旅行も、いまは1回の飛行で2500万円ほどかかりますから、まずは富裕層をターゲットにしたものになります。ですがいずれ、年間何万人、何百万人という人が行くようになれば、規模の経済が働きますから、200万円、あるいは20万円程度にまで安くなるでしょう。
もちろん人を乗せて宇宙に行くのは、コスト面、安全面で難しく、実現までにはいくつもの壁があるでしょうが、私たちが生きている間には確実に、「週末、宇宙旅行に行ってきます」という時代は来るはずです。
── サブオービタルの先、宇宙ステーションなどへのオービタル(軌道)や、月、火星への飛行はどうなるでしょうか。
サブオービタル飛行は現在2500万円ですが、オービタル飛行*8は数十億円もかかります。桁が2つ違いますから、それぞれが独立した市場を形成し、双方とも徐々に値段が下がっていく、ということになると思います。たとえるならプロペラ機とジェット機の市場のようになっていくのではという感触です。
オービタル飛行はリスクも大きいので、数十億円からコストを劇的に下げるのは大変ですが、日本でもインターステラテクノロジズ社などがコストダウンを目指しています。また、民間の宇宙ステーションが打ち上がるという構想もあるので、オービタル飛行の宇宙旅行もどんどん成長していくでしょうし、いつか月や火星に旅行ができる時代も来ると思います。
 |
宇宙ビジネスのトレンドその4「宇宙探査」
── そして、さらに将来を見据えて、宇宙探査や他の天体への移住をビジネス化しようという動きもありますね。
宇宙探査ビジネスは、はっきりいってまだお金にならない分野です。ですが、2050年ごろには当たり前になっていると思います。それを考えると、いまから動き出していないと手遅れですし、すでに動き出している人や企業もあります。
たとえば国ではアラブ首長国連邦が火星に、企業ではスペースX社が月や火星への移住を計画しています。こうして誰かが動き出している以上、他の天体に人が住む時代は必ずやってくるはずです。
ならば、その時代に向けて、いまから事業の立ち上げや投資をしようという動きがあるのも当然でしょう。
── 宇宙探査といえばこれまではNASAなど国が行う事業でした。そして民間にとっては、失敗時や成果が出なかった場合のリスクが大きな事業です。国と民間の役割分担はどうあるべきでしょうか。
たとえば月や火星には水があるといわれていますが、それを民間だけで探しに行こうというのは難しく、リスクが高すぎます。
そのため、民間にできることは民間に任せつつ、NASAやJAXAなど国の宇宙機関にしかできないところは、国が責任をもってやるべきです。国と民間がうまく連携して、国が主導しつつ、民間の安価な技術やスピード感をいかしてやっていく、ということが必要になります。
実際に過去には、NASAが国際宇宙ステーションへの補給物資の輸送を民間に任せるという計画を立ち上げました。その結果、スペースX社などが低コストかつスピーディーにロケットや補給船を開発し、成功を収めています。同じ流れが宇宙探査でも起こるでしょう。
── 宇宙探査、あるいは移住の目的地として、月に行くべきだ、いや火星だ、いや小惑星だ、とさまざまな意見がありますが、青木さんはどうお考えですか。
それは、ある種の宗教だと思っています。「月だ」と信じている人は月に行きますし、「火星だ」と信じている人は火星に行きます。小惑星、さらに木星の衛星を目指す人も出てくるでしょう。
国の宇宙機関は色んな天体を探査しようとしますが、民間には難しいので、それぞれの企業が「ここだ」と決めた目的地に行くことになると思います。その結果、色んな天体が開拓されていくのではないでしょうか。
私も、月、あるいは火星といった特定の目的地に絞るつもりはなく、すべての目的地にビジネスチャンスがあると考えています。
日本の宇宙ビジネスの現状
 |
── こと日本に目を向けると、宇宙ビジネスはまだ十分に浸透しているとはいえない状況だと思います。現状と、今後の展望についてどう見ておられますか。
日本の宇宙開発はかつて、アメリカ、ロシア(ソ連)、欧州に次ぐ世界第4位の規模でした。しかし近年では、予算規模や実力で中国とインドに抜かれ、さらに一企業にさえ抜かれようとしています。
日本の国の宇宙開発予算は2000〜3000億円で横ばいの状態です。そして宇宙開発をやっている日本の大企業は「いかに国から予算を取ってくるか」にフォーカスを置いています。国やJAXAが立てる宇宙計画にしたがって、各社が事業計画に落とし込んで、限られた企業のみが継続受注しているのです。健全なビジネスとは言い難いです。これでは民間の資金も入ってきませんし、競争も起きませんので、産業は発展しません。
その中で、日本はやり方を変えないといけないという危機感は、国も企業も感じているところだと思います。そのためには官民が連携して盛り上げていく必要があるでしょう。
たとえば日本は依然として世界第3位の経済大国で、大企業が保有する内部留保の額は、アメリカ企業の約2倍、日本のGDPにも匹敵するほどとされます。その一部でも宇宙に投資してくれれば、日本の国の宇宙開発予算を大きく超え、宇宙予算全体の規模は大きく膨らむことになります。
こうした大企業に眠っているお金、そして人材をいかして、新陳代謝を起こすことができれば、日本の宇宙ビジネスは大きく飛躍することになると思います。
いま日本に宇宙ベンチャーは20社ほどしかありません。そこに新しいプレイヤーが入ってきて、さらに既存の大企業も入ってくれば、競争が起こります。とにかくいろんな人が入ってきて、切磋琢磨する必要があります。もちろん成功する人も失敗する人も出てくるでしょうが、それが新しい産業が生まれるときの流れです。
だから大企業でくすぶっている技術者の方には、どんどん外に出て宇宙ベンチャーを立ち上げていただきたいです。
日本の技術者よ、「ビジネス・マインド」を持て
── 最後に、これからの技術者たちに向けたメッセージとして、持つべき視野や資質にはどんなものがあるでしょうか。
確実に言えるのは「ビジネス・マインド」を持つべき、ということです。
技術者は、ひとつのことを研究しているとどうしても視野が狭くなり、外部との交流や情報収集がおろそかになってしまいます。ですが、たとえばいま研究している技術は、他の業界ではすでに実用化されていたり、他の分野と連携、協調することでさらなる成果や利益を生み出せたりということもあります。
ですから、若い技術者の方は同じ業界の同じ学会ばかりに行かず、さまざまな視点から他の業界も見てください。そして経営の知識を学び、ビジネス・マインドを持ってやっていく必要があると思います。
たとえばアメリカの大手技術系メーカーでは、30代の若手技術者に経営の勉強をさせる研修制度があります。一方、日本の大企業では、課長や部長など、技術者の中から上に登ってきた人だけを抽出して、とつぜん経営をやれと命じます。でも、知識がない人にいきなり経営をやれと言っても難しいわけです。それが前述した技術系メーカーの衰退につながった要因のひとつでもあると思っています。
私もすでに日本の企業にこうしたアドバイスをしていますが、なかなか変わろうとする企業はありません。やはり大企業であるほど、方針を変えるのは難しいですから。
しかし、近年日本の技術系メーカーがいくつも苦境に陥っていることで、「明日は我が身」と危機感を抱いている企業や経営者は多いはずです。ですから変われる企業は変わって生き残り、変われない企業は淘汰され消えていくでしょう。
私の好きな名言の中に、The best way to predict the future is to create it. (未来を予測する最善の方法は、自ら未来を創りだすことだ)というのがあります。若い技術者の方には、高度な技術を武器に新たな産業を創り出していって欲しいと思います。
── ありがとうございました。
[ 脚注 ]
- *1オービタル・サイエンシズ(Orbital Sciences)社
- 1982年に設立された、世界初の宇宙ベンチャーのひとつ。ハーバード大学の経営学修士(MBA)を取った若者たちが立ち上げた。当時、アメリカの宇宙企業といえばボーイングやロッキードといった大企業しかない中で、ロケットを空中発射することで、小型衛星を安価に宇宙に打ち上げるというアイディアを打ち出し、アメリカ航空宇宙局(NASA)から資金を獲得。その後も数多くのロケットや衛星の開発を手がけ、現在は大企業にまで成長した(2015年よりオービタルATKに改称)。
- *2ワンウェブ(OneWeb)社
- 技術者・起業家のグレッグ・ワイラー氏によって、2012年に立ち上げられた企業。数千機の人工衛星を使い、全世界に高速インターネット通信サービスを提供することを目指している。2016年12月には、ソフトバンクグループが同社に10億ドルを出資することを発表し、大きな話題になった。
- *3スペースX(SpaceX)社
- 実業家のイーロン・マスク氏によって、2002年に立ち上げられた宇宙企業。小型ロケットの開発に始まり、現在では大型ロケットの打ち上げを事業として展開。NASAや世界各国の衛星などを次々に打ち上げている。最大の特長はロケットが再使用できることで、これにより打ち上げコストの大幅な削減に挑んでいる。さらに月や火星への有人飛行や移住という壮大な構想も掲げ、すでにそのための巨大ロケットの開発も進んでいる。
- *4アクセルスペース
- 2008年に設立された日本の宇宙ベンチャー。東京大学や東京工業大学でキューブサット(超小型衛星)を開発し、世界に先駆けて成功させた技術者たちによって立ち上げられた。これまでにウェザーニューズの気象・海象を観測する衛星「WNISAT-1R」をはじめとする超小型衛星の開発を手がけたほか、50機もの衛星で地球全体を高頻度に撮影・観測する地球観測網「AxelGlobe」の実現に向けた開発を続けている。
- *5ヴァージン・ギャラクティック(Virgin Galactic)社
- 実業家のリチャード・ブランソン氏によって、2004年に立ち上げられた宇宙企業。サブオービタル飛行ができる宇宙船「スペースシップツー」を使って、宇宙旅行ビジネスを行うことを目指している。2014年には試験中に墜落事故を起こし、しばらく停滞していたが、早ければ今年中の宇宙飛行の実現を目指している。
- *6ブルー・オリジン(Blue Origin)社
- Amazon.comの創業者としても知られるジェフ・ベゾス氏によって、2000年に立ち上げられた宇宙企業。サブオービタル飛行ができる宇宙船「ニュー・シェパード」を開発しており、早ければ今年中の宇宙飛行の実現を目指している。またオービタル飛行ができる大型ロケットや宇宙船、さらに月の移住に向けた宇宙船の開発も進めている。
- *7サブオービタル飛行
- 高度100km以上の宇宙空間には達するものの、地球を周回する軌道には乗らない宇宙飛行のこと。
- *8オービタル飛行
- 地球を周回する軌道に乗る宇宙飛行のこと。いわゆる宇宙旅行、宇宙飛行といえば、一般的にはこちらの意味を指す。
- Profile
-
- 青木 英剛(あおき ひでたか)
-
三菱電機、ドリームインキュベータを経て、現在はグローバル・ブレインで宇宙・ロボティクス担当パートナーを務める。三菱電機では、日本初の宇宙船「こうのとり」の開発に従事し、多くの賞を受賞。ドリームインキュベータでは、技術系企業の戦略立案や実行支援に従事した。宇宙エバンジェリストとして宇宙開発や宇宙ビジネスの啓蒙活動も行う。
- Writer
-
鳥嶋 真也(とりしま しんや)
-
宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。
国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。
- Webサイト:http://kosmograd.info/
- Twitter:@Kosmograd_Info
- https://note.com/celestial_worlds

