JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Laboratories
- 研究室紹介
技術・情報の力で、レジリエントな社会に貢献する
- 東北大学 災害科学国際研究所
- 第1部:
- 災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
- 越村 俊一 教授
- 2021.11.04
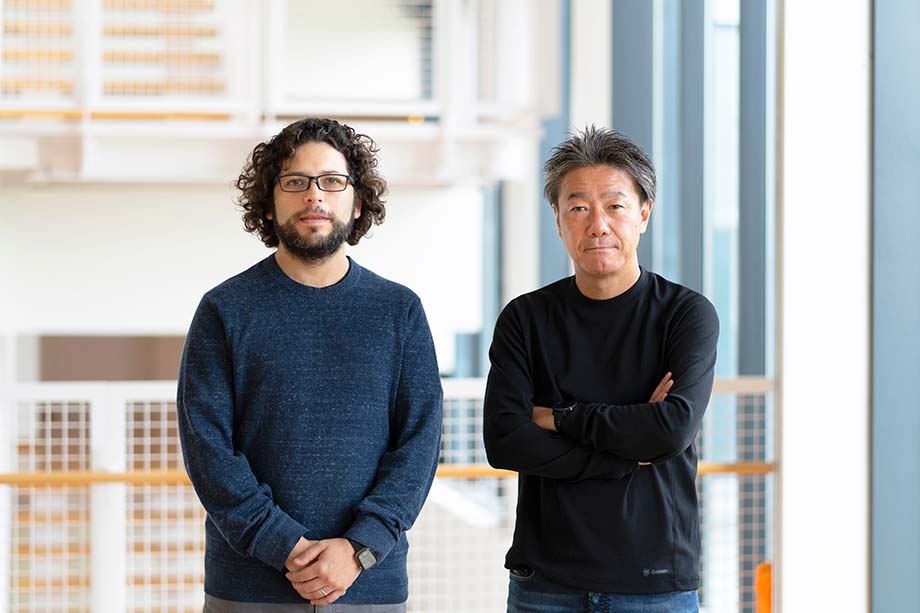
地震や津波の予測は極めて困難だ。同様に、災害が発生した後に被害状況を迅速・正確に把握することも難しい。東日本大震災では、ニュース映像などを通じて、誰もが愕然とする被災地の状況を目の当たりにした。そして、映像を見た日本中・世界中の人々が、被災地の救援や支援に向けてひとつになった。ただし、被災した人々に適切に手を差し伸べることができたかと言えば、反省点は多い。被災地のある地域には十分すぎるほどの救援物資が届いた一方で、本当に助けが必要なところには何も届かないという事態も発生した。実は、映像で見えていた部分だけが被災地ではなかったのだ。最新テクノロジーを駆使して、被災者を確実に救援・支援するための情報を収集・解析・提供する方法論を研究しているのが東北大学の越村俊一教授である。越村研究室で取り組む研究の内容と困難なテーマに挑む研究者が感じる意義について聞いた。
(インタビュー・文/伊藤 元昭 撮影/尾苗 清〈アマナ〉)
-

-
第1部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
越村 俊一 教授
-

-
第2部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
准教授 マス・エリックさん

災害大国日本、被害の最小化と共に早期回復に向けた方策も重要
── 地震や台風など、自然災害の脅威が集中する日本に暮らす私たちにとって、災害に対する備えは大きな関心事です。東北大学の災害科学国際研究所(以下、災害研)は、どのような経緯で設立され、どのような活動をしている組織なのでしょうか。
越村 ── 東北大学の災害研は、東日本大震災を契機に、大災害の教訓を研究して、新たな発見や気付き、知見を後世に伝えていくため、2012年4月に設立されました。近年、災害対策でよく使われる「レジリエント」という言葉があります。強靭という意味のほか、しなやかさや回復力という意味合いを持つ言葉です。災害研は、災害からしなやかに回復する、レジリエントな社会の実現に貢献することをミッションにしています。
日本の過去の災害対策は、災害の被害をできるだけゼロに近づけるべく、抑止力を重視して、津波を阻止する防潮堤などの構造物による防災を中心に考えられてきました。ところが、1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災のような大災害を経験して、こうした構造物だけで被害を最小化することがいかに困難であるか思い知りました。そして、被害ゼロという理想を実現することの難しさを認識した上で、被った被害からいかに早く回復するかという点に注目した対応手法の重要性が再認識されたのです。災害研では、こうした教訓に基づいた研究を進めています。
── コロナ禍でも、ウィルスとの共存を念頭に置いた「ウィズ・コロナ」という対応方針の重要性が指摘されています。災害も、同様なのですね。越村先生は、どのような経緯で災害研究の道に入ったのでしょうか。
越村 ── 私は、学生時代に東北大学の土木工学科に所属していたのですが、災害関連の研究に進んだきっかけは全くの偶然でした。4年生になる前に、学生の希望を取って研究室に配属されます。私は、橋など大きな構造物が好きで土木技術者になりたいと考えていたので、そうした研究をテーマにしている研究室を希望しました。ところが望んでいた研究室の希望者が多く、じゃんけんで決めることになり、負けてしまったのです。そして残った配属先となった津波工学の研究室に所属することになりました。最初は、いやいや研究室に入って勉強を始めたのですが、実際に研究してみると非常に興味深いテーマであることに気づきました。そして、いつしか配属された研究室で大学院に進むことを考え、最終的には2000年に博士号を取得するまで所属することになりました。
── きっかけは偶然でも、東北で津波を研究テーマにしたというのは、研究者としてのめぐり合わせがあったのかもしれませんね。
越村 ── そうですね。入ってから知ったのですが、東北大学の津波工学の研究室は、世界の津波研究のフロントランナー的な存在だったのです。もしも希望通りに橋梁工学を専攻していたら、今頃はゼネコンや橋梁メーカーで働いていたかもしれません。

真っ先に助けなければならない人は、助けを呼べない状況にいる
── 越村先生の研究室は、災害研の中で、どのような分野の研究を担っているのですか。
越村 ── 現在は、災害ジオインフォマティクス研究分野という研究室の名称を掲げていますが、これは2021年4月に名称変更した後の名前で、それまでは広域被害把握研究分野と呼んでいました。
意外に感じるかもしれませんが、自然災害が発生した後で被害を迅速かつ正確に把握することは思いのほか難しいことなのです。例えば、東日本大震災による津波では、大きな揺れがあった直後に津波警報が出されました。しかし、警報だけでは、どの程度の被害が発生して、どこに被災者がいて、どのような救援活動が必要なのかといった、災害対応に向けた情報は、全く把握できなかったのです。
人が災害に見舞われたとき、黄金の72時間と言われるように、発災後72時間を超えると生存率が著しく低下してしまいます。東日本大震災では、被害を受けた地域があまりにも広域であり、しかも状況を把握する技術が未熟だったため、被災地の救助や救援の活動が後手に回ってしまいました。実際に災害が起きてみると、事前の想定通りになることはまずありません。刻々と変化する被害状況を、いかにリアルタイムに把握し、迅速で適切に対処するかが重要になるのです。そうした対応に役立つ情報の取得と活用法を考えるのが私たちの役割です(図1)。

── 確かに、警報が出せることと、適切な災害対応ができることは別問題ですね。
越村 ── 災害が起きると、テレビのニュースなどで映し出される空撮映像などを通じて、被害を受けた現場が見えたかのように思われます。しかし、実際には、映っている場所だけが被害を受けているわけではありません。本当に大きな被害が出ている場所では、社会の機能が停止してしまい、被害報告さえできない可能性が高いのです。真っ先に、救助、救援に向かわなければならないのは、そうした場所ではないでしょうか。

現実世界での被害把握と仮想世界での被害予測の両面から対応法を高度化
── 現在の研究室の名称である災害ジオインフォマティクス研究分野とは、何を目的とした、どのような技術なのでしょうか。
越村 ── ジオインフォマティクスとは、日本語で言えば、空間情報科学という意味になります。災害による被害の把握と適切な対応を考える際の切り口を、これまで以上に多角化させるアプローチの研究に取り組んでいます。自然災害の被害は、単に建物が壊れるだけではなくて、人やモノが、どこを、どのように動いているのかといった社会の動態も大きく変えてしまいます。こうした情報も、適切な被害対応をしていくために欠かせない情報です。
── 具体的には、どのような研究テーマがあるのですか。
越村 ── 災害によって社会に及ぶ被害の質や量は、「どのような災害(自然力)が発生したのか」「災害の影響を受ける社会の状況」「災害によって被害が発生する仕組み」の3つの要素の掛け合わせで決まります(図2)。私たちは、災害による被害を現場から迅速かつ正確に直接観測するための研究「リモートセンシング」と、3つの要素を考慮して災害発生後に時間経過とともに広がる被害の様子をコンピュータ上で予測する研究「シミュレーション」の両面から、適切な対応法を導き出すアプローチを取っています。

- [図2]災害研 ジオインフォマティックス研究分野の研究アプローチ
- 左辺はリモートセンシングによって把握する現実世界の情報、右辺は災害後の被害を予想するために仮想世界でのシミュレーションによって得る情報
── 現実世界で起きた出来事を把握する研究と、仮想世界で少し先の未来を見通すための研究、それぞれの成果を融合させて適切な対応を取れるようにするということですね。
越村 ── その通りです。災害の観測情報に加えて、社会の性質や動きに関する情報をコンピュータ・モデルである「デジタルツイン」に実際に起きた災害に関する情報として入力し、時間の経過と共に社会や暮らす人たちにどのような被害が及ぶのか、仮想世界でシミュレーションして予想し、そこで適切な対応策を検討・検証して、現実世界にフィードバックします。デジタルツインは、航空機のジェットエンジンの疲労劣化や故障を予測し、事前に対処できるようにするための手段としても実用化している技術です。
── まさに、Society 5.0で構築を目指す、CPS(Cyber Physical System)そのものですね。コンピュータ・モデルならば、住民を危険に晒すことなく、事前に様々な対処法を試し、最適な対処法を探し出すことができそうですね。
越村 ── デジタルツインの中で様々な対応シナリオを試せば、効果的な対応法の探索や想定外の事態の発生に備えることが可能になります。さらに、社会に内在する脆弱性を事前に洗い出しておくこともできます。既に災害医療に携わっている方々が参画して、災害急性期に活動できる機動性を持つトレーニングを受けた医療チームである「DMAT(Disaster Medical Assistance Team)」が利用する、災害医療デジタルツインを構築する取り組みも行われています(図3)。

── 現実世界で起きる現象を扱う研究と、仮想世界で扱うモデルとその解析を行う幅広い知見が求められる研究ですね。
越村 ── 私たちの研究室では、現実世界で起きていることを被災地外から観測するリモートセンシングチームと、仮想世界のモデルを通じて起き得る現象を予測するシミュレーションチームが、それぞれの研究に取り組んでいます。現実世界と仮想世界の両方から情報を得るからこそ見える知見があります。この点は私たちの研究室の独自性の源になっていると思います。

複数の観測手段を複合的に活用して、ありのままの被害状況を把握
── リモートセンシングチームでは、具体的にどのような研究をしているのでしょうか。
越村 ── 被害を把握する際には、観測する視座の高さが異なるプラットフォームと、観測可能な現象が異なるセンサーを、用途や観測環境に応じて使い分けます。プラットフォームとはセンサーを搭載する機材のことであり、視座の高いものから人工衛星、航空機、ドローンなどがあります(図4)。一方、センサーには、デジカメで撮った写真と同様に状態を把握できる光学センサーや温度を検知できる熱赤外センサー、さらには雨や雲を透過して昼夜を問わず地表の凹凸を高精度に検知できる合成開口レーダー(synthetic aperture radar:SAR)と呼ばれるマイクロ波センサーなどがあります。プラットフォームが違えば観測可能な範囲や頻度、分解能、精度が変わります。一方、センサーが違えば、得られる情報の内容が変わってきます。

── 例えば、SARで地表の凹凸を観測することで、災害時に起きるどのような現象が分かるのですか。
越村 ── 人工物がある部分と水に浸かってしまっている部分が一目瞭然になり、津波や洪水による被害状況を明確に把握できます(図5)。

- [図5]合成開口レーダーによる被災地観測の例
- 津波の前の様子(左)と津波によって浸水した後の様子(右)
── 浸水の有無は、光学センサーでは分からないのでしょうか。
越村 ── 確かに光学センサーでも浸水の状況は分かりますが、上空から地表をハッキリと見通せる時だけに利用できる観測手段になってしまいます。災害による被害の把握では、一刻も早く情報を得たいわけです。例えば、台風や豪雨による被害状況の把握では現地はしばらくの間雲で覆われているのが普通です。このため、SARのような観測環境を問わず利用できる観測手段が必要になります。多様なセンサーを活用して、多様な観測条件下で、多様な情報を取得する方法は、「センサーフュージョン」と呼ばれています。多様なプラットフォームやセンサーを併用することが、知りたい情報を確実に得るために必要です。
── 現在、自動車メーカーが精力的に開発している自動運転システムでも、カメラや超音波、レーザー測距(LiDAR)など様々なセンサーや電磁波を併用して、多様な走行環境下で確実に状況把握できるようにしています。同じアプローチですね。
越村 ── 取得した情報の解析・活用法は異なりますが、状況把握に用いる技術は同じですね。私たちも、LiDARを使って、瓦礫の有無など3次元的に計測する技術を研究しています(図6)。

── 自動車向けとして発達中の技術が、災害対策のような意外な領域でも活用できるというのは面白いですね。様々なプラットフォームやセンサーを使って収集したデータは、どのようにして被害対応に活用できる情報に変えるのでしょうか。
越村 ── 画像解析によって起きている被害を高精度に判断するためにAIなどを活用しています。専門家でも見逃してしまうような異常を画像データから見つけ出すのは、AIが得意な作業です。医療分野でも、X線写真を読影し、専門医でも見逃してしまうようなガンの初期段階を見つける技術が開発されており、他分野の知見を取り入れることができる領域です。より賢いAIを作る方法を確立することは、災害対策においても、大きな研究テーマのひとつだと思います。

地震発生後、津波被害を受ける場所と時間、程度を迅速に予測
── シミュレーションチームでは、具体的に、どのような研究をしているのでしょうか。
越村 ── 主に、災害の発生直後から、どこで、どのような被害が、どのように広がっていくのかを予測するリアルタイム・シミュレーションに注力した研究をしています。例えば、リアルタイム津波浸水予測システムを、津波工学、計算機工学、地球物理学の研究者の知見を結集する多分野融合によって開発しています。スーパーコンピュータを活用する現状のシステムを使って、震災が発生した直後にデータを入力してこうしたシミュレーションを実施して、被害予測を即時的に行うことが可能です。リアルタイムで計算できるようになれば、適切な対応が打てるようになります。我々の開発した「リアルタイム津波浸水被害予測システム」は、すでに国の災害対応システムの一部に採用されています。
── 高い技術的ハードルに挑んでいるのですね。システムの確立に向けて、多分野融合という研究開発のアプローチを取っている理由は。
越村 ── 津波を予測するためには、まず原因となった地震によって断層がどのように破壊され、海底の地盤の押し上げや沈み込みが起きるか解析し、海面に発生する凹凸を予測する必要があります。断層の破壊による地盤の動きを知るには地球物理学の知見が必要であり、津波の伝播・遡上を知るには津波工学の知見に基づいて流体の運動をコンピュータで計算する必要があります。さらに、被害対応に利用できるまでに計算時間を短縮するにはスーパーコンピュータの研究者の知見も欠かせません。3分野の知見を融合させて、初めて目的とするシステムが実現するのです。
── 開発したシステムは、どのように社会実装していくのでしょうか。
越村 ── 防災研究は、単に論文を書いて終わってしまったのでは、半分の価値しか無いと思います。社会実装に向けた道筋を明確にして、実行することが重要です。社会実装の実施機関として、開発した「リアルタイム津波浸水被害予測システム」の運用と情報サービスの提供を担う東北大発ベンチャー企業、株式会社RTi-castを設立しました。
── 設立した企業は、誰を顧客にしてサービスを提供するのでしょうか。
越村 ── 現在の顧客は、日本政府、内閣府です。私たちは、2017年に南海トラフで起きる津波のエリアを対象にしたシステムを構築し、2020年度には日本海溝沿いを対象にしたシステムも完成しました。これによって、太平洋岸に沿った海域で大きな津波が発生すれば、被害をリアルタイムで予測できます。地震発生後、30分以内に予測レポートを内閣府に提出する契約を結んでいます(図7)。また、高知県でも導入されています。

── 地震発生後30分というのは、何を基準にして決めた時間なのですか。
越村 ── 30分以内に予測レポートを作成できれば、多くの人命を守るための対策を考えるために役立つ情報になります。大きな災害が起きた際には、被災した自治体や国で対処方針を決める災害対策本部会議が開催されますが、それが開催されるのが地震発生後30分~1時間後です。これまでは、この会議が開催された直後には現場の状況はほとんど何も分かっていない状況でした。このため、迅速に会議が招集されても、効果的な対策が立てられず、総理大臣や知事は「被害状況を把握せよ」という方針くらいしか言えない状態だったのです。私たちが提出する資料があれば、1回目の本部会議の時点で、どこでどれぐらいの被害が発生しているのか、データとして検討できますから、適切な救命・救援活動の指示ができます。
── 今後、さらにシステムが進化する余地はあるのでしょうか。
越村 ── 十分あります。現在、災害発生後の人の流れに関する情報の統合に挑んでいます(図8)。これが実現できれば地形を考慮した被害の予測だけではなく、人がいる場所や活動状況を考慮した被害を予測すること、助けを求める人が集まる場所にピンポイントで救援を送ることができるようになります。また、津波が沿岸に到達する前に浸水予測を完了して、避難先や経路を伝えるガイドするための避難シミュレーションの研究にも取り組んでいます。


研究のための研究では終われない、責任ある研究
── 先生の研究室は、現在何人くらいのスタッフと学生が在籍しているのですか。
越村 ── 現在12名ですが、大体例年、10名ぐらいいます。
── 学生を指導する際には、どのような点に留意しているのですか。
越村 ── 卒業論文や修士論文に取り組む学生には、指導教員として、どのような点に着目して研究成果を評価するのか最初にきちんと伝えるようにしています。新しい発見を目指すことはとても重要な取り組みであり、高く評価します。さらに、既存の方法論であっても、独自の視点から上手に改善して、新しい価値やより良い価値を生み出すことも重要なことです。そして何より、社会的意義がある研究を高く評価するようにしています。私たちの研究室では、研究のための研究で終わってはダメで、何の役に立つのかということを常に問い続けることが大切だと考えています。
── 災害対策の研究に携わる学生や若い研究者にはどのようなことを期待したいですか。
越村 ── まずは、一生懸命勉強すること。そして、研究者になるならば、自分の研究の内容を説明するだけではなく、社会的意義や展望を自分の言葉で説明できるようになってほしいと考えています。

 |
 |
-

-
第1部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
越村 俊一 教授
-

-
第2部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
准教授 マス・エリックさん
- Profile

-
越村 俊一(こしむら しゅんいち)
-
東北大学災害科学国際研究所・教授
1972年生まれ。1995年に東北大学工学部土木工学科卒業、2000年に同大学院工学研究科博士後期課程を修了し博士(工)を取得。同年4月,日本学術振興会特別研究員となり,東京大学地震研究所およびアメリカ海洋大気局に勤務して津波の研究に取り組んだ。その後,財団法人阪神淡路大震災記念協会「人と防災未来センター」専任研究員を経て、2005年5月に東北大学大学院工学研究科助教授、2012年4月に東北大学災害科学国際研究所教授(現職)に就任.2018年3月に,津波浸水予測の業務を実施する株式会社RTi-castを設立,ファウンダー・CTOとして活動中(兼任)。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

