JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Laboratories
- 研究室紹介
技術・情報の力で、レジリエントな社会に貢献する
- 東北大学 災害科学国際研究所
- 第2部:
- 災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
- 准教授 マス・エリックさん
- 2021.11.04
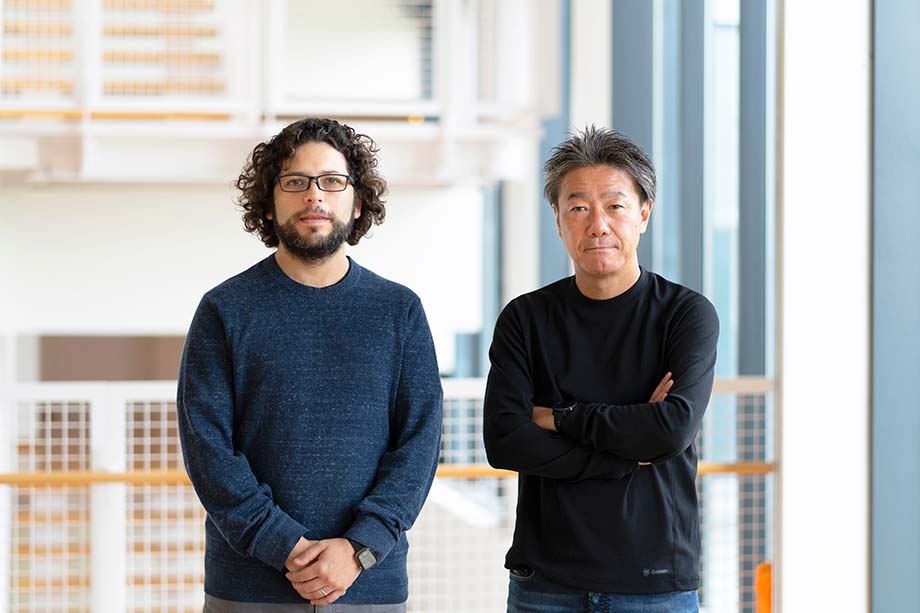
地震や津波の予測は極めて困難だ。同様に、災害が発生した後に被害状況を迅速・正確に把握することも難しい。東日本大震災では、ニュース映像などを通じて、誰もが愕然とする被災地の状況を目の当たりにした。そして、映像を見た日本中・世界中の人々が、被災地の救援や支援に向けてひとつになった。ただし、被災した人々に適切に手を差し伸べることができたかと言えば、反省点は多い。被災地のある地域には十分すぎるほどの救援物資が届いた一方で、本当に助けが必要なところには何も届かないという事態も発生した。実は、映像で見えていた部分だけが被災地ではなかったのだ。最新テクノロジーを駆使して、被災者を確実に救援・支援するための情報を収集・解析・提供する方法論を研究しているのが東北大学の越村俊一教授である。越村研究室で取り組む研究の内容と困難なテーマに挑む研究者が感じる意義について聞いた。
(インタビュー・文/伊藤 元昭 撮影/尾苗 清〈アマナ〉)
-

-
第1部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
越村 俊一 教授
-

-
第2部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
准教授 マス・エリックさん

── エリック先生が津波対策の研究を始めた経緯を教えてください。
マス ── 私は、ペルー出身です。母国の大学の土木専攻の学部生だった2004年、インド洋の大津波が発生し、大きな被害がニュースになりました。ペルーには、地震や津波による被害が発生した歴史が多くあります。特に首都のリマは、沿岸部にあり、津波の被害が発生する可能性が高い地域です。実際、1746年には、マグニチュード9クラスの大地震で発生した津波で大きな被害を受けました。2007年や2019年にも大きな地震がありましたが、その際には幸い大きな津波の被害は出ませんでした。また、チリで発生する地震や太平洋を挟んだ日本で起きた地震による津波が押し寄せることもあります。そうした地震や津波のリスクがある土地柄ですが、インド洋の大津波が発生した当時のペルーでは、地震は研究されているのですが、津波についてはほとんど手つかずの状態でした。ちょうど私は、学部の卒業を控えた時期だったこともあり、指導教員の先生と相談して津波の研究を始めました。
── 大学卒業後は、すぐに研究生活に入ったのですか。
マス ── 大学を卒業後5年間は、防災担当の公務員として働きました。その後、もっと災害対策について深く知るために修士課程に進み、修士取得後に博士課程で津波の研究を続けるための場を探しました。その時、進学先の選択肢には米国と日本の大学があったのですが、ペルーと同様に津波のリスクを常に抱え、津波に関する知見や経験が豊富な日本の大学を選択しました。私の指導教員が日系のペルー人であり、日本の文化に親しみがあったというのも日本の大学を選択した理由のひとつです。そして、2009年に、今村文彦先生と越村俊一先生がいる東北大学の津波工学研究室に入りました。博士課程に在籍していた際に、2つの大津波が起きました。2010年にはチリ津波が発生し、その際には、越村先生と一緒に初めて現地調査に出向き、研究者として貴重な経験を積むことができました。そして、2011年には東日本大震災の津波を経験し、そこでも多くのことを学びました。2012年に博士号を取得した後、そのまま災害研に入り研究を続けています。
── 津波災害の研究者として、大きな津波を立て続けに経験したというのは、得難い機会でしたね。
マス ── 3.11の地震発生時には、仙台ではなく、東京にいました。東京では大きな揺れを感じただけですが、仙台に戻り、現地に行って被害を目の当たりにして、あまりの恐ろしい光景に愕然としました。
── 研究対象として津波を熟知していたはずのエリック先生にとっても衝撃的な被害だったのですね。先生が博士号取得後に災害研に残って研究を続けることを選んだ理由は。
マス ── 越村先生との現地調査などを通じて研究室の雰囲気が分かっていましたし、災害研の組織ができて研究テーマが刷新され、私が興味を持っていたことを深めていくことができると考え、ここで研究しています。
── 研究内容を教えて下さい。
マス ── マルチエージェント・シミュレーションという技術を活用して、災害発生時にリアルタイムに避難誘導するためのシステムを研究しています。この研究は、核となるのは工学的な研究なのですが、人の心の動きを知るための心理学の理論や津波の動きを解析するための知見など分野を超えた知識を融合させて、社会の中での人の動きを理解した上での避難誘導を目指しています。
── 心理学も取り入れるのですか。確かに、非常事態の中では人間は思いもしなかったような行動をしがちですから、適切な避難誘導をするためには必要な気がします。
マス ── いち早く避難しなければならない状況になったとき、実際にどのように考え、どのように行動するかは、年齢や性別によって傾向が異なってきます。また、一人でいる場合と、グループで避難する場合でも変わってきます。そうした心理的な要素を組み込んで、多くの人同士の相互作用を勘案しながら、様々な状況を想定し、どのように誘導すれば適切に避難させることができるのかを探ります。
── 情報処理の手法も、AIが発達したり、量子コンピュータが使えるようになったりと、日々進歩しています。こうした技術の進歩が著しい時代だからこそ、面白い研究テーマのように思えます。
マス ── 新たに活用できるようになる技術については、私もいつも追い続けています。学部生の時代にはAIのような技術は利用できる状態ではありませんでしたが、現在では有効な解析手段になっています。今でも、学生になった気持ちで学び続けることができて、エキサイティングな研究です。
── 研究室の中で接する越村先生は、どのような方ですか。
マス ── 私が日本に来て、初めて研究室を訪れた際には、今村先生がちょうど不在で越村先生に迎えていただきました。その時には不安と緊張でいっぱいでしたが、本当に気持ちよく歓迎してくれて研究室の方々に優しく紹介していただいて、とても安心したのを覚えています。研究者としての越村先生は、学術論文や発表の資料などを見て、すぐに全体像を把握してしまうことに驚きます。これは、研究者としてのビジョンを明確に持っているからこそできるのではないかと考えています。目指したい研究者のモデルとなる方ですね。
── 災害研は、災害研究に向けた組織としては、世界有数の場だと思います。そこで研究することで得たことは何ですか。
マス ── たくさんありますね。特に、医療の研究者など、様々な学術的分野の研究者と一緒に研究できる点は、災害研だからこその利点だと思います。自分の工学的マインドとは異なる発想に触れて、別の視点や気づきが得られています。
── 今後、取り組んでいきたいことや目標をお聞かせください。
マス ── 災害の研究者として、少しでも人的被害を減らすために貢献できればと考えています。研究テーマとしては、現実世界と仮想世界の融合を推し進めて、避難誘導などに役立てるため、リアルタイムでのシミュレーションの実現に向けて取り組んでいきます。

 |
 |
-

-
第1部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
越村 俊一 教授
-

-
第2部:
東北大学 災害科学国際研究所
災害評価・低減研究部門 災害ジオインフォマティクス研究分野
准教授 マス・エリックさん
- Profile

- Mas Erick(マス・エリック)
-
東北大学災害科学国際研究所・准教授
1981年生まれ。2009年ペルー国立工科大学修士課程修了、2012年東北大学大学院工学研究科博士課程修了、2012年より東北大学災害科学国際研究所に助教として勤務、2016年より現職。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

