JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
新興国も取り残すことなく脱炭素化、電動バイクが起こすモビリティ革新
- 文/伊藤 元昭
- 2022.07.06
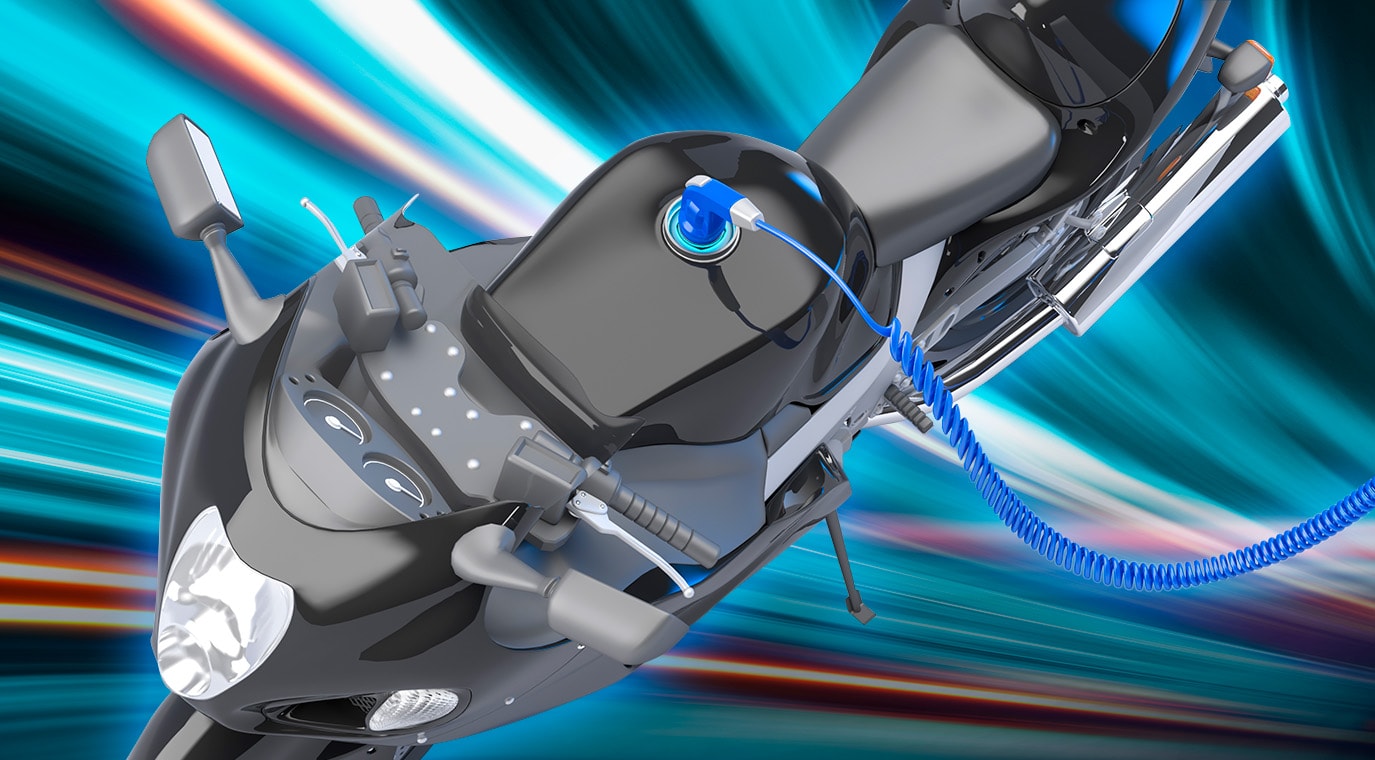
国際連合が掲げる「SDGs(Sustainable Development Goals)」の理念は、「誰一人取り残さない」というもの。世界の人々を取り巻く環境は多様であり、違いを正しく認識して、持続可能な世界の実現を目指そうとしている。カーボンニュートラル達成に向けた取り組みは、SDGsと同じ方向を向いているはずだが、実際には脱炭素化に向けたテクノロジー開発と活用は先進国目線で考えがちである。例えば、モビリティの分野では電気自動車(EV)への移行が加速しているが、新興国・途上国での生活の足である二輪車では四輪車ほど脱炭素化が進んでいない。世界が一丸となって取り組む課題であれば、こうした「取り残された状況」は放置できない。この記事では、二輪車における脱炭素化の取り組み動向と、そこを起点としたモビリティビジネスの新たな展開について解説する。
世界中でカーボンニュートラル達成に向けた取り組みが加速している。その一環で、自動車業界では、電動化、特にEVの普及が本格化しそうだ。生活やビジネス、社会活動に欠かせない存在であるモビリティを、地球温暖化ガスの排出を最小限に抑えながら運用するためには、こうした動きが必然だと言える。だが、これだけでモビリティの脱炭素化が完結するのだろうか。世界のモビリティは、持続可能なものになるのだろうか。
新興国・途上国のモビリティの中心は二輪車
カーボンニュートラルを達成する具体的な時期目標を掲げている国や地域の数は、世界で150に達する(図1)。この中には、エネルギーの消費量が多い先進国だけでなく、エネルギーの消費形態が異なる新興国や途上国も含まれている。世界人口の8割以上を新興国や途上国が占めているわけで、それらの人々が生活や社会活動を営む上で欠かせないモビリティを、持続可能な形で提供することが極めて重要だ。

- [図1]カーボンニュートラル達成の時期目標を表明している国や地域
- 出典:経済産業省 資源エネルギー庁
先進国の政府や世論は、四輪の自家用車や商用車中心にモビリティの脱炭素化を考えがちだ。しかし、新興国や途上国、特にアジア地域の国々の中には、四輪車よりも二輪車を生活の足として利用しているところが多い(図2)。一般に、一人当たりのGDPが3000米ドルを超えると、モータリゼーションが起こり、自動車(四輪車)の大衆化が進むと言われている。カーボンニュートラル達成に向けた取り組みに参加する国や地域の中には、この水準に達しないところが多く、あまねく脱炭素化の成果を上げるためには、四輪車向けだけでなく、二輪車向けの脱炭素技術も確立する必要がある。


- [図2]カーボンニュートラル達成の時期目標を表明している国や地域
- 出典:富国生命投資顧問
ところが、二輪車の脱炭素化に向けた技術開発とビジネスの取り組みは、四輪車ほど進んでいない。
モビリティの脱炭素化には、バッテリーと制御技術、高効率なモーター駆動技術のような先進的技術の投入が必要であり、四輪車も二輪車も、技術開発をリードする大手メーカーは主に先進国にある。脱炭素化の技術開発が四輪車向けで先行するのは、先進技術の投資を回収しやすい大市場を形成し、メーカーの中核拠点が置かれて消費者動向に目が行き届きやすいからだ。国土交通省によると、日本では二輪車の二酸化炭素(CO₂)排出量は年間79万トンと全体のわずか0.074%に過ぎない(2018年実績)。一方で、四輪車は全体の15%を占めているため、こちらが中心になるのは理解できる。こうした先進国の事情が、二輪車の脱炭素化を後回しにする傾向に拍車を掛けている。
世界の二輪車の年間需要は、四輪車の約6割に当たる5000~6000万台である。そして、二輪車市場における日本企業のシェアは極めて高い。メーカー各社の資料を統合すると、2020年時点での金額ベースのシェアは、本田技研工業(ホンダ)が22.6%でダントツの世界1位、ヤマハ発動機(ヤマハ)(10.4%)が2位、スズキ(2.6%)が8位、川崎重工業(カワサキ)(2.3%)が9位である。2020年はコロナ禍の中で市場が収縮した特異年だったこと、近年はインド、中国、台湾などのメーカーがシェアを伸ばしていることを勘案しても、世界市場における日本企業の存在感の大きさが分かる。ちなみに、四輪車では、世界1位のトヨタ自動車でもシェアは約10%。二輪車ほど偏っているわけではない。つまり、二輪車での脱炭素化を技術開発とビジネスの取り組みの両面からリードしていくべき責任を負うのは、日本企業だと言える。
カーボンニュートラル達成に向け、二輪車も脱炭素化の対象に
こうした状況を問題視する二輪車メーカー各社は、近年、にわかに電動化に注力。2000年代以降、二輪車での電動化がジリジリと広がり、2020年以降には、その動きが急加速する傾向が見えてきている。矢野経済研究所の予測では、2030年時点の電動バイクの市場は最大で1305万台、最小で751万台にまで達するという(図3)。その時点での二輪車全体の市場は、約6576万台とみられていることから、1割強~約2割が電動化される可能性がある計算だ。

- [図3]世界の二輪車市場と電動化の予測
- 出典:矢野経済研究所
これまで二輪車は、キャタライザー(排気ガス中の有害成分を除去し、無害化する機構)やECU(Engine Control Unit)のプログラム調整のみで排ガス規制をクリアできていた。このため、四輪車のような大規模な電動化技術開発が活発に行われてきたわけではなかった。そもそも、四輪車に比べると燃費に優れ、1台当たりのCO₂排出量も少なく、電動化する理由に乏しかったのだ。しかし、カーボンニュートラル達成に向けて各国政府の取り組みが本格化し、ICE(内燃機関)四輪車の販売禁止が協議されている2030年以降に向けて、二輪車も電動化が求められるようになった。
既に中国では、電動自転車を含む電動二輪車が身近な移動ツールの1つになっており、現時点で、約2億台保有されていると言われている。こうした普及の背景には、現在、中国の中規模以上の都市で、エンジンバイクの利用が禁止されている点がある。ただし、これは脱炭素化を狙った施策ではなく、大気汚染や事故防止を狙って実施されたものだ。また、普及が進んでいるのは、大部分が現地メーカー製の電動自転車寄りの小型電動バイクである。
一方、インドは、2030年までに国内で販売する二輪車やリキシャ(小型三輪モビリティ)などを含めたすべての車両を電動にすると発表。こちらは、脱炭素化を狙った施策であり、先進国でも同様の動きが出てきている。イギリスやフランスは2040年から内燃機関車の販売を停止すると宣言しており、エンジンバイクから電動バイクへのシフトが進みそうだ。日本でも、東京都が、2035年までに都内の二輪車販売(新車)をすべて非ガソリン化する方針を掲げている。
試用フェーズから、エンジンバイクの代替を狙った実用化フェーズへ
市場の本格的な伸びはこれからというところだが、二輪車メーカーによる電動バイクの開発・実用化の取り組みには、意外と長い歴史がある。これまでの日本のメーカーの取り組みを紹介したい。
1994年、ホンダが電動スクーター「CUV ES」を、官公庁や自治体向けに200台限定でリース販売した(図4)。ただし、これはあくまでも二輪車の電動化が、いかなるメリットをもたらすのか、その可能性を模索することを目的とした取り組みだった。そして、2002年には、ヤマハが量産型の電動バイク「パッソル」を初めて発売。電動バイクを、ビジネス化する取り組みが始まった。そして、ホンダとスズキもこの動きに追随した。ただし、この時点では、既存のエンジンバイクの使い勝手と燃費が優れていたため、電動車両の比率が拡大する動きにはならなかった。
2010年代後半になると、いよいよ脱炭素化に向けた電動車両の投入を、各バイクメーカーが開発・市場投入するようになった。用途に応じてエンジンバイクと棲み分けるのではなく、代替することを明確に念頭に置いて技術開発と製品企画をした点が、それまでとの違いである。さらに、四輪のEV用の部品の性能が飛躍的に向上したため、バッテリーやモーター駆動などの面で技術的恩恵がバイクにも及び、電動バイクの性能が急速に進化した。
そして、2018年にホンダは、エンジンバイクの代替を見据えた原付二種電動スクーター「PCXエレクトリック」を、日本と大市場である東南アジア各国で発売した。これは、明確に世界市場を狙いに行ったバイクである。同社は、現在、ビジネス向けを優先して、電動バイクの取り組みを強化。2020年には出前や宅配便などの配達用途を想定したビジネス用電動スクーター「BENLY e:」を、2021年には大型低床荷台を採用したビジネス用電動三輪スクーター「GYRO e:」を市場投入した。同社は、現在2割程度のビジネス用電動スクーターの電動化比率を2025年までに7割強まで高めるとしている。パーソナル用途に関しては、2024年までにパーソナルユースの原一、原二クラスなど3種類の新型電動バイクを市場投入する計画である。
一方、カワサキは、2019年に開発中の電動スポーツバイク「EV Project」を公開した。電動モーターの特長である太いトルクによる加速を重視したバイクである。バイクは、生活の足という側面以外に、マニアが愛でる嗜好品という側面もある。四輪車では、テスラ(アメリカ)が同様の目的に応える電動スポーツカーの市場投入で成功している。真剣にエンジンバイクの代替を目指すならば、こうした取り組みも重要になる。

- [図4]電動バイクは試用フェーズから実用化フェーズに移行
- ホンダの電動スクーター「CUV ES」(左上)、ヤマハが量産型の電動バイク「パッソル」(右上)、ホンダのエンジンバイクの代替を見据えた原付二種電動スクーター「PCXエレクトリック」(左下)、カワサキの電動スポーツバイク「EV Project」(右下)
出典:ホンダ、ヤマハ、カワサキ
一方、海外メーカーの取り組みも活発化してきている。例えば、アメリカのハーレーダビットソン(Harley-Davidson)やドイツのBMWはスポーツタイプの電動バイクを、台湾のキムコは生活の足となる車種とスポーツタイプ両方の電動バイクの投入に積極的である。また、自動車よりも開発費が安く済み、ビジネスの参入障壁が低いことから、新興メーカーにとって絶好の商材となっている。現在シェアが高い日本企業もうかうかしていられない。
こうした海外勢の動きを横目に、ホンダは四輪車同様に二輪車でも電動化シフトを加速させていく方針だ。ヤマハは電動バイクの販売比率を2035年までに20%まで引き上げる目標を掲げ、カワサキはさらに積極的に2035年までに先進国向け主要モデルの新車販売のすべてを電動車に切り替える方針を打ち出している。
安全性とメンテナンス性を徹底強化した電源ユニット
現在、市場投入されている電動バイクの電源ユニットは、どのようなシステム構成を取っているのか、ホンダのビジネス用電動三輪スクーター「GYRO e:」を例に解説したい(図5)。

- [図5]電動バイクの電動ユニットのシステム構成例(ホンダ「GYRO e:」)
- 出典:ホンダ
多くの電動バイクがそうであるように、GYRO e:には、エンジン版の兄弟車種がある。雨よけのキャノピーを付けて、ピザの宅配などに多く利用されているスクーターがそれだ。その既存のエンジン車から最小限の変更で電動化対応できるように、GYRO e:の電動ユニットは開発されている。バッテリーは、48V系の着脱式バッテリーパックを横に2個、シート下のスペースに配列し、直列接続した構成を取っている。そして、96Vの出力をパワー・コントロール・ユニットで三相交流に変換してモーターを駆動している。
ドライバーが機械にまたがって操縦するバイクは、四輪のEV以上にバッテリーに安全対策を施す必要がある。風雨や振動の中での走行など、信頼性面で厳しい条件が多いからだ。発火物が詰まったリチウムイオン電池を内蔵したバッテリーパックは、安全第一で設計する必要がある。しかも、詳しい理由は後述するが、GYRO e:に搭載しているバッテリーは着脱式である。ユーザーがバッテリーを持ち歩くことも想定して、交換時にバッテリーに水が掛かったり、落下したりしても安全な対策が必要になる。このため、筐体外装が損傷しても防水性を損なわないように、バッテリーパックの内部に防水構造を設けている。さらに、筐体を落とした際に、セルや制御基板への衝撃を軽減するための衝撃吸収構造を内部に導入している。シート下に2つ配置した着脱式バッテリーは、1回のハンドル操作でバッテリーの固定とコネクターの嵌合を可能にしており、簡単に着脱できる。
また、GYRO e:のようなビジネス用途の車種は、スポーツバイクなどより稼働率が高い。長期間の使用を想定すると、モーターの交換を伴うメンテナンスが発生する場合もあるため、モーター交換の作業性を向上させておく必要がある。GYRO e:は、アルミ製のケースとカバーを用意し、モーターを構成するステーター(固定子)とローター(回転子)を固定・ユニット化することで、車両への着脱は、ユニット交換だけで済ませられるようにしている。
大容量バッテリーを搭載できない欠点を逆手に取って難問解決
電動バイクには、普及を阻む3つの課題がある。「長い充電時間」「短い航続距離」「高い車両コスト」である。ただし、これらの課題は二輪車固有というわけではなく、四輪のEVも同様に抱えている。課題の難易度の度合いと、導入可能な解決手法が二輪と四輪では異なる。
四輪のEVで、「長い充電時間」と「短い航続距離」の2つを解消するためには、全固体電池や超急速充電器の実用化など、技術的なブレイクスルーが欠かせない。特に、「長い充電時間」を解消するためには、充電待ちを解消するため、現状のガソリンスタンドをはるかに超えるほど多くの充電ステーションを整備する必要がある。一方、「高い車両コスト」については、モジュール設計によって開発と生産のコストを削減しながら、市場の拡大によって、EV向けの部品・材料の価格が、大量生産の原理で低下するのを待つしかない状態だ。
一方、電動バイクには、四輪よりも課題の解決が難しい固有の事情もある。バッテリーの設置スペースが狭く、加えてコスト上の制約がより厳しいことだ。このため、新型電池や大容量電池を利用しにくいことがネックになる。新興国や途上国の市場に投入できる商品にするためには、ここは譲れない点である。
ただし、バイクメーカー各社は、こうした困難な課題の解決法を既に見つけている。大容量化できないことを逆手に取った、持ち運び可能なサイズの着脱式バッテリーの採用が、問題を一気に解決するブレイクスルーになる。
着脱式バッテリーとは、車両内に固定設置されたバッテリーを充電するのではなく、バッテリー交換ステーションで満充電状態のバッテリーごと交換するという、簡単かつ一瞬で補給を終わらせる仕組みである。交換ステーションに立ち寄った利用者が、到着してから充電を始めるわけでないので、「長い充電時間」という課題は解消する。約10秒でバッテリー交換を終えることができるので、エンジンバイクの給油時間よりも短いくらいだ。
一般に、バッテリーパックの仕様は、各メーカーまちまちだ。形状も、出力電圧も、容量も異なる。例えば、ホンダは、「Honda Mobile Power Pack(ホンダ・モバイルパワーパック):MPP」という名称で、バッテリーパックの仕様を規格化している。台湾メーカーのキムコ(KYMCO)やゴゴロ(Gogoro)も、それぞれ個別の仕様のバッテリーパックを導入している(図6)。このため、相互利用することができない。

- [図6]各メーカーで異なる電動バイク向けバッテリーパックの仕様
- 出典:ホンダ、KYMCO、Gororo
着脱式バッテリーの採用により、バイクの所有者がバッテリーも所有するのではなく、充電されたバッテリーを借りて利用することを前提としたビジネスを描くようになった。車両価格のコストを押し上げる最大の要因であるバッテリーが含まれないため、「高い車両コスト」という課題も解決できる。もちろん、MPPの使用料は必要になるが、運用コストの考え方はガソリン代と大差ない。ホンダをはじめとするバイクメーカーは、バッテリーのシェアリングサービスを事業化することで、自社のビジネスモデルを「モノづくり」から「コトづくり」へと転換し、継続的に顧客とつながるビジネスにしようとしている。
一般に、電力を充電するバッテリー交換ステーションは、危険物を扱うガソリンスタンドよりも、設置が容易だ。簡素な設備で安全に給電・備蓄できる。その気になれば、コンビニ1店舗ごとに1台、さらには家の軒先に交換ステーションを据え付けることも可能だ。実際、ホンダのMPPに対応する交換ステーション「Honda Mobile Power Pack Exchanger e:」は、飲料の自動販売機とほぼ同サイズであり、ガソリンスタンドとは比べ物にならないほど、低コストかつ安全に設置できる(図7)。1台のステーションには最大12個のバッテリーパックをストック可能であり、設置場所の需要に応じて最大7台まで連結して設置できる。このため、どんな場所にも、ガソリンスタンド以上に多くの交換ステーションを設置することが可能になり、「短い航続距離」の不安も解消する道が拓く。

- [図7]ホンダのMPP向け交換ステーション「Honda Mobile Power Pack Exchanger e:」、一緒に写っているモビリティはインド市場向けの電動リキシャ
- 出典:ホンダ
バッテリーパックの標準化で、電動バイクの普及を後押し
着脱式バッテリーの採用は、電動バイクの普及を阻む課題を一気に解消する妙案である。ただし、バッテリーの仕様がバイクメーカーごとに異なったままでは、使い勝手が悪い。各交換ステーションには、メーカーごとのバッテリーを個別に用意しなければならないため、市場でのシェアが小さいメーカーのバッテリーは用意されない可能性がある。仮に無数の仕様が乱立・共存すれば、現時点でシェアが大きいメーカーが有利になり、最終的にはバイクメーカーの寡占化が進むことだろう。また、それぞれの仕様ごとのバッテリーパックの総数が細分化されてしまうため、低価格化が進まない可能性もある。
こうした問題を放置しておけば、一見、大手二輪車メーカーに有利になるように見える。しかし実際には、電動バイク市場のパイの拡大を阻む要因となり、大手メーカーも困ることになるため、業界全体で取り組むべき問題だと言える。そこで、着脱式バッテリーを標準化し、どのメーカー製の電動バイクでも利用できる充電ステーションを作るための仕組みづくりが始まっている。
2021年3月、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの日系二輪車メーカー4社が、着脱式バッテリーの仕様を標準化することで合意した。まず、二輪車や小型モビリティなどの電源の規格をホンダのMPPに統一することで用途を拡大。MPPの使用量を増やして、大量生産の原理によるバッテリーパック自体の低コスト化を促し、競争力強化を図る。そして、4社は、仕様を標準化したバッテリーパックの相互利用を促進する「電動二輪車用交換式バッテリーコンソーシアム」を設立した。
日系メーカーの標準化の動きが、現在の二輪車市場でのシェアの高さを背景にして、そのままグローバル標準になるかと言えば、そうでもなさそうだ。新興国の企業を中心にした標準化の動きが別途あるからだ。同業種同士の協力関係ではなく、ユーザーを巻き込んだ協力関係を推し進めている点が、海外企業による標準化の取り組みの特徴だ。
例えば、ゴゴロは、インドネシアのオンライン配車・配送サービス大手のゴジェック(Gojek)や、オンライン配車大手グラブ(Grab)と共同で、インドネシアでゴゴロ仕様の着脱式バッテリーのエコシステム構築を推し進めている。こうした動きに、日本企業も敏感に反応し、対策を取っている。ホンダは、インドで、電動三輪タクシー(リキシャ)向けの電池シェアリング事業を2022年から始めると発表している。
電動バイクとビジネス用途の相性は極めてよい。動力源がエンジンからモーターに変わることで、オイルやフィルター、チェーンといった消耗品の交換が不要になるからだ。このメリットは、1台当たりの走行距離が長いビジネス用途でこそ有利になる。加えて、これは日本市場限定のメリットだが、現在の日本の道路運送車両法では、どんなに出力が大きくても電動バイクは軽二輪扱いになり、車検は不要である。
バイク市場全体から見れば配車サービスやリキシャなどで使われるバイクの数は10%程度であり、しかもそこで利用されるのは低価格モデルが中心だ。二輪車メーカーには、それほどうまみのあるビジネスには見えない。しかし、ここで大きなシェアを取ればバッテリーパックを大量生産するための基盤となり、パーソナル用途向けでも有利に働く可能性がある。
電動バイクを起点に、イノベーションを小型モビリティ全体へと拡大
電動バイク向けの着脱式バッテリーパックと、交換ステーションで利用者に貸与するシェアリングサービスは、モビリティビジネス全体に、思ってもみなかったようなインパクトを及ぼす可能性が出てきている。物流で宅配便など小口の配達に利用する配送車や農業機械、建設機械などが、軒並みダウンサイジングし、その電源として電動バイク向け着脱式バッテリーパックを適用する公算が高いからだ(図8)。

- [図8]自動車用の自動運転技術の進化を転用して、働くクルマをイノベーション
- 写真:Adobe Stock、Harper Adams大学、鹿島、Starship Technologies
作成:伊藤元昭
あらゆる国や地域で、物流用トラックのドライバーや農業従事者、建設従事者が不足している。いかに人手を省いて、きめ細かな業務をこなすかが世界共通の課題である。そして、その解決手法を新しいテクノロジーに求めるようになってきている。こうした課題解決にピッタリな技術が、自動運転技術である。配送車や農機、建機を自動運転・自動作業できるロボットにすることで、人手不足が解消する。すると、人手を掛けず、柔軟な作業要求にきめ細かく応えるため、それぞれの作業を担うモビリティが小型化する。こうした変化は、工場の中で部品や完成品を運ぶ搬送車の自動化という形で、既に顕在化している。
小型モビリティは、自動運転技術の進歩とともに、現在よりもずっと数が多くなることだろう。その時、電源を供給するのは、電動バイク向けに先行整備された業界標準のバッテリーパックや交換ステーションになる可能性が高い。実際、ホンダは、自動運転技術を適用しているわけではないが、自社規格のバッテリーパックMPPを、世界でのシェアが高い自社製の芝刈り機や除雪機、小型耕うん機、小型建機などの電動化に利用しつつある。
電動バイク向けビジネスを制することで、近未来の小型モビリティビジネス全体を制する力を持つ企業が生まれる可能性さえある。電動バイク向け技術とビジネス開発から目が離せない。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

