JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
2024年秋から続出するAI搭載パソコンやスマホを徹底解説
ー 生成AIをエッジで使う
- 文/津田 建二
- 2024.10.02
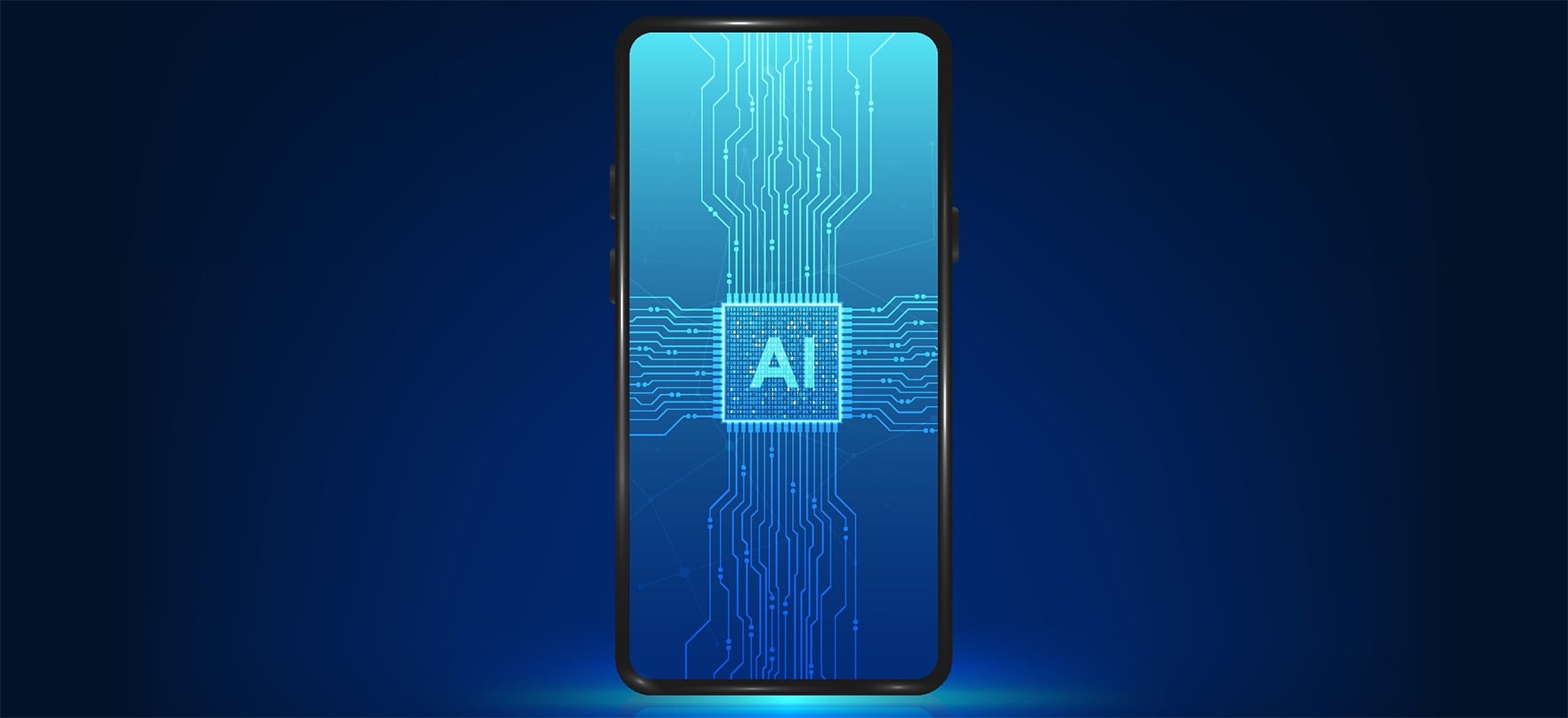
生成AIがPCベースで使えるようになる。これまではPC本体の能力が不足していたため、クラウドベースで生成AIを使ってきた。ところが、SoC半導体チップが強力になり、CPU(中央プロセッサ)、GPU(グラフィックスプロセッサ)、NPU(ニューラルプロセッサ)を1パッケージに集積した結果、OSにAI機能を入れることができるようになった。Apple(アメリカ)は6月に開催したWWDC(世界開発者会議)において、PCやスマホで生成AIを実行するデモを見せた。Microsoft(アメリカ)もWindows 11以降の機種にAI機能を含めるように提案した。いよいよPCやスマホ本体で生成AIを使える時代がやってくる。
AIや生成AI機能を搭載したPC時代へ
AIや生成AI機能を搭載したPCが、この秋に続々登場する。すでにAppleがApple Intelligenceと呼ぶAI機能を搭載したMacを6月のWWDCで発表している。MicrosoftもWindows 11以降の機種にAI機能を実現するNPUを搭載し始めている。AI PCを定義したCopilot+(コパイロットプラス)機能を持ち、40 TOPS(Trillion Operations Per Second)以上という高速のAI演算性能と、1日中使えるほど低消費電力などを実現している。
AI機能搭載PC市場は24年秋から増加
新製品のPC全てにAI機能が載るのは2030年になると、市場調査会社のCanalysは予想している(図1)。また、2024年の新製品のうちAI PCになるのは19%と、アーリーアダプターと呼ばれる愛好家たちは予想する参考資料1。それが2025年には37%、2026年には53%、2027年には60%に上がっていくと、Canalysは、さらに予想する。ただし、Canalysが定義するAI PCとは、CPUやGPUの他に、ニューラルネットワークモデルを実行できるNPUを搭載している機種のことを指している。

- [図1]AI PC市場は26年には過半数に増加
- 出典:Canalys
これまでにPCは飽和市場となっており、スマホも同様の道を歩んでいる。どちらも買い替え需要に依存しており、中古市場も着実に育っている。リユース経済新聞によると、2022年のPCと携帯・スマホの中古市場はPCが1036億円、携帯・スマホは691億円に上り、特に後者は前年比17%も成長しているという。
PCやスマホは、自動車と同様に中古市場が成長しており、新製品市場は、ほぼ毎年同程度の規模になっている。ただし、これまでの電気・電子製品と違い、その売り上げが下がらない。この状態はこれからも続くだろう。内部機能が便利に、そしてインテリジェントに進化し続けるからだ。内部の機能・性能が毎年向上しているため、出荷台数は減少しない。買い替えることで出荷台数は維持される。
Appleから学ぶAI PC
この秋から続出するAI PCは、これまでクラウドベースでしか提供できなかった生成AIをクラウドにつなげなくても使えるようになる。これまでのPCの買い替え需要では実現できなかった生成AI機能が実現できるようになりそうだ。
AI PCの先駆者であるAppleが、PCにおけるAIの役割を示している。AppleはWWDCイベントの基調講演参考資料2において、AppleのAI機能である、Apple Intelligenceの5つの特長を紹介している。まず性能が向上したこと(Powerful)、次に直感的で使いやすい操作(Intuitive)、ユーザー体験を統合していること(Integrated)、さらに最も重要なことは個人的(Personal)、すなわち日常的なルーティンや個人的な関係、そのやり取りなど個人に関することで生成AIに問い合わせることができるようになること、そしてプライバシー保護(Private)、つまりクラウドを使わなくても生成AIを使えるためプライバシーが損なわれる心配はないのである。「これら全てをAIで実現する。Appleにとってこの機能は次のビッグステップになる」とApple社のTim Cook CEOは語っている(図2)。

- [図2]Apple本社の屋根の上でプレゼンするTim Cook CEO
- 出典:Apple
AI PCと、従来のPCとの技術的な違い
これから登場するAI PCとこれまでのPCとの技術的な違いは、従来のAIだけではなく、生成AIを導入しているという点だ。
生成AIにより、テキスト入力や音声入力によるテキストや画像の生成、絵文字の生成などが可能になる上、音声入力技術であるSiriの飛躍的な向上が図れる。そしてクラウドを経由せずに生成AIを使えることで、ユーザー自身の個人的なコンテキストやユーザー体験などをPC内に格納することができる。このためプライバシーがクラウドへ吸い込まれることはなくなる。
Cook CEOがApple Intelligenceを6月に発表した時は、PCのMacの話だと感じていたが、新しいiPhone 16にも搭載されることが9月の同社の発表で明らかになった。もちろん、PCとスマホではニューラルエンジン(Appleの専用ニューラルプロセッサ)の規模が違うため、それぞれに最適な生成AIの規模を使えるように振り分けている。MetaがオープンにしているLlama-3には8B(80億パラメータ)モデルと70B(700億パラメータ)モデルがある。用途に応じて使い分けられるようになっている。
これから登場するAI PCの機能例
ではPCで、どのような機能を生成AIで実現するのか。生成AIらしさが出ている機能としてWriting Tools(ライティングツール)とGenmoji(ジェンモジ)、Image Playground(イメージプレイグランド)、Siri(シリ)などを紹介しよう。これらの機能はWindowsベースのPCでも実現できる。
まず、Writing Toolsでは、メールやドキュメントなど文章を書いたら、その文章のスペルミスや文法の誤りを修正するだけではなく、より適切な表現に書き直してくれる。親しい友人に送るテキストであれば親しみを感じる表現に、業務上のテキストであれば、それにふさわしい文章に直してくれるのだ。さらに長い文章だと要約を付けることも可能である。時には詩を作り、テキストの一部に加えてくれることもできる。これなら文章を書くことが苦手な人も自信を持てるようになる。
Genmojiは絵文字を生成する(Generating Emoji)機能である。PCやスマホでは絵文字でメールやSNSを発信することが多いが、独自の絵文字を生成してくれるのがGenmoji機能だ。もともと絵文字は英語でもemojiと書き、そのまま「エモジ」と発音する。絵文字は日本だけではなく海外でも標準搭載されている「画像」であり、誰でも使う機能となっている。Genmojiでは、好きなことやモノにはハートマークを付けたり、冬は雪で表現したり、浜辺はヤシの木などで表現したり生成してくれる(図3)。

- [図3]自分で好きな絵文字を作れるGenmoji機能
- 出典:Apple
画像生成Image playgroundでは、生成したい画像を3つ程度のテキストで表現すると、画像を生成する。ストーリーを付けると動画も生成する。また、同様な画像生成機能の一つImage Wandは、ラフなスケッチを書いて指定すると、きれいでもっとビジュアルに優れたな画像に仕上げてくれる。
また、ユーザーの顔写真がPCやスマホなどに保存されていれば、SNSやメールなどで、誕生日おめでとうというメッセージを、自分とよく似た顔のイラスト付きで送ることができる(図4)。

- [図4]自分の写真に似せたイラストで誕生日祝いのメッセージを送る
- 出典:Apple
Siriも大きく変わった。Siriは13年前に導入された自然言語認識技術であるが、AIによって言語理解能力が向上した上に、生成AIと組み合わせることでデバイスに口頭で問い合わせて答えをもらうこともできる。生成AIによって、Siriが回答するボキャブラリが増えたと実感できるようになる。
言語を認識するだけではなく、ユーザーの行動(コンテキスト)も理解するようになった。これまでの画面に表示されたコンテンツを認識する機能(On-screen awareness機能)により、Siriは時間が経つにつれて、より多くのアプリでユーザーのコンテンツを理解し、アクションを実行できるようになる。例えば、友人がメッセージで新しい住所を送ってきた場合、受信者は「この住所を彼の連絡先カードに追加して」と言えば追加してくれる。また、ニューヨークにいる友達のピンクのコートを着ている写真を出してと言えば、すぐに写真が出てくる。
また、口頭で話をしにくいような場所では、テキストで問い合わせることもできる。これは従来のチャットGPTと同じ仕組みだが、生成AIならではの応用だと言える。
Appleは、このApple IntelligenceをMacだけではなく、iPadとiPhoneでも実現できるように、SoC半導体チップとOSの高位版を使えるようにアップグレードしている。Mac用のSoC半導体チップはiPhoneのA17 Pro以降の製品に対応するし、macOS Sequoiaと、iPadOS 18、iPhone15以降のiOS18でApple Intelligenceが使えるようになる。
Windowsが定義するAI PCとは
Microsoft WindowsでもCopilot+機能を載せたPCをAI PCとして定義している。これまでもAI機能を搭載したPCはあったが、生成AI機能を搭載したPCはない。PCレベルで、コンテンツ生成やコード生成、デジタルアシスタントなどに使えるようになる。
また、従来のAI搭載機種は、それほど大きな規模ではない学習データを使用していたが、この秋から登場するPCは大規模な言語モデルを用いた生成AIを実行できるほどの数十億パラメータ程度の規模のAIを使う。このためNPU(ニューラルプロセッシングユニット)と呼ばれるAI専用チップや、AI IP(チップ内のAI回路)を搭載し先端プロセスを使ったSoCが必要になる。
スマホ向けプロセッサ「Snapdragon」をPC向けに改良
これまでWindows向けのプロセッサは、アメリカのIntelやAMDのx86アーキテクチャに基づくものがほとんどだった。ところがQualcomm(アメリカ)がWindowsのAI PC向けのプロセッサ「Snapdragon X Elite」を6月のComputex Taipeiで発表したのだ。1カ月前には少し機能を落とした「Snapdragon X Plus」を発表しており、Snapdragon Xシリーズは、Copilot+対応の最初のWindowsチップとなった。
QualcommがMicrosoftと業務提携してWindows向けのプロセッサSnapdragonシリーズを開発するという話は以前から聞いていたが、これがCopilot+仕様のAI PCだったのだ。これまではX86アーキテクチャしかWindowsに入り込めていなかったが、ここにQualcommが入り込んだということは、同社がAI PC市場で今後の成長を狙っていると言えそうだ。
AI PC向け「Snapdragon」驚くべき機能と性能
Snapdragon X Eliteは、イギリスのArmベースの64ビットCPUコア「Oryon」(最大12コア)に加え、最大処理能力3.8および4.6 TPOSのGPUコア「Adreno」、最大AI処理能力45 TOPSのNPUコア「Hexagon」、センシングハブのコアなどを集積している。メモリにはLPDDR5xを接続し、その転送速度は8448MT/sと高速で、バンド幅は135GB/s、メモリ容量は最大64GBをカバーする。CPUは最大周波数3.8GHzで、キャッシュ容量は42MB集積としている。台湾のTSMCの4nmプロセスで製造されており、最大動作周波数は3.4GHzと3.8GHzなど性能によって4種類の製品がある。
ここでのGPUはグラフィックス画像を創り出すためのプロセッサであり、GenAIなどのAI機能はNPUの「Hexagon」が担う。NPUは、生成やビデオ会議、セキュリティ、プロダクティビティアシスタントなどの機能を提供するほか、クラウドと接続しなくても済むように生成AIのLLM(大規模言語モデル)を130億パラメータに絞り、PC上だけで動作できるようにした。低消費電力のセンシングハブ機能には、最新のマイクロNPUが集積されており、セキュリティを高め、ログイン体験やプライバシーを守ることにも使われている。
このSnapdragon X Eliteを搭載したPCは、5月に20種類以上発表されており(図5)台湾のAcerやASUS、Dell(アメリカ)、Lenovo(中国)、HP(アメリカ)、Samsung(韓国)などのPCメーカーがSnapdragon XシリーズをSoCプロセッサに使うことを表明している。

- [図5]Snapdragon XシリーズのSoC半導体を搭載するPC群
- 出典:Qualcomm
IntelとAMDの動きも活発に
元々スマホのアプリケーションプロセッサを主要製品としてきたQualcommがPCにも本格的に進出したことは、X86アーキテクチャ陣営にとっては痛手であった。ただ、IntelとAMDも手をこまねいていた訳ではない。
Intelは24年5月にAI PC向けのプロセッサ「Lunar Lake」(コード名)を発表した。これは、MicrosoftのCopilot+仕様に対応するプロセッサだ。Lunar LakeにはCPUとGPU、NPUなどを集積しており、NPUの演算能力は40TOPSだが、GPUは60TOPSもあり、場合によってはNPUの他にGPUも加わってAI処理を行うことも可能だ。IntelはLunar Lakeを搭載したPCが、今年の後半には20社以上のOEMメーカーから80機種以上出てくるだろうと見込んでいる。
AMDはComputex Taipei 2024において、Copilot+仕様のSoCである「AMD Ryzen AI 300」シリーズを発表している。その一つ「AMD Ryzen AI 9 HX370」には、やはりCPUとGPU、NPUを搭載しており、その性能は最も高い。CPUはQualcommやIntelと同じ12コア、24スレッドだが、最大動作周波数が5.1GHzと高い。NPUの演算能力は50TOPSと最も高い。GPUには16のCompute Unitを集積している。同社のLisa Sue CEOは同イベントでこのチップを手で持って示している(図6)。

- [図6]Computex Taipei 2024において、Copilot+仕様チップでAI機能の高いAMD Ryzen AI 300チップを持つCEOのLisa Sue氏
まとめ
これらの半導体SoCを搭載したPCは、この秋から続々登場すると見込まれており、繰り返しになるがPC側だけで生成AI機能を実現できるため、パーソナルな情報をクラウド上で晒される心配は全くなくなる。もちろんPCのセキュリティも強化される。それもSoCチップ上にセキュリティ回路が働くため、ソフトウエアよりも強固なハードウエアセキュリティになる。PCベースで生成AIが利用できるようになると、もっと身近で楽しい操作ができることにつながる。
また、PCだけではなく、AppleのようにMac、iPad、iPhoneと一連のデバイスで全て生成AIを使えるようになる。それぞれのデバイスにはもっと楽しい機能が付く一方で、セキュリティが強化され、家庭用の癒しロボットの実用化も近づくことになりそうだ。
[ 参考資料 ]
- 1. Now and Next for AI-Capable PCs, Canalys, Complimentary Report
- https://canalys.com/reports/AI-PC-market-forecasts
- 2. Tim Cook *Keynote、Apple Worldwide Developer Conference 2024、(2024/06/10)
- https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2024/101/?time=3870
- Writer
-
津田 建二(つだ けんじ)
-
国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。
現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。
30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。
半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。
- URL: http://newsandchips.com/

