JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
世界が注目するインドの半導体事情
ー 半導体産業の創出・育成に邁進する理数系人材大国
- 文/伊藤 元昭
- 2024.10.09
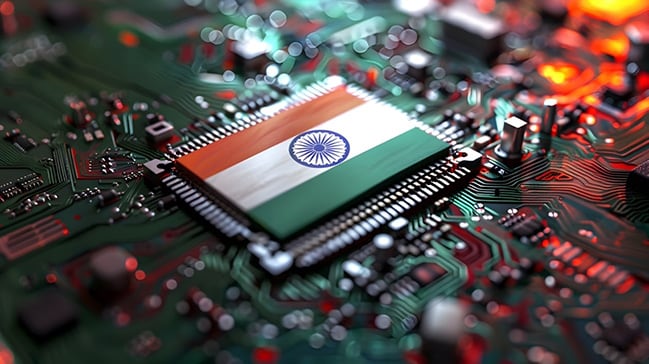
世界一の人口を背景にした莫大な数の高度理数系人材を擁するインドが、政府主導の半導体産業創出・育成に邁進している。近年、中国による半導体産業の成長に注目が集まっていたが、顕在化したアメリカと中国の対立の中で急ブレーキがかかる中、中国に代わって新たに台頭する半導体新興国となると目されてきているのがインドである。
半導体産業全体の動向
半導体産業は、平均年率10%以上で継続的に成長し、2030年には1兆ドルに達すると予想される伸び代がまだまだ大きく残された巨大産業である。しかもそこで作られている製品は、あらゆる業界・業種が推し進めるデジタルトランスフォーメーション(DX)を後押しする役割を果たし、安全保障上の重要性も増している。多くの国や地域が競争力の高い半導体産業を保有したいと考え、実際にあの手この手の支援政策を打ち出している。
そうした中、自国市場での伸び代と強力な財閥の存在を背景にした資金力、質と量共に豊富な人材力、政府の強力なリーダーシップなど総合的観点から、インドは次世代の半導体大国になる可能性が高いとみなされている。
需要が高まるインドの半導体市場
Custom Market Insightsによると、インドの2023年時点での半導体市場規模は343億ドルである。ただし、現時点では、国内に大規模な半導体工場、特に前工程は存在せず、消費する半導体のほとんどを輸入に頼っている状況だ。
今後、インドでの半導体市場(応用機器などでの消費規模)は平均年率20.1%のペースで成長し、2032年には約1002億ドルに達すると予測されている。足元ではスマートフォンやコンピュータなどでの需要が中心であり、これに加えて電気自動車(EV)や人工知能(AI)関連での需要が急増していく見込みである。
ちなみに2023年時点での日本の半導体市場の規模は約467億5000万ドルであり、インドよりも多く消費している。ただし、平均成長率は5%にとどまり、単純計算で2032年には725億ドルとなることから、インドの方が大きな半導体消費国になると予想されている。日本においても、国内産業の競争力の維持・強化に向けた半導体産業の再興への取り組みが進められている。付加価値の高い工業製品の中核部品である半導体の調達を輸入に頼る状態に危機感を感じるのは日本もインドも同じである。
インドのハイレベル理数系人材を積極活用する外資系企業
インドは、いわゆるSTEM(科学、技術、工学、数学)分野での大学の卒業生数で世界をリードしており、半導体産業に必要な高度な人材を豊富に供給できるポテンシャルを持っている(図1)。インドには5917もの工学・技術系教育機関が存在し、理工系の学部に進む学生の数は日本の約15倍とされている。近年、日本や韓国などでは理系志望者の上位層は医学部志向が強いが、インドではステータスと給与水準の高いIT産業や半導体産業の人気が極めて高い。

- [図1]インドは世界の理数系人材の供給源になっている
こうした豊富な人材力を活用すべく、アメリカのAMD、Qualcomm、Intel、Texas Instruments、スイスのSTMicroelectronicsなど、多くの外資系企業がインドに半導体の設計拠点を置いている。特にアメリカ企業は、英語が共用語であること、昼夜が逆の時間帯となり効率的な開発が進められること、現時点で国家間が対立関係にないことなどから、インドの人材を積極活用する傾向がある。
加えて地元にも、世界最大のITサービスプロバイダであるTata Consultancy Service(TCS)やInfosys、Wipro、HCL Technologies、Tech Mahindraなど、ICTや電気電子システム開発の分野でビジネスを展開する10万人以上の従業員を抱える巨大グローバル企業が複数ある。これらの企業は、半導体の設計や応用開発を推し進める技術力を既に保有している。つまり、高度な半導体の潜在的ニーズが高く、新たな半導体を自国内で独自開発していく素地もあるということだ。さらに、Moschip Semiconductor Technologiesといったファブレスの半導体メーカーも登場しており、スタートアップの活力も高い。
半導体の国内製造の整備に向けて支援制度を立ち上げ
インドのモディ首相は、「21世紀は技術主導の世紀であり、電子チップなしではインドの未来の発展を想像できない。Made in IndiaとDesign in Indiaのチップは、インドを自立に向かわせる大きな能力を生み出す」と、半導体産業がインドの技術的自立に不可欠であることを強調。産業育成に向けた継続的な支援と投資を行う方針を打ち出している。
2021年12月には「インド半導体ミッション(ISM)」を立ち上げ、7600億ルピー(約1兆3000億円)規模の支援制度を発表した。半導体の設計、製造、パッケージング、テストを国内で一貫して行うことができる体制を整備することを狙ったもので、工場設置に伴う設備投資の50%を補助金として供与する。設計拠点を置いているヨーロッパやアメリカの半導体メーカーも、インド国内での半導体製造体制の整備は、台湾や韓国に集中する現在の生産体制の地政学的リスクを軽減する観点から好感を持っている。
ISMの施行は、地元の大手財閥の積極的な投資も呼び込んでいる。特にTataグループは、電子機器製造受託サービス(EMS)やICTのコンサルティングやシステム開発サービスなど半導体応用ビジネスを多く保有しており、シナジー効果を狙って積極的だ。
「インド半導体ミッション(ISM)」の現状とこれから
2023年3月には、ISMの枠内で、総額1兆2600億ルピー(約2兆2790億円)の3つの大型プロジェクトが承認された。各プロジェクトには、現地企業だけでなく、日本を含む海外の企業も参画し、直ちに工場建設が開始された。
まず、Tata Electronicsと台湾のPowerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC)が、クジャラート州ドーレラに9100億ルピー(約1兆5860億円)を投じてインドで初めての前工程工場を建設する(図2)。月産5万枚の生産能力を立ち上げ、EV、高性能コンピュータ(HPC)、通信機器、防衛設備、民生用電子機器などに向けたチップの生産を目指すという。対応するプロセスノードは、28nm、40nm、55nm、90nm、110nmなどになる予定だ。

- [図2]Tataグループと台湾のPSMCが合弁し、いよいよ前工程での生産を開始
- 写真:AdobeStock
Tata Semiconductor Assembly and Test(TSAT)は、アッサム州モリガオンに、270億ルピー(約470億円)を投じて組立・テスト工場を建設している。生産能力は1日当たり最大4800万個であり、ここではフリップチップの実装やシステム・イン・パッケージ(SiP)の組み立てを行う計画である。
一方、CG Power and Industrial Solutionsは、ルネサスエレクトロニクスとタイのStars Microelectronicsと合弁で、クジャラート州サナンドに76億ルピー(約130億円)を投じて組立・テスト工場を設置する。この合弁は、外部半導体メーカーからの受託で組立・テストを行う専業企業のいわゆる「OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & Test)」になる。防衛設備、宇宙、EV、高速鉄道など、比較的専門性の高いニッチな分野に向けたチップを、日産最大1500万個の規模で生産する。
このほか、Micron Technologyがクジャラート州に27億5000万ドル(約4000億円)規模のDRAMとNAND型フラッシュメモリーを組立・テストする工場を建設中である。さらに、アナログICのファウンドリービジネスを展開しているイスラエルのTower Semiconductorも、80億ドル(約1兆1700億円)を投じて前工程工場を建設する計画案を提出している。インドでは複数の半導体工場の建設プロジェクトが、水面下で進行中だ。
爆発的な成長の実現に向けて、解決すべき課題とは
今後の急成長を予感させる状況証拠が多いインドの半導体産業だが、実際に成長していくために解決しておくべき課題は多い。

- [図3]ユーティリティとサプライチェーンの整備に課題
- 写真:AdobeStock
まず、インフラ整備が不十分な点が課題として挙がる(図3)。半導体工場の建設には広大な用地と安定した電力・水の供給が不可欠である。ところが、インドではこれらのインフラが脆弱なままである。さらに現状では、生産に必要な、ウエハーなどの材料、薬品、ガスなどの多くを輸入に頼っている。このため、グローバルなサプライチェーンが混乱すれば、大きなダメージを受ける可能性が残っている。これらの課題の解決は、インド政府のこれからの施策に注目だ。
また、豊富な理数系人材が存在することは確かなのだが、現時点では設計領域に偏っており、チップの量産に不可欠な物理・化学、半導体工学、プロセス生産技術などの知識を持つエンジニアがほとんどいないのが現状だ。だからこそ、ここを海外のインド系エンジニアを呼び寄せて、当面の人材育成の核にしようと考えている。
現在、台湾の半導体関連企業がインド企業との合弁に積極的だが、その背景のひとつに製造に強い台湾と設計と応用開発に強いインドは補完関係にあると考えていることがある。そうした意味では、半導体の生産能力を再興しようとしている日本も、インドとは補完関係を構築できる可能性がある。
アメリカのGAFAMの経営トップにインド系人材が多いことからもわかるように、ICT産業の中でのインドの存在感は既に大きい。近未来の半導体産業の中で、インドがどのようなポジションを獲得していくのか、またルネサスのように日本企業がいかなる形で関わっていくことになるのか目が離せない。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

