JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
SDVとは?クルマの未来を考える
- 文/津田 建二
- 2025.02.12
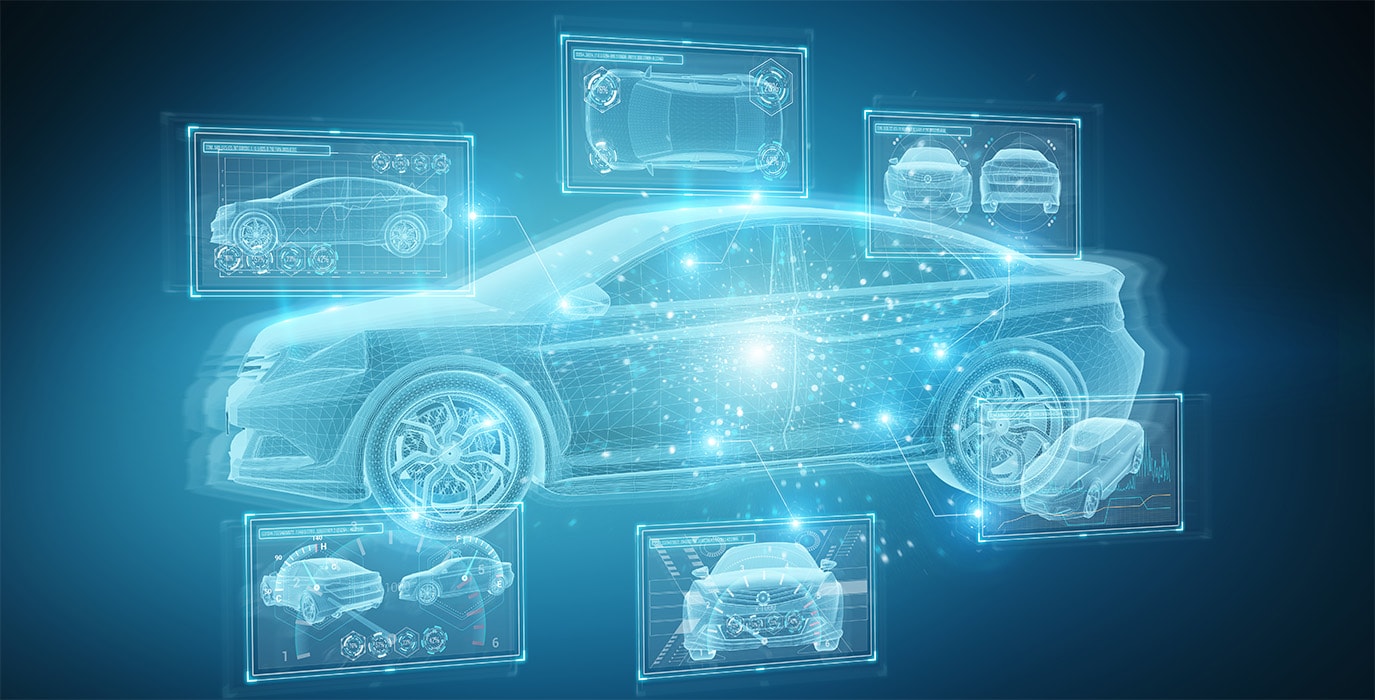
自動車業界で最近叫ばれているSDV(Software Defined Vehicle:ソフトウェア定義のクルマ)とはいったい何か。クルマをソフトウェアで定義するとは、どういう意味なのか。クルマには40年以上に渡りコンピュータが積まれてきた。そのコンピュータを中核にして、クルマ全体を再設計しようという考えのようだ。コンピュータは、ハードウェアという基盤(プラットフォーム)を作り、その上でソフトウェアをいろいろ取り替えると、さまざまな機能を実現する機械である。SDVの定義は、企業やメディアによってまちまちだが、企業がそのように呼ぶテクノロジーを紹介し、SDVとは何かを考えてみよう。
SDVとは何か
SDV(Software Defined Vehicle:ソフトウェア定義のクルマ)は、狭い意味では、基本的なハードウェアをプラットフォームとして、ソフトウェアで機能を変えたり追加したりするようなクルマ、と言える。
そもそも、SDX(ソフトウェア定義のX)は1990年代後半に、SDR(Software Defined Radio:ソフトウェア定義の無線)から始まった。ここでの無線とは、無線機のモデム(変復調器)のこと。デジタルラジオのモデム方式が国ごとに違うヨーロッパをクルマで移動する場合、別の国に入るとラジオが聴けなくなる。ラジオを聴くためには、それぞれの国のモデムをラジオに搭載しなくてはならない。これはコスト増になる上、装置も複雑になる。そこで、ラジオにコンピュータを導入し、デジタルモデムをソフトウェア化して、国ごとにソフトウェアを取り替えてラジオ放送を聴くことができるようにした。このテクノロジーをSDRと呼んでいた。
その後、SDX はSDN(Software Defined Network:ソフトウェア定義の通信ネットワーク)という言葉へも波及した。これも無線通信の基地局の設計概念を変えた。基地局の通信機器を基盤プレーンとデータプレーンに切り分け、基盤プレーンをハードウェアで構成し、データプレーンをコンピュータソフトウェアで構成することで、通信基地局内のハードウェアを1台でプラットフォームとして簡略化した。
その後、急速にSDXという言葉が広がり、現在、クルマもSDVと言われるようになったのである。クルマはコネクテッドカーと呼ばれるように外部と常に通信するようになり、ソフトウェアを更新するのは、OTA(Over The Air)と呼ばれる無線通信である。
コンピュータを中核にしたクルマを再定義し設計するために
クルマがコンピュータ化する現状
一方、車内のコンピュータ化も進化し続け、今やECU(電子制御ユニット)は、高級車で80~100個、大衆車でも20~40個搭載されるようになった。
ECUがクルマに初めて載ったのは1970年代だ。当時はエンジンの燃焼効率を上げることで排気ガスを制御しようと、最適な点火タイミングを選ぶためにECUを使った。その後、急ブレーキをかけても車が前につんのめりそうにならないようにするサスペンション制御、安定走行させるためのセンサー制御、さらに雨などの悪天候でのブレーキの空回りを防ぐためのABS(アンチブレーキングシステム)など、安全、事故の低減目的でのコンピュータ制御が徐々に増えてきた。
さらに、パワーウィンドウやブレーキランプ、ワイパーなどにもECUが搭載されるようになった。今さらクルマの窓開けに、手で取っ手を回すという行為を行う人はいないだろう。便利さを享受すれば、元には戻れないのだ。
安いマイコン(正確にはマイクロコントローラ:MCU)が登場し、ソフトウェアを書き換えるだけで、いろいろな電子制御を実現できるようになったため、ECUはどんどん増え続けた。今ではECUが多すぎる、という状態が目立ってきた。
再定義に必要な考え方
そこで、ドメインアーキテクチャとゾーンアーキテクチャという二つの考え方が出てきた(図1)。

- [図1]ゾーンアーキテクチャとドメインアーキテクチャ
- 出典:Marvell Technology
ゾーンアーキテクチャは、車内のゾーン内にある複数のECUを、一つのECUにまとめるもので、例えば、ブレーキをかけるABSとディスプレイECUを一緒にするように、近くにある機能をまとめてしまおうという考え方だ。こうすれば、配線ケーブルはすっきりし、軽量化につながる。
一方、ドメインアーキテクチャは、似たような機能を一つのコンピュータにまとめる考え方であり、例えば、インフォテインメント系は、カーナビやコックピット表示、映像データ処理などを、一つのECUにまとめ、ドメインコントローラとする。
日本ではドメインアーキテクチャが多いが、ヨーロッパではゾーンアーキテクチャに移行している。配線ケーブルのネットワークがシンプルになるからだ。
いずれの方式でもコンピュータ同士をまとめるために、仮想化技術を使う。これは大きな1台のコンピュータ(クルマ用ではマルチコアのSoC:システムオンチップ など)を複数台あるかのように見せるための技術である。データセンターなどでは、多数のコンピュータをつなげておき、「ハイパーバイザー」と呼ばれるソフトウェアで、利用するユーザーごとにコンピューティング能力を提供している(図2)。これと同様に、クルマの中のコンピュータを一つにまとめて、例えば、パワーウィンドウや駐車時に使うアラウンドビューモニター機能などへ、ハイパーバイザーで切り分けるのである。

- [図2]仮想化技術の概念
- ハイパーバイザーがユーザーごとのコンピュータに切り分ける。
- 出典:Blackberry QNX
ゾーンアーキテクチャにせよドメインアーキテクチャにせよ、このような仮想化コンピュータに用いる半導体には、CPUコアを複数集積したマルチコアSoCやハイエンドMCUなどが求められる。
さらに、車内のコンピュータと無線で接続するためのコネクティビティも重要になる。コンピュータに搭載されたソフトウェアを更新する際にOTAと呼ばれる無線通信を使うからだ。外部のクラウドコンピューティングとつながれば、車内のデータの処理、保存、再利用に加え、AI学習も利用できる。
再設計の概念
一方で、車が外部とつながると、車内のコンピュータを外部のハッカーをはじめとする攻撃者から守る必要がある。つまり、セキュリティをしっかり担保しなくてはならない。車内のコンピュータと車外とのコネクティビティを考慮した上で、クルマ全体のコンピュータを再構築することになる。
そこで、これからのクルマに必要なコンピュータシステムを再定義して、根本的に再設計することになる。現在、クルマで用いられるコンピュータの姿を図3に示す。

- [図3]SDVのイメージ
- クラウドからのデータは薄緑色のHPC1から入り、以下のHPC、あるいは紫色のゾーンコントローラにつながる。HPC1にはセキュリティのしっかりした半導体ICが必要になる。
- 出典:Infineon Technologies
現実のクルマはデータセンターのようなハイエンドコンピュータとは違う。クルマの想定寿命は15〜20年。従来なら機能アップは全くできなかった。しかし、クルマが走るコンピュータになれば、現実の15~20年の寿命は変えることができないものの、OTAを通じてソフトウェアをアップグレードすることで機能をアップできるようになる。
上のSDVの概念を確認したのは、2024年5月下旬に開催されたComputex Taipeiにおいて、NVIDIA(アメリカ)のJensun Huang CEOとMediaTek(台湾)のRick Tsai会長との対談の中であった。クルマの機能はSDVで向上できることを訴求していた。
SDVの実現には半導体メーカーの協力が必須に
では、SDVがどのような形から始まっているかを見てみよう。現時点では、自動車メーカーがSDVを作ったという段階ではなく、半導体メーカーがOEM(自動車メーカー)に対して、SDVに必要な半導体チップを提案している段階だ。自動車メーカーが半導体メーカーと提携するのはSDVを探っていると言えるだろう。CES 2025の基調講演の中で、NVIDIAのJensen Huang CEOがトヨタと提携したと述べたのはSDVへの道そのものだ。
クルマの運転手の前にあるスピードメーターとタコメーターに代わって、液晶や有機ELなどの平面ディスプレイが映し出す表示板をコックピットと呼ぶようになった。このディスプレイは、スピードメーターだけではなく、前方のクルマの拡大や、走行状態、バッテリ残量、レベル2あるいは3の自動運転表示など、クルマに関する情報を表示する。
将来のクルマは、コックピットをカーコンピュータのメイン表示板として対話するSDVになるだろう。例えばNVIDIAは、NVIDIA DRIVE AGXと呼ぶプラットフォームを、すでに開発している参考資料1。これは半導体チップ(ハードウェア)だけではなく、ソフトウェアも搭載した基本となるプラットフォームである。このプラットフォームを使って、自動車メーカーやティア1サプライヤは、自動運転機能や車内での没入体験を開発する。
NVIDIA DRIVE AGXは、ハードウェアとしても中央コンピュータとしても使えるOrinチップ、AIコックピットとADAS(先進ドライバ支援システム)を組み合わせられる次世代版の中央コンピュータのThor(ソアと発音)チップ、さらにこれらのチップを搭載したリファレンスデザイン回路ボードHyperionも用意しており、このボードに自動運転やAIベースの演算機能などを搭載している。Arm(イギリス)によると、Thorチップには次世代SDV向けCPUコアとして、Arm Neoverse-V3AEを集積しているという参考資料2。
これはもう完全にコンピュータそのものであり、ソフトウェアはNVIDIA DRIVE OSで動作するオープンなプラットフォームとなっている。このDRIVE OSには、効率よく並列処理コンピューティングするためのソフトウェアライブラリのCUDAや、リアルタイムでAI推論するためのTensorRT、そしてセンサー入力処理用のNvMediaを搭載している。DRIVE OS上で動作するミドルウェアのNVIDIA DriveWorksは、自動運転車の開発に必要な基本的なソフトウェアである。センサーデータ抽象化層(SAL)やDNN(ディープニューラルネットワーク)などのソフトウェアモジュールなどからできている。さらにAI支援の運転プラットフォームのNVIDIA Chauffeurは、高速道路も都市部の道路にも対応でき、出発点から目的地まで案内する。
Qualcomm(アメリカ)も、SDVに向けコックピットをもっと直感的に理解できることを狙った半導体チップ「Snapdragon Cockpit」を発表している参考資料3。このチップは、コンピューティング能力を高め、AI機能とクラウドへのコネクティビティに必要な処理能力を持ち、個人認証や便利さ、ハイレベルの安全性などを提供するという。先進的なGPUとAIエンジンを持ち、仮想化に対応するハイパーバイザーを使える豊富なソフトウェアスタックも備えているほか、自然言語処理やLLM(大規模言語モデル)、音声やタッチ動作可能なインターフェイスを持っている。MediaTekも同様なチップを開発するためNVIDIAと昨年提携した。
ソフトウェアベンダーも動く
車内システムのSDV化には半導体チップが必須であるが、自動車のデータが全てミッションクリティカルというわけではない。例えば道路の混雑状況や地図情報、デジタルキー管理などはクラウドベースで対応できれば良い。このような考えで、これからのSDVに向けソフトウェア開発を手掛ける、WirelessCar(スウェーデン)が、昨年秋に日本支社を設立した。
WirelessCarは、クルマとクラウドをつなぐコネクテッドカーのサービスを提供している。コネクテッドカーのソフトウェアAPI(Application Programming Interface)をビジネスとしてOEMに販売してきた実績がある。2012年にOEM5社と提携し、100万台のクルマにコネクテッドカーのソフトウェアを納入したが、2024年には1400万台のクルマに納入したという。日本支社を設立したことによって今後、日本のOEMとの関係を強化する。「クラウドベースのソフトウェアはミッションクリティカルではないが、日本のOEMはミッションクリティカルな製品に強いため、お互い相補関係を構築できる」とWirelessCarのNiklas Floren CEOは語る。
SDV用のソフトウェアを開発しやすくするため、SOAFEE(Scalable Open Architecture for Embedded Edge)と呼ぶコンソーシアムができ、ソフト開発を促進できるように標準化する動きもある。このコンソーシアムでは、できるだけオープンで共通化を図るため、3つの制約がある。一つは大衆車から高級車まで同じソフトウェアを使えるようにすること、二つ目はクラウドとエッジでのソフトウェアの一貫性を確保すること、3つ目は自動車全体のAI機能進化に対応させること、である。
半導体IP(知的財産)ベンダーであるArmが積極的にSOAFEEで活動しており、自動車のコンピュータ化に対応するArm Compute Subsystem(CSS)Automotiveを開発、2025年に提供する予定だ。
SDVの実用化に向けてコンソーシアムの役割が重要に
今後、SDVが実用化されたとき、5Gや5G Advancedのセルラー無線ネットワークはコネクテッドカーで重要な役割を演じる。自動運転のクルマ同士が通信するためにはリアルタイム通信が必須だからである。時刻も全てのクルマときっちり合わせる必要があるため、衛星信号を使った時刻の設定が5Gの規格にすでにある。車内コンピュータではリアルタイムOSとLinuxなどの通常のOSとの両方が求められる。SDV実用化に向け、コンピュータのソフトウェア、半導体チップ、IPベンダーなど、情報共有するコンソーシアムが果たす役割は大きい。
[ 参考資料 ]
- 1. “In-Vehicle Computing for AI-Defined Cars”, Self-Driving Vehicles, NVIDIA website.
- https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/in-vehicle-computing/
- 2. “The Tech Trends to Look Out For at CES 2025”, Arm Newsroom Blogs, December 18、2024
- https://newsroom.arm.com/blog/arm-tech-trends-ces-2025
- 3. “5G and the Next Generation of Software-Defined Vehicle Technology”, Autoraiders, January 6, 2025
- https://autoraiders.com/2025/01/06/5g-and-the-next-generation-of-software-defined-vehicle-technology/
- Writer
-
津田 建二(つだ けんじ)
-
国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。
現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。
30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。
半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。
- URL: http://newsandchips.com/

