JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
半導体性能向上の鍵を握る新技術「ハイブリッドボンディング」
- 文/伊藤 元昭
- 2025.05.07
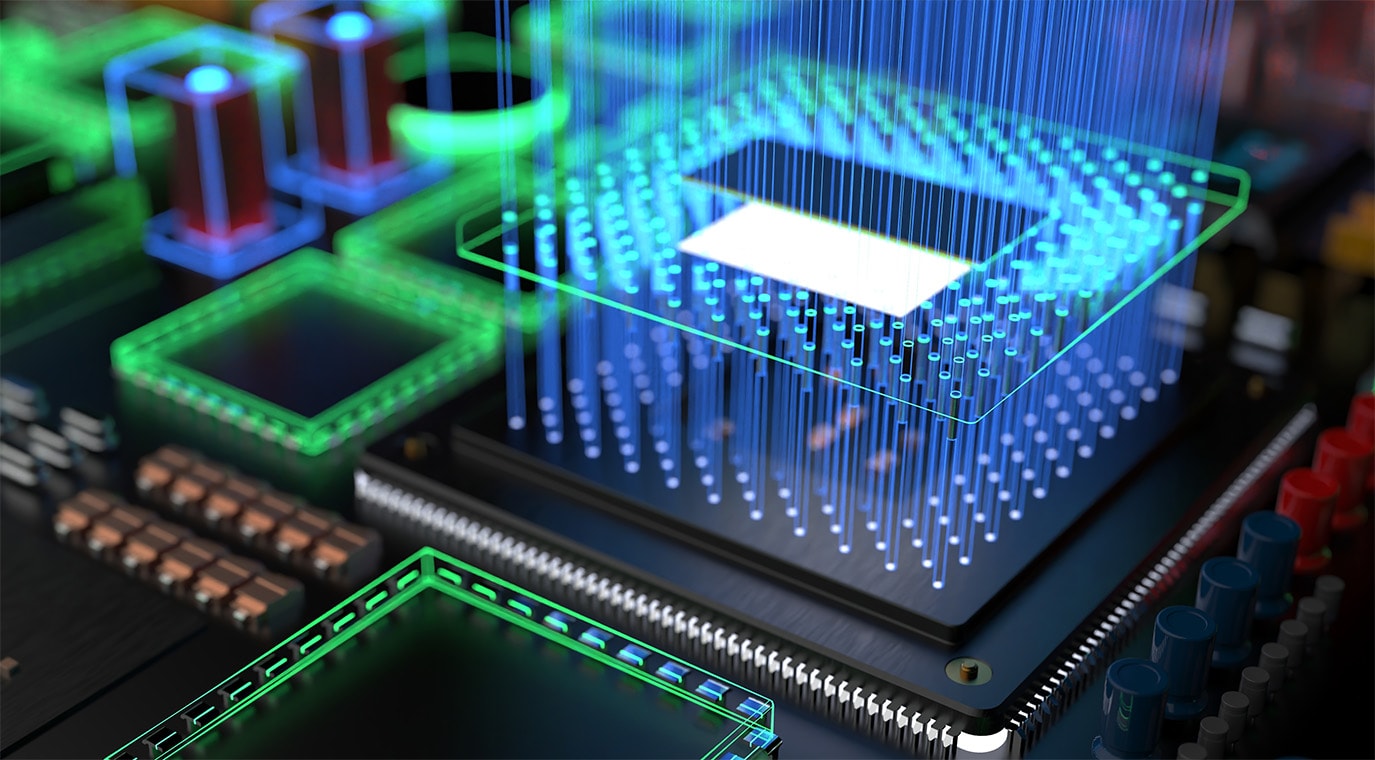
スマートフォンやサーバーなどに搭載するデジタル半導体チップの性能を、さらに高める技術として、「ハイブリッドボンディング」と呼ばれる、新たな配線接合技術に注目が集まっている。複数枚の半導体チップを積み重ねて3D積層する際に、チップ間でより大容量・高速・低消費電力なデータ伝送を可能にする技術である。さらなる電子回路の小型化にも貢献する。近年の人工知能(AI)の高度化と応用先の拡大に対応するために、データセンター用サーバーに搭載するプロセッサーやメモリーの、さらなる高性能化と低消費電力化が求められているのだ。ハイブリッドボンディングは、そうした要求に応えるための技術として期待されている。
微細化の進歩だけでは、デジタル半導体の性能向上が困難に
最先端デジタル半導体の性能向上には、チップ上に集積可能な回路の大規模化が不可欠である。演算器・記憶素子の数が多いほど、より複雑で高度な処理を実行できるからだ。
これまでの半導体産業では、電子回路の構成要素であるトランジスタや配線のサイズを2次元的に微細化していくことで、1個のチップ片(ダイ)上の集積度を継続的に高めてきた。高性能化に向けたこのアプローチは、半導体集積回路が発明されて以来、60年以上変わることなく連綿と適用され、「ムーアの法則」に沿った指数関数的な性能向上を実現してきた。
ところが近年、微細加工技術の進歩だけに頼った技術開発を推し進めるだけでは、デジタル半導体の進化が困難になってきた(図1)。微細加工を継続し、その効果を発現させるためには、チップレットや3D積層などの後工程での革新技術の併用が必須になりつつある。チップレットとは、まとまった大規模回路をあえて複数領域に個片化して微細トランジスタを形成し、各領域が完成した後にインターポーザ(配線だけを形成した基板)上に実装、相互接続して大規模回路を構成する技術。一方、3D積層とは、回路形成した複数のダイやチップレットを3次元的に積み重ねることで、より短い配線による高速・高密度・低消費電力な相互接続とデジタル半導体の小型化を実現する技術である。

- [図1]最先端の微細加工技術で半導体チップを作る際に併用すべき新技術
- 出典:経済産業省、「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」のラピダスの資料
こうした半導体の技術開発トレンドを背景にして、活発な技術開発が進められている新たな配線接合技術が「ハイブリッドボンディング」である。チップレットや3D積層の活用効果の、さらなる向上を促す技術として期待されている。
ハイブリッドボンディングとは、従来技術に対する利点
最先端デジタル半導体チップにチップレットや3D積層を適用するためには、必然的に、チップ同士もしくはチップレットとインターポーザの間を、相互に接続する技術を導入する必要がある。これまでの半導体製品では、こうした相互接続には、ワイヤーボンディングやフリップチップボンディングなどの接合技術を利用していた。ワイヤーボンディングとは細い金属製ワイヤーでつなぐ技術であり、フリップチップボンディングとはチップ表面に形成した微小なハンダの突起(バンプ)を介してつなぐ技術である。
これらは、いずれも多くの量産適用例が存在する信頼性の高い技術である。ただし、今後の半導体の、さらなる高性能化を見据えると、将来には適用が困難になってくる可能性が高い。接続ピッチ(端子の間隔)の高密度化が限界に達しつつあるからだ(図2)。現時点の見通しでは、ワイヤーボンディングでは50μm、フリップチップでは20μmが最小ピッチとみられている。加えて、チップ上に形成した主に銅(Cu)を素材とした微細配線とは異質な材料を介してつないでいるため、接合部の界面で抵抗値が高まり、データをやり取りする信号の高速化や低消費電力化、信頼性の確保を阻害する要因となる課題も抱えていた。

- [図2]チップレットや3D積層などを適用する際に利用する各相互接続技術の利害得失
- 作成:伊藤元昭、図中の写真はOrbray、Zeiss、imec
ハイブリッドボンディングならば、こうした従来技術が抱える問題点を解決できる。ハイブリッドボンディングでは、積層するチップそれぞれの表面に形成した配線(金属)領域と絶縁領域を、ワイヤーやバンプなどの中間的接続材料を介することなく、直接接続する。金属材料(一般的には銅(Cu))と絶縁材料(一般的には二酸化ケイ素(SiO2)もしくは窒化ケイ素(SiN))の両方を同時に接合することから、ハイブリッドボンディングと呼ばれている。
ハイブリッドボンディングならば、従来の接合手法よりも微細な10μm以下のピッチでの高密度接続を実現できる。0.4μmピッチの実現例もある。また、Cu同士を直接接続しているため、電気抵抗と静電容量がフリップチップなど従来接合手法よりも小さい。抵抗が小さければ電気信号がより流れやすくなり、静電容量が小さければ信号の遅延が抑制される。しかも、積み重ねられたチップ間のデータ伝送経路を短縮できるため、データ処理速度が大幅に向上できる。低抵抗化と伝送経路の短縮は、データ伝送の際に熱として失われるエネルギー損失も低減し、チップ全体の消費電力の削減に寄与する。
ハイブリッドボンディングの種類と接合工程
現時点で量産適用されているハイブリッドボンディングには、大きく2つの方式がある(図3)。
W2W 方式:W2W(Wafer to Wafer)と呼ぶ、ウェーハからダイを切り出していない状態のまま接合対象となるウェーハの対を積層し、接合する方法である。
D2W方式:D2W(Die to Wafer)と呼ぶ、回路形成後の切り出していないウェーハ上に、個片に切り出した後のダイを積層して接合する方式である。

- [図3]2つのハイブリッドボンディングの方式
- 作成:伊藤元昭
このうち、ウェーハ対を一括積層するW2Wは生産性に優れる。ただし、それぞれのウェーハ上に形成した回路に不良が含まれている場合もあるため、歩留まりが低くなる傾向がある。一方、D2Wは、接合対象の一方を1つずつ選別・積層していくため、生産性では劣る。ただし、良品のダイだけを選別して積層できるため、歩留まりは高い。チップレットをインターポーザに接合する場合には、必然的にD2W方式を適用することになる。
ハイブリッドボンディングの製造ラインでは、以下のような手順で接合していく。
- ① まず、接合対象となるダイやチップレット、インターポーザの接合面に、CMP(化学的機械的平坦化)や特殊な化学薬品を使った洗浄などの処理を施し、極めて平坦で清浄な状態にしておく。
- ② 次に、接合対象を正確に位置合わせしながら接触させ、温度、圧力、電界などを加えて、化学的・機械的に接合させる。
- ③ そして接合した後に、特定温度、一定時間の熱処理を施し、接合を強化して信頼性を高める。
- ④ 最後に、ウェーハから個々のチップを切り出し、結合後のチップをパッケージングしてデジタル半導体を完成させる。
AI関連処理の性能と消費電力のボトルネックは、チップ間データ伝送
歴史的には、ハイブリッドボンディングの技術開発と量産適用では日本企業がリードしてきた(図4)。量産する半導体製品に、最も早くハイブリッドボンディングを適用したのはソニーグループである。2016年に、イメージセンサーの製造における画素アレイチップと信号処理用ロジックチップを積層するためにW2W方式のハイブリッドボンディングを導入した。これによって、より優れた画像品質と多様な機能を実現している。現在では、9割以上のイメージセンサー製品において、配線部のみの直接接合もしくはハイブリッドボンディングが導入されている。

- [図4]ハイブリッドボンディングの多様な応用への適用例
- 作成:伊藤元昭、図中の写真はソニー、YMTC、AMD、SK Hynix
その後、2018年には中国のYangtze Memory Technology Corp(YMTC)が、NAND型フラッシュメモリーで、本来最適な製造条件が異なるCMOS回路とメモリーセルを分離製造する手法として導入。大容量化・高性能化を実現する技術として、量産適用した。キオクシアなども同様の技術開発を進めている。
そして現在では、AI関連処理やハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)などの領域への適用を想定し、さらなる高密度化を推し進めた技術の開発・適用が推し進められるようになった。すでに、日本、アメリカ、ヨーロッパ、台湾、韓国、中国などの企業間で、開発と量産適用の競争が始まっており、一部のサーバー用高性能CPUへの広帯域・大容量の3次キャッシュメモリーの導入などに利用され、量産適用されている。また、AIサーバーに導入されるGPU(Graphics Processing Unit)モジュール中に導入する「広帯域メモリー(High Bandwidth Memory:HBM)」では、2026年頃に市場投入予定の「HMB4」に、ハイブリッドボンディングが適用されるとみられている。
AI関連処理では、GPUなどのプロセッサーとメモリーの間でのデータ転送の頻度が高く、すでに転送処理がシステム全体の性能や消費電力に大きな影響を及ぼすようになった。そして、さらなる広帯域化・高速化と同時に、より低消費電力なデータ転送が強く求められている。ハイブリッドボンディングを適用すれば、こうした要求に応えることができる。
課題は低コスト化
2025年現在の時点で、ハイブリッドボンディングの製造コストは、フリップチップボンディングに比べて2〜3倍以上と高価である。微細な配線を高信頼に接合するためには、クラス100以下の極めて清潔なクリーンルーム環境が必須になるからだ。さらに、表面の平坦化にもチップ上に回路形成する前工程と同等の複雑で精密なプロセスが必須になる。加えて、接合面に露出する配線領域と絶縁領域の材料には、特に純度と均一性の高い材料の適用が求められ、この点も製造コストを押し上げる要因になる。
フリップチップなど従来の後工程の生産ラインは、これほど清浄な環境に置く必要がなかった。このため、フリップチップボンディングは主に後工程受託事業者(OSAT)が、ハイブリッドボンディングは前工程用のクリーンルームを備えるファウンドリーや垂直統合型半導体メーカー(IDM)が行うことが多い。ハイブリッドボンディングを活用して半導体製品を製造しているTSMC(台湾)やIntel(アメリカ)は、2025年内には製造コストを従来比で30%削減する目標を掲げ、製造技術の改善を推し進めている。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

