JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
量子コンピュータ最前線 ─ 4方式の量子チップそれぞれのメリットとは
- 文/ 伊藤 元昭
- 2025.08.13
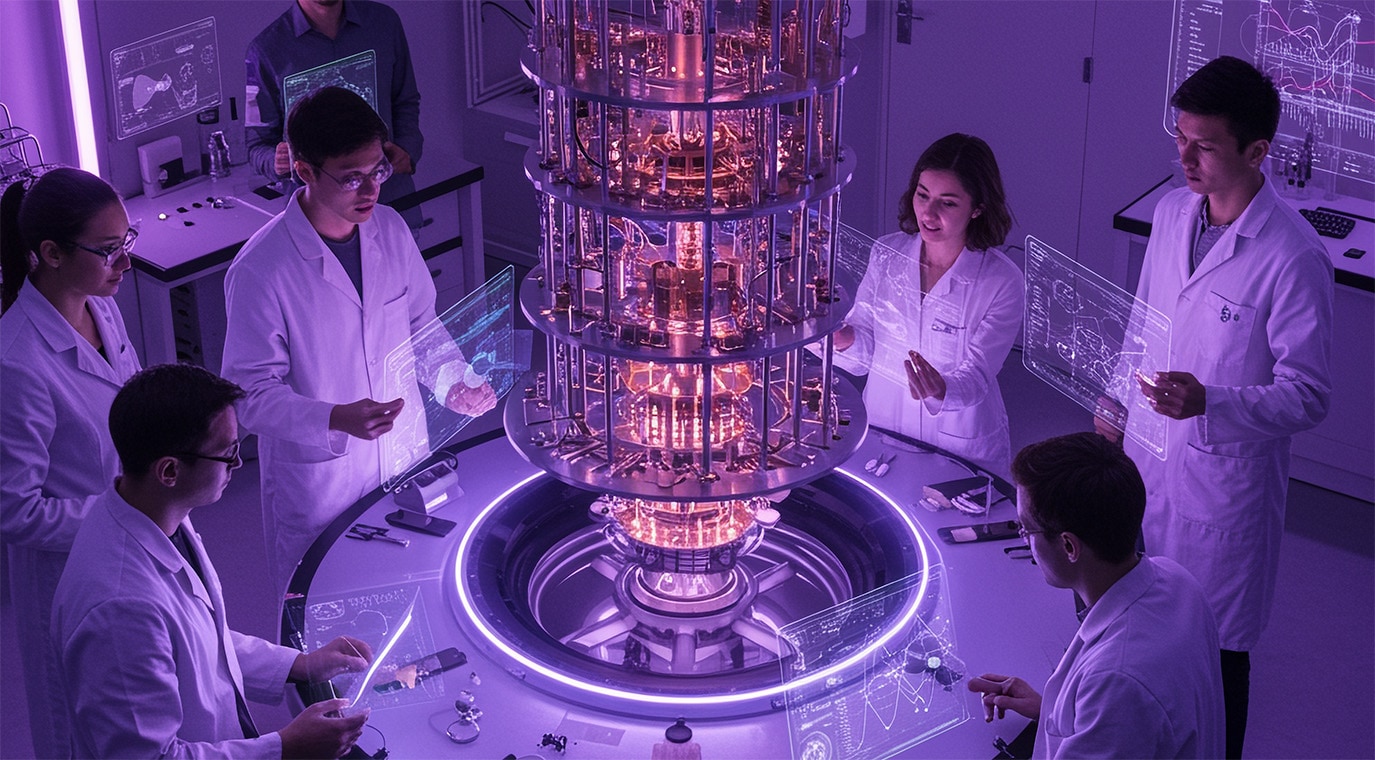
既存の最速コンピュータを使っても、天文学的に長い計算時間を要するような、莫大かつ複雑な処理を、一瞬で終えてしまうことができる可能性を秘めている量子コンピュータ。そんな夢の計算機が、いよいよ本格的活用の時代を迎えようとしている。その動きを加速させているのが、量子コンピュータの頭脳部となる「量子チップ」の著しい進化である(図1)。日々の生活からビジネス、社会システムまで、現代はコンピュータの活用なしでは全く成り立たない状態になってきている。そして今では、行政、法曹、農業、建設といった、これまでIT技術とは縁遠かった分野でも業務のデジタル化が進み、その重要性は高まる一方だ。劇的に進化した量子チップを搭載した量子コンピュータの活用領域が拡大することによって、私たちの暮らしや社会の身近なところでも大きなインパクトが及ぶことになりそうだ。
 |
 |
近未来のコンピュータを構成する3つの革新技術
現時点でのコンピュータ技術の開発最前線では、基本的な動作原理の刷新をも伴う、まさに100年に一度の大規模モデルチェンジが進行中である。既存のノイマン型コンピュータ(プロセッサとメモリーで構成されたハードウェア上で、ソフトウエアを動作させることで汎用的な処理を実行するコンピュータ)も順当に進化させながら、同時に新たに2つの新技術を用途に応じて複合的に使い分け、これまで対応できなかった処理を実現するというものだ。
新たに投入される技術の一つが、すでに多方面で大きなインパクトを生み出している人工知能(AI)。機械学習やディープラーニング(深層学習)の実用化によって、既に特定作業で人間を超える能力を実現できるようになった。直近では、言語やイメージなどを自在に操る生成AIへと進化した。今後は、さらに多様な用途に適用できて複合的な判断・意思決定が可能な汎用人工知能(AGI)や人工超知能(ASI)へと進化していくとみられている。
そして、これから新たに本格的活用のフェーズに入り、ケタ違いの情報処理能力によって革命的成果を上げることが確実視されている、もう一つの新技術が、量子コンピュータである。実用化直前の時点でのAIにおいて見られたように、現在の量子コンピュータの技術は “日進月歩”どころか“秒進分歩”で進歩しているような状態だ。そして、ノイマン型コンピュータではCPUの進化が、AIではAIアクセラレータの一種であるGPUの進化が、コンピュータの進化の核心であったのと同様に、量子コンピュータにおいても、量子チップの開発が、にわかに活発化してきている。その開発には多くの企業・研究機関が参入し、いかなる技術を保有する、どの企業が主導権を握るのだろうか。CPUのIntel(米国)やGPU(AIアクセラレータの一種)のNVIDIA(米国)のような、次世代の覇権を握るチップメーカーの座を争う競争が始まっている。
既存コンピュータ・AI・量子コンピュータには、それぞれ得手不得手がある
量子チップの技術開発動向を紹介する前に、まず近未来のコンピュータの中での量子コンピュータの位置付けを明確にしておきたい(図2)。現在の量子チップに求められている、ユーザーサイドからの要件を正確に把握しておく必要があるからだ。
処理内容に応じて、3つのコンピュータ技術を使い分け

| 用途カテゴリ | ノイマン型 | AI(機械学習/深層学習) | 量子コンピュータ |
|---|---|---|---|
| ① 一般業務処理(文書、表計算、管理) | ◎ | △ | × |
| ② 科学技術計算(流体解析、構造解析) | ◎ | △ | △(将来的に○) |
| ③ 制御システム(PLC、ロボット制御) | ◎ | ○(適応型制御) | × |
| ④ 音声・画像認識 | △ | ◎ | × |
| ⑤ 自然言語処理(翻訳、対話、要約) | △ | ◎ | × |
| ⑥ 異常検知(製造、セキュリティ) | ○ | ◎ | △ |
| ⑦ レコメンデーション(EC、広告) | △ | ◎ | × |
| ⑧ 医療診断支援(画像診断、病名予測) | △ | ◎ | × |
| ⑨ 暗号解読/因数分解 | × | × | ◎(Shorアルゴリズム) |
| ⑩ 最適化問題(ルート計画、ポートフォリオ) | ○(探索アルゴリズム) | △ | ◎(量子アニーリング等) |
| ⑪ 材料設計・分子シミュレーション | △ | △ | ◎(量子系に特化) |
| ⑫ 金融リスク計算・オプション評価 | ○ | ○(回帰・分類) | ◎(PoC進行中) |
| ⑬ ゲノム解析・創薬 | △ | ◎ | ○(特定領域でPoC進行中) |
| ⑭ ロジスティクス管理(在庫・倉庫配置) | ◎ | ○ | ○(将来的に強み) |
| ⑮ 教育・言語学習支援 | △ | ◎ | × |
- [図2]近未来のコンピュータを構成する3つの技術要素と使い分け
- 作成:伊藤元昭
「AIや量子コンピュータは、既存コンピュータに取って代わる存在である」。このように考えている人は意外と多い。しかし、これは一面では正しいと言える部分もあるものの、正しくないと言える部分も多い。実際には、将来においても、既存のノイマン型コンピュータは確実に使い続けられることになるからだ。ただし、既存コンピュータで実行していた処理の中には、AIや量子コンピュータで実行した方が飛躍的に高速化できる処理や、そもそも既存コンピュータでは実用的計算時間では実行できない処理も多い。
量子コンピュータには、大きく2つの方式がある。特定用途で極めて高い計算能力を持つ量子アニーリング方式と、多くの用途に適用可能な量子ゲート方式である。ただし、比較的汎用性が高い量子ゲート方式でも、既存のコンピュータや現在のAIに比べれば、応用適性の高い処理がはるかに限定的である。適用範囲内で、極めてピーキーな性能を持つのが量子コンピュータなのだ。また、量子コンピュータの処理の結果として得られる情報は、高確率で正解であると思われる解であり、必ずしも正解であることが確約されているわけではない。こうした一種のあいまいさを残している点はAIと同様であり、既存のコンピュータに対する大きな違いである。その一方で、量子コンピュータは、AIほど処理過程がブラックボックス化されているわけではない。このため、計算結果の背景を理解しやすい面がある。この点では、AIよりも、既存コンピュータの性質に近いと言える。
一般に、コンピュータで処理したい業務は、特徴の異なる複数の作業要素が複雑に組み合わされて構成されている。既存コンピュータとAI、量子コンピュータは、それぞれ応用適性が異なるため、応用に応じて使い分けて機能を相互補完していくことになる。さらに、既存コンピュータやAIが、量子コンピュータの能力の底上げや適用範囲の拡大に寄与したり、逆に量子コンピュータが、その他のコンピュータの能力を高めたりする面もある。
量子コンピュータの適用が向いているとされる処理として、以下のようなものが挙がる。まず、化学・材料科学における量子系の精密シミュレーション。自然界で起きている現象は、量子力学の法則に基づいて起きているため、その再現には同一原理で動く量子コンピュータが向いている。また、宅配便の配送経路やバイトのシフトスケジュールの最適化、金融サービスでのリスク評価やポートフォリオの最適化、交通渋滞を解消するための車両管制、公開鍵暗号の解読など、既存コンピュータでは現実的計算時間内では解が得られない高負荷な演算処理も量子コンピュータの適用が期待される分野である。状態の重ね合わせ表現が可能で、多様な状態を対象にした演算を並列実行できる特徴が生きるからだ。その一方で、従来のノイマン型は演算精度、制御、安定性が求められる決まった手順でのタスクで確実に強みがあり、AIは非構造データ(属性が明らかでない整理されていないデータ)からの意味抽出やパターン認識に強い。
ここで注意したい点は、量子コンピュータの適性が高い応用に宅配便の配送経路やバイトのシフトスケジュールなどが含まれていることからも分かるように、向いている計算が限定的でありながら、意外と身近なところで大きなインパクトを生み出す可能性があることだ。
ここまで紹介してきたように、近未来の情報処理では、3種類のコンピュータを適用先で求められる処理の特性に合わせて使い分けることになる。こうしたコンピュータの利用法を前提にすると、ユーザー自らが3種類を使い分けるのではなく、処理するタスクの性質に合わせて自動的に最適なハードへと割り振ってもらった方がありがたい。このため、データセンターに既存コンピュータとAI、量子コンピュータの3つを置いて、クラウドサービス側で最適運用する例が一般的になるとみられている。
また、近年では、データセンターに置くサーバーに搭載するCPUやAIアクセラレータを、クラウドサービスを提供する潤沢な資金力を持つIT企業が独自開発するトレンドが見られるようになった。量子チップも同様に、巨大IT企業主導で技術開発を進める潮流が見られる。
5軸の進化で、量子チップの利用シーンを拡大
ノイマン型コンピュータの発展ではCPUの進化が、AIの発展ではGPUの進化が、システムレベルの技術の進化や応用領域の拡大に極めて重要な役割を果たした。同様に、量子チップが進化することによって、量子コンピュータの実用性、経済性、応用可能領域は大きく広がることになりそうだ。進化は多軸で進むことになり、進化軸には以下のようなものがある(図3)。
| 技術要素/ 応用分野 |
医薬・材料設計 (分子シミュレーション) |
金融 (最適化・リスク評価) |
暗号 (RSA・格子暗号 など) |
AI・機械学習 (量子ML) |
ロジスティクス・ 交通計画 |
クラウド・ B2Bサービス |
組込機器・IoT・ 宇宙 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化軸 | ①動作温度 の向上 |
閉鎖空間不要の材料探索施設 | 常温環境での試算可能性 | 大きな影響なし | モバイルAI端末への実装 | 局所ノードでの運用可能 | データセンター冷却簡素化 | 宇宙探査機・ドローン搭載 |
| ②制御性の 向上 |
分子軌道計算の精度向上 | ポートフォリオ最適化精度向上 | スペクトル解析による暗号解析 | 高精度強化学習・量子NN | 信号経路・配送最適化精度向上 | クラウドAPIとして信頼性向上 | 安定制御で小型化しやすい | |
| ③CMOS製造互換性 | 医療分析機器への組み込み | 金融業務向けASICとの統合 | 暗号解読 アクセラレータ集積 |
AIチップとの協調処理 | エッジ最適化チップと統合可能 | FPGAとの共存・設計資産活用 | 民生機器・IoTでの普及容易化 | |
| ④スケーラビリティ | タンパク質・創薬候補の網羅的計算 | 金融市場全体シナリオ解析 | RSA4096ビット解読など現実化 | 超大規模モデル学習 | グローバル最適化可能 | 大規模ユーザー対応 クラウド量子基盤 |
エッジ-クラウド 連携基盤 |
|
| ⑤エラー率 の改善 |
誤差の少ない新薬スクリーニング | 商用利用可能な金融分析 | 信頼性のある量子攻撃対策評価 | 実機での安定学習・推論 | 安定動作による長期計画最適化 | SLA保証付きの量子API | コンパクトな量子演算モジュール | |
- [図3]量子チップの進化軸となる5つの技術要素と、それぞれ応用に与えるインパクト
- 作成:伊藤元昭
まずは、動作温度の向上である。現在、試作されている量子チップの多くは、動作環境の温度を数mK(ケルビン) 〜数Kといった極低温に下げて利用する必要がある。このため、大型の極低温冷却装置の適用が必要になる。動作環境を数十K、理想的には室温近傍にまで高めることができれば、量子コンピュータのコストは劇的に低減し、設置場所の制約も緩和される。さらに将来的には、ロボットや医療機器などに組み込んで処理を実行するエッジ量子コンピュータへと進化する道が拓かれ、応用現場での手軽な活用が可能になる。
次に、量子ビット数の拡大や配線の最適化によるスケーラビリティ(多量子ビット化)の向上。演算に適用可能な量子ビットの数が現時点の1000量子ビットから100万量子ビットといった多ビット化が実現すれば、より複雑なアルゴリズムの実行が可能になる。これによって、より大規模な最適化・組み合わせ問題を解けるようになり、RSA暗号の解読や巨大分子の精密解析や、より複雑な状況を対象にした都市交通や物流網の設計などへの適用が可能になってくる。
さらに、エラー訂正不要な方式もしくは効果的エラー訂正手法の導入によるエラー率の改善も重要な進化軸である。実現できれば、1000量子ビットの論理ビットを、数量子ビットの物理ビットで構成できるようになる。これによって、量子コンピュータ全体のハードウェア規模を縮小することが可能になり、同時に演算速度も高まる。こうした改善が続けば、量子AIや量子通信のリアルタイム処理が可能になり、中小企業や小規模な研究所などでも量子計算を利用可能になる可能性が出てくる。
また、ゲート精度・読み出し精度・クロック安定性といった制御性の向上に向けた技術開発も進められている。制御性の改善は、量子演算の精度向上や実行可能なアルゴリズムの拡大に直結する要素である。この部分の技術開発が進めば、医薬・素材設計で用いる化学シミュレーションの精度向上や、金融分野でのリスク評価やポートフォリオ最適化に用いるモデルの高精度化、機械学習の強化学習系への応用加速が実現する。
そして、既存の半導体チップを作る際のCMOSプロセスとの製造互換性の向上も注目されている進化軸の一つである。実現すれば、量子ビットとCMOS制御回路CMOSを1チップ化した統合製造が可能になる。量子チップをCPUやGPUと統合したり、標準的な半導体チップの設計フローと統合したりして、民生用や組み込み用途への展開が実現する可能性が拓かれる。さらに、既存ファウンドリでの大規模なチップ量産による低コスト化も実現する。
提案されている特徴が異なる4方式の量子チップ
一般に、量子コンピュータの頭脳部である量子チップは、CPUやGPUなどデジタル半導体チップとは根本的に異なる材料・構造・動作原理で作られている。そして現時点では、動作が高速な「超伝導方式」、従来の半導体製造ラインで生産できる可能性が高い「半導体量子ドット方式」、誤り率が極めて低く高精度計算が可能な「イオントラップ方式」、室温での動作が可能な「光方式」といった、大きく4種類の方式の量子チップが提案され、それぞれ個別に技術開発が進められている(図4、図5)。
 |
 |
 |
 |
このうち、超伝導方式は、米国のGoogleやIBMが技術開発をリードしている。最初に開発・試作が進められた量子コンピュータに搭載されたチップがこの方式である。超伝導回路のマクロな電気状態(電流や電圧の波動関数)を利用して量子ビットの状態を表現。チップは、アルミニウムやニオブ、酸化アルミニウムなどの材料で作られたジョセフソン接合素子や共振回路などを集積して構成し、マイクロ波信号によって量子ゲートを制御して動作させる。ただし、この方式のチップは、超伝導状態を維持するために極低温で動作させる必要があり、この点がコストを押し上げる要因のひとつになっている。より大規模な演算への適用に向けたスケーラビリティはほどほどであり、現在で数百〜千量子ビット規模のチップが試作されている。ただし、エラー率は比較的高めであり、利用に際してはエラー訂正の併用が必須になる。この点が、実用化に向けた最大の壁になる。
| 比較項目 | 超伝導方式 | 半導体量子ドット方式 | イオントラップ方式 | 光方式 | 従来の半導体チップ(CPU/GPU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算単位 | 量子ビット(超伝導回路の電流や電圧の波動関数でのマクロ電気状態) | 量子ビット(電子スピン) | 量子ビット(イオンの内部状態) | 量子ビット(光子の状態) | 古典ビット(電圧の0または1) |
| 重ね合わせ・もつれ | あり | あり | あり | あり | なし(0または1) |
| 主な材料 | アルミニウム、ニオブ | 高純度シリコン、ゲルマニウム等 | 金属イオン、電極 | シリコン、窒化シリコン、BBO、KTP、Nd YAG結晶など | シリコン、銅、絶縁膜、SiGe等 |
| 構造 | ジョセフソン接合、共振回路 | ナノ電極による量子ドット | 電極+イオン浮遊構造 | 光導波路、非線形光学結晶、レーザーなどの光回路 | トランジスタ(CMOS) |
| 動作温度 | 極低温(〜10 mK) | 極低温(10〜100 mK) | 低温~室温(〜10 K) | 室温で動作可能 | 常温または高温(〜100℃) |
| 制御方式 | マイクロ波 | 電場・マイクロ波 | レーザー光 | レーザー光(偏光・経路など) | 電圧・電流制御 |
| 製造プロセス互換性 | 一部対応 | 高い(CMOS互換) | 低い(MEMS系) | 中(フォトニック集積回路技術) | 完全対応(CMOS) |
| スケーラビリティ | 中(数百〜千量子ビット) | 高(将来の大規模化に期待) | 低〜中(精度は高いが大型化困難) | 高(フォトニックチップ化が鍵) | 非常に高い(数十億トランジスタ) |
| エラー率(忠実度) | 中(エラー訂正必要) | 中(エラー訂正必要) | 低(忠実度高) | 中(損失低減が課題) | 非常に低い |
| 主な用途 | 最適化、量子化学、誤り訂正実証 | 集積化実験、将来の量産候補 | 高精度量子演算、標準器等 | 通信・分散量子計算、計測 | 汎用処理、AI、グラフィックス等 |
| 課題 | 冷却・拡張性・安定性 | 読み出し精度・制御の困難 | レーザー制御、スケーラビリティ | 損失、光源の安定性、量産性 | 消費電力、ムーアの法則の限界 |
- [図5]4方式の量子チップそれぞれの特徴
- 作成:伊藤元昭
IBMは、量子コンピューティングのパイオニアであり、長年にわたり自社開発した量子コンピュータをクラウド経由で一般に公開してきた。そこに搭載されている量子チップも自社開発しており、超伝導方式を採用している。同社は詳細な技術ロードマップを公表しており、2029年までには計算エラーを自動的に訂正できる「フォールトトレラント(耐障害性)量子コンピュータ」を、そして2033年までに10万量子ビットのシステムを実現するという目標を掲げている。一方、同じく超伝導方式を採用するGoogleは、2019年に「量子超越性」、すなわち特定の計算において量子コンピュータが世界最速のスーパーコンピュータの性能に勝ったことを実証したことで知られる 。Googleもまた、超伝導方式によるフォールトトレラント量子コンピュータの構築に注力しており、2029年までに1000論理量子ビット(エラー訂正後の実用的な量子ビット)の実現を目標としている。さらに、AIアクセラレータであるGPUの最大手NVIDIAと提携し、量子AIプロセッサの共同開発にも乗り出している。
半導体量子ドット方式は、Intelや世界的半導体技術の研究機関であるベルギーのimec、理化学研究所などが技術開発をリードしている。この方式は、電子スピンの状態を量子ビットとして利用。極低温環境下で、電場やマイクロ波によって電子スピンを制御して動作させる。ただし、制御難易度は高い。チップには、既存の半導体チップと同様の高純度シリコンやゲルマニウム、酸化膜などの材料で作られたナノ電極による量子ドットやスピントラップなどが集積されている。製造プロセスは、既存のCMOS半導体プロセスとの互換性が高く、微細加工技術の転用による集積度の向上が期待されている。ただし、エラー率は比較的高く、利用に際してはエラー訂正の併用が必須になる。
イオントラップ方式は、米国のスタートアップ企業であるIonQやQuantinuumなどが技術開発をリードしている傾向が見られる。この方式は、浮遊イオンの内部状態を量子ビットとして利用。10K程度と比較的緩やかな低温から室温での動作が可能であり、レーザー光によって量子状態を制御することで動作させる。金属イオン(Yb+やCa+など)や金属薄膜電極などの材料で作られたイオントラップや、制御用レーザーなどを集積してチップが構成されている。この方式の最大の特徴は、量子状態の保持時間(コヒーレンス時間)が長く、計算エラー率が極めて低い「高忠実度」な演算が可能となること。計算の正確性が何よりも重視されるアルゴリズムの実行において大きな利点である。その一方で、量子ビットのスケーラビリティは低く、1〜100量子ビットのチップの試作にとどまっている。光学制御が複雑である点も、課題となっている。また、製造プロセスには、MEMSと同様の加工と真空デバイス技術が必要になり、新たな技術開発項目が多い。ちなみに、イオントラップ方式は米国のクラウドサービスの大手に好まれる傾向があり、Amazon Web Services (AWS) はIonQなどの、MicrosoftはIonQとQuantinuumなどのハードを利用したサービスを提供している。
光方式は、光子の状態(偏光、位相、経路など)で量子ビットを表現する。PsiQuantum(米国)、Xanadu(カナダ)といったスタートアップに加え、NTTなどが技術開発している。非線形光学結晶、導波路、レーザーなどで構成された光回路を演算器として用いて、レーザー光の偏光・経路などで制御する。最大の特徴は、演算時に熱をほとんど発生せず、室温での動作が可能な点である。スケーラビリティも高い。ノイズには比較的強く、エラー率は中程度。シリコン基板上に光回路を形成するため、CMOSプロセスとの互換性はある程度あるが、新規導入すべき工程も複数ある。実用化に向けた課題は、損失の低減、光源の安定性、量産性などである。
現時点で、4方式にはそれぞれ利害得失があり、それが動作原理に即した本質的な特徴となっている面がある。このため、将来的には4方式を併用し、量子コンピュータに向いたタスクを4方式の中から最適なものに振り分けて演算を実行することになる可能性がある。4方式はチップの材料やチップ内の素子・回路の構造と構成、さらには製造プロセスが異なっている面があるため、量子チップの製造では多品種少量生産になり、この点が技術開発投資や設備投資の分散を招く要因になるかもしれない。未来に向けて、ブレイクスルー技術の開発による、4方式それぞれのメリットを兼ね備えた量子チップの実現が渇望されている。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

