JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
コンピュータ・半導体・通信の歴史と未来 ─
AI時代を見据えて
- 文/津田 建二
- 2025.09.10
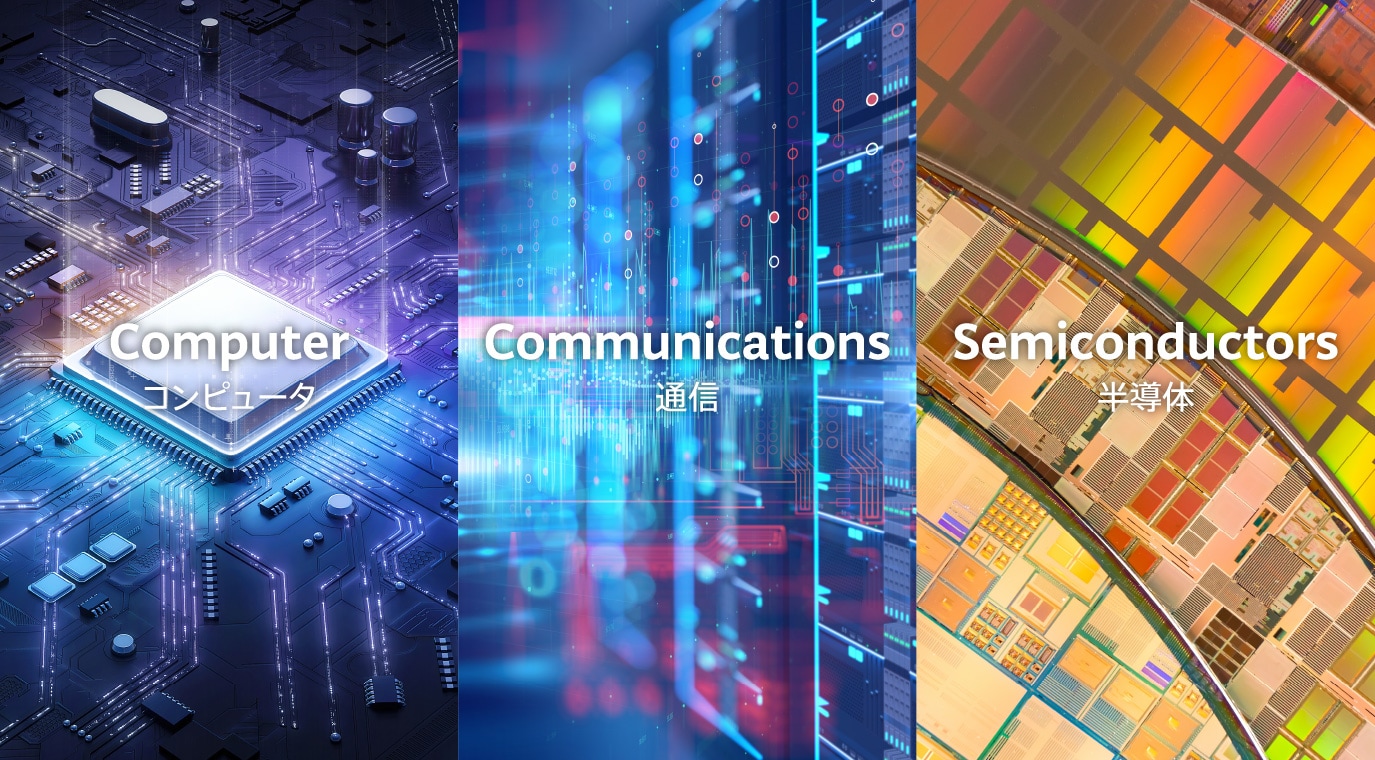
IT(Information Technology)を構成する3大要素は、コンピュータ、通信、半導体、と言えるだろう。これらの内どれ一つが欠けてもITとして機能しない。もちろん、コンピュータと通信技術がなければITとは言えない。さらに半導体は、コンピュータも通信機器も支える重要なデバイスになっている。半導体回路には小規模であれ大規模であれ、コンピュータ技術や、入出力データをやり取り、すなわち通信する技術も集積されている。これらの3大要素はどのようにして発展し、ITをけん引するようになってきたのか、振り返ってみたい。
最近は、ITという言葉を使わず、デジタル化、あるいはデジタルという言葉を使うようになった。しかし、技術から見るとデジタルという言葉は正確ではない。ITシステムには、アナログ半導体が大量に使われているからだ。デジタルトランスフォーメーション(DX)は、IoTのようなセンサを複数用いて、センサからのアナログ信号をデジタルに変換し、さまざまなセンサデータの意味をアルゴリズムで表現して、人間の世界にわかりやすいように翻訳している。私たちは、その翻訳されたデータ(=情報)を見て改善・改良に取り組むことができるのだ。
しかも、デジタルやDXという表現は、海外企業のウェブサイトではあまり見かけない。むしろ昔からのITという言葉の方が一般的だ。ITという言葉には、ソフトウェアだけではなくハードウェアや半導体、電子機器製造請負など電子技術も含んでいる。例えば台湾ではIT企業の月次売上額報告が行なわれているが、そのIT企業の中にパソコンメーカーは言うまでもないが、TSMCもあればEMS(電子機器製造の請負サービス企業)の鴻海精密工業もある。
コンピュータの役割とは
コンピュータは単なる計算機ではない。データや信号の流れを右や左に変えたり、また、いずれに送るべきかを判断したりする「制御」という機能も含む。台湾やシンガポールではコンピュータを「計算機」と「電脳」という二つの言葉で使い分けている。演算は計算機、制御も含むと電脳となる。コンピュータの中核をなすCPUは主に演算命令と制御命令を持つ。
また、コンピュータは、1台のハードウェア(最近ではプラットフォームという言い方をする)上で、さまざまなソフトウェアを走らせることによって、さまざまな機能を実現するシステムである。計算や制御を行うデータや命令を記憶させるために送り込む機能、受け取る機能、すなわち通信機能も備えている。コンピュータと通信は切っても切れない関係にある。そのハードウェアは共に半導体ICで作られている。だからこそ、半導体とコンピュータは切っても切れない関係にある。
半導体ユーザーは電機からITへ
通信システムでは有線の黒電話がなくなり、無線のモバイル通信が主流になった。残った有線もほとんどが光ファイバに置き換えられた。光ファイバは、幹線となる基地局同士をつなぐ重要なデバイスから、基地局内の通信機器同士をつなぐだけではなく、コンピュータが大量に並んだデータセンター内のコンピュータラック同士をつなぐように広がっている。
かつて半導体を購入していたのは電機企業であり、ソニー、パナソニック、東芝、日立などが並んでいた。ところが今は米国のDellやH-P、Apple、中国のLenovo、韓国のSamsungなどパソコンやスマートフォンなどのIT機器を製造している企業に加え、鴻海精密などのEMS企業などが並ぶ(表1)。日本の電機はソニー1社しかない。半導体ユーザーが明らかに電機からITに変わったのだ。

- [表1]半導体購入額のトップ10社はスマホやパソコンなどのIT企業が多い
- 出典:Gartner
デジタルの本質を見抜けなかった電機
その動きは2000年頃から現れていた。アナログ技術の粋を集めたVTR(ビデオテープレコーダー)からCDプレイヤー、さらにDVDプレイヤーへとデジタル化にシフトした時に、日本の電機メーカーは、これまでのアナログ手法でCDやDVDに対応したため、デジタルの本質を見抜くことができなかった。つまり、アップデート可能、データ圧縮可能、誤り訂正可能、というデジタル特有の特長を生かせなかった。
VTRの読み出しヘッドの角度調整は難しく、日本の電機メーカーが長年築いてきたアナログ技術の粋は秘中の秘となり、日本はこの大事な技術を守ってきた。このためアジア勢はそう簡単にVTRを作れなかったが、デジタル化に代わったとたんに作れるようになった。このあたりの事情は、元東京大学教授の藤本隆宏教授グループが詳細に研究している参考資料1ので、こちらを参考していただきたい。
現代のプラットフォームがCPU
現在はコンピュータがさまざまな電子製品に入るようになっている。CPUというプラットフォームを持ち、さまざまなソフトウェアをその上で走らせることで、さまざまな電子製品を作ることができる。アナログや標準ロジックだけで電子製品を作ろうとするなら、製品ごとにアナログ回路とデジタル回路を作り込む必要がある。しかしCPUというハードウェアの上にソフトウェアで製品を定義すれば、一つのCPUから様々な電子製品を作り込むことができる。
CPUは、コンピュータそのものであり、半導体で作られている。マイクロプロセッサは言うまでもなく、マイコンも携帯電話用のアプリケーションプロセッサ(またはモバイルプロセッサ)などもCPUを集積しており、コンピュータの中核であると同時に半導体チップでもある。
半導体ユーザーが電機からIT企業へと移ったということは、電子製品がアナログからCPUベースの製品に移ったという意味である。共通のCPUベースのプラットフォームに、ソフトウェアで差別化する時代に移ってきたのである。最近、聞かれるようになったソフトウェア定義のXというSD-Xは、まさにコンピュータ化の意味に他ならない。
IT3大要素のバックキャスト
ITの3大要素がどうやって発展してきたのか、バックキャストしてみよう。図1はコンピュータと通信と半導体の進化を表したものである。筆者がそれぞれの歴史的な発展をいくつかピックアップしたもので、抜けている点があるかも知れないが、重要な出来事は網羅したつもりである。
- コンピュータ
- 半導体
- 通信
| インターネット サービス |
セキュリティ サービス |
||||||
| ミニコン、オフコン、WSの全盛 | PC加速、インターネット勃興 | インターネット成長 | ビッグデータ/クラウド | クラウドの普及/コンピュータの多様化 | |||
| メインフレーム全盛 |
DRAM隆盛
|
MPU性能優先
|
マルチコア、Arm
|
モバイルプロセッサ、NAND
|
ハード/ソフト融合、セキュリティ | ||
| IBM360 |
MPUとメモリの
発明 |
有線、無線のデジタル通信 | データ速度加速 | Broadband Mobile Wireless | デジタル通信高速化、スマホ全盛 | 5G時代、光ファイバの普及 | |
|
ICの発明
|
デジタル通信勃興期 |
IoT、センサ知能化
|
AIチップ、RISC-V、ファウンドリ
|
||||
| 三つの発明の 勃興期 |
アナログ電話機 |
半導体がシステムの中心に
|
|||||
| 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 |
| 技術の誕生期と揺籃期 | 技術開発の時代 | ムーアの法則の時代 | PCの時代 | インターネット時代 | モバイル時代 | AI時代の揺籃期 | |
- [図1]1946~48年に生まれたコンピュータ・半導体・通信の進展
- 作成:津田建二
ペンシルバニア大学にいたジョン・エッカートとジョン・モークリーによって1946年に発明されたENIACが最初の電子式コンピュータと言われている。半導体は、電流を自由に制御できる3端子のトランジスタの発明が最初といってよいだろう。また通信技術は、現在につながるデジタル通信の理論をベル研究所のクロード・シャノンが1948年に提唱した。いずれも第二次世界大戦後の1946~48年に集中して発明された技術であり、今日のIT技術の基礎となったことは興味深い。
本格的なコンピュータはIBM360から
初期のコンピュータは、真空管で動作させていたが、真空管の寿命が短いため、何千本もある真空管を取り替える作業に明け暮れていたという。このため真空管のように電子を制御できる固体の3端子素子(トランジスタ)を強く求めた。1953年に最初のトランジスタ式のコンピュータをマンチェスター大学が発明したと言われているが、産業的に大きなインパクトを与えたコンピュータは1964年にリリースした米国のIBM System/360だと言われている。
IBM 360は、1960年代を代表するコンピュータであり、新しいトランジスタで製造されていた。トランジスタを組み合わせてCPUボードを設計・作製し、これがコンピュータの心臓部となっていた。1970年代もメインフレーム時代が続き、80年代にはワークステーションやミニコン、オフコンなどが活躍した。80年代後半から90年代にはパソコンがオフィスでも活動し始め、1995年のWindows95の登場でパソコン全盛時代になった。その後はインターネットの成長と共にパソコンも成長し、2010年前後からクラウドコンピュータが始まった。
半導体は材料名からICへ
半導体は元々材料の名前だった。その材料物性は1800年代からさまざまな学者によって調べられていたが、今日の半導体はトランジスタの発明によって電流を自由に制御できるようになった。このトランジスタは、1947年にアメリカのベル研究所にいたジョン・バーディーンとウォルター・ブラッテンによって試作され、増幅作用も示した。上司のウィリアム・ショックレイが出張中に発見したこともあり、ショックレイは最初の点接触トランジスタでは工業化できないとして工業化に適した接合型トランジスタのアイデアを翌年生み出した。この3人が後にノーベル賞を受賞した。
その後、米国のTexas Instruments(TI)のジャック・キルビーとFairchild Semiconductorにいたロバート・ノイスが別々に集積回路(IC)を発明、半導体はトランジスタから集積回路へと発展した。1965年にはやはりFairchild Semiconductorのゴードン・ムーアが集積化の方向に気づき、「ICの集積度は毎年2倍で増加する」という法則を提唱した。いわゆるムーアの法則である。
1971年には米国のIntelがマイクロプロセッサとメモリーを発明し、当初の4ビットのi4004から8ビット、16ビット、そして32ビットの複雑なマイクロプロセッサまで作り上げると、ワークステーションなどのコンピュータメーカーは、標準ロジックやゲートアレイなどの組み合わせでCPUボードを作るよりも、32ビットチップを購入してコンピュータを作る方が早いことに気がついた。この1990年前後から、コンピュータの性能を支配するのがコンピュータメーカーから半導体メーカーに移った。
特にMOSトランジスタは集積化に向き、微細化すればするほど小型化だけではなく、高性能化、低消費電力化も同時に実現することにIBMのロバート・デナードらが気づいた。このため集積化は微細化によって推進されてきた。デザインルールはi4004の10µmから始まり、3µm頃には、光の波長限界に近い1µmくらいが限界だろうとIEDM(国際電子デバイス会議)などで真剣に議論された。しかし、ディープUVと言われるg線、i線を越え、エキシマレーザー(KrFやArF)などの短波長光に進展、さらに光源の形状や化学増幅レジスト、液浸などの技術が開発され、波長限界を超えた。半導体は今やICを指す言葉となった。
通信はモバイル時代から半導体ICが中核に
通信と半導体の関係は、コンピュータよりも遅かった。1960年代、70年代はアナログ方式黒電話の全盛期であり、半導体はほとんど使われていなかった。通信基地局のある電子交換機や基地局同士を接続する中継器などに使われていただけにすぎなかったのだ。それでも日本と米国を結ぶ海底中継器向けの半導体は70年前後から開発されていた。
それが1980年代にプッシュホンが採用されると半導体が大量に使われ、さらに90年代に携帯電話が登場すると半導体が通信技術の中核となった。携帯電話は初期のアナログ式からデジタル式に代わり、さらにブロードバンド化、3G、4G、5Gへと進んだ。携帯電話とインターネットが結び付き、さらなる高速化を求める声が高まると共に、基地局側でももっとデータレートを速めなければ多数のユーザーが同時に使う状況に対応できなくなった。5Gになりデータレートは最大10Gbpsとなり、多数の人たちが同時に使ってもスピードはさほど落ちなくなった。しかも人口カバー率は95%以上になった。
スマートフォンのような小さな筐体の中に、かつての基地局以上の機能を載せるためには半導体の高集積化以外に手段はない。このため、スマホは半導体の微細化をけん引する応用製品となった。そして現在では、コンピュータ、通信、半導体は切っても切れない関係となったのである。
これからの行く先; AIの広がり
コンピュータの所で書き忘れたように見えるが、AIの登場はこれから先の状況を占う上で極めて重要な出来事である。自然言語処理や画像認識などのコンピュータ技術に、人間の脳の中にあるニューラルネットワーク(神経網)のモデルを使ったディープラーニングモデル、すなわちAIがこれまでとは異なる力を発揮しているからだ。単なるコンピュータ技術からあらゆる分野(農業から漁業、鉱業、製造業、サービス業、医療、航空宇宙、ロボットなどあらゆる産業)に使えることがわかってきたのだ。しかも従来よりも業務効率を上げられそうだ。
全ての産業にAIが入り込むまでに5年、10年は軽くかかる。その間AIは成長し続ける。AmazonやMicrosoft、Meta(旧Facebook)、Googleなどの米国のISP(インターネットサービスプロバイダ)が今、身の丈を超えるような巨大な投資を進めているのは、AIデータセンターをもっと拡大したいからだ。拡大することで大量のユーザーにサービスを提供できると、互いに競争しているのだ。ここに割って入ろうと中国のISPも拡大を続けており、政府も乗り出しつつある。
かつて中国政府は、アリババを自らの敵とみなした。売り上げや時価総額が政府予算に近づくほど巨大になってきたからだ。ところが最近、中国政府はアリババを味方に使うことで、米国に対抗しようとし始めている。本当の仮想敵国は米国なのだ。
IT技術は、AIを取り込み、あらゆる分野へ影響力を持つようになった。このため政府までもIT企業を利用し始めた。いわば地政学的な影響を受けるようになり、ITはあらゆる産業、あらゆる国と仲良くビジネスできる機会が増えている。一方で国家間の争いに巻き込まれるリスクも現れ始めた。この先、私たち半導体産業に従事する者たちは、地政学上のリスクを含むが、ITを駆使することで地球上の人類を幸せにするというITの方向は決して忘れてはならない。
[ 参考資料 ]
- 1. 藤本隆宏編、「モノづくり経営学 製造業を超える生産思想」、光文社新書
- https://books.kobunsha.com/book/b10124346.html
- Writer
-
津田 建二(つだ けんじ)
-
国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。
現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。
30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。
半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。
- URL: http://newsandchips.com/

