JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
チップレットなど後工程技術が先導する、半導体開発のゲームチェンジ
- 文/ 伊藤 元昭
- 2025.10.01
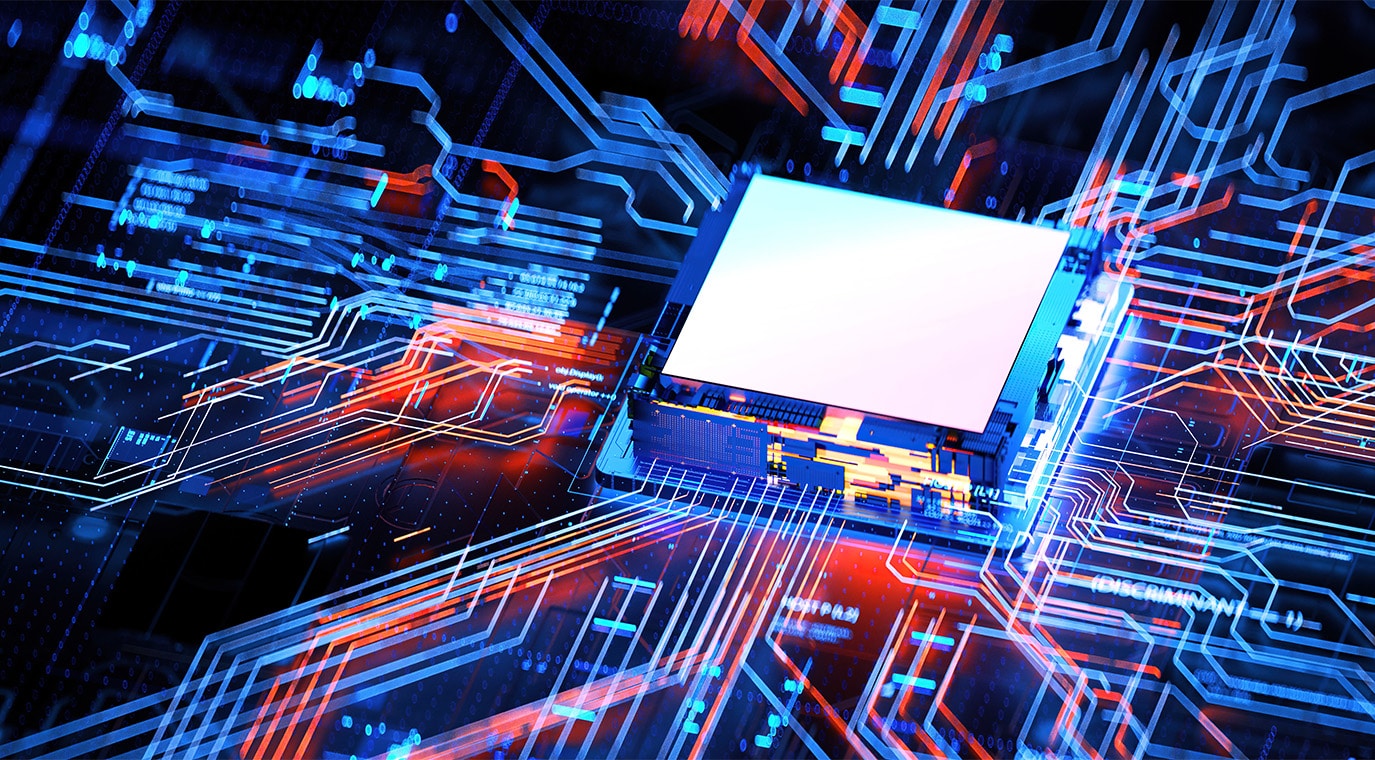
チップレットをはじめとする最新の半導体後工程技術を活用することによって、NVIDIAやIntelのような半導体専業メーカーの独壇場だった最先端チップの開発を、多様な業界・業種の企業でも行うことができるようになった。最先端チップの開発競争、特にチップサプライヤーとユーザーの関係が再定義されつつある。
チップレットとは、チップ化する大規模な回路をあえて個片分割し、それぞれを最適技術で製造した後に、組立・パッケージング工程(後工程)によって巨大チップを構成する技術のことだ。チップレットの活用によって、独自機能を搭載したチップ全体に最先端微細加工技術を適用しなくても競争力の高いチップを開発・調達できるようになった。
Amazonに見る独自チップ開発がもたらす威力
IT機器メーカーやクラウドサービスのベンダーなど、これまで半導体ユーザーだった企業において、独自チップを開発し、自社の製品やサービスなどに活用することで競争力の高いビジネスを展開する機運が高まっている。自動車や家電製品など、あらゆる機器の機能がデジタル化・スマート化していく中、独自チップ開発の動きは多様な業界へと拡大していく兆しが見えてきた。
クラウドコンピューティングの巨人であるAmazon Web Services(AWS)の取り組みを例にして、独自チップを開発・活用している企業の動きと、その狙い、効果を紹介する。同社では、データセンターに置くサーバーの頭脳となる多種多様なチップを独自開発し、それぞれを明確に使い分けることによって、競争力の高いクラウドサービスを提供するようになった。
独自開発しているサーバーの頭脳となるチップは、大きく3つの系統がある(図1)。1番目は、コストパフォーマンスの最大化を狙った「AWS Gravitonプロセッサ」。ウェブサーバーやマイクロサービス、データ分析など多様な処理に対応する汎用CPUである。2番目はAIモデル開発の時間短縮を狙った「AWS Trainium アクセラレータ」。大規模言語モデル(LLM)や画像生成AIなど、巨大モデルの学習に特化し、性能と電力効率の底上げを狙ったチップだ。3番目は、AIの実行コストの劇的な削減を狙った「AWS Inferentia アクセラレータ」。学習済みのAIモデルを実際に動かして結果を得る、推論処理に特化したチップである。チャットボットの応答や画像認識など、リアルタイム性が求められる処理を低コストで実行するために導入している。その他にも、インスタンスの仮想化・セキュリティ、ネットワーク処理の最適化に向けた専用チップ「AWS Nitro」も独自開発している。

- [図1]データセンターの頭脳部を独自開発し、競争力の高いクラウドサービスを提供するAWS
- AWS Gravitonプロセッサ(左上)、AWS Trainium アクセラレータ(右上)、AWS Inferentia アクセラレータ(左下)、AWS Nitro(右下)
- 出典:AWS
一般に、データセンターでは、規模・手順・内容の異なる多様な処理を同時実行している。AWSでは、多様な独自チップ、及び外部調達したチップそれぞれの特徴を生かして、要件に応じて最適なチップに処理を振り分けながら、チップリソースを効率的に利用する仕組みを開発し、性能面でもコスト面でも競争力の高いクラウドサービスを提供している。
一般的には、パソコンメーカーはIntel製もしくはAMD製のx86系CPUを、AI関連のクラウドサービスのベンダーならばNVIDIA製のGPUを調達、利用して自社の製品・サービスを生み出すための頭脳として利用している(AWSでも、顧客にニーズに応えるため、これら外部企業製チップも併用している)。ただし、これらの外部企業から調達するチップに依存したのでは、機器やサービスの価値を大きく左右する重要チップであるが故に、競合に対するサービスの差異化が困難になる。しかも、これらのチップの供給は一部のメーカーが寡占し、なおかつ需要も旺盛であるため、どうしても調達価格が高騰しがちだった。
AWSのように、自社で独自チップを開発し、活用すれば、チップサプライヤーのチップにロックイン(他社製品に切り替え困難な状態)されることなく、独自性の高い製品・サービスを、最小限のコストで提供できるようになる可能性がある。こうした独自チップの利用は、Appleのスマートフォン向け「Aシリーズ」及びパソコン向け「Mシリーズ」、GoogleのAIチップ「TPU(Tensor Processing Unit)」が先駆けとなって始まり、現在では自動車業界でTeslaが自動運転用チップを開発・活用するなど、他業界へと波及してきている。
特に、製品の主要機能のソフトウェア化(ソフトウェア定義車両(SDV)の開発・市場投入)が進み、処理を実行するチップが製品の価値を大きく左右する方向へと向かう自動車業界では、トヨタ自動車など複数の企業が独自チップ開発を推し進めるようになった。これまで自動車業界では、半導体チップは、ティア2に位置付けられる半導体メーカーから調達すれば事足りると考えていたのだから、認識が大きく変わっていると言える。
強者をさらに強化する手段だった、これまでの独自チップ開発
ただし、直近で独自チップを開発し、自社の製品・サービスの競争力向上に役立てることができている企業は、潤沢な資金力を持つ超巨大企業ばかりであると言える。IT業界では、米国のGAFAM(Google,Apple,Meta(旧Facebook),Amazon,Microsoft)や中国のBATH(Baidu,Alibaba,Tencent,Huawei)は、例外なく独自チップを保有している。その一方で、日本企業で独自チップを開発し、定常的な製品やサービスに活用している例は稀である。代表例として挙げられるのは、ゲーム機向け独自チップを開発してプラットフォームビジネスの展開に利用しているソニーや任天堂であろう。一般的には大企業とみなされる国内IT企業やトヨタ自動車以外の自動車メーカーも、単独ではチップ開発に踏み込むことができない状態にある。つまり、現在の独自チップ開発は、強者をさらに強化するための手段となっていると言える。
独自チップの開発・活用が強者限定の差異化手段となっている理由は明白だ。機器やサービスの競争力を高めるような最先端チップは、開発(主に設計)や製造(ファウンドリなどへの委託)に要するコストがとんでもなく高額だからだ(図2)。ウエハー上に大規模回路パターン形成する半導体製造工程(前工程)の微細加工技術の進歩に伴って高コスト化が進み、1品種のチップを最先端製造技術対応で設計・製造するのに、機器を生産する工場を建設するのと同等の投資が必要になってきている。

| ノード | 設計コスト(EDA/IP/検証等) | マスクセット価格 | 量産ウエハー価格(目安) |
|---|---|---|---|
| 90〜65nm(参考) | 数百万~1000万米ドル台 | 数百万米ドル台 | 数千米ドル |
| 28nm | 4000万〜5000万米ドル | 数百万米ドル台 | 数千米ドル台後半 |
| 7nm | 2億〜2.2億米ドル | 1000万米ドル | 1万米ドル前後 |
| 5nm | 4.1億〜4.4億米ドル | 2000万~3000万米ドル以上 | 約1.6万米ドル |
| 3nm | 5.9億〜6.5億米ドル | 3000万~5000万米ドル | 約1.8万米ドル |
| 2nm(見込み) | 6億米ドル以上 | 数千万米ドル | 約3万米ドル |
- [図2]ロジック半導体のプロセスノードごとの設計・製造コストの目安
- 作成:伊藤元昭、写真:AdobeStock
例えば、2025年現在で最先端のプロセスノード(微細加工技術の世代とほぼ同義)である3nmノードのチップを設計、製造すると、AIチップなど1品種当たり設計コストは約6億米ドル、製造時に利用する回路パターンの原版であるマスクの価格が1セットで約4000万米ドル掛かり、量産時の製造コストはウエハー1枚当たり約1800万米ドルになる。
もちろん、開発するチップの設計や量産規模によって価格は大きく変動する。しかし、現時点での最先端技術を適用しようとすれば、一般的な大企業でも簡単に手出しできないコストを覚悟する必要があることには変わりない。しかも、今後、さらにこれらのコストは増大していくことが確実だ。そこでGoogleなどの超巨大企業であっても、独自開発したチップを外部企業に販売し、生産量を増やして生産コストの削減や投資回収を図るとともに、自社技術の業界標準化を推し進める戦略を取るようになった。
開発のハードルを劇的に下げた「チップレット」という発明
近年、チップレットや3Dパッケージ技術などの先進的な後(中)工程技術の活用が拡大してきている(図3)。一昔前は、半導体の進化とは、すなわち微細加工技術の進化であるとみなされていた。ところが現在は、微細加工技術を変えなくても、 3Dパッケージなど最新の後工程技術を適用してより高性能・高付加価値なチップを開発できるようにもなってきている。特にチップレットは、設計と生産の両面で、最先端微細加工技術の適用シーンの再定義が進むほど大きなインパクトをもたらし、独自チップ開発のハードルを劇的に下げる効果が得られるようになってきた。

- [図3]半導体の後工程技術の進化が加速し、最先端微細加工技術に頼らなくても競争力の高いチップを開発・調達可能になった
- 出典:Cadence Design Systems
そもそも、高性能な半導体を独自開発するのに巨額の開発・製造コストが必要だった最大の理由は、開発するチップ全体を設計し、大面積のチップ全体を高価な最先端製造プロセスで製造する必要があったからだ。
ところが、チップ全体を独自開発する必要があるのかと言えば、そのような例は意外と少ない。独自演算器を搭載したプロセッサコアやメモリー間のインタフェースには独自技術を投入したいが、メモリー内部や周辺回路まで独自設計する必要はないような例がほとんどではないか。また、大量のコアを搭載しているチップも、一枚板のチップに全てのコアを搭載する必要性はない場合も多い。全ての回路を1チップ化するためには、当然、設計・マスク・製造のコストは1チップ分必要になるが、独自性を盛り込みたいのはチップ内の一部に過ぎないというもったいない状況になっている。
また、チップ上の回路をすべて最先端プロセスで製造したいかと言えば、そうでもない。周辺回路などは、成熟した製造技術を適用しても十分要求性能を実現できる場合が多い。一般に、より微細な製造技術であるほど製造時の歩留まりを高めるのは難しい。無闇に回路の1チップ化を推し進めれば、難易度の高い製造技術で大面積のチップを低歩留りで製造しなければならなくなる。結果的に製造コストが増大する。
これが、チップレットを適用することによって、最先端プロセスが不要な部分は最適プロセス向けに設計し、合理的なコストで製造できるようになる。さらに、独自設計が不要な機能ブロックについては、チップレットの形態で汎用的な標準品として外部調達できる可能性もある。このため、独自開発すべき対象を大きく絞り込むことができるようになる(図4)。さらに、DRAMや不揮発性メモリー、アナログ回路、パワー回路、RF回路、受動部品など、本来デジタル回路との1チップ化が困難な回路を集積することも可能だ。こうしたヘテロインテグレーションと呼ばれる手法を適用すれば、1枚のダイに集積(モノリシック化)した独自開発チップよりも高い競争力を持つ可能性さえある。

- [図4]戦略的機能回路のみを独自開発し、最適プロセスで生産して独自チップ開発のハードルを下げる
- 作成:伊藤元昭
かつて独自開発に積極的だった日本企業にも勝機が
現時点で独自チップを開発していない機器メーカーやサービスベンダーも、可能ならば、チップ開発に踏み切りたいと考えているのではないか。特に、日本のIT企業や産業機器メーカーなどの中には、2000年代まで自社内に半導体部門や半導体設計の部署を保有していたところも多い。独自開発の効果を熟知しながら、コスト面で独自開発を断念せざるを得ない状況にあったのだからなおさらだ。
チップを開発するためには、相応の知見・設計技術の育成と開発環境の整備が求められる。既に、スーパーコンピュータ向けCPU「MONAKA」を開発した富士通や、産業用のAIアクセラレータチップ「MN-Coreシリーズ」を独自開発するPreferred Networksのような新たな挑戦者も出てきている。自動車業界においても、トヨタ、日産自動車、ホンダ、マツダ、スバルなどが参加する自動車用先端SoC技術研究組合(ASRA)で、チップレットを活用した車載用SoCを開発中である。また、半導体メーカーであるルネサスエレクトロニクスと共同で高性能SoCの開発に取り組むホンダのような企業も出てきている。今後は、先進的な後工程技術の積極活用が進み、より多くの国内企業が、戦略性の高い独自チップを開発していくことだろう。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

