JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Cross Talk
- クロストーク
ハピネスとテクノロジー前編
幸せは最上位概念
- 前野 隆司
- 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント教授
- 矢野 和男
- ハピネスプラネット 代表取締役CEO
- 2020.09.29
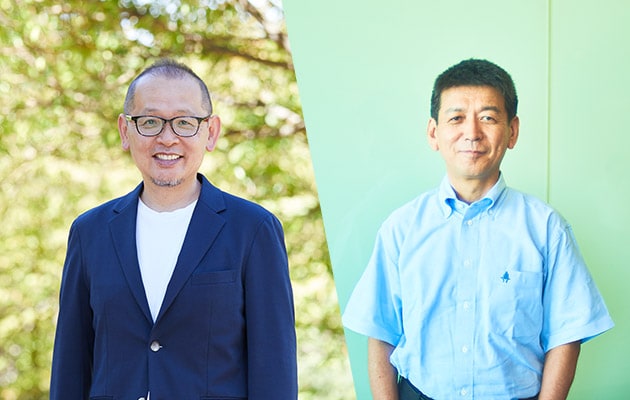
「ハピネス(幸福)」は、歴史的にいつも人々が求めてきたものだが、そのあり方は不明で一様でもない。だからこそ、ハピネスは文学、宗教学、哲学、社会学などがさまざまな方法で探求するテーマとなってきた。近年は科学とテクノロジーの発展によって、ハピネスの状態を観察、計測したりするばかりでなく、人々をハピネスに導く方法が模索されるようになった。専門の機械工学において「幸せ」が設計変数に欠けていることから幸せ研究に進んだ慶応大学教授の前野隆司氏、そして物理学の手法を用いて若い頃からの関心ごとだった幸せに取り組むハピネスプラネットCEOの矢野和男氏。理系の視点から捉えたハピネスを語り合っていただいた。
(構成・文/瀧口範子 写真/黒滝千里〈アマナ〉)
工学と物理から、ハピネス研究に至った道
 |
── 最初に、工学や物理の専門家だったお二人が、そもそもどのようにして「ハピネス」の研究に至ったのか、その経緯をお話しいただけますか。
前野 ── あとで詳しく述べますが、私は「ハピネス」ではなく「幸せ」の研究をしています。私がもともと研究していた機械工学には、設計論という分野があります。製品やサービスを設計するわけですが、人間にとって最も大切な価値はやはり幸せになることじゃないでしょうか。それなのに設計変数には「幸せ」が入っていません。それは設計論の欠陥だと気づいたのです。
カメラを作る時も、ロボットを作る時も、あるいは街を作る時も、コミュニティーを作るときも、幸せという設計変数があれば、住むほど幸せになる町や、使うほどに幸せを感じるカメラが作れるのに、そんな指標はありません。幸せを分解して、設計可能にしなければいけないと思ったのが始まりです。
矢野 ── 私は、幸せについては学生時代から非常に関心があって、当時から一番の愛読書がヒルティの『幸福論』です。「幸せに関わるような仕事したい」という妄想を友達にも話していたようなのですが、もちろんそんな仕事はあるわけもなく、卒業後は日立に入社しました。当時、日の出の勢いだった半導体部門に配属され、世界の先端的な環境の中で楽しく仕事をしました。
しかし、20年ぐらい経った後に日本の半導体が不調となり、事業が撤退となりました。リセットして新しいことを始めなければいけないという状況の中で、これからはデータが大切になるのではないか、それも人間のデータは面白そうだという直感を持ったのです。
そこで、2003年ごろからデバイスやネットワーク開発などデータを収集する道具も作り始めました。2006年ごろから毎日すごい量のデータが集まるようになったのですが、データだけあってもどうしようもないので、何か目的が必要だと思い始めたのです。
仕事だから生産性かなとも考えましたが、ここで学生時代からの想いが蘇ってきました。たまたまその頃に「ポジティブ心理学」という分野が目に入ってきたり、幸せな人たちは生産性が高いという論文が出始めたりしていて、幸せを目的変数にしてデータから何かがつかめたら、単なる機械化とは違う形でテクノロジーが価値を生むのではないかという直感がしました。その辺から、周りには「矢野は何か宗教みたいなことをやっているぞ」と言われましたけれどね。
 |
前野 ── 私もキヤノンから大学に移ってロボット研究をし、13年目の2008年に幸せの研究を始めました。社会全体を俯瞰し学問分野を超えて問題解決をしようという「システムデザイン・マネジメント(SDM)」のための大学院研究科ができたのです。それなら、同様に幸せという最上位概念を問題解決すべきだと、自然に幸せの研究を始めました。
ところが、当時は同僚たちから「SDMというコンセプトとあなたの宗教みたいな研究は関係ない」と誤解されましたね。矢野さんが研究を始めたのは2003年ですか。2008年でも全く理解されませんでしたから、もっと理解されなかったでしょうね。
矢野 ── ましてや企業の中ですから。幸せが大切なことは誰も否定はしないわけですが、その幸せという上位概念と、具体的な製品やビジネスや産業との間にあまりにギャップがあるので、そこを埋める動きをしなければなりません。勉強していくと、幸せに関わる研究をしている人たちがいることがわかり、それで心理学という畑違いの分野の大家のミハイ・チクセントミハイ教授やカリフォルニア大学のソニア・リュボミアスキー教授のところへ飛び込みで訪ねて行ったら、割と気さくに話してくれました。
幸いだったのは、われわれがデータをちゃんと持っていたことです。そこは、ある意味、リスペクトされました。そもそもデータは今でこそ資産だとされますが、当時はコンピュータで処理されるものとしか認識されていませんでした。しかし、大量のセンサーからとった人間行動のデータを持っていることで、どんな分野の人と話をしても相手とコミュニケーションが成り立ちました。
── 「ハピネス」については、幸福、ウェルビーイングといろいろな表現があります。エイジングも無関係ではありませんし、吾唯足るを知るという禅の教えや、マインドフルネスという新しい考え方もあります。どの言葉を使うかにこだわりはありますか。
前野 ── 幸せの研究は心理学が中心ですが、そこではよく「ウェルビーイング・アンド・ハピネス」と言われます。ハピネスと幸せは日本では1対 1で対応していると思われがちですが、ハピネスは狭い言葉です。以前シンギュラリティ大学の先生と話していて、「ハピネスの研究とはけしからんね」と言われたことがあります。ドラッグをやったり酒を飲んだりしてハッピーになった状態の研究をするものではないのではないか、と言うのです。
それで気付いたのですが、ハピネスとは感情としての幸せなのです。美味しいものを食べて幸せといった、短時間の感情を指していて、辛いこともあったけれど幸せな人生だったなあという時の幸せとはちょっと意味が違うんですね。つまり、幸せよりハッピーの方が意味合いが狭いのです。
また、ウェルビーイングも面白い言葉で、日本の心理学者は幸せと訳しますが、お医者さんは健康、福祉関係の人は福祉と訳すのです。ウェルビーイングというのは近代になって作られた言葉で、心と体と社会の良い状態を意味しています。ですからハピネスより幸せの方が意味合いが広くて、それよりもずっと広いのがウェルビーイングということになります。
また、感情は非常に短いスパンの人間の反応ですけれど、気分はもうちょっと長いスパンです。幸せは、感情よりも気分に関わっていますが、幸せな人生という時は、そういう心の状態ではなく「あり方」みたいなものでしょう。もっと長い状態までを含むのが幸せという言葉だと思うのです。
ですから、私が携わっている研究分野は「ハピネス」ではなく「幸せ・幸福」ないしは「ウェルビーイング」だと考えています。
矢野 ── ドイツ語では、「運」を意味する「Glück(グリュック)」が幸せを指す言葉です。ヒルティの『幸福論』のタイトルもまさに「Glück」です。昨年行ったフィンランドでは、「Sisu」という言い方があると言われました。これは逆境に負けない強さみたいな意味です。ですから、どこを強調するかは文化的、歴史的背景で違うのですが、私が目指しているのは、人類が大事にしている多様な面を全部包含して見えるようにしたいということです。
実は今、幸せに関する言葉を分類しています。受け入れる、覚悟する、挑戦する、情熱を持つ、冒険する、信頼をする、感謝する、謙虚になる、対等な関係を結ぶ、結束するなど、ランダムなようで、こうした言葉は体系づけることができる。それが俯瞰できれば、幸せの本当の姿が見えてくるのかなと思っています。幸せがいい言葉だなと思うのは、剣道の「仕合う」と同じ語源で、交わるという意味があるからです。フィンランドの人は逆境に耐える、ドイツは運がいい、日本人は人と人の交わりの中に大事なものがあると伝えている。そこは、日本人として誇りに思うところですね。
幸せは結果ではなく、原因
 |
── 時代ごとに何を幸せとするのかは変わってきたと思いますが、幸せ感やそれを捉える方法の変容についてはどう捉えておられますか。
前野 ── 矢野さんもおっしゃっていますが、語源に遡ると中国の幸福は幸運という意味もあります。ですから、幸せと運はもともと同じ意味だったと言われているのです。ハッピーの語源の「ハップ」もめぐり合わせという意味で、やはり関係性や運を強調しています。つまり、いろんなことをした結果として運のいい人は幸せになる、運の悪い人は不幸せになると捉える傾向が、大雑把にいって、もともとは世界中で見られたということなのです。
宗教から見ても天命のような決定論的なものが想定されていました。しかし、今アメリカ人がハッピーと言う時には、別に運という意味では使わないですよね。科学が発展するにつれて、運命論ではなく自分たちで人生を切り開いていくのだという方向に語感が変わっていったのではないでしょうか。
ここ数十年で言うと、やはり心理学の分野で幸せな心の状態を作っておくと、その結果、創造性が増すとか利他的になるといった相関がわかってきました。例えば感謝する人は、その結果、幸せになる。つまり、従来は、幸せは結果だと思われてきたのが、実は原因にもなるということが介入実験や時系列的に追いかけていく研究でわかってきたのです。だから、目指せるものとして、幸せの研究が盛んになってきたともいえるでしょう。
つまり幸せな心の状態を作っておくと、その結果生産性が上がったり創造性が上がったり寿命が伸びたりする。矢野さんがおっしゃったポジティブ心理学も、まさにポジティブな心の状態作っておくとそれが予防医学になるということですね。ですから、今は「健康に気をつけて」と言いますけれど、いずれは「幸せに気をつけている?」という風に使われるようになるのではないかと思うのです。
矢野 ── 私はもともと理論物理を研究していました。物理とはものの理(ことわり)を探求する学問ですが、対象は何でもいいのです。実際、物理は対象どんどん広げてきた歴史でもあります。宇宙にビッグバンという始まりがあったなんて 60〜70年前にはわからなかったのですが、そう考えないと実際の観測データが説明できません。物理の基本原理になっているのは計測であり、そこから得たデータによって仮説を反証していくというプロセスです。素朴な直感よりもデータや観測を重んじるということによって、物理や物理に関わる分野は過去 100年ものすごく進歩してきたのです。
それと比較すると、社会・人文科学は、物理に憧れている部分がありながら、そうなり切れなかった歴史があります。その理由は計測データの不足にあるのではないかというのが私の仮説です。逆に計測やデータがあれば、物理のような定量的な反証によってより幅広い人や社会活動に関わって法則性が見出されるのではないかと考えたわけです。データを測る手段の方も日進月歩で、ウエアラブルやスマホ、カメラなどがこの 20年間でどんどん発展し、かつ専用に計測しなくても、たまたま溜まっていたデータの中に人間の非常に基本的な法則性を見出せるといったことも可能になっています。
前野 ── 私も元は機械工学を研究していたのですが、早く幸せを分析したくなって対象を変えました。その際、既存の多変量解析という確立された分析手法で幸せを分析しようと思ったのです。幸せを研究する心理学者は個別分野を深く探求することが多いのですが、私は幸せと関係ある物事の全体像を多変量解析することから始めました。
その結果、幸せの4つの因子や、幸せな働き方の7因子と不幸せな働き方の7因子などが出てきました。そこで、最近はそれを使って、人々が幸せになるような職場づくりとか、幸せな街づくりとか、ハウスメーカーと一緒に住めば住むほど幸せになる家の設計などを行なっています。機械工学は応用物理で、世の中の役に立つものを作ります。その目的は今も同じです。
計測とデータで、幸せの行動パターンを探る
 |
── 矢野さんは、加速度センサーで人の動きを計測されてきたわけですが、動きはハピネスにどう関連しているのでしょうか。
矢野 ── この10年以上にわたって、人々が3次元的にどう動いているかのデータをミリセカンドレベルで、合計1000万日以上集めてきました。加えて、誰と誰が対面しているかも計測し、これに心理学の質問紙への回答や経営学の指標、時系列に沿った仕事の生産性のデータも照らし合わせます。そこから、幸せな組織、幸せでない組織に見られる行動パターンがわかったのです。
一番わかりやすいものだと、幸せな組織では5分か 10分の短い会話の頻度が多い。仕事をしていたら、ちょっと確認したいことや耳に入れておきたいことなどがいっぱいありますよね。普通の会社だと、予定表に入れるような会議が2週間に一度あったりするわけですが、不幸せな職場の典型はそれ以外の日に会話がありません。逆に幸せな職場のパターンでは 5分、 10分の短い会話が毎日のように起こっているのです。
また、会話の際の発言権の平等性も重要です。幸せな組織では皆に平等に近い発言権が見られるのに、不幸せな組織では特定の人に発言権が偏っているのです。発言の平等性は心理的安全性という文脈でも捉えられますが、グーグルが大々的に行なっている高生産性チームの研究『Project Aristotle』では、まさに発言権の平等性を取り上げていて、チームの能力の総計やパーソナリティーとは無関係に発言権の平等性が効いていたことが報告されています。
また、カーネギーメロン大学とMITで集団的知性についての研究も行いました。ここでは、何百というチームに互いに協力し合わなければ解けない問題を与えました。集団にも一種のIQがあって、それは単なる個人のIQの足し算ではないのではという仮説からスタートした研究です。結果的に、うまく問題を解き集団的にIQが高かったチームは、やはりチームの中での発言権が平等だったことがわかりました。
さらに面白いのは、写真の目の部分だけを見せて「この人はどんな感情ですか」というテストをやると、この部分的な情報から相手の感情を推定する能力の高い人たちが集団的にインテリジェントでした。一般的に問題解決能力と言われているものと全然違うところ、つまり平等に発言したりアイデアを出したりする関係性が作れて、相手の気持ちがわかるということが集団として生産的な組織の特徴であると言えるのかもしれません。前野先生が言われたように、いろいろな視点を同時並行的に捉えてこうした研究をやっていますが、データから知見を得る方法はこの20年で大きく進化し、そこに貢献できたかと思っています。
 |
前野 ── 人と人との対話を活性化すると、人は幸せになるんですよね。感謝について語り合ったり、励まし合ったりするのは、むしろ昔の人が普通にやっていたことです。実は今、旧石器時代や縄文時代にすごく興味があります。これらの時代は農耕革命以前で、生活は貧しいのですが、貧しいから助け合いながら生きていたと言われています。もちろん隣の部族と闘うなど、いろいろな闘いはあったと考えられますが、そもそも富がないので、富を巡って争うことはありませんでした。
ところが農耕革命が起きると、米や小麦を蓄えられるようになりました。飢え死にしたかもしれない狩猟採集生活とは違って、蓄えて安心できるようになったのですが、その結果、生産性が低くなったと言われています。狩猟採集生活ではほとんど遊んでいて、お腹が空いたらちょっと魚でも取ってくるかと出かけていく程度でも生きていけたため労働時間が短かったのに対し、農耕生活ではたとえば田んぼをきちんと作る必要があるため、ものすごく長時間労働するんです。つまり、単位面積に住む人が多いから土地面積当たりの効率は高いものの、1人当たりの労働時間は増えてしまった。それこそ働き方改革の視点で見れば、旧石器時代の方がよほどライフワークバランスが取れていました。だから、農耕革命以来、人間は自然を変えて豊かになったつもりでも、実は1人当たりの労働は増えているのです。
300年前に起こった産業革命後には、便利になったはずがさらに忙しくなりました。インターネットもそうでしょう。便利だと思っていますが、みんなメールに追われています。そう考えると、人類は旧石器時代が一番幸せだったのではないでしょうか。科学技術が発展した一方で、地球環境も破壊され、格差問題も解決できていません。そろそろこの発展を終わりにして、みんなが幸せの世界を取り戻すべきなのではないかと思うのです。人類は自然と共に生きる世界に帰っていくべきなのだと思っています。
矢野さんが最先端の研究をやっているのに対して、私は旧石器時代のアプローチです。テクノロジーから離れていって、哲学や考古学に興味があります。理系から始まって同じ幸せを研究しているのに、方法は全然違っていますが、これは役割分担だと思うんですよ。
── そうした狩猟採集時代の生活のいいところを、テクノロジーで実現するといったアプローチがあればいいですよね。
前野 ── コロナ禍中オンラインで働くようになり、北海道や沖縄に移住した人もいます。大自然の中で生きつつ、最先端のテクノロジーを使って会いたくなったら3次元で会えるといったことが可能になっています。未来社会では、まさに進歩と古いものが一体化するのだと思います。
[後編へ続く]- Profile
-

-
前野 隆司(まえの たかし)
-
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授
慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長1984年東京工業大学卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼務。博士(工学)。
著書に、『幸せな職場の経営学』(2019年)、『幸福学×経営学』(2018年)、『幸せのメカニズム』(2014年)、『脳はなぜ「心」を作ったのか』(筑摩書房,2004年)など多数。日本機械学会賞(論文)(1999年)、日本ロボット学会論文賞(2003年)、日本バーチャルリアリティー学会論文賞(2007年)などを受賞。専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育など。

-
矢野 和男(やの かずお)
-
株式会社 日立製作所 フェロー
株式会社ハピネスプラネット 代表取締役CEO
博士(工学)
IEEE Fellow
東京工業大学 情報理工学院 特定教授山形県酒田市出身。1984年早稲田大学物理修士卒。1991年から1992年まで、アリゾナ州立大にてナノデバイスに関する共同研究に従事。1993年単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功し、ニューヨークタイムズなどに取り上げられ、ナノデバイスの室温動作に道を拓く。
さらに、2004年から先行してウエアラブル技術とビッグデータ収集・活用で世界を牽引。論文被引用件数は2500件、特許出願350件を越える。「ハーバードビジネスレビュー」誌に「Business Microscope(日本語名:ビジネス顕鏡)」が「歴史に残るウエアラブルデバイス」として紹介されるなど、世界的注目を集める。のべ100万日を超えるデータを使った企業業績向上の研究と心理学や人工知能からナノテクまでの専門性の広さと深さで知られる。特にウエアラブルによるハピネスや充実感の定量化に関する研究で先導的な役割を果たす。
博士(工学)。IEEE Fellow。電子情報通信学会、応用物理学会、日本物理学会、人工知能学会会員。日立返仁会 監事。東京工業大学 情報理工学院 特定教授。文科省情報科学技術委員。これまでにJST CREST領域アドバイザー。IEEE Spectrumアドバイザリ・ボードメンバーなどを歴任。
1994年、IEEE Paul Rappaport Award。1996年、IEEE Lewis Winner Award。1998年、IEEE Jack Raper Award。2007年、Mind, Brain, and Education Erice Prize。2012年、Social Informatics国際学会最優秀論文など、国際的な賞を多数受賞。
2014年7月に上梓した著書『データの見えざる手: ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則』が、BookVinegar社の2014年ビジネス書ベスト10に選ばれる。
- Writer
-
瀧口 範子(たきぐち のりこ)
-
フリーランスの編集者・ジャーナリスト。
上智大学外国学部ドイツ語学科卒業。雑誌社で編集者を務めた後、フリーランスに。1996-98年にフルブライト奨学生として(ジャーナリスト・プログラム)、スタンフォード大学工学部コンピューター・サイエンス学科にて客員研究員。現在はシリコンバレーに在住し、テクノロジー、ビジネス、文化一般に関する記事を新聞や雑誌に幅広く寄稿する。著書に『行動主義:レム・コールハース ドキュメント』(TOTO出版)『にほんの建築家:伊東豊雄観察記』(TOTO出版)、訳書に 『ソフトウェアの達人たち(Bringing Design to Software)』(アジソンウェスレイ・ジャパン刊)、『エンジニアの心象風景:ピーター・ライス自伝』(鹿島出版会 共訳)、『人工知能は敵か味方か』(日経BP社)などがある。

