JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Laboratories
- 研究室紹介
人に寄り添って泣き笑いするドラえもん、その実現は時代の要請
── 学生や異分野の専門家とともに未来を目指す
- 日本大学 文理学部 情報科学科 大澤研究室
- 第2部:
- 日本大学 大学院 総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻 博士課程前期1年
川島 遼介さん
日本大学 文理学部 情報科学科4年 下田 音里さん
日本大学 文理学部 情報科学科3年 山本 英弥さん - 2022.11.02

近年、ロボットの研究開発には1つの大きな潮流がある。生活や社会活動の場に溶け込み、人と一緒に暮らすロボットを目指す動きである。人間では実現できないパワー、スピード、耐久力で、さまざまな作業を自動化する従来の産業ロボットの開発とは一線を画するものだ。少子高齢化による人手不足が社会問題となり、人とロボットの共存・連携は時代の要請となっている。日本は、特撮やアニメの分野で多くの有名ロボットを世に輩出してきた「ロボット大国」だ。数あるロボットの中で、暮らしや社会に溶け込み、人と良好な関係を築いて活躍する時代を先取りしたロボットの代表例がドラえもんではないか。日本大学 文理学部 情報科学科 助教の大澤正彦先生は、「ドラえもんをつくる」という大胆だが、時代の要請に応える研究に取り組んでいる。
(インタビュー・文/伊藤 元昭 撮影/氏家 岳寛〈アマナ〉)
-

-
第1部:
日本大学 文理学部 情報科学科 大澤研究室
次世代社会研究センター RINGS センター長
大澤 正彦 助教
-

-
第2部:
日本大学 大学院 総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻 博士課程前期1年
川島 遼介さん
日本大学 文理学部 情報科学科4年
下田 音里さん
日本大学 文理学部 情報科学科3年
山本 英弥さん

どんなに長い人生でも、「ドラえもんをつくる」なんていう夢に関わる機会は他にない
── どのような理由で、大澤研究室を選んだのでしょうか。
川島 ── 僕は、大澤研究室の一期生です。学部時代には専修大学に在籍していました。元々、専修大学の別の先生の研究室に入りたいと大学1年生の頃から考えていたのですが、その先生が、配属される研究室が決まるタイミングで大学を離れることになってしまいました。その先生に相談したところ、「自分の後輩が兼任講師として着任するのでそこに行ってみたらどうか」と勧められました。それが大澤先生でした。
私は、シャンプーボトルの中身がなくなったら自動発注するといった、お風呂のIoTを個人的に開発していました。それまでは、同様の技術を極めたいと思っていたので、大澤先生の研究とはちょっと畑違いになるのかなとも思っていました。しかし、大澤先生と出会って、エージェントという技術の可能性や面白さを知り、それを研究テーマにすることにしました。そして、大澤先生と出会って2年間研究していくうちに、大学院に進みたいと考えるようにもなりました。現在は、大澤先生が本務として活動している日本大学の大学院に移り活動しています。
下田 ── 私は、2期生になります。実は研究室を選ぶ段階では、これといって希望はない状態だったのです。所属先を決めるため、いろいろな研究室のお話を聞いていたのですが、その時大澤先生が話された「ドラえもんをつくる研究室です」というキャッチーなフレーズに惹かれて、大澤研究室を選びました。
何と言っても、ワクワクする研究テーマですし、その研究室に所属した未来の自分を想像したら、ドラえもんをつくっている自分の姿に夢が膨らんだのです。実際に、自分でドラえもんをつくりたいと思い、行動に移すことができるのは、よほど時間やお金、人脈などに余裕がある場合に限られるのだと思うのです。そんな、未来に叶うかどうかもわからない夢に取り組む場が、今、自分が所属する大学の学部で、希望すれば手が届く場所にあるわけです。これに飛びつかない手はないなという風に思いました。
山本 ── 私も、研究室を選んだ理由に深いものはなかったですね。ただ、何でもできそうな研究室だなと考えて選びました。でも、大澤先生とは不思議なつながりがありました。私は、一浪一留しているのですが、留年するタイミングで、大澤先生の授業で私以外の学生がたまたまみんな欠席して私と先生が一対一で話す状態になる機会があったのです。もう大学をやめようかとも考えていた時でしたが、大澤先生と話していて、この先生がいれば何でもできそうだと思い、このまま社会に出るよりも大澤研究室に行けば何か面白いことがありそうで、行ってみたいなと思いました。
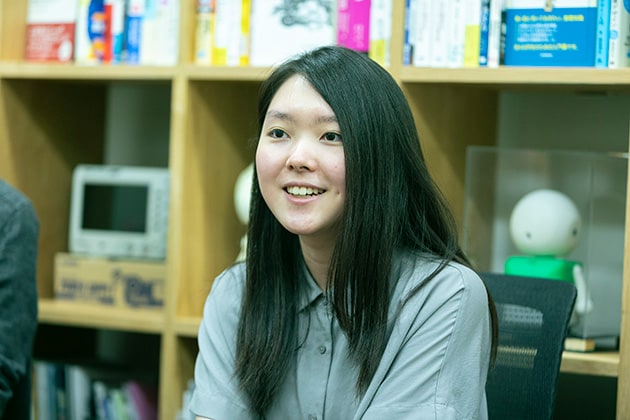
かわいく励ましてやる気を引き出してくれる秘書アプリ
── 現在は、どのような研究に取り組んでいるのでしょうか。
川島 ── 私は、インプリメンテーションチームの中で、サイバーエージェントと共同で、商品を上手に販売するエージェントを研究しています。身体のある販売ロボットを使って商品を販売させようとすると、ロボットが話している言葉の内容を憶えにくかったり、インタラクション時に恥ずかしさを感じさせたりしてしまうことがあります。そこで、ロボットの体を取り払って、声だけで商品を推薦可能な「音エージェント」を開発しています。
音エージェントは、スーパーなどの売り場に置いて使うような利用シーンを想定して開発しています。ロボットのように物理的なボディはないわけですから、動作を実装しなくてもよいため安価な開発・設置が可能であり、ボディがない分、売り場面積を広く確保できるといった利点があります。将来的には、思念体という頭の中に直接話しかけてくる、ロボットとは異なるSFのようなアプローチでの販売もできるようになるのではと考えています。
下田 ── 私は、インテリジェンスチームで、「他者モデル」をベースにした、心を持っているかのように振る舞えるロボットの実現を目指す研究をしています。他者モデルとは、例えば、人が他者を見て、何を感じて、次はどう動こうとしているかをモデル化したものです。それを用いることで、エージェントが人間に近い行動を取ることや人がエージェントの行動を予測・解釈できるようになり、人が人を思いやるような行動もエージェントが再現できるのではと考えています。
こうしたエージェントができると、人の生活がちょっとだけ豊かになるのかなと思っています。既に、声で指示すれば照明を消してくれたりするAIアシスタントが、日常生活の中で少しずつ使われるようになってきました。そうしたエージェントとの関係も、研究成果を生かせば、人に命令されたとおりに動くといった一方的な関係ではなくなると思っています。周囲にいる人のことを思いやって、照明を消した方がよいのか、点けたままにしておくのか、適切に判断してくれるAIアシスタントが登場してくる可能性があると思うのです。そして、さらに進化していけば、家に家族が一人増えるというか、心を通わすことができるドラえもんのような存在と一緒に生活する時代がやってくるかもしれません。
山本 ── 僕は、インタラクションチームで、かわいさを使って、人のやる気を高める研究をしています。インタラクションチームでは、ロボットが会話の中でうなずくことで人はどう感じるのかとか、人から募金を集めるためにはどのようなロボットがいればよいのかといった問題を検証しています。そして、そうした研究の中で、僕が一番注目している点が、かわいさから、人はどのようにやる気が起きるのかという点なのです。
人間の心の深い部分に直接訴えるかわいいの力は結構強く、ネットゲームでもかわいいキャラクターから声を掛けられれば、ついつい課金してしまったり、憧れのアイドルに「勉強がんばって」と言われただけで、必死になって勉強したりするわけです。かわいいと感じる対象は、性的指向に合致した対象だけではなく、動物でも、ドラえもんでもいいのですが、それらをどのように表現して活用すればやる気が上がるのか考えています。
── かわいいは日本の文化ですからね。かわいさのある機械は、日本の特産品になりそうです。日本のアニメなどのかわいさは海外の人たちにも通用していますから、グローバルな技術になります。ぜひやってほしいですね。

空想のように思えたことを、理論を詰めて実験を重ねて具体化する楽しさ
── 取り組んでいる研究で、面白いところ、難しいところがあればお聞かせください。
川島 ── 研究テーマというより、研究そのものの面白さになるかもしれませんが、最初は空想のように思えていたことが、ロジックを練って、実験を積み重ねていき、具体的な形があるモノになっていく過程が面白いですね。具体的な形になると、大人が「面白いじゃん」とか「理にかなっているね」と声を掛けてくれるようになりますから、それがとてもうれしく、面白く感じます。
その一方で、研究の方向性が定まる前の問いを探す段階では、難しさを感じることが多いように思います。エージェントという技術の行く先はどこなのか、進化することで何ができるようになるのか、果たして、それはエージェントでなければできないことなのか。そうしたことをひたすら考え続ける必要があります。実際に、今現在も、そうした点で悩んでいます。やるべきことが決まってしまえば、後は検証を積み重ねるたびどんどん進んでいけるので、難しさよりも好奇心や楽しさが勝っている感じがします。
── 研究で悩みに直面したときには、どうしているのですか。
川島 ── こうした悩みに突き当たった時には、とりあえず人に話してみるのが一番かなと思っています。自分だけで考えていても、発想には限界があります。共同研究者が何人もいるので相談してみたり、同級生や後輩に話して、ひょんなところからヒントをつかんだりと、いろいろ模索しています。専門性が違う人から、ヒントをもらえることはよくあります。
── 下田さんは、ご自身の研究のどのような点に面白さを感じますか。
下田 ── 人の心の中を深く考えるようになり、その過程自体が面白く感じます。人は誰でも、他人が何を考えているのか知りたいと考えているのだと思います。でも、実際には想像するだけで、ハッキリとはわかりません。そんな分かりにくい人の心の中を、熟慮して突き詰めモデル化することで、キッチリと見える化できるようにしていく過程が一番楽しいですね。そこが上手くいくと、日常的なコミュニケーションですら、研究の材料になります。今、この人は、このように考えて、こうした行動に出たのだろうなという風に、他者モデルに当てはめながら考えることで、見えないはずの他人の心の動きが理解できるようになってきます。
その一方で、立てたモデルに正解がない点には難しさを感じることがあります。自分なりによく考えて立てたモデルでも、「自分はそうは考えていない」といった指摘が返ってくることがよくあります。誰もが納得できる説明ができる、否定のしようがないモデルを作るのは、とても難しいのだと感じています。それでも、少しでも納得感のあるモデルを作るために、ひたすら議論を繰り返し、学会で情報を収集し、多くの先生方と話をして、多角的な見地から他者モデルや自己モデルの認知アーキテクチャを評価してもらい、ブラッシュアップしていく必要があるのだと思っています。
── 研究を通じて得た思考形態が、日常生活も変えるそうですね。山本さんはどうでしょう。
山本 ── 僕は、本能を刺激されながらアイドルなどの推しに熱狂するパワーを、自分のマネージメントや夢の実現に役立てることができれば、日本人の能力はもっと高まるのではないかと思っているのです。今、私は塾の講師をやっているのですが、塾の授業に出ている子でも、席に座った途端、一瞬にしてスマホを触ってしまうのです。集中力がスマホに削がれてしまって、がんばることができない子たちがたくさんいます。だからこそ、アプリの中の何らかのユーモアやかわいさによって気分が高まり、がんばることができる子が増えれば、世界が大きく変わると思うのです。そういった、大きな可能性がある研究ができているところに面白さを感じています。
── やる気を引き出すというのは、多くの職場や教育現場での永遠の課題です。研究成果の社会的なインパクトは大きそうですね。

学生に寄り添って、一緒に悩み込んでくれる頼れる存在
── みなさんにとって、大澤先生はどのような存在ですか。
川島 ── 授業で教えてもらうチャンスがなかったこと、5歳しか年が離れていないことなども影響しているのかもしれませんが、実は、正直先生だとは思っていないところがあります。ものすごく相談しやすいメンターと言いますか、ちょっと上のお兄ちゃんぐらいの気持ちでみています。例えていうなら、映画のアベンジャーズの中での、スパイダーマンに活躍の場を提供して成果を期待してくれる、アイアンマンのような存在です。研究だけでなく、プライベートの相談とかも気軽に投げ掛けたりできる、本当に付き合いやすい方だと思います。
下田 ── 私も大澤先生のことは、あまり先生とは思っていませんね。どちらかと言いますと、学校側の人ではなく、学生寄りの存在なのかなと感じています。学生に向かって、知識を教えて誘導して指導するというのが私の中の先生像だったのですが、大澤先生は、「一緒にやっていこう。一緒に悩もう」と学生に寄り添ってくれます。研究においても、何かをやれというのではなく、やってみたいと提案したら、否定するのでもなく「やれるものなら、やってみよう」という感じで、生徒の自主性にある種の信頼感を持って接してくれています。そして、学生が出来ないことに直面した場合には、キッチリとフォローしてくれるので、のびのびと研究できる研究室だと感じています。
── 自分よりも明らかに知識もスキルもある先生が、一緒に悩み込んでくれるということは、なかなか経験できないことです。安心して、難しいことに挑戦できそうです。山本さんはいかがでしょう。
山本 ── フォローするわけではありませんが、はっきりと先生だと思っています。僕は、浪人しても、留年しても、誰に怒られることもなく生きてきたようなところがあり、しっかりと指導してくれる先生がほしかったのかもしれません。大澤先生は、そんな僕にも本当にしっかり指導してくれます。普段から少しでも困ったことがあれば、大澤先生に相談しに行ってこようと思っています。師匠というのはおこがましいのですが、頼れる先生だと思っています。

頼れる仲間と先生に囲まれて、自分の名前で売り出せる成果を生み出す
── 研究室に入って、得たことがあればお聞かせください。
川島 ── 壮大な話になってしまいますが、人生をやり直すチャンスを得たなという風に思っています。実は僕も浪人して大学生になったのですが、特別何を成し得たということもなく、何も考えずに生きてきました。家族や親戚の目を感じながら、それがコンプレックスとなっていたのです。大澤研究室での、何でも自由にやっていいし、何かあれば全力でフォローするという恵まれた環境の中で、「ここで何かしら、僕の川島遼介という名前で売れるモノを作れるようにがんばってみたい」と思っています。実際に論文を書いたり、学会に出たり、という経験を通じて何者かになり始めている感触も感じています。
下田 ── 自分に自信が持てるようになりました。大澤研究室は、ドラえもんをつくるという大澤先生の夢に乗る研究室であると同時に、所属している学生一人ひとりが持つ夢を実現する研究室でもあると思っています。未知のモノに自分が挑戦していくことに対する自信や、自分が取り組むことに関する自信が、研究室に入る前よりもはるかに大きくなったように感じています。
山本 ── まだ発展途上の段階ではありますが、人との関わり方が少し上手くできるようになったような気がします。僕は、何でも自分一人で出来ると思いがちで、進んで人に自分の考えを打ち明けるようなことはしませんでした。それが、大澤研究室には、めちゃめちゃすごい人たちが、懸命に取り組んですごい成果を出しています。その様子を間近で見て、すごい人たちともっとたくさん会話し、何かを吸収したいという思いが高まっています。
 |
 |
-

-
第1部:
日本大学 文理学部 情報科学科 大澤研究室
次世代社会研究センター RINGS センター長
大澤 正彦 助教
-

-
第2部:
日本大学 大学院 総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻 博士課程前期1年
川島 遼介さん
日本大学 文理学部 情報科学科4年
下田 音里さん
日本大学 文理学部 情報科学科3年
山本 英弥さん
- Profile
-

-
川島 遼介(かわしま りょうすけ)
-
日本大学 大学院 総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻 博士課程前期1年
2020年 専修大学 大澤研究室 参画。 2022年 専修大学 卒業。同年 日本大学大学院 前期博士課程 入学。
同年よりRINGSセンター生。2019年からボードゲームショップにて販売員。600本のゲームを紹介できる販売スキルを活かし、現在は株式会社サイバーエージェントAI Labとの共同研究にて、商品販売エージェントの開発に従事。ロボットの有効性に着目する同社および大澤研究室の中で「ロボットは不要」という持論を展開中。
第1回文理研究交流アワード ベストプレゼンテーション賞受賞。

-
下田 音里(しもだ ねり)
-
日本大学 文理学部 情報科学科4年
2019年 日本大学文理学部情報科学科 入学。2021年 大澤研究室 配属。同年よりRINGS センター生。
「人を支える裏方になりたい」という志を掲げ、特定意志薄弱学生監視指導員として活動中。人の幸せを喜び人の不幸を悲しむことができるため、よく相談を受ける。
しかし研究テーマが、人の不幸を喜ぶ“メシウマ”感情(シャーデンフロイデ)であるため、印象とのギャップに驚かれることが多い。ネガティブな感情を理解することが、ネガティブな感情に寄り添えるドラえもんの近道と考えている。

-
山本 英弥(やまもと ひでや)
-
日本大学 文理学部 情報科学科3年
2018年 東京電機大学高等学校卒業(あと1日欠席で留年)。2019年 日本大学文理学部情報科学科 入学。2022年 大澤研究室 配属。同年よりRINGSセンター生。
現在までを振り返って、自分自身を「計画性のないのび太である」と自称。研究室配属後、「ドラえもんのめんどうみの良さ」と「しずかちゃんのかわいさ」を兼ね備えた秘書さんがいれば自分は頑張れると考え、かわいい秘書AIの開発を志す。現在、秘書AIの開発が遅れているのは、秘書AIが未完成だからとのこと。
- Writer
-
伊藤 元昭(いとう もとあき)
-
株式会社エンライト 代表
富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。
2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。
- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/

