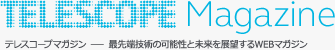生きるための体の働きを取り戻す遺伝子治療、
難病の根治には手が届きかけている
2017.02.28

人の体の働きが、細胞中にある遺伝子のレベルで解明されるようになった。これにより、これまで原因すら分かっていなかった難病を発症するメカニズムが、詳細に分かるようになってきている。さらに、遺伝子レベルで体の働きを正常な状態に戻す手段も開発されてきた。それが遺伝子治療である。体の外から、病気によって失った体の働きを取り戻すための遺伝子を導入し、難病の根治を目指す医療技術だ。パーキンソン病、アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、治癒は困難とされてきた神経関連の難病の克服は、もはや手が届きかけている。かつて遺伝子治療は、その安全性が疑問視された時期があった。しかし、医療技術の進歩によって、安全性に対する不安は払拭されている。既に遺伝子治療の研究開発の舞台は、大学などの研究室から、実用化を見据えた企業へと移りつつあるのだ。神経関連の病気を対象とした遺伝子治療の研究で数々の実績を挙げ、さらには実用化を加速するためのベンチャー企業まで設立した自治医科大学村松慎一特命教授に、遺伝子治療の最先端の動きと、実用化に向けた展望を聞いた。
── 遺伝子治療の最前線で研究されている先生が、東洋医学部門に籍を置いているというのは面白いですね。素人目には、医療技術の両極端を担当しているように見えます。
確かに奇妙に感じられるかもしれませんね。ですが、神経に関わる病気を扱う医師として、遺伝子治療と漢方は、何の違和感もなく両立していると考えます。これまで、脳や神経の病気は、治すことができないと思われてきました。このため、しびれやめまい、頭痛といった症状の緩和が治療の中心だったのです。こうした症状には漢方が有効でした。実際、今も私の外来患者の約8割に漢方を使っています。私は、学生時代から30年以上にわたって東洋医学を研究してきました。漢方自体は神経以外の病気でも重要な治療法のひとつですが、学内で最も詳しいのが私だったので、東洋医学部門の教授をしています。かつては、日本東洋医学学会の副会長もしていました。
ところが近年、神経の病気を治せる可能性がある医療技術が出てきました。それが遺伝子治療だったのです。症状を和らげるだけではなく、治癒させることを目指して、遺伝子治療の研究と実用化に注力しています。
生きるための機能を外から補う
── なるほど、対症療法として東洋医学が重要で、根治療法には遺伝子治療が必要だったということですか。先生が治療の対象としている神経の病気とは、どのようなものなのでしょうか。
日本では高齢化が急速に進み、20年後には80歳以上が人口の14.5%を占めると予測されています。そして、高齢になるとパーキンソン病やアルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多系統萎縮症(MSA)などの神経変性疾患に罹る人が増えてきます。神経変性疾患とは、脳や脊髄の中の特定の神経細胞が、徐々に死んでいくことで起きる病気です。パーキンソン病では筋肉がこわばって手が震えるといった症状が、アルツハイマー病では記憶障害や判断能力の低下といった症状が出てきます。
世界保健機関(WHO)の予測では、2040年には、がんや心臓病に次いで、あるいはそれら以上に、神経変性疾患が原因で亡くなる人が多くなるとみられています。これからの高齢化社会において、その治療の重要性は極めて高まり、遺伝子治療はそこで大きな貢献をすることでしょう。
── 遺伝子治療とは、どのような治療法なのでしょうか。
遺伝子には、私たちが生きていくために必要な、体を正しく動かしたり、維持・成長させたりするタンパク質を作る情報が書き込まれています。遺伝子治療では、体の外から遺伝子を患部の細胞中に入れることで、病気によって失われた正しいタンパク質を作り出す機能を回復します。
遺伝子を細胞に導入する方法には様々なものがありますが、私たちはベクターという、導入したい遺伝子を組み込んだウイルスを媒体として使う方法を採用しています。あらかじめ、ウイルスの遺伝子の中に導入したい遺伝子を組み込み、それを導入先の細胞(宿主細胞)に感染させます。すると、ウイルスは宿主細胞中に自らの遺伝子とともに目的の遺伝子も入れます。こうすることで、狙ったタンパク質を作り出す遺伝子が宿主細胞の中で発現(機能を発揮)し、病気を治すことができるのです。
遺伝子治療の安全性は飛躍的に高まった
── 体の外から遺伝子を入れる、しかもウイルスを使うと聞くと、ちょっと不安になります。副作用はないのでしょうか。
あまり心配することはないでしょう。
確かに、遺伝子治療の歴史は、決して平坦なものではありませんでした。遺伝子治療に用いるベクターには、レトロウイルス*1、アデノウイルス*2、アデノ随伴ウイルス(AAV)*3など、いくつかの種類があります。このうち、レトロウイルスでは、導入した遺伝子が人の染色体に組み込まれたことで、がんを引き起こす遺伝子を活動させてしまった例がありました。さらに、アデノウイルスでも、特殊な遺伝病を持つ患者の治療において、強烈な免疫反応による全身の炎症を起こして亡くなった例がありました。この2つの事故から、遺伝子治療はリスクが高い治療であるという印象を持った人は多いと思います。
ところが、AAVをベクターに活用する技術が確立され、こうした状況は一変しました。AAVを使った遺伝子治療は、血友病、網膜色素変性症、嚢胞性線維症などで盛んに臨床試験が実施されてきました。これまでに世界中で173の例がありますが、AAVベクターが原因とされる有害事象は全く発生していません。もちろん、私たちが取り組んでいる遺伝子治療の研究開発でも、AAVベクターを利用しています。
[ 脚注 ]
- *1
- レトロウイルス: 生物はDNAとRNAの2つの遺伝子を持っているが、ウイルスはこの内のひとつしか持っていない。DNAしか持っていないものをDNAウイルス、RNAしか持っていないものをRNAウイルスと呼ぶ。RNAウイルスのうち、感染した細胞の中で2本鎖RNAを一度2本鎖DNAとして複製し、それを宿主細胞の染色体に組み込んで発現するものをレトロウイルスと呼ぶ。大きさは80〜130nm。HIVやインフルエンザウイルスなどが、レトロウイルスの代表例であり、ベクターにはモロニーマウス白血病ウイルス(MoMLV)を利用する。レトロウイルスベクターには、遺伝子が子孫細胞に安定して伝わるといった特徴があり、長期に渡って遺伝子の発現を維持できる利点がある。
- *2
- アデノウイルス:
2本鎖直鎖状DNAを持つDNAウイルス。ウイルスの大きさは70〜90nm。アデノウイルスは、風邪の原因ウイルスのひとつである。アデノウイルスベクターは、多くの細胞種に感染し、約36キロ塩基(レトロウイルスは8〜9キロ塩基)と大きなサイズの遺伝子を導入できる利点がある。その半面、感染した細胞での遺伝子の発現は一過性であり、細胞毒性や免疫的傷害性が高い欠点を持つ。
なお、キロ塩基とは、核酸を構成する4種類の塩基いずれかが、いくつ連なっているかを示す単位である。36キロ塩基ならば、塩基が36000個連なってひとつの核酸の分子を構成していることを示している。キロベース(kb)と表示する場合もある。DNAのように2本の高分子が対になっている場合には、1対を1塩基としている。厳密に1塩基対(bp)と示す場合もある。
- *3
- アデノ随伴ウイルス(AAV): 1本鎖DNAを持つDNAウイルス。細胞内で2本鎖DNAに変換されて、導入遺伝子が発現する。自己増殖能力がなく、アデノウイルスなどと共に感染した時だけ増殖できる。このため、安全性が高い。ウイルスの大きさは18〜26nmで、遺伝子の大きさは約5キロ塩基。また神経などの終末分化した非分裂細胞にも遺伝子を導入可能で、さらに非分裂細胞中では長期間の発現が期待できる。その半面、導入できる遺伝子のサイズは4.5キロ塩基と小さい。