JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Laboratories
- 研究室紹介
人工生命の探求から、人間の本質をあらためて見つめる。
- 東京大学 大学院 総合文化研究科 池上研究室
- 第1部:
- 池上 高志 教授
- 2019.10.31
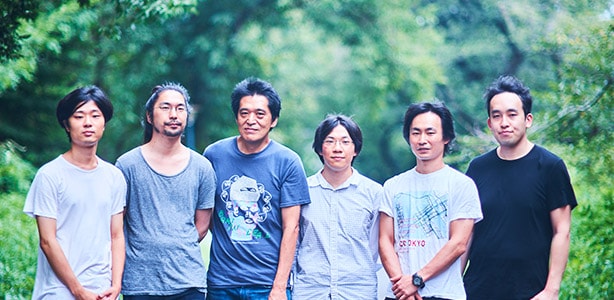
複雑系科学の研究者として「生命とは何か」という究極の問いに挑む、東京大学大学院の池上高志教授。アーティストとしても国内外で知られ、音楽家や写真家と共同アートプロジェクトに取り組むなど、その活躍は多岐にわたる。近年では、大阪大学の石黒 浩教授との共同研究として、オペラの舞台にも上がるアンドロイド「オルタ(Alter)」を開発、バージョンアップを重ねている。研究者とアーティストで、自身のスタンスに違いはないとする池上氏が語ったのは「生と死」の問題。研究室が生み出すALife(人工生命)で、それらに立ち向かえるのか。
(インタビュー・文/神吉弘邦 写真/黒滝千里〈アマナ〉)
-

-
第1部:
東京大学 大学院 総合文化研究科
池上研究室
池上 高志 教授
-

-
第2部:
東京大学
大学院総合文化研究科
修士1年
廣田 隆造さん
-

-
第3部:
東京大学
大学院総合文化研究科
博士研究員 升森 敦士さん、
特任研究員 土井 樹さん

生命と非生命の「境」は?
── 今回の号は「デジタルテクノロジーが拓くエンターテインメント新時代」という特集を組んでいます。池上先生が取り組むアートとエンターテインメントの世界は異なるものと知りつつ、お邪魔したのですが……。
池上 ── エンターテインメントは単に楽しめればいいのに対して、アートは「生死」の問題に迫るわけですから、まるで別物ですよね。優れたアート作品にはすべて「生と死の問題」が絡んできます。自分の本当に大事な人が亡くなりそうだという場面に遭遇したことありますか?
── かなり前なのですが、ありました。
池上 ── そうですか。僕も父を亡くしましたが、その瞬間にすごく思うことがある。そんなこととダイレクトに繋がるのがアートだと思うんです。「生命」を考えるとき、アートであっても研究であっても、そうした問題とは切っても切り離せません。
── 最初に伺いたかったのは、池上先生の中で「アーティストと研究者という立場が、どのように共存しているのか」でした。
池上 ── ひとりの人間が違った人格を2つは持てないように、僕の中で両者のスタンスは変わりません。「生と死」の問題を考えるという意味では、本当に同じなんですよ。
個々に興味深いと感じることがあって、それを計算したり、シミュレーションしたり、何かをつくったりする。そうやって世の中に発表したものを「それはアートだ」と言う人もいるし、「サイエンス的なことはわからない」と反応する人もいる。まぁ、論文を書いて、文字になると「研究」だと多くの人が思うみたいですが。
── 研究にはアートの側面があり、アートには研究の側面があると。
池上 ── ダ・ヴィンチに会いに行けたとして「あなたがやっているのはサイエンスですか? それともアートですか?」と聞いたら、「えっ、どういう意味ですか?」と返されるはずです。最先端にいる人たちは「自分はダ・ヴィンチのように領域を超えた活動ができるだろうか」と思いながらやっていると思います。
── 研究がどんどん細分化していったことで生まれた区別かもしれないですね。この教養学部棟(東大駒場キャンパス)の玄関にある案内板でも「○○学科△△専攻」という文字がズラッと並んでいました。
池上 ── それらは60~70年前に、官僚の皆さんが決めた枠組みです。でも、世の中はどんどん変わっています。対象そのものが、今までの枠に入らない場合があるでしょう。例えば「脳科学」をどういう分野で扱うか?
── 現在の所属とは違うのでしょうが、キャンパスで見かけた看板によると、先生の研究室は、かつて「物性理論研究室」だったんですね。
池上 ── 脳も原子分子からできていますからね。「同じ原子分子から、なぜ、脳みたいなものが出現するか?」を考えるのも面白いかも。同じ原子や分子が“生(せい)”になることもあれば、非生命的な物質の材料になることもある。その境は何か? そう考えることもできる。
 |
池上 ── もしかしたら「生と死は哲学の問題だから、科学者が考えたって仕方ないんじゃないか?」と言われるかもしれないけど、「人間性」の問題とか、「生死」の問題こそ、技術により答えを出せる問題だと僕は思うんです。哲学書で「この文章の中に、人間性や生死の本質がある』と言われたって、いつまで経っても処理できないじゃないですか。
自分から外在化された技術の中で問われることで、初めて「生と死」の問題について考えを新たにでき、やがて克服できるのだと思います。だからこそ、人工生命というものは重要です。こういう少し変わったかたちで「生命とは何か?」をわかろうとしているんです。
 |
「自律性」の有無が鍵になる
── 石黒 浩教授(大阪大学)との共著(『人間と機械のあいだ 心はどこにあるのか』)を読み、池上先生がテーマにする「ALife(人工生命)」とは何かと考えました。極言すると「身体を持ったAI(人工知能)」ということになるのかと感じたのですが。
池上 ── 僕自身はそういう風に思ったことはないです(苦笑)
── 失礼しました……完全に著書を読み違えています。
池上 ── いえいえ。では、わかりやすい例で考えましょう。クルマに人間の脳をただ乗っけても「生命」にはなりませんよね。そこが生命とロボットの違うところです。身体を持つロボットの中に、ディープラーニングでつくった情報処理のネットワークがある場合も同じです。これならALifeと言えるのではないか……そう考えてしまう人がいたならば、それは誤解です。
── 先ほどの著書には「機械化と人工生命は違う」という記述がありました。そこでキーワードになるのが「自律性」だと。出来の悪い生徒で恐縮ですが、自律性という言葉の解説をお願いしたいです。
池上 ── 出来の悪い学生との議論は好きじゃないんだよなぁ(笑)。それは冗談として、馬に乗られたことはありますか?
── ええ。
池上 ── それならば話が早い。自分で馬に乗っているときとクルマに乗っているときを比べると、馬には任せる部分も多いじゃないですか。馬が行きたいところ、自分が行きたいところの協調行動の結果として、前へ進んでいくでしょう。
馬を信頼したり、馬が好きなことを考えたりもしますよね。長く走らせたら「苦しくないかな」と心配して、停まって水を飲ませる。いわゆる“心のボンディング(結び付き)”というものがあるけれど、さすがのクルマ好きも「愛車が苦しんでいるかな?」と心からは思わないでしょう。
── 確かに、普通そこまでは考えないです。
池上 ── 今、盲導犬の代わりにAIやスマホに視覚障害者を誘導させようとする研究がありますが、はたしてスマホは盲導犬にとって代われるか。「両者の違いは何か?」です。ALifeは、その点について考える問題とも言えます。
── すごく高度なセンサを持ったロボットが、経験を積んで自分で判断をする機能や能力を持ったとしても、それは池上先生の考える「自律性」ではない。
池上 ── 現代の技術開発は、そういった機能的なものばかりを考えています。飛ぶという機能は同じだから「飛行機は鳥が進んだもの」と捉えるような科学技術が発展している。でも、犬の機能はなんだ? カブトムシの機能は? 僕らはそこにアンチテーゼを唱えるところから始まったんです。つまり、機能からは考えない科学技術。
── それを実証するのがALifeなのでしょうか。
池上 ── 生命のそういう点を強調するのがALifeです。僕はこうしたことこそが「生命」の本質かと思います。そういう意味で「生命」と「心」の理解は、かけ離れたものではないと思っているんです。
 |
機械に意識は宿るのか?
── 心、つまり意識を持った機械を将来つくることはできるのでしょうか?
池上 ── 可能だと思います。実際、まさにそれをやろうとしています。人工の意識は、将来的には生成可能だと思いますよ。
── そのための条件というのは?
池上 ── それがわかっていたら、もう完成していますね(笑)。おそらく、意識自体は「人間から取ってくる」ことになると思っています。意識というのは、人間と接触することで、人間から伝染するものだという仮説です。
人間同士がしゃべっていると、他の人から「心」も移ってくる。例えば、仲のいい人同士は、ものの見方が似てきたり、振る舞いも似てきたりするじゃないですか。
生まれてから一度も社会と接触しない人間がいたとしたら、その人の意識や心の状態というのは、ものすごく我々と違うものだと思うんです。あるいは、生まれてきたばかりの子どもは「心」がなくて、お母さんからどんどんコピーされるものである、と。学校というものも、いろんなかたちの「心のコピー」を融合しながら生まれ育っていくための場なんでしょうね。
── 生まれてきた子どもは、心を学習していく。
池上 ── そうです。トレヴァーセン*1の行った実験に「子どもとお母さんの実験」があります。お母さんが笑うと、子どもも笑顔になる。お母さんが怒ると、子どもも怒った顔をする。一見、お母さんから子どもに対して、情報が一方的に流れているように見えますが、お母さんの笑顔や怒った顔をビデオ映像に置き換えた途端、子どもは真似しなくなってしまう。非常に微細なんですが、「真似してもらっている」といった情報がお母さんへと流れることで、模倣が初めて成立するんですね。
 |
池上 ── 今つくっている「オルタ3(Alter 3)」というアンドロイドも、目の前に来た人の真似をするようプログラムされています。ただし、英国の「バービカン(Barbican)ミュ―ジアム」で展示したときは、来場者の側がアンドロイドのほうを一生懸命に真似していたんです。「真似してくれ」なんて、ひと言も言ってないですよ。一見すると、どっちが模倣しているのか、よくわからない状況になるんです。
しかし「ああ、そうか。われわれ人間、生命体というものは、やはり人間的な意図が感じられると模倣するものだ」と再確認しました。そのことで、アンドロイド自身の模倣の学習と記憶をもとに、彼自身の運動のスタイルを生成していく実験が進んでいます。
── 人間の表情だとか表現、あるいは感情といったものは、外から来たものの反映であって、ただ学習したものを再現しているということですか?
池上 ── 最初はそうであっても、あるところでトランジション(遷移)が起きるんです。つまり、模倣している状態の先に、自分の「固有性」というものが生まれ、それを徐々に発露していく。人間だと3歳くらいから移り変わっていくんじゃないでしょうか。
── なるほど。ちょっと安心しました(笑)。
池上 ── そうは言っても、人間はそれくらいの年齢までが面白いと思うんですよね。3歳の「心」を維持できる装置ができるなら、僕は全力でつくりたい。彼らは純粋なんです。ちゃんと考えたままにしゃべるし、くだらないことを考えないし、社会に染まっていない。さっき言ったことと矛盾するわけではなく、人間や生命とは、本来そういうものなんだと思います。僕の恩師の津田一郎*2さんが『心はすべて数学である』という本を書かれていますが、本当にそう思う。あるいは「数学はすべて心である」のかもしれない。
人間って「意味の病」にかかり過ぎると思うんです。「それにどういう意味があるのか?」とか。さっきの機能重視問題と同じです。僕は、そうしたものから逃れたい意識が強い。「意味」に絡め取られないよう、頑張って抽象的な世界に逃げるのかもしれません。だから元気がないときは、数学の本を読むと元気になります(笑)。
── YCAM(山口情報芸術センター)で展示された「MTM[Mind Time Machine]」も「意識」をテーマにした作品でしたね。
![池上高志「MTM[Mind Time Machine]」(2010年)](./img/MTM.jpg) |
池上 ── 僕の「意識」の定義は、「記憶を貯めながら維持できるもの」。記憶を自己組織化しながら維持して、長く編集して使えるようにする仕組みです。機械に比べたら、生命って長持ちしますよね。人間は80年とか100年とか生きますから。そういう生命活動をちゃんとメンテナンスする仕組みとして、意識が存在するのだと思います。
池上 ── Googleなどが持っているいくつかの仕組みは、巨大なデータシステムが落ちないように頑張って非同期に、並列的に処理するシステムですが、「それこそが意識だ」と僕は思いました。実際、そういう仕組みは脳にも見られます。長時間にわたって大規模に、並列的に動くシステム。誰かが中央集権的に一生懸命やっていない分散的な仕組みです。そうした構造の中に、おそらく「意識」の片鱗が見えるんじゃないかと。
そういうもののミニマルな機械をつくって山口情報芸術センターの屋外に3カ月間置かせてもらい、「放っておいたらどう進化するか?」を試しました。そうした「遊ばせ方」を大っぴらにできるのが、アートの良いところです。
 |
人工生命が多様性をもたらす
── 池上研究室には今、どんなメンバーが集まっているのですか。
池上 ── 多様性があったほうがいいと思っていて、これまでも哲学者とか、生物学者とか、言語学者とか、物理学者とか、いろんなバックグラウンドの人が集まって、さまざまな議論ができる場にしてきました。だから、全員を共同研究者と考えていますね。研究テーマは彼らが持ってくるものもありますが、僕から提案することもある。「こういうのやろうぜ!」と。
── それは先生が必要だと思うテーマだったり、学生さんを見て「こういうテーマが得意だろうな」と考えたりするのでしょうか。
池上 ── 雑談して話すうちに、面白そうなテーマが見つかるんですね。「この問題って、どうやって取り組めばいいんだろう?」と始まる感じです。彼らはプログラミングのスピードも僕より優れている。僕が教えられるのは、ある種の「図々しさ」とか「どこかでやったのと同じものだから使えるぞ」みたいな経験則だけです(笑)
大学というのは、相互作用的な場所だと思います。学生と話をする必要性を感じないのなら、企業の研究所に入って独りでやればいい。研究が生活の一部になっている状況で、彼らと話し合えることがキャンパスの良さ。むしろ、それ以外のメリットはないんじゃないかというくらいです。
── 最後に、今後の研究の目標をお聞かせください。
池上 ── ヒューマニティーを助けるテクノロジーというか、本当の意味での「多様性」を日本にどう持ち込めるのかを考えています。
日本の社会では、日本国内だけのマーケットに向け、日本の会社がいろいろなものをつくってきましたが、そういう仕組みがもう限界になっている。外から人を全然入れない、とても変わった国です。数日前のワシントン・ポストに、日本特派員からのこんな記事が載りました。「米国で移民を抑制するとどうなるのか知りたければ、日本に来るといい。この奇妙な国は多様性を捨てて均質性を選んだことで、徐々に滅びゆく道を歩んでいる」と。
多様性という意味で、これからALifeは日本でも大事な存在になっていくはずです。僕は「ALife everywhere」という言葉を使っていますが、あらゆるところにALifeが作られ、人々が自由に接触できる未来になったら、もうちょっと生命のみかたが変わり、多様で面白い社会になるんじゃないかと考えています。
── 非常に楽しみです。そうした研究室の成果に触れられるオープンな機会というものはありますか?
池上 ── 今年の5月に「東京大学芸術創造連携研究機構」という組織が立ち上がり、トークイベントやシンポジウムのかたちで社会連携をしています。また、来年3月には人工生命に関するちょっとした国際会議の開催を予定していますので、その場で私たちのALifeの研究成果も報告できると思っています。
 |
 |
 |
-

-
第1部:
東京大学 大学院 総合文化研究科
池上研究室
池上 高志 教授
-

-
第2部:
東京大学
大学院総合文化研究科
修士1年
廣田 隆造さん
-

-
第3部:
東京大学
大学院総合文化研究科
博士研究員 升森 敦士さん、
特任研究員 土井 樹さん
[ 脚注 ]
- *1 コールウィン・トレヴァーセン(Colwyn Trevarthen):
- 1931年生まれ。英国の児童心理学者、心理生物学者。エジンバラ大学名誉教授。共著書に『自閉症の子どもたち―間主観性の発達心理学からのアプローチ』、編書に『絆の音楽性: つながりの基盤を求めて』がある。
- *2 津田一郎:
- 1953年生まれ。日本の数理科学者、応用数学者、物理学者、文芸家。脳のダイナミクスにいち早く着目し、カオス脳理論、脳の解釈学を提唱。複雑系科学研究の先駆者として世界的に知られる。著書に『カオス的脳観―脳の新しいモデルをめざして』『ダイナミックな脳 カオス的解釈』『脳のなかに数学を見る』ほか。
- Profile

-
池上 高志(いけがみ たかし)
-
東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 広域システム科学系教授、
複雑系科学研究者。博士(理学)。1961年長野県生まれ。
1984年東京大学理学部物理学科卒業。1989年同大学院理学系研究科物理・博士課程修了。1990年神戸大学大学院自然科学研究科助手。1994年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻助教授(准教授)を経て、2008年より現職。2017年6月より「あらゆるものに生命性をインストールする」というビジョンを掲げて設立された、株式会社オルタナティヴ・マシン最高科学責任者(CSO)に就任。
複雑系とALife(人工生命)という方法論で、「生命とは何か」という究極の問いに研究者として取り組みながら、世界的なアーティストとして活動。⾳楽家・渋⾕慶⼀郎⽒とのプロジェクト「第三項⾳楽」「Filmachine」(2006年)、「Alter」(2017年)、写真家・新津保建秀⽒とのプロジェクト「MTM」(2010年)、「LongGood-Bye」(2017年)など多岐にわたる。Ars Electronica Honors mention(2007年)・STARTS PRIZE(2018年)、文化庁メディア芸術祭(2010年)審査委員賞・優秀賞を受賞。
著書に『動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ』(青土社)、『生命のサンドウィッチ理論』(講談社)。共著に『複雑系の進化的シナリオ』(朝倉書店)、『ゲーム―駆け引きの世界』 (東京大学出版会)、『人間と機械のあいだ 心はどこにあるのか』。共訳書にAndy Clark著『現れる存在―脳と身体と世界の再統合』(NTT出版)がある。
- URL: http://sacral.c.u-tokyo.ac.jp/
- Writer
-
神吉 弘邦(かんき ひろくに)
-
1974年生まれ。ライター/エディター。
日経BP社『日経パソコン』『日経ベストPC』編集部の後、同社のカルチャー誌『soltero』とメタローグ社の書評誌『recoreco』の創刊編集を担当。デザイン誌『AXIS』編集部を経て2010年よりフリー。広義のデザインをキーワードに、カルチャー誌、建築誌などの媒体で編集・執筆活動を行う。
2018年8月より、アマナ「NATURE & SCIENCE」編集長。 - URL: https://nature-and-science.jp/

