JavaScriptが無効になっています。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- Science Report
- サイエンス リポート
過去や未来へ旅しよう!
タイムマシンは実現できるか?
- 文/鳥嶋 真也
- 2020.02.28
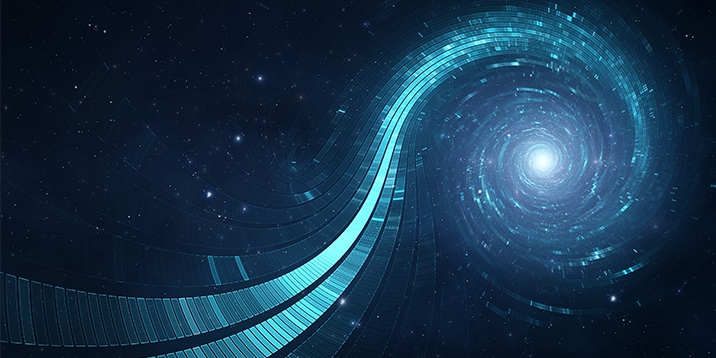
過去をやり直したい、未来の自分が何をしているか見てみたい――。誰でも一度は、そんな妄想をしたことがあるに違いない。その妄想を叶える道具として、古今東西さまざまな作品に出てくるのが「タイムマシン」である。超光速航法(ワープ)と同じく、現代の科学では実現不可能とされているが、相対性理論やワームホールなどをうまく使うことで、もしかしたら可能になるかもしれないという研究が行われている。どうやって過去や未来に行くのか? 本当に行けるのか? そして、タイムトラベルが実現したら、どんなことが起こるのか? といった謎について迫ってみたい。
タイムマシンとは?
世界で初めて「タイムマシン」というガジェットを持ち出し、過去と現代、そして未来を自由に行き来できる「タイムトラベル」を物語として紡いだのは、1895年に作家H・G・ウェルズ(1866~1946年)が発表したSF小説『タイムマシン』だった。
その後、多くの作品でタイムトラベルが描かれ、またタイムマシンという乗り物に乗って時間移動するものだけでなく、時空に穴を空けるなどして、その中を通って過去や未来に移動するもの、さらに通信などを介して情報や記憶のみを移動させるものなど、じつにさまざまな形態のタイムトラベルが描かれてきた。
 |
タイムトラベルもまた、超光速航法と同じく、現代の技術では実現は不可能とされている。しかし、まだ見つかっていない物質などがあると仮定した状態で、数式の上では実現できそうだという研究があり、いまもさらなる研究や、また議論の的となっている。
そのはじまりとなったのは、連載第2回の超光速航法の回でも触れた、米国の物理学者キップ・ソーン氏(1940~)の研究である。天文学者のカール・セーガン(1934~1996)が小説『コンタクト』を執筆しているとき、地球から約26光年離れた、こと座のヴェガにある惑星へ瞬時に移動する方法はないかと考えた。セーガンはまず、ブラックホールを使って移動することを考え、友人でもあったソーン氏に、それが理論的に正しいかどうか検証を依頼。その結果ソーン氏は、ブラックホールよりワームホールを使ったほうがいいと考えた。
ワームホールとは、その入口と出口が時空を貫いて直接つながったトンネルのようなものである。たとえるなら、『ドラえもん』に出てくる「どこでもドア」のようなもので、ワームホールのある一方の出入り口を地球に置いたとして、もう一方の口を月に置こうが、火星に置こうが、あるいは何億光年離れた星に置こうが、その間の時空を貫いて、瞬時に移動できる。
ワームホールが存在しうるということは、物理学者のアルベルト・アインシュタイン(1879~1955)が一般相対性理論を作った直後の1916年には、計算で導き出されていた。ソーン氏はそれをもとに、ワームホールで本当に超光速航法は可能なのか、そしてその実現には何が必要なのかといったことを考え、理論を考案。『コンタクト』に活かされたばかりか、論文としても発表した。
もっとも、その実現のためには「エキゾチック物質」と呼ばれるもののひとつである、“負の質量”をもった物質が必要であるとされている。さらに、これはあくまで仮定の物質であり、実在することは証明されていない。また、その後ほかの科学者による研究などでは、ワームホールを作るには宇宙を創り出すのと同じくらいのエネルギー量が必要であるとされたり、やはりワームホールを作ることなど不可能なのではないかといった研究結果が出されたりなど、あくまで計算上の話であるうえに、異論も多い。
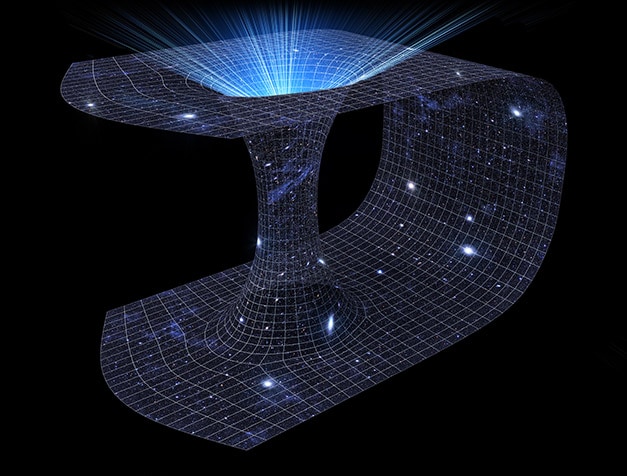 |
タイムマシンを実現する鍵は浦島太郎にあり
このアイディアを考案したソーン氏は、その後、同僚からの指摘もあり、この方法で超光速航法ができるならタイムマシンもできるのではないか? と思いつく。まず、ワームホールの入口を地球に置き、出口をロケットに載せ、光速に近い速さで移動させたのち、地球に帰還させる。すると、タイムマシンができるというのである。
狐につままれたような話だが、この理論の基礎にあるのは「ウラシマ効果」というものである。相対性理論では、時間の進み方は見る人の場所によって変わる、すなわち相対的であるとされており、速く移動するものは、外から見ると時間の流れがゆっくりになって時間差が生じ、また速度差が大きければ大きいほどその時間差も大きくなる。さらに光速に近づくにつれて、その物体の時間の進み方はゼロに近くなり、つまり時間が止まったかのように見える。たとえば、ほぼ光速で飛べるロケットに乗り、その中で1年過ごすと、地球上では50年もの年月が流れるのである。
ちなみにウラシマとは、昔話の『浦島太郎』で、竜宮城に小一時間しか滞在していなかったにもかかわらず、浦島太郎が砂浜に戻ってくると、友達がみんな老人になっていた、という話に由来する。もちろん、この話が創られたころにはタイムマシンの概念はなかったが、たとえば助けた亀に乗った浦島太郎が光速に近い速度で移動していたとしたら、この話の辻褄が合う。
そして、このウラシマ効果とワームホールをうまく使えば、理論的にはタイムマシンを作ることができる。まず、2020年にワームホールを作ったとする。このとき、ワームホールの両側の出入り口の時間は、同じ2020年である。次に、一方の口だけを宇宙船に乗せ、光速に近い速さで飛ばしたのち、地球に帰還させる。すると、地球は2030年になっているのに、宇宙船の中は2021年にしかなっていないということが起こる(この時間差は宇宙船がどれだけ光速に近い速度で飛ぶかによって変わる)。
そして、2030年の地球の人がその宇宙船に乗り込み、中のワームホールに入る。すると、そのワームホールは2021年の時間にあるため、それを抜けた先も同じ時間、すなわち2021年の地球に行くことができるのである。
もちろん、これにはまず、前述のようにワームホールが本当に存在し、そして負の質量をもったエキゾチック物質が本当に存在して、人や宇宙船が通れるようなワームホールを人工的に作り出せることができ、さらにワームホールの位置を自由に動かすことができるなら……という、いくつもの条件がつく。現時点では、そのどれもが実現しておらず、見込みも立っていない。
 |
超光速粒子「タキオン」で過去に情報を送る
人や宇宙船ごとタイムトラベルするのは難しいかもしれない。しかし、それとはまた別の方法で、そしてもう少し簡単そうな方法が、第2回で触れた超光速粒子「タキオン」を使って過去に情報を送るというアイディアである。
タキオンはエキゾチック物質のひとつと考えられている粒子で、つねに光速を超える速度で運動しているとされている。あくまで理論上考えられうるというもので、これまでに実際に観測されたことはないが、仮にタキオンが存在し、そしてその粒子を、電波や光のように利用して通信ができるとしたら、過去にも未来にも情報を送ることができると考えられている。
ここで使うのは、ワームホールを使ったタイムトラベルでも使った、光速に近い速度で飛ぶ宇宙船とウラシマ効果である。まず、地球から宇宙船を光速に近い速さで打ち上げる。そして、地球上の時間である程度が経ったころに、タキオンを使って地球から宇宙船に向けて情報を送る。超光速で飛ぶタキオンは、すぐに宇宙船に追いつき、その情報が伝えられる。このとき、宇宙船の中の時間は、情報を送った地球の時間よりも大きく遅れているため、たとえば地球の時間で2050年に情報を送ったら、宇宙船の時間では2050年よりも前にその情報が届くことになる。
そしてこのとき、宇宙船側からは、地球のほうが光速に近い速さで遠ざかっているように見えている。つまり宇宙船からすれば、地球のほうが時間の流れが遅くなっているのである。そして、宇宙船から地球に向けて、先程届いた情報をそのままタキオンで送り返すと、宇宙船の中の時間よりもさらに過去の地球に、すなわち情報を送った2050年よりも前に、その情報が届くことになるのである。
少し釈然としない感じもするが、前述のように時間の進み方は見る人の場所によって変わる(相対的である)ことから、理論的には矛盾していない。
もし、こうしたタキオン通信が実現すれば、たとえば番号選択式の宝くじの当たり番号を過去の自分に教えたり、事故に遭う前の自分に気をつけるように忠告したりといったことができるかもしれない。
 |
タイムパラドックスと時間順序保護説
ところで、もしタイムマシンやタイムトラベル、過去への通信が実現したら、とても大変なことが起こってしまう。
1985年の映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では、主人公のマーティが、ひょんなことから30年前にタイムスリップし、自分の父と母が出会うきっかけを邪魔してしまう。2人が結ばれなければマーティが生まれることもないため、自分の存在が消滅する危機に直面。それを回避するために奮闘する様子が描かれる。
 |
このように、もしタイムマシンが実現し、過去に行って自分が生まれてこないように改変したとすると、自分という人間は存在しなくなるため、タイムマシンで過去を改変することもできなくなってしまう。ところが、過去を改変しなかったら、自分は生まれるはずであり、タイムマシンで自分が生まれる前の時代に行くことが可能になり……と、話が堂々巡りになる。あるいは、前述のタキオン通信の活用例でいえば、過去の自分が宝くじで大金持ちになったり、遭うはずだった事故に遭わずにすんだりと、過去と現在に矛盾が生じてしまうのである。
実際に、過去と現在に矛盾が生じるようなタイムパラドックスが起こった場合、自分や世界はどうなるのか? ということを巡っては、さまざまな仮説がある。
たとえば「多世界解釈」という考え方では、過去にさかのぼって自分の出生を改変した時点で、「過去を改変していない宇宙」と「過去を改変した宇宙」(並行宇宙)とが生まれるとされる。その結果、自分は「過去を改変していない宇宙」で生まれたので消えることはなく、その一方で「過去を改変した宇宙」が生まれ、自分が存在しない世界が続いていくのだという。
別の仮説では、この世には因果律、すなわち原因と結果の間には一定の関係が存在するという原理を、厳格に守ろうとする力が存在し、過去を変更しようとしても、なんらかの形で邪魔が入って、どうやっても過去を改変することができないという考えもある。さらに、過去を変えた結果、その変えた過去のほうが真実となり、つまり自分は過去を改変せずに存在しているということに落ち着く、という説もある。つまり「過去に戻ろう」、「過去を改変しよう」といった、人間が自分の意志で決めたはずのことも含め、すべての物事は因果律が支配しており、すなわち人間の自由意志など幻想に過ぎないという前提に立った仮説である。
こうしたなかで、とりわけ「タイムトラベルは不可能」と強く主張していたのが、かの有名な理論物理学者スティーヴン・ホーキング(1942~2018)である。彼は1990年に「時間順序保護仮説(Chronology Protection Conjecture)」という仮説を立て、ソーン氏の研究などのように、たとえ相対性理論のうえでは矛盾しないタイムマシンが仮定できるとしても、相対性理論と並んで現代物理学の根幹をなす「量子論」によって、因果律は保護されているのではないかと提唱。実際にはワームホールは量子重力的不安定性により壊れて通ることはできず、それを維持するには無限大のエネルギーが必要である、すなわち不可能であるとしている。
彼はまた、「量子論がタイムパトロールの役割を果たすに違いない」という比喩を用いて、この仮説を説明している。
 |
タイムマシンはすでに存在する!?
ここまで、とても実現しそうにないタイムマシンについて見てきたが、最後に、すでに存在するタイムマシンについて紹介したい。
前述したウラシマ効果では、光速に近い速度で飛ぶ宇宙船を例に出したが、じつはそこまで速くなくても、ウラシマ効果は起こることがわかっている。
たとえば、地上と人工衛星にそれぞれものすごく正確な時計を置き、時間の流れ方を見比べると、秒速数kmの速さで地球を回る衛星の時計は、地上の時計よりもゆっくり進むことが実際に確認できる。ちなみに、スマホなどでおなじみのGPS(グローバル・ポジショニング・システム)は、衛星から正確な時間を発信することで測位・航法などを行っているが、この時間のずれが大きな問題になるため、地球上の時計と完全に一致するように、GPS衛星に搭載されている時計は1秒間に100億分の4.45秒遅く進むよう補正されている。
人工衛星に限らず、時間の相対性はどんなものの間でも生じる。たとえば立ち止まっている人と飛行機、新幹線、自動車の間でも、私たちが気づかないほどきわめて小さいものの、時間の進み方に差が生まれているのである。
 |
ウラシマ効果では未来に、それも現代の科学力では誰も気づかないほどの、ほんの少しの未来にしか行けないが、それとは別に過去を見ることができるタイムマシンもある。
第2回で触れたように、光の速度は有限である。そのため、遠くにある天体の光が地球に届くまでには、その距離に応じて時間がかかる。たとえば、私たちの頭上でさんさんと輝く太陽なら約8分前、オリオン座の「ベテルギウス」なら約642年、アンドロメダ銀河なら約250万年前に出された光が地球に届いている。つまり、天体望遠鏡で遠くの宇宙を見るということは、昔の宇宙を見ているということなのである。
そして、もしかしたら私たちは見ている側だけでなく、見られている側かもしれない。この宇宙には無数の恒星があり、そこにはさらに無数の惑星が回っている。地球からほんの数十光年以内にもいくつもの恒星があり、これまでの観測で地球に似ている可能性がある惑星もいくつか見つかっている。
もし、どこかの惑星に地球のような、あるいは地球より進んだ文明があれば、望遠鏡を使って、私たちの過去の行いを覗かれているのかもしれない。
過去から学び、より良い未来を創っていくこともまた、ある意味でタイムマシンであり、そしてその最もいい使い方なのかもしれない。
 |
- Writer
-
鳥嶋 真也(とりしま しんや)
-
宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。
国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。
- Webサイト:http://kosmograd.info/
- Twitter:@Kosmograd_Info

