昔から変わらない
「東京エレクトロン」マインドとは?
OB×若手座談会
Culture

東京エレクトロングループは、あらゆる世代の従業員がお互いを尊重しあい、高い志に向かって進んでいける企業です。今回は、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズのさまざまな部署で働く5名の若手社員が集まり、開発畑で定年退職まで勤め上げたOBをアドバイザーに迎えて、座談会を実施。ここで働く醍醐味や会社の好きなところ、成長するためのマインドなどを話しあいました。
プロフィール
-

人事部
中澤ゆきな(ファシリテーター) -

アドバイザー
保坂 重敏1985年入社。長年、開発畑に従事し、2021年に定年退職したあとはアドバイザーとして、人事業務をサポート。「OBとして、後輩たちとお互いの経験を共有しあえたら」。 -

要素技術開発第二部
瀬本 宗久2018年入社。プラズマ装置の要素技術やモニター技術の開発、新規装置の設計・開発を担当。先日、入社以来ずっと関わってきた装置が顧客に納入され、達成感を感じている。 -

シミュレーション技術開発部
京兼 広和2018年入社。機械学習やデータサイエンスの基礎開発を担当。わずかな実験データから仮説を立てて、未来につながるモデリング技術を開発することにやりがいを感じている。 -

TS開発部
糠信 知基2018年入社。製品開発グループに所属するエレキエンジニア。現在は主に新規開発装置における、ウェーハ搬送系ユニットシステムのエレキ設計業務オーナーとしてプロジェクトを牽引。 -

要素技術開発第一部
深見 駿2019年入社。次世代の装置に搭載するガスの流量制御技術を、海外サプライヤー・メーカーと協業して開発した経験をもつ。環境負荷低減などのニーズも見越した新規アイテムの開発に従事している。 -

制御技術部
南 真彩2019年入社。エレキエンジニアとして、開発装置・量産装置を担当。複雑な設計をどれだけ簡略化できるかが設計者の腕の見せ所なので、難しそうな案件にこそワクワクするという。
- 座談会を実施した2023年12月時点の情報です。
自分のやりたいことは主張するのがTEL流
東京エレクトロン(以下:TEL)グループで働いてきて、特にやりがいを感じた仕事や印象的だった出来事、得た学びを教えてください。
糠信
私は、ちょうどいま担当している新規装置開発プロジェクトにとてもやりがいを感じています。案件が動き始める前から、上司に「エンジニアとしてシステムの全体を見てみたい」と伝えていたため、ウェーハ搬送系ユニットシステムの設計業務オーナーを拝命。それまでシステム設計のオーナー経験がなかったので自分に務まるかは不安でしたが、周囲のサポートもあり、もうすぐ納品というところまでこぎ着けています。

保坂
初めてのオーナーだったんですね。特にどんなところが大変でしたか?
糠信
技術的な部分やスケジュールはもとより、自分のやりたいことと周囲の流れが違ったときには悩みましたね。「装置の環境性能を見える化するために電力センサーを付けるか?」という議論で、私は付けたほうがいいと考えました。でも、従来の類似案件ではセンサーを付けず、消費量を推測することが多かったんです。もちろん、新たにセンサーを搭載すればコストは上がります。でも、これからの開発にはそうした環境配慮が当たり前になっていきますし、省エネ性能を上げることで装置の付加価値も高まる。最終的には、自分の提案が通り、電力センサーを装置に実装しました。
保坂
それでいいと思いますよ。根拠のある提案なら「自分はこう思う」と主張するべきだし、そこで遠慮したらTELらしくないからね。
糠信
じつは上司にも、まさに保坂さんのおっしゃるように「やりたいことを主張していいよ」と背中を押してもらったんです。プロジェクトが進み、設計どおりに動作確認できたときはうれしかったですね。提案が通ったぶん、リリース後はちゃんと成果が出てほしいと願っています。
瀬本
私は合併時の思い出が印象深いです。山梨と東北の拠点が合体し、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズができてまだ一年も経たない頃に入社したため、当時はまだ、お互いのルールを確認しているタイミングでした。私が開発を担当していた装置は、まさに合作の第一号。細かな仕事のやり方を一つずつすりあわせていく必要があり、コミュニケーションに苦労はあったと感じます。でも、どちらも自分たちのルールを押し付けたいわけではなくて、どうやったらうまくいくかを考えていましたので、一つの目標に向かっている一体感がありました。

保坂
同じ仕事を進めていくにも、各拠点でまったく文化が違ったりするんですよね。私にも経験があります。でも、お互いにいいものをつくろうとする意識があるから、最終的にはなんとかなるというか。
瀬本
そうなんです。それに、別拠点だった人たちと新たに連携していく経験が、また別の仕事につながったりもします。コミュニケーションが欠かせなかったぶん、お互いの人となりを知る機会も多かったと思います。私たちの同期がとても仲が良いのも、そうした経験を分かちあったおかげです。合併による人との交流が、のちの大きな財産にもなりました。
切磋琢磨して、お互いの力を伸ばしていく社風
みなさんが思う「TELグループの好きなところ」を教えてください。
南
先ほど糠信さんのお話でもあったとおり、一人ひとりの意志を尊重してくれるところが好きです。私は入社2年目のとき、さっそく開発装置の立ち上げに参加させてもらいました。もともと興味があったため見学したいと申し出ていたら、上司が「じゃあ担当してみたら?」と一言。エレキエンジニアの代表として別部署のミーティングなどにも出席し、立ち上げの終わりまでをしっかり見届けることができました。私のような新人がチャレンジさせてもらえるんだと驚きましたが、自信を育むきっかけになりました。

保坂
やる気に対して機会を提供することやチャレンジ精神は、TELに創業時からあるマインドだと思います。いい経験をしましたね。
南
もちろん業務はわからないことばかりでしたが、投げ出されてしまえばおのずと勉強しますし、なんとか対応することができました。それよりも、信じて任せてもらえたことがうれしかったです。部署内の面談が多く、上司との距離が近いところも気に入っています。「当社は風通しがいい」というセリフはどこの会社でも聞くけれど、TELは本当にいいです。
保坂
昔は改まった面談はなくて、コミュニケーションはもっぱら夜の飲み会でした(笑)。でも、世代や年次を問わず意見をかわしあえるのは、昔からのカルチャーですね。
南
どんなに若手でも会社に対して意見を言える空気があるからこそ、TELが進化し続けられるんだろうなと思いますね。
京兼
分かります。根っこの部分に風通しのよさがありますよね。それから私もやっぱり、社員のやりたいことをポジティブに受け止めてくれるところが好きです。

いまの私の部署はデータサイエンスを扱っているのですが、入社時はまだプロセス技術の分野でデータを積極的に活用する働きはなく、専門のチームもありませんでした。入社2年目にデータ活用をおこなうチームができ、私もそのチームに入りました。そこで「経験的にやる仕事は属人化してしまうから、いまあるデータを活用して、誰でもデータドリブンで成果を出せるような仕組みをつくるべきだ」と、提案しました。メリットを説明したり、技術交流会で発表していく中で、上司からGOが出て、時間やお金などのリソースを配分してくれることになりました。いざ「やってみよう」となれば、全力で社員の背中を押してくれる会社だなと感じます。
保坂
そもそも、京兼さんがそうやって自分から提案して仕事をつくっていく姿勢がいいですね。
京兼
思いきって提案をしたとき「新人が変なことを言い出した」といった反応をせず、一技術者として対等に「その提案は本当に役立つのか?」と受け止めてくれたことにも感謝しています。世代を問わず、たがいに切磋琢磨する空気が流れていると感じます。
瀬本
私は、グローバルな仕事ができるのもTELの魅力だと思います。以前、韓国から来たフィールドエンジニアに、エレキ関係のトレーニングをする機会がありました。さまざまな国の人と協力し合いながら仕事を進めていけるのも、雑談でお互いの国のことを知っていくのも、とても楽しいです。
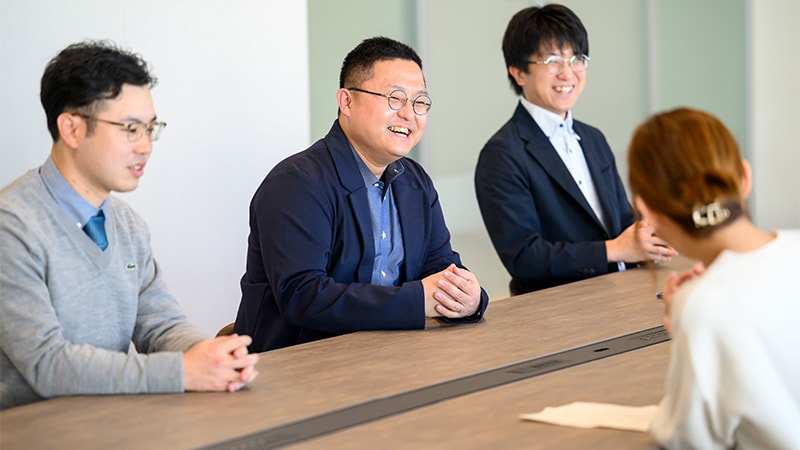
深見
僕は、TELの事業とシナジーを生む海外の半導体関連のベンチャーに投資して、ともに開発を進めることで、海外の優れた技術を取り込む体制をつくっているのもいいなと思っています。そのうちの一つを担当しているのですが、相手方もTELを信頼してくれているのが伝わってくるんですよね。信頼し合える仲間が世界中にいて、ともに技術を伸ばしていけるのは、開発者としても大きなやりがいです。

保坂
私も在職時、海外の会社を買収するプロジェクトを担当したことがありました。お互いの常識や文化をすり合わせるのは大変だけど、革新的な技術が生まれることもあるから、面白いよね。協業だけでなく、社内にもどんどん多様なバックグラウンドの従業員が増えたらいいなと思っています。
京兼
最後に保坂さんに伺ってみたいんですが……保坂さんが入社されたときといまでは、TELの事業規模や環境って大きく変わっていますよね。いまこの状況だからこそできること、いまこそやるべきことって、何があると思いますか?

保坂
ここまでみなさんが話してくれたように、お互いが切磋琢磨しながら挑戦していくことは、昔から変わらずTELが大切にしていることです。でも、昔といまが違うのは、挑戦できる規模。会社が成長し続けているから、社員たちが見られる夢も広がっていると思います。もちろん、やり方はちゃんと考える必要があります。でも、ちょっとくらい時間や予算がかかることでも、やりたいことを見つけたらどんどん口に出していけばいい。面白い提案ならちゃんと採用してくれるし、みなさんの成長がさらなる会社の成長にもつながっていくと思います。
京兼
ありがとうございます!チャレンジ精神を発揮して、どんどん頑張っていきたいです。




