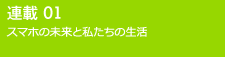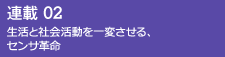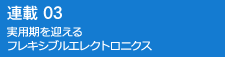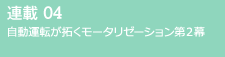第1回
なぜ今センサなのか
- 2015.08.31

一般消費者の目のつくところ、また人目につかないところに置かれた機器や設備の奥底で、さまざまなセンサが数多く活用されるようになった。今や、センサをいかに使いこなすかは、電子機器のヒット商品を生み出す上での鍵にもなっている。それだけではない。エネルギーや交通、医療、そしてモノづくりを支える社会システムの中に莫大な数のセンサが組み込まれて、人々や社会の状況や営みをありのままに把握する役割を担いつつある。地球温暖化や少子高齢化など、これから世界が直面する数々の社会問題を解決できるか否かは、センサの効果的な活用にかかっている。本連載では、第1回でセンサが生活や社会に生み出す革新、第2回は広がるセンサの応用、第3回は高度化するセンサ技術について、それぞれ紹介する。
革新的な機器の中で、センサが効果的に活用されている例が目立ってきた。例えばApple社の「iPhone 6」には、わずか123.8mm×58.6mm×7.6mmの筐体の中に800万画素のメインカメラと120万画素のフロントカメラ、マルチタッチセンサ、マイク、その他にも指紋、加速度、3軸角速度(ジャイロ)、近接、環境光、指紋認証、気圧などを検知するセンサがそれぞれ搭載されている。まさにセンサ技術のデパートといった様相である。
センサが電子機器の付加価値を生み出す時代に
電子機器や家電製品、家庭や工場などで使われる設備にセンサが組み込まれるようになったのは、今に始まったことではない。オーブンレンジには設定した庫内の温度制御を行う温度センサが搭載されてきた。自動ドアには人の接近を検知する人感センサが搭載されてきた。ハードディスクドライブのように、一見センサに関係無いような機器にも、機器の落下を検知する加速度センサが搭載され、衝撃に弱い読み書き機構を故障から守るために使われてきた。ただし、さまざまな場所で使われていたセンサではあったが、その役割は、機器の本来の機能を支える脇役としての仕事が中心だった。
ところが近年、センサを効果的に活用することで、機器や設備に新たな価値を盛り込む動きが活発化してきた(図1)。中には、従来の機器のあり方を一変させてしまうインパクトを持つ機器、新市場を生み出す魅力を持つ機器、利用するシーンや場所を大きく広げる機器が、次々と生み出されるようになった。こうしたセンサを活用した新しい機器に共通していることは、センサ自体は従来からあるものが使われているものの、その活用法に画期的なアイデアが盛り込まれている点である。こうした指針に基いて開発された代表的な電子機器を少し具体的に見てみよう。
 |