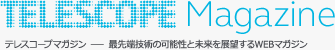|
冒険とは、まだ誰も見たことがない世界に挑むこと。そう語るのは、登山家の栗城史多氏だ。重度の凍傷にかかって9本の指を失った今も、エベレストの無酸素・単独登頂に挑み続ける。大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻の松崎典弥准教授も、挑戦と挫折を繰り返しながら、細胞の積層を制御する基盤技術の確立に成功。将来の再生医療に役立てるため、生体に近い3次元組織を生み出す歩みを着実に進めている。二人が挑み続けるのは、自分自身の「山」に向かう冒険だ。 |
苦しさが喜びに変わる時
栗城 ── 再生医療については、研究をしている方にいろいろ質問してみたいことがあったので、お話しできるのを楽しみにしていました。
松崎 ── 登山家と対談をするのは初めてです。栗城さんが山登りを始められたのは、いつ頃ですか?
栗城 ── 大学生の時です。その頃から世界六大陸の最高峰を登ってきました。8,000m級の山というのは、世界に14峰あって、その内の4座を単独・無酸素登頂しました。そして今は世界最高峰のエベレスト(8,848m)の単独・無酸素登頂に挑戦しています。
 |
かれこれ、もう気象条件の厳しい秋に6回チャレンジしていますが、まだ登頂できていません。秋に単独無酸素で登頂した人は、世界にまだ誰もいません。成功すれば、世界初なんです。僕は「冒険の共有」といってエベレストからの生中継をやる予定です。
松崎 ── 登っている時にですか?
栗城 ── はい。全部ではないのですが、部分ごとの配信や中継をしています。誰もやったことがないことをやるのが冒険ですから、失敗と挫折の連続です。その姿をあえて共有しながら、見ている皆が自分自身の「見えない山」という目標に向かう支えになったらいいなと思い、2009年から始めました。
 |
松崎 ── エベレスト登山は、何日くらいの行程ですか?
栗城 ── 遠征期間は、出発してからトータルで約2ヶ月間。うち1ヶ月半はベースキャンプに滞在します。その地点は5,300m位ですけど、頂上まですぐに上がってはいけないんです。上がって、下がってを繰り返しながら、身体を高度に順応させて、徐々に標高を上げていくんです。
エベレストは、上の方は酸素が地上の3分の1しかないので、普通は酸素ボンベがないと生きていけない世界です。
松崎 ── 登るだけでも困難なのに、無酸素で行うのはなぜですか?
栗城 ── 無酸素は本当に苦しいんですけど、それがエベレストという自然のあるがままの世界じゃないですか。僕は苦しみや困難も自然の一部と捉えていて、それを感じながら登りたいんです。
しかも、荷物を軽量化しなくてはいけないので、1日に食べられる食事の摂取量がカップラーメン1個分くらいで。登っている時は、脈拍が1分間に170近くまで上がりますし、ずっと寒いし、悪天候になったらテントから出られないし、困難続きです。
松崎 ── 山にいる時の栗城さんは、それを受け入れている。
栗城 ── そうです。苦しいのが楽しいという感じなのかな。山登りって、苦しくないと喜びが生まれないんです。喜びと苦しみは振り子みたいになっているので、楽な方法を選んで登頂してもあまり喜びが湧きませんから。エベレストが、誰もが安全・確実に登れるようになったら、登山家は誰も行かなくなるでしょうね(笑)。
もちろん単に苦しいだけではダメです。登山の場合、やはり登頂という目標があって、そこに向かうプロセスで味わう困難さや苦しみが、喜びに繋がるのではないかと思っています。
 |
松崎 ── 非常に共感しますね。私の場合は常々、頭のどこかで研究のことを考えています。しかし予想に反してうまくいかないことばかりなので、それをどうやったら解決できるのか、運転している時も、シャワーを浴びている時も考えてしまうんです。寝ている時も考え続けていて、ふと起きてメモしたりとか。
ある瞬間に「あ、これだったら解決できるんじゃないか」というアイデアが浮かび、実際にやってうまくいくと「研究をやっていてよかった」という喜びが得られます。考えたことがうまく繋がった瞬間、非常に大きな喜びが研究者に訪れるんですね。
医工の連携を担いたかった
松崎 ── 医療と関連はありますが、私の専攻は化学です。身体の中の現象は全て化学的なので、細胞を化学的な方法で整理していくのがテーマです。
栗城 ── なるほど、化学、医学、生物学の融合が再生医療なんですね。
松崎 ── そうですね。私が研究しているのは、そうした境界にある領域にあたります。それから、ひと口に化学といっても物理化学もありますし、流体的なこともありますし、いろんな分野の連携がないと、やっぱり複雑な問題は解決できません。
再生医療に関して一番大事なプレーヤーは細胞なのですが、彼らは生きていますから、タンパク質だとか、血液、栄養、酸素などの環境を整えてあげないといけません。その供給をどうするのか、計算をどうするのか、お医者さんだけではわからないこともいっぱいあるんです。
それらに対して、私たちのように化学であったり、物理学であったり、薬学であったり、いろんな分野の人たちでチームを組んで解決しようという認識が最近はあります。
栗城 ── 異分野の人たちとのコラボレーションはしやすくなってきていますか?
松崎 ── 昔に比べると、かなりしやすくなりましたね。「医工連携」で取り組もうという気運が生まれてきています。皆でチームを組んで、連携してやっていきましょう、という雰囲気がありますね。
 |
栗城 ── もともとは異なる分野である化学から、医療の分野に興味を持ったのはどういうきっかけだったのですか?
松崎 ── 学生の頃に入ったのが「医療分野に使えるような材料を作っていきましょう」という化学の研究室でした。当時、まだ再生医療という言葉もなく、「組織工学」と呼ばれていました。学位を取った後、自分はやはり直接的に人間の役に立つ研究をしたい、医療に役立つ研究をしていきたいと考えるようになったんです。
人間の臓器、組織に近いものを作るのは、当時はもちろん現状でも達成できていないところがある。私は医療従事者ではありませんが、化学者の立場から未来の医療技術の基礎を作るのにチャレンジしていこうと思ったのです。