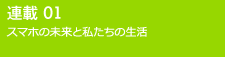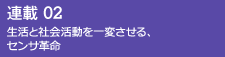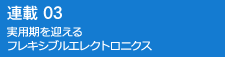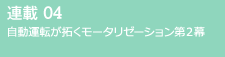地下街や建物内での行動も把握
スマホを使ったこれからの機能として、地下街や建物内での位置検出を高める研究も行われている。地下街では衛星からの電波を受信できないため、それ以外の方法で人の軌跡を追跡する方法が開発されている。スマホの持つ加速度センサやジャイロセンサを利用すれば入った場所まではGPSで記録できるから、その位置からどちらの方向に移動したかを測定し、その経路をたどるのである。X、Y、Zの3軸の加速度と3軸の回転角度、角速度を測定することで、その人の軌跡をたどる。
但し、この方法だけでは精度が不十分なので、さらに屋内に基準となる電波を出すモノも必要となる。GPSの衛星を利用することと同じように、屋内で電波を常に出すのである。IMES(Indoor Messaging System)やiBeaconで代表されるビーコンを決まった位置に多数設置し、一定の強さの電波を発射する。iPhoneにはBluetooth LE (Low Energy) が標準装備されており、Androidにもこれからは標準装備されようとしている。このためビーコンからBluetooth LEの電波が常に発射されていれば、あるビーコンAからの電波の強度が弱まっていき、別のビーコンBからの強度が強くなってくる、という状態であれば、AからBへ移動していることがわかる。
これらのスマホに搭載されている加速度センサやジャイロセンサ、気圧センサ、さらにはBluetooth LE機能を全て駆使することで、地下街の中や高層ビルの中の位置を検出できるようになる。実際にこのような実験は進められている。例えば、英国の半導体ファブレスCSR社はBluetoothチップを使って、地上から地下街に入る人の軌跡を表示していく実験を東京駅の地下街で行っている(図4)。これを発展させると、地下街を歩く人を見つけることができるようになるので、例えば親と子でスマホを持てばお互いにどの場所にいるのかがわかり迷子にならない。後はそれを表示するアプリケーションがあればいい。
 |
さらに視覚障がい者が地下街やビル内でショッピングを楽しむ実験も行われている。日本IBMは清水建設と共同で、視覚障がい者が健常者と同じように知らない街でウィンドウショッピングをしたり、買い物をしたりできるように、ビーコンやIMESを設置した街づくりを進めている(図5)。スマホからの音声で「右側50メートル先にブティックがあります」とか、「10メートル先にベンチがあります。休憩しますか」などと案内してくれる。これに対し「休憩します」と答えると、「ベンチまであと2メートルです」と応答してくれる。これはスマホのBluetooth LEがビーコンを受け、音声認識、案内のサーバーを通してクラウド上から案内するシステムである。
 |
スマホをハブとして、体に身につけたウェアラブル端末からのデータを受け取る通信もBluetooth LEを利用する。AppleWatchのような時計型のウェアラブル端末や米FitBit社のブレスレット型の端末もある(図6)。端末から健康状態を示す心拍数・体温などを測り、そのデータをスマホが受け取り、インターネットを通してかかりつけ医や病院に届ける。医師はそのデータを見て診断して、その結果をスマホに送る。
 |