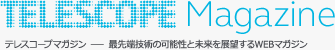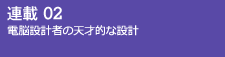|
コンピューターの登場を背景として20世紀末に生まれたメディアアート。東京・初台で1997年に開館し、今年で20周年を迎える「NTTインターコミュニケーション・センター(以下ICC)」は、開館の準備期間を含めれば、メディアアートの草創期から今日に至る流れを見届けてきた存在だ。ICCの主任学芸員として国内外の作家からの信頼も篤い畠中実氏は「ジャンルを逸脱するダイナミズムこそがメディアアートの醍醐味」と語る。今回は、人工知能(以下AI)が生成する言語モデルをビジュアライズした最新作をICCで発表した徳井直生氏を迎え、アートとテクノロジーの関係性について意見を交わした。 |
進路を決めたメディアアート作品
徳井 ── 大学3年生で自分の研究室を決めないといけない時に、ICCでカール・シムズの「ガラパゴス」という作品を見ました。それがAIに関する研究をやっている研究室を選ぶ大きなきっかけになりました。
  |
畠中 ── 遺伝的アルゴリズムを使った、ALife(人工生命)の作品ですね。シリコン・グラフィックス*1のコンピューターに繋がった12台のCRTモニター*2がズラっと並んでいて、それぞれの中でAlifeが生きています。
それぞれのモニターの前にはフットスイッチがあって、観客が任意に気に入った個体を2つ選んで掛け合わせることができて、すると、そこからまた12の新しい個体が、次の世代として生まれるんです。
徳井 ── 各個体は簡単な数式で表現されている、仮想的な生き物です。最初はランダムにつくられているのでそれほど面白くないのですが、それらを掛け合わせていくとだんだん面白いものが出てくる。自分が気に入ったものをいくつか選ぶと、その数式を掛け合わせて新しい各個体が生まれるのです。
数式を掛け合わせる時は、例えば「個体Aの数式の前半と個体Bの数式の後半を組み合わせる」というような、まさにDNAの交配みたいなことをやって次の世代が生まれる。それを何回も繰り返していくと、どんどん複雑な人工生命になるんです。
すごくシンプルな仕組みですが、結果的に出てくるものが、作者も想像していなかったようなところに到達していたことにロマンを感じました。
畠中 ── ICCが開館した90年代末頃には、ちょっとした人工生命ブームがありました。メディアアートの世界でも、インタラクティブな要素と組み合わせることによって観客がそれに関与することができる作品や、ゲームなどでも画面の中で人工生命に触ると喜んだり増えたりするものが登場して、社会的な関心も集めていました。
 |
コンピューターの可能性に触れた80年代
── 開館準備からICCに関わっていた畠中さんは、それ以前からテクノロジーを使ったアートに関心があったり、自分で制作したりしていたのですか?
畠中 ── 大学では絵を描いたり、映像をつくったりはしていました。コンピューターを使わずにですが。時代的にはコンピュータを使った表現が注目され出したころでしたが、自分で何かをするということはしていません。
僕は80年代のいわゆる「ニューアカデミズム」と同時代に高校や大学時代を過ごした世代です。ICCが設立されるきっかけとして、1992年には機関誌『InterCommunication』誌が創刊されました。その編集委員が浅田彰さんや伊藤俊治さんだったのですが、それはどこか80年代の再来のようにも感じられて、またこういった世界に関心を持つようになりました。
浅田さんは80年代には、ICCの初期の「見えないミュージアム」のようなプログラムを深夜のテレビ番組(『TV-EV電視進化論』1986年)でやっていました。僕はそれを浪人していた頃に見て、当時のコンピュータグラフィックスやサンプリング*3の技術などの状況を目の当たりにしたんです。
徳井 ── 音楽の世界でもサンプリングの技術に影響を受けたアーティストがたくさん登場した時代ですね。
畠中 ── ええ。当時はコンピューターも高かったし、個人で手を出すことはできなかったけれど、すごく関心はありました。その後、紆余曲折あって今に至るという感じです。
[ 脚注 ]
- *1
- シリコン・グラフィックス: 1982年にジム・クラークがカリフォルニアで創業。3次元のCGを高速描画できる端末(ワークステーション)が主軸商品。ハイエンド市場で一定の人気を保っていたが、高性能なPCの低価格化とともに衰退、2009年に倒産した。2016年に米ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社によって買収される。
- *2
- CRTモニター: ブラウン管(Cathode Ray Tube)を使ったディスプレイ装置。2000年ごろまでのPCやテレビでは一般的だったが、徐々に液晶などに置き換わっていった。
- *3
- サンプリング: 過去の楽曲や音源、歌唱などの一部を引用し、それらを再構築して新たな楽曲を制作したり演奏したりする技法。複数のチャンネルでレコーディングされた楽曲から個別の音源を使うこともある。ヒップホップの台頭や電子音楽の発展を背景に80年代から一般的になった。