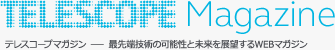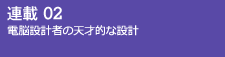第2回
ヒトは機械を、機械は生き物に似たモノを生み出す
- 2017.7.31

コンピュータを使った自動設計手法、いわば「電脳設計者」が、様々な工業製品の開発現場で活用され、ベテラン設計者が手掛けた製品を上回る性能を実現するようになった。電脳設計者が生み出すモノは、なぜか植物の形や動物の骨格のような生物的な印象を与える形であることが多い。それには理由がある。電脳設計者は自然が何億年もの間繰り返してきた生物の進化のプロセスを、コンピュータ内で短時間に再現しているからである。製品を使う環境への適応と淘汰を繰り返し、行き着いた先にあるのが生物に似た形なのだ。連載第2回の今回は、電脳設計者を生み出した技術の詳細と、建築物の設計意匠デザインへの応用、さらには人工知能(AI)を活用した将来の設計技術について解説する。
要求条件を満たす形を即座に導き出す電脳設計者は、短時間で数百通りもの設計案を作り出す「自動設計ツール」である。うまく使いこなせば、人間が行っている作業を大幅に効率化できる。しかし、電脳設計者の本当の価値は、作業の効率化ではない。人間では思いつかないような設計案の存在を、あぶり出すことこそが電脳設計者にしかできない仕事なのだ。
機械設計の分野では、電脳設計者が実現した技術のことを「最適化」と極めて素っ気ない名称で呼んでいる。人間の設計者が指定した設計条件を満たすように、モノの形を自動で最適化することを目的とした技術だからだ。ただし、何のひねりもないその名称の印象に反して、その技術で生み出される形は斬新なものばかりであり、人間の設計者に与えるインパクトも絶大だ。今や、工業製品の構造設計だけではなく、建築や意匠デザインの分野でも、電脳設計者を活用するようになっている。
環境への適応と自然淘汰をコンピュータ内で繰り返す
人間の設計者は、定規やコンパスなどを使って幾何学的な模様を描き、複雑に組み合わせながら様々な機械や道具を設計してきた。それらは直線や単純な曲線で形作られるため、どうしても機械っぽさを感じさせてしまう。ところが、電脳設計者が最適化技術を駆使して生み出す形は、なぜか生物的な印象のモノが多く(図1)、天才建築家アントニオ・ガウディ氏の作風に似た感じも受ける。そのように感じるのは、生物が現在の形に至った進化のプロセスと、電脳設計者がモノの形を最適化するプロセスがほぼ同じだからだ。
 |
最適化技術では、コンピュータの中に初期形状となる3次元設計モデルを入れ、その形を意図的に変え、変化後の形の特性をコンピュータシミュレーションで検証する。そして、変化の前後の特性を比較し、よい特性の形を残す作業を繰り返す。生物の進化プロセスになぞらえれば、形を変える作業は突然変異、特性を比較して優れた形を残す作業は自然淘汰と同じと言える。電脳設計者とは、進化のプロセスをコンピュータによって高速再現する、言わば「進化シミュレーター」なのである。
形状を効率よく進化させるための工夫
設計モデルの形を変える際に無計画に形を変えて、すべての特性を検証するのではコンピュータの能力がいくらあっても足りない。そこで、なるべく少ない計算量で最適解に近い形を見つけるための戦略が必要になってくる。いくつか方法があり、代表は「逐次2次計画法」と「遺伝的アルゴリズム」である。それぞれの方法には一長一短があるが、設計条件への適合度(生物であれば環境への適応度)を調べ、適合度が劣る形を排除しながら最適解を目指すという大筋は同じである。
逐次2次計画法では、まず初期形状からちょっとだけ変えた形を何パターンか作り、それぞれの特性を調べて変化させるべき部分がどこなのか、そこをどのように変化させればよいのか傾向をつかんで方針を決める。そして、決めた方針に従って、徐々に形を変化させて最も特性が優れた条件を特定する。そこを新たな初期形状として、同じことを繰り返す。このプロセスを何度も行うことで最適解に近づいていく。
遺伝的アルゴリズムでは、まず複数の初期形状を作っておく。そして、それぞれが設計条件にどの程度適合しているのかを評価する。次に適合度の高い形状を何個か選び出し、これを親とする。そして、それぞれの親の特徴の一部を引き継ぎ、子の世代の形状を作り出す。この作業を何世代にもわたって繰り返し、最適解に近づけていく。さらに、遺伝的アルゴリズムでは、たまに親とは全く似ていない特徴を持った突然変異を一定の確率で意図的に作り出している。これによって、能力の高い近親同士で配合したときに最適解とは別の形に収束してしまうこと ── サラブレッドの血統で言うところの「血の袋小路」 ── を避ける工夫をして、多様性を維持しながら進化させるのだ。