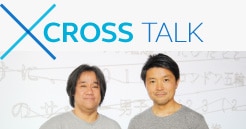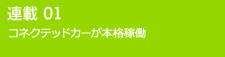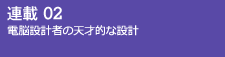V2VやV2Xも
コネクテッドカーといっても、クルマが常にインターネットだけにつながっているとは限らない。クルマ同士、あるいはクルマと道路をつなごうという動きもある。これはそれぞれV2V(ビークル-ツー-ビークル)、V2X(ビークル-ツー-周囲)などと呼ばれている。V2Vはクルマ同士が電波(信号)を発信しており、その距離情報を常に互いに確認し、クルマ同士の衝突の心配がない。また決してぶつかることなく、ドライバレスで縦列走行ができるようになるものである。
欧州ではドイツとスウェーデン、ベルギーの6メーカーのトラックを数台使い、それぞれの国からオランダのアムステルダムまで縦列走行するという公道実験を行っている(参考資料1)。トラックはレーダーとWi-Fi通信、GPS位置情報システムで互いの位置を保ちながら、先頭のドライバーはハンドルを握っていても、後続のクルマのドライバーはハンドルから手を放して走行する(図4)。道路に何か荷物が散乱していれば、先頭のクルマが止まれば、後続のクルマも止まる。またトラックとトラックの間に乗用車が割り込んできても、割り込んだ乗用車をトラックが検出しているため、そのクルマとの車間距離を自動的に取りながら進む。他にも、その乗用車が車線を変えて縦列隊から離れていく、といったデモがある。3台の縦列走行の例では、後続のトラックは先頭のトラックよりも走行中の空気抵抗が減るため燃費が2割改善し、CO2削減につながったという。
 |
今日の自動運転車のレベルでは、ドライバーがいつでもハンドルを握れる状態であることが要求されている。しかし将来的には先頭車のみドライバーが乗車し、数台のトラックを引き連れて走行できるようになれば、ドライバー不足の問題解決にも役に立つ。日本でもNEDOが産業技術総合研究所つくばセンターのテストコースで走行実験を行っている。
クルマ同士だけではなく、クルマと道路に沿う交差点との通信(V2X)では、交通信号がない場合でも横の道路からのクルマの有無を、交差点の手前から知ることができるようになる(図5)。見えない交差道路を走行するクルマの存在を把握できれば、交差点に進入する速度を緩めることで事故を回避できる。自動運転のグーグルカーが交差点で事故を起こした時はカメラでクルマなどを検出していたが、夕暮れ時だったため、夕日がまぶしすぎてカメラで横切るトラックを検出できなかったと言われている。そのような場合はレーダーや超音波信号を利用する手も考えられている。
 |