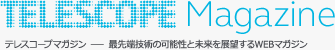進化の代償で操作感を失ったクルマ
機械的なUIを廃したことで操作感を失い、対策すべき切実な問題を抱えてしまうことになりそうな例が身近にある。それはクルマだ。
現在の多くのクルマは、ブレーキをかけるためのペダルと実際にタイヤの動きを制動するパッドは、機械的につながっていない。ペダルの踏み込みをセンサーで検知し、その出力信号によってモーターでパッドを動かす仕組みになっている。ペダルとブレーキパッドをつなぐのは、電気信号を伝えるワイヤーだけだ。ブレーキだけではなく、アクセルやハンドル、変速器など、ドライバーが操作する機構のすべてを同様の仕組みにする方向で技術開発が進められており、これを「ドライブ・バイ・ワイヤー」と呼んでいる。
「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本機能を細かく電子制御できるドライブ・バイ・ワイヤーのメリットは多い。まず、軽量化や部品点数の削減につながる。さらに、自動ブレーキなど高度運転支援システム(ADAS)や自動運転車は、クルマの機構をドライブ・バイ・ワイヤー化することが前提になる。
その一方で、ドライバーと操作対象を分離してしまうため、操作感が得にくくなるという欠点がある。クルマの状況や操作感覚、路面情報を感じる機械的な反力を感じることができないのだ。例えば、ブレーキをどのくらい踏み込んだのか感触がつかめない、悪路を走ってもガタツキがハンドルから伝わらず気づかない、といった状況が生まれる。これは、ドライバーから、感覚による危機管理能力を奪っていると言える。
失われた操作感を取り戻す
こうした操作感の欠落を補うために利用されている技術がフォースフィードバック技術である。状況に応じた反力を人工的に作り出し、ドライバーに伝える技術だ(図2)。例えば、ハンドルに応用する場合、角度センサーでハンドルの回転角度を読み込み、その角度に応じて、あらかじめ入力しておいたフィーリングデータに基づいた反力を電磁力で作り出し、ハンドルを戻そうとする力を加える。反力は1種類ではなく、複数のモデル化された力を状況に応じて使い分ける。さらに、タイヤ、ブレーキなどにもセンサーを取り付けておけば、アンチ・ロック・ブレーキ(ABS)を動作させた時などに、悪路を走る擬似的な感触を表現できるようになる。
 |
フォースフィードバックの技術は年々進化し、より細かな状況を再現できるようになってきている。例えば、慶応義塾大学ハプティクス研究センターは、「IoTハンドル」と呼ぶ路面の状態をハンドルで感じ取ることができる技術を開発した(図2の右下)。砂利道や凍結した道など路面の情報を、ドライバーが手元で感じることで安全な運転が可能になり、同時に操作する楽しさを表現できる。
操作効率の向上に触覚を活用
失った操作感を、人工的に作り出した触覚や力覚で取り戻す試みは、IT機器にも広がっている。スマートフォンやタブレット端末のUIであるタッチパネルには、機器に直接触れながら操作するにもかかわらず、操作感が感じられないという欠点があった。その欠点を補うため、クリックしたアイコンを拡大したり、色を変化させるなど、現状では視覚的な効果を工夫して対処されている。しかし、それでも失った操作感を補うには足りない。
そこで富士通は、タッチパネルの表面で、ツルツル感やザラザラ感を表現できる技術を開発し、これを実装したタブレット端末を試作した。その方法とは、超音波でパネル表面の強化ガラス板を振動させて感触を作り出すというものだ。超音波でガラス板を振動させると、パネル表面の摩擦係数が少なくなるため、振動がない場合よりもスベスベだと感じる。さらに、ユーザーの指の位置に合わせた振動を加えることで、パネル上にあたかも高さを持つボタンがあるように感じさせることもできるという。
操作感の向上に加えて、操作効率の向上にも、触覚や力覚を利用しようとする動きも出てきている。最も知られた例が、本連載第1回でも触れた「iPhone」の「3D Touch」である。アイコンを普通に押した感触と、さらにアイコンを深く押し込んだ感触を作り分け、それぞれ別の操作を割り当てている。これによって、ひとつのアイコンで、複数の機能を使い分けることができるようになった。
視覚と聴覚が使えない状況でのUI
視覚と聴覚を使って機器を操作できない状況でのUIに、触覚を積極的に利用しようとする動きもある。例えば、クルマを運転しているドライバーが、エアコンの調整をする場合などがこれに当たる。ドライバーの視線は常に前方もしくはミラーに向けられているし、高速走行中は騒音などで音声での操作も難しい。こうした状況下では、手探りで操作できるUIが活躍する。
Robert Bosch社は、触覚フィードバックを利用して、タッチパネルを手探りで操作できるディスプレイを開発した(図3)。車載機器の多くは、手探りで操作することが想定されているため、機械的なUIが好んで使われている。しかしBosch社が開発したディスプレイでは、画面に表示した複数のボタンの表面の感触を、凹凸の具合や模様の違いなどで表現し分けることで、画面を見なくても目的のボタンを探り当てられるようにした。このディスプレイの背面にはアクチュエーターがあり、これを振動させて様々な感触を作り分けている。こうした触覚を利用するUIは、視覚や聴覚に障害を持つ人にとっても極めて有用になる。
 |