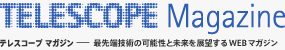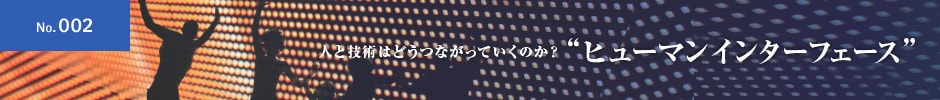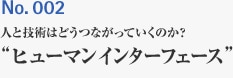3次元画像を研究した経歴が
インターフェース分野につながった
──今回のオープンハウスで発表された研究は、"魔法のようなもの"を意図したものではないということでしょうか。美術品にコンピューターからの情報をオーバーレイするような装置は、十分に不思議な感覚です。
例えば、デジタルミュージアムの展示支援を目的とした「MRsionCase」は、複数のレイヤーを持つ空中像を用いることで、多方向からの鑑賞を可能にする"複合現実感ショーケース"です。
浮き上がる文字や映像を4方向の鑑賞地点すべてで変えられるため、ある意味でLumisight Tableがもたらす体験と似ています。実用面に則して言えば、国内のミュージアムがインバウンド(海外からの観光客)を呼びこむために、多国語や映像でのガイドを情報技術で付加することができるものです。
ただ、この研究で私たちが目指した一番の目的は、展示物の周囲を「思わずグルグル回ってしまう行為」を誘発することでした。
──中国語や韓国語が分からなくても、他の角度からはどのように見えるのだろう、と気になって覗いてしまいますね。
直感的でなければ、何かのブレーキがかかってしまう。だから「人間が思わずやらされてしまう」というインターフェースは、非常に上手につくられていて、うまく機能している、と私は考えるようになりました。
──すると、以前とは研究室が志向するものが変わっているのですか?
情報技術を、人々の行動を支援する仕掛けに活用していく方向にシフトしてきているとは思います。
今は「何でも検索すれば情報は出てくる」という便利な時代ですが、本当にクリエイティブな仕事は限られてしまっていますよね。単にネットワークから知識がどんどん入ってくるとか、情報技術で武装してようやく実現するコミュニケーションには限界があります。
それよりも、上手に相手の能力を引き出したりとか、思わずやる気にさせられてしまうとか、人間の内面を刺激して能力を引き出すメディア技術をつくりたい、というのが最近のモチベーションです。
 |
──ここで少し苗村さんの研究者としての経歴について振り返ってお聞かせください。
私は大学時代、ホログラフィーや3次元ディスプレイの研究で知られた大越孝敬先生*4の研究室にいました。ここではフォトン(光子)の数を数えるような卒論を書いています。デバイス系、物理系の研究でしたね。その後、修士では顔画像処理で著名な原島博先生*5の研究室で情報系の研究をしました。
そうした出自もあって、物理と情報、両方のエッセンスが入った研究を自分のテーマにしたいと、3次元画像の通信に関する研究を選んだのです。
──その後、スタンフォード大へと。
ええ、2000~2002年ですから「Googleという新興企業の勢いがスゴい!」と言われていた時代でした。周囲では3DCGを研究していた人たちが「3次元ディスプレイの技術がCG分野に役に立つのでは?」と気付いた頃です。彼らが「これがバイブルだ」と読み始めていた本があったのですが、それが大越先生の本だったのです。
──そこでつながってしまうとは。
いったい、私は何をしにアメリカまで来たのかと(笑)。でも、これで日本の研究が海外に対して決して劣っているわけではない、モチベーションなどの紙一重の部分で負けているだけだ、と分かったのは収穫でしたね。
僕がいた研究室は、読売巨人軍じゃないですけど「あそこにスゴいヤツがいるらしい」と分かると、海外から人を引っ張ってくるんです。すると、そこにいる人同士で化学反応を起こします。非常に人材には恵まれていました。
──研究者にとっては理想の環境です。
ええ。最近、ネットで話題になっていた「Lytro(ライトロ)」*6という撮影後にフォーカスを変えられるスチルカメラも、私が渡米していたときの学生が起こしたスタートアップです。
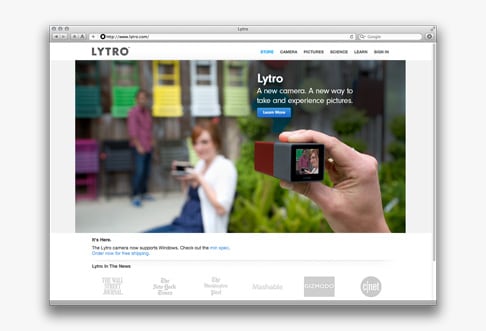 |
レンズをたくさん並べて3次元空間の写真を撮りましょう、それをCG合成でいろんな方向から見えるようにしましょう、という研究は今までよくありました。その学生は、レンズの光の振る舞いを計算してあげると、奥にピントが合ったり、手前にピントが合ったりというフォーカスを後で変えるように、非常に自然な映像をつくれることを見つけたんです。
彼は一生懸命、3Dの本を勉強していましたよ。それまでの3次元撮影方法の思い込みにとらわれず、ちゃんと商品として世に出した努力は素晴らしいです。