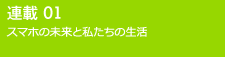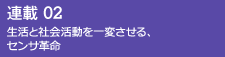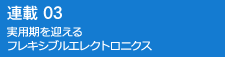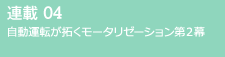日本とヨーロッパで別々に検討してた探査機が瓜二つだった
──どのような経緯でヨーロッパとの共同計画になったのでしょう。
1990年代半ば、当時の宇宙科学研究所の内部で、日本で水星探査をやるとしたらどんな探査機が考えられるかという検討を進めたことがありました。検討の結果、当時の研究所の予算規模から考えると無理があったため検討を一時中断したんです。ただ、こんな計画を検討しましたということを国際学会などで話をしていました。
同じころヨーロッパでも、今のベピコロンボと同じように周回機を2機、水星に送り込むことを考えていました。そのうちの1機が、我々が検討していた探査機とほとんど瓜二つ、双子のようなものだったんです。そこでヨーロッパ側から一緒にやらないかという声がかかりました。その後の検討を経て、実際に進めることになったのがベピコロンボ計画です。
 |
──ヨーロッパとの共同計画は初めてですか?
これまでも、衛星に搭載する一部の観測器をヨーロッパから提供されることはありました。ただ衛星を1機ずつ作りましょうというような大掛かりな計画は初めてですね。互いに手探りしながら進めてきたところもあります。
──文化の違いを感じることはありますか?
すごくありますね。向こうは書類文化なんです。MMOはおそらく、宇宙研が今までやった衛星の中では、いちばん書類が多いんじゃないでしょうか。日本だったら関係者がちょっと集まって話し合えばすんでしまうようなことが、決まるまでになかなか時間がかかるということもあります。
一方で、見習うべきところもたくさんあります。たとえば問題が発生した後の検証がものすごく徹底しているようなところは見習うべきところだと思います。
──ところで、ベピコロンボというのは日本人にはなじみのない言葉ですが、どんな意味なのでしょうか。
ベピコロンボは、もともとESAで考えていた計画の名称です。1984年に亡くなったイタリアの応用数学者ジュゼッペ・コロンボという方の名前に由来していて、ジュゼッペの愛称がベピですので、名前をそのままいただいたんですね。
初めて水星を探査したマリナー10号は、金星でフライバイをした後に水星へ向かい、水星に3回接近しながら観測を行いました。ジュゼッペ・コロンボさんは、フライバイを利用した水星探査の方策をNASAに提案した人です。また水星は公転周期が約88日、自転周期が約59日で正確に3対2で同期していますが、彼はそのことを数学的に示した人でもあり、水星にはゆかりのある人なんです。
 |
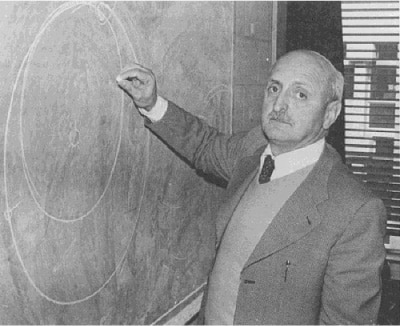 |