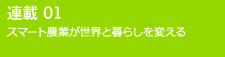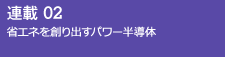安全性は確保されているか?
 |
佐藤 ── 今はだいぶクリアになっているのかもしれませんが、一般的には「水素はちょっと怖い」というイメージがありますよね。
大平 ── ええ。でも水素に限らず、エネルギーはやっぱり怖い面があるんですよ。ガソリンもそうですし、天然ガスもみんなそうですが、使い方を間違えると大変なことになる。
水素はまだエネルギーとしては始まったばかりです。これまで長い期間をかけてデータを取ってルール化し、すでに安全に使う技術もできています。ただ、「普通のもの」として認識をしてもらうのはまだまだ時間がかかりますし、これには「安心」を得るための時間も含まれます。
佐藤 ── 水素イコール爆発というイメージがあると思うんですが、実際にどうなんでしょうか?
大平 ── ある一定の濃度、具体的には大気中に4%以上の濃度になると燃焼しやすくなるという性質があります。ただ、その割合に達するには、すごい量の水素を放出しなければなりません。
なぜかというと、水素はとても軽いからすぐ拡散してしまうんですよ。ちょっとでも隙間があれば、どんどん外へ逃げて行ってしまう。だから爆発という条件を作ることが、逆に難しいと言えます。
佐藤 ── なるほど。交通事故の際にはどうですか?
大平 ── FCVでは高圧の水素で貯めていますので、タンクに亀裂が入って破裂、というイメージがあるかもしれませんが、タンクには非常に硬い素材が使われており、また衝突試験で安全性は確認しています。
また火災に巻き込まれたときも、100℃になるとタンクの一部の栓が溶けて水素を逃すようになっているんですね。
水素がガソリンと違うのは、一度抜けたらもう溜まらない点です。ガソリンの場合は漏れるとそこに溜まって引火する可能性があるのですが、水素はすぐ拡散する。ただし絶対というものはありませんから、どうやって社会に受け入れられる形にするかが鍵なんです。
佐藤 ── 今の自動車もガソリンという可燃物を積んでいるわけですからね。でも今は、技術が進歩して安全性が飛躍的に上がり、安心して運転できるようになった。これはレーシングカーの世界も全く同じです。
僕のチームオーナーのA.J.フォイト氏*3は今82歳なんですが、60歳近くまで現役のレーサーとして乗っていたんですね。彼が20代から30代の頃、今からたった50年から60年前の話ですけれど、アルミの燃料タンクがコックピットの両脇にあったそうです。
クラッシュしたら火だるまになってしまう危険な世界。彼は本当に多くの同僚を事故で亡くしてきました。そういう話を聞くと、今のレーシングカーの安全性とはレベルが違いすぎます。僕らは今、炭素素材でできた非常に強靭な車体に乗っていて、その中にケプラー繊維製のタンクを積んでいます。
絶対ではないとは言え、通常のクラッシュにおいて、火でも衝撃でも中身が漏れないタンクができているんです。ぶつかって爆発する、火が出るというケースはほとんどありません。火が出るシーンがあったとしたら、ギアボックスのオイルとかエンジンオイルなどです。そうしたオイルは爆発せず、メラメラと燃えるだけですからね。
僕らの世界において、スピードは非常に大きなエネルギーですから、死と隣り合わせと言われることもあります。けれど、ドライバーの僕が死を意識するようなことはありません。むしろ、レーシングカーに乗ると非常に守られている感じがある。
FCVというのは、大きな事故になる可能性があるものを積んでいるとしても、水素とガソリンはそんなに変わらない、あるいはそれほど危なくないということがみんなの意識の中に入っていけば、未知なものへのアレルギーはなくなりますよね。
扱ったことがないので、イメージとして怖いと思うかもしれないけれど、実際は違うんですよ、ということを啓蒙していけばいいのでは。
大平 ── 水素は目に見えないガスの状態で扱うことと、非常に高圧で扱うことへの不安があると思います。インフラの整備においても安全性をしっかりお伝えするのは大事ですね。例えば、ガソリンスタンドは震災があっても強固に守られていましたが、同様に水素ステーションも相当強固に設計されています。
非常時のライフラインとしても
大平 ── 信頼や安心を得るには、時間をかけて事故を起こさないようにしていくのはもちろんですが、ガソリンスタンドが水素ステーションに置き変わっていくときに、どんな価値を出していけるかも考えなくてはいけません。
例えば、水素を使って発電ができるので、非常時には地域の方々に電気を供給するライフラインになれるのではと期待しています。
佐藤 ── 蓄電というか、パワーソースというか、広くエネルギーの供給元になれるのは面白いです。停電で家への電力供給がなくなっても、ハイブリッド車は一晩くらい電気を生み出せます。ガソリン車だったらそうはいかないですからね。
大平 ── FCVだと水素を満タンに積んでいれば、一般家庭の1週間分くらいは電力を供給できる計算です。
佐藤 ── 緊急事態のときライフラインになり得るのは頼もしいですね。
大平 ── 社会が1つものを飛び越えていくときには、いろんな新しいリスクが付いて回るのだと思います。そこで利便性が上がるとか、新しい価値が生まれるといったことが伝わったとき、初めてリスクを受け入れてもらう余地が増えるのかもしれません。
後編のあらすじ
後編では、大平英二氏が水素をエネルギーとして利用する近未来社会の姿と普及への課題を引き続き解説。佐藤琢磨氏からはモータースポーツのさらなる進化と開催される都市像について話題が展開します。最新のFCVの乗り心地、そして持続可能な社会に向けた二人の思いとは。
[ 脚注 ]
- *3
- A.J.フォイト: アメリカの元レーシングドライバーであり、インディカー・シリーズに参戦するレーシングチームオーナー。インディ500における4度の優勝(1961年・1964年・1967年・1977)は、歴代最多タイ勝利記録。

Profile
大平 英二(おおひら えいじ)
1968年秋田県生まれ。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)新エネルギー部主任研究員。
1992年東京理科大学理学部卒、同年NEDO入講。主にエネルギー・環境関連の技術開発プロジェクトに携わり、NEDO蓄電技術開発室長などを経て、2013年4月より現職。
現在は水素エネルギーの普及展開に向け、多くの企業、大学が参画する技術開発プロジェクトのマネージャーとして、次世代の燃料電池や、水素を活用する新しいエネルギー・システム構築のための研究開発を推進。その傍ら、地方自治体における水素エネルギー普及計画策定のための委員会への参画、国内外での数多くの講演をこなしつつ、TVなどメディアを通じた水素エネルギーのわかりやすい情報発信に尽力。
共著に『水素エネルギー白書』、『図解 燃料電池技術』(ともに日刊工業新聞社)
佐藤 琢磨(さとう たくま)
1977年東京生まれ。学生時代の自転車競技から一転、20歳でレーシングスクールに入り、モータスポーツの世界へ入る。
2002年にF1デビューし、僅か2年後の2004年アメリカグランプリにて日本人歴代2人目となる表彰台に上がる。2010年からはインディカー・シリーズにチャレンジし、2013年ロングビーチグランプリにて日本人初優勝を成し遂げ、世界最高峰のレースと言われるF1とインディー両方で表彰台に上がった唯一の日本人ドライバーとなる。2016年は4シーズン目となるAJフォイト・レーシングから参戦した。
日本を代表するレーシングドライバーとして活躍する一方、オフシーズンでは自身で立ち上げた「With you Japan」プロジェクトとして2011年から復興地支援を毎年続けて活動。昨今では復興地支援と合わせて子供たちにカートの楽しさを伝えるキッズカートイベントを開催している。
Writer
神吉 弘邦(かんき ひろくに)
1974年生まれ。ライター/エディター。
日経BP社『日経パソコン』『日経ベストPC』編集部の後、同社のカルチャー誌『soltero』とメタローグ社の書評誌『recoreco』の創刊編集を担当。デザイン誌『AXIS』編集部を経て2010年よりフリー。広義のデザインをキーワードに、カルチャー誌、建築誌などの媒体で編集・執筆活動を行う。Twitterアカウントは、@h_kanki