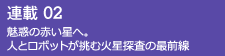知恵と自律性を備えたAGI
──AIとは何でしょうか?どのように定義していますか
かつて、AGIとは何か、という本を執筆し、そこに書きましたが、今は厳密には定義はできなくなりました。ゴールが余りも複雑だからです。
例えば、インテリジェンスという言葉にも、レベルが色々あります。ネズミ、ゴキブリなどのレベルから人間のレベルまで幅広くあります。AIはインテリジェンスを人間レベルまで高めたものと言えます。コンピュータソフトウエアは、自然の生体をモデル化していないのでインテリジェンスとはいえません。ゴキブリにも学習機能はあるようですが、インテリジェンスではなく自律的に動いているにすぎません。*3
自然界には人間の他に、インテリジェンスな生物は存在しませんが、自律的に動く生物はいます。かれらは自律的に自分をコントロールします。一方で、コンピュータソフトウエアに、私たちは学習する能力をもたせ始めましたが、自律的ではありません。ソフトウエアプログラムは、人間がコンピュータに指令する道具であり、自律的に自分で変えながら改良していくものではありません。
しかしながら、ソフトウエアは学習を始めました。これをツールAIと呼びます。今後、10年間でツールAI は、自律的に学習するようにシフトしていくでしょう。
AGIのような汎用のインテリジェンスには、この自律的な動きを備える必要があります。目的のコースを知っており、必要なものを選択し、ユーザーが誰かを知っており、コンテクストを知っています。そのコンテクストがインテリジェンスをさらに磨きます。AGIはインテリジェンスと自律的な動きの両方を備えることを目指しています。おそらく将来AGIは人々に恐れられるようになるかもしれません。人がAGIを頼って話を聴くことになるからです。
今は、予測可能なAGIを作ろうとしている段階で、人間は銀行口座を管理するだけですが、今後、AGIはリスクプロファイルを作り、リスクプロセスとのバランスを取ります。(例えばリスクが高まりそうだと判断できれば、株の買いを指示しません。)AGIは将来、フィナンシャルマネージャー以上の存在になるでしょう。
東京には、AGIをよく知っている研究者が大勢います。彼らとWBAI(Whole Brain Architecture Initiative)という組織を作り、毎月、AGIについてディスカッションしています。彼らのアプローチは、人間の脳をモデルにしていますので、ユニークで面白いと思います。ただ、商用にするための資金集めに苦労していると聞いています。
──ロボットへの応用のメリットは
わたしたちは、産業用ロボットではなく、ソーシャル、かつエモーショナルなロボットを開発しています。人間の持つ感情を理解し対話できるロボット、すなわちAGIを採り入れたロボットを目指します。香港では工場向けの産業用ロボットを安く作ることに力をいれています。私が目指すのは、大阪大学の石黒教授が開発しているようなロボットです。しかし、石黒教授のロボットのコストは100万ドル。私が目指すのはコストが1000〜2000ドルのロボットです。それでいて人間と同じような顔で人間の言葉を理解し対話できるロボットを2018年のクリスマスまでに開発します。
日本でロボットを商用化するのは難しいでしょうね。日本はハードウエアの開発能力が高く、とても洗練されたものを作るのが得意ですが、製造コストが高いからです。一方、中国は製造コストは安いのですが、ガラクタのようなものが多い印象です。
当社は、2〜3年のうちに人間スケールのロボットを作る予定です。ヘルスケアや介護にも使えるロボットで、人間のコンテクストを理解するものです。人々を支援し、対話可能なので、高齢者の癒しに向くでしょう。子供の相手をすることもできます。しかも、子供の言いなりにならず必要なしつけも行えるのです。
[ 脚注 ]
- *3
- センサで何かを感じたらそれに対応するように動くものを自律的に動くと言う。これに対しこれまでのロボットは、コンピュータのソフトウエアで書いたとおりに動くだけで、人間の思うように適切に対応しない。
 |
Profile
ベン・ゲーツェル(Ben Goertzel)
アイデア(Aidyia)社 創業者・会長兼チーフ・サイエンティスト
ハンソン・ロボティクス(Hanson Robotics)社 チーフ・サイエンティスト
1966年、ブラジル生まれ。米国Temple大学で数学の博士号(Ph.D)を取得、ネバダ大学、ニューヨーク市立大学など数校の大学で、数学やコンピュータ・サイエンス、コグニティブ・サイエンスの研究に従事。数学の知識を活かし、AIのアルゴリズムの開発に集中した。その後、AIの汎用性を高めて人間に近いAGI(Artificial General Intelligence:汎用AI)を提案、研究開発するようになった。ロボット開発では、人間と同じようにいろいろな話題にも反応できるように高齢者、幼児らの言葉まで理解できるようなロボットを目指す。AGIはそのロボットに応用するための頭脳となる。
Writer
津田 建二(つだ けんじ)
国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト
現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。
30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニスト。
半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。書籍「メガトレンド 半導体2014-2023」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)など。