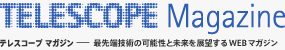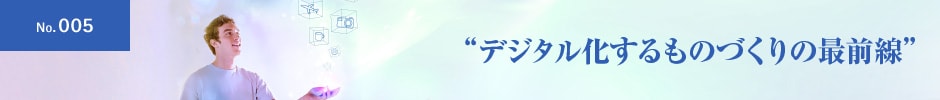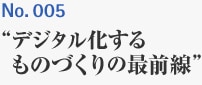ソフトウェアにあわせてハードウェアを作る発想が当たり前に
──Cerevo*5のような大手メーカーでは出さないような製品を出すベンチャーが登場したり、少し文脈は異なりますが、パーソナルファブリケーションや個人でのモノづくりへの関心も高まっています。今後、ユビキタスエンターテインメントのように、ソフトウェアを専門にしていた企業が、ハードウェア開発に乗り出す事例は増えていくのでしょうか。
今後は、サービス業の人たちが、自分達のサービスをよりよくするために、自分達のためのハードウェアをつくるケースが増えてくるのではないかと思います。例えば、iPhoneの新OS「iOS7」の目玉として、iBeacon*6という機能がありますが、この機能は店舗のIT化の実現を支援します。例えば、iBeaconをバーゲン品の近くに置いておくと、その商品に近づいた顧客のスマホからクーポンが出てきて、そのクーポンをつかってスマホで清算することができるのです。他にも、ヤマダ電機もEveryPadというオリジナルブランドのタブレット端末を出しています。そういったソフトとハードが一体化する事例が、増えてくるのではないでしょうか。その結果、ハードウェアがソフトウェアの一部だという認識がなされてくるのではないかと考えています。実際、AppleとApple以外の会社の違いは、ハードとソフトをバラバラに扱うか、一緒に扱うかの違いしかないと思います。GoogleがNexusシリーズをわざわざ作っているのは、標準となるハードウェアを用意しなければいけないという使命感があってのこと。やはり、ソフトからハードまで、自分達で全部でデザインできることが、今後求められてくることなのではないでしょうか。
──それはかなり大きなパラダイムシフトですよね。今までの発想だと、ハードウェアがあって、そのハードウェアにあわせて何かソフトウェアを作る感じでした。
そうです。だから、これからはそうじゃなくて、ソフトウェアにあわせてハードウェアを作るということになると思います。
──enchantMOONはその先駆けみたいなものですか?
まあ、先駆けかどうかはわからないけど、こういう発想が自然になっていくのではないかなと思っています。
[ 脚注 ]
- *1
- enchantMOONの特徴的なUIであり、アイコンやメニューなどの目に見えるようなUIを用意せず、指で丸を書き、その中にペンでコマンドを書くことで、操作を行うというコンセプト
- *2
- ビル・アトキンソンが開発したMac OS用ソフトウェア。カードとカードを繋ぐことでハイパーテキストを実現し、HyperTalkと呼ばれるスクリプト言語でプログラムの記述が可能
- *3
- 複数のテキスト(文書)を相互に関連づけ、結びつける仕組み。Webサイトは代表的なハイパーテキストである
- *4
- enchantMOONに実装されているビジュアルプログラミング環境。ブロックを並べていくことでプログラミングが可能であり、子供でも簡単にプログラミングを行える
- *5
- 岩佐琢磨氏が創業した家電ベンチャー。PC不要でUstream配信ができるLiveShellなど、大手メーカーが製造しないようなニッチな製品の開発で注目を集めている
- *6
- iOS7から実装されたBluetooth LEを使った機能で、乾電池で動くBeaconセンサー端末(ARMプロセッサー、標準で加速度センサーを搭載)とアプリ上で通信できる。
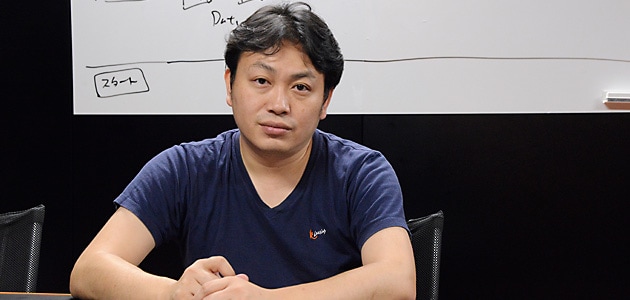 |
Profile
清水 亮(しみず りょう)
1976年生まれ。電気通信大学在学中に米Microsoft Corp.の次世代ゲーム機向けOSの開発に関わり、1998年末に株式会社ドワンゴ入社。 1999年に同社で携帯電話事業を立ち上げる。 2002年退社し、米DWANGO North America Inc.のコンテント開発担当副社長を経て2003年独立。 2005年、独立行政法人情報処理推進機構により、天才プログラマー/スーパークリエイターとして認定される。ベストセラーとなった携帯向けコンテンツマネジメントシステム「ZEKE CMS」や大手通信キャリアに採用されたミドルウェアの「microzZEKE」、HTML5ベースの「enchant.js」などを世に送り出した。
Writer
石井 英男(いしい ひでお)
1970年生まれ。東京大学大学院工学系研究科材料学専攻修士課程卒業。
ライター歴20年。大学在学中より、PC雑誌のレビュー記事や書籍の執筆を開始し、大学院卒業後専業ライターとなる。得意分野は、ノートPCやモバイル機器、PC自作などのハードウェア系記事だが、広くサイエンス全般に関心がある。主に「週刊アスキー」や「ASCII.jp」、「PC Watch」などで記事を書いており、書籍やムックは共著を中心に十数冊。