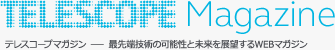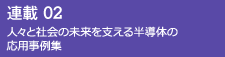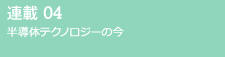第3回
IoT向け半導体
- 2015.05.01

「IoT(Internet of Things)」という言葉をよく耳にするようになった。直訳すると「モノのインターネット」。今ひとつピンとこない言葉である。しかし、このIoTこそが、今後の半導体産業、ひいては電子産業全体、さらに言ってしまえば人々の暮らしや社会活動を一変させる可能性を秘めたコンセプトなのだ。これからのIoTには半導体が欠かせないことを紹介する。
IoTとは、これまでのIT機器の範疇には入らない"モノ"の間をインターネットでつなぎ、情報をやり取りするネットワークを指す。冷蔵庫、机、道路、ボールペン、畑のキャベツ、犬、猫、そして人間、世の中のありとあらゆる"モノ"をインターネットにつないでしまう壮大な構想である(図1)。もちろん、いきなりこれら全てが一気につながることにはならないが、今後は徐々に、そして確実に、相互接続される"モノ"が増えていくことだろう。
 |
世の中全体を巨大なコンピュータに
では、"モノ"をインターネットにつないで一体何がしたいのか。世の中全体を一つの巨大なコンピュータとして機能させ、"モノ"の動きや状態をきめ細かく管理・制御しようとしているのである。半導体技術やICT(情報通信技術)の進化によって、データセンターに集めた莫大なデータ(ビッグデータ)の中から意味のある情報を抽出できるようになった。これを豊かな暮らしや継続可能な社会を作り出すために利用するのだ。産業、エネルギー、医療、建設、農業など、IoTによって変革がもたらされる分野は驚くほど広い。しかも、これまでICTとは縁遠かった分野ほど大きな変革が起きるだろう。
ただし、ICTが進歩するだけでは、ビッグデータの活用はできない。「朝起きた時の体温」「橋を渡るクルマの重量」「工場での部品在庫」「冷蔵庫の中の食品の賞味期限」−−−。こうした人々の活動や社会の動きを知るためのデータを、あらゆる場所から吸い上げ続けて、ビッグデータを作る仕組みが欠かせない。ここを埋めるのが、新たに登場してくるIoT関連機器の役割になる。
IoTが作り出す"神様の眼"
グーグルは、インターネット上の膨大な情報を整理することで、新しい価値を持つ斬新なサービスを作り出した。仮想空間ともいうべきインターネット上のビッグデータと、物理的な現実のIoT関連機器との融合は、インターネットの新しいサービスを、現実の社会にまで拡張する。例えば、「今、この瞬間に起きている人は、世界中に何人いるのか?」という問いにはまだ誰も答えられないが、IoTの行き着く先では、こうした問いに即座に答える"神様の眼"のようなサービスが登場する可能性さえある。
現在のIoTに大きな影響を与えた、発想の原点となる構想がかつてあった。米カリフォルニア大学バークレイ校のクリストファー・ピスター教授が打ち出した「Smart Dust(賢い塵)」である。実体は、照度と温度を測るセンサー、無線通信装置などを集積した「Mote(粒)」と呼ばれる数ミリ大のデバイス(図2)。これをバラまくと、Mote同士が自動的にセンサーネットワークを形成し、それぞれの場所の情報を送り続けるというものだ。ビルや家の壁に塗り込んで、エネルギーの消費を管理するといった用途が想定されていた。
 |
このSmart Dustの考えをビジネスに発展させた企業がダストネットワークスであり、アナログICの高収益企業のリニアテクノロジーが2011年末にダストネットワークスを買収した。「リニア」は今やワイヤレスセンサネットワークから一歩進んだ、IoTシステムを活用したセキュリティまで確立している。
これまでにもIoTと同様の抽象的な技術革新を表したコンセプトがブームになった。「情報処理と家電と通信の融合」を目指した"マルチメディア"はインターネットとして、「いつでも、どこでも、誰とでも」を目指した"ユビキタス"はスマートフォンとして結実した。IoTもいずれ死語となり、より具体的なサービス、システムの名称で呼ばれることだろう。その先駆けは、既に見えている。これらの先行例から、IoTがどのようなサービスやシステム、機器を生み出すのか、そこではどのような半導体が求められるのか、垣間見ることができる。