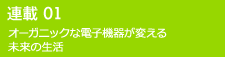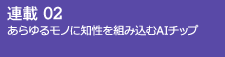|
2020年の国内サービス開始に向けて動き出した、次世代通信規格「5G(ファイブジー)」。通信の大容量化や低遅延化に加えて、多数端末が同時接続できるメリットを謳っている。これは、携帯電話だけでなく、家電やクルマ、社会インフラなど、さまざまなデバイスが繋がるための規格だ。長年にわたって情報通信分野の最先端で研究を続けてきた森川博之教授と、国内外の携帯電話業界を中心に旺盛な取材活動を続ける石川温氏が、未だ我々の想像の先にある2020年代の5G社会を見通した。 |
享受できる3つのメリット
森川 ── 携帯電話業界の最新情勢を伝える石川さんの記事は、いつも興味深く読ませてもらっています。どの位のペースで海外取材へ行かれているんですか?
石川 ── 展示会が重なるようなときは、週2〜3回になりますね。情報の鮮度が大切なので、常に締め切りに追われているような日々です。でも、僕たちジャーナリストは研究者や開発者の成果を後追いで伝える存在ですから、今日は現場の貴重なお話を伺える機会だと楽しみにしていました。
── まず「5G」という次世代の通信規格は、何を実現させるのでしょう。簡単なおさらいとして、森川先生からご解説いただけますか?
森川 ── 5Gの大きな特徴として、3つの目的が挙げられます。まずは「大容量化」。単純に、現在の通信がもっと速くなるということですね。
2つ目は「リアルタイム性」です。これは通信の遅延が少なくなることで実現されるもので、例えば、クルマとクルマの間といった「エンド・トゥ・エンド」の通信が、リアルタイムで行えるようになります。
最後は「超多数同時接続」。つまり、接続できる端末の数が圧倒的に増やせるのです。これによって、ちょろちょろと通信するようなIoTデバイスをたくさん収容することができます。
リアルタイム性と膨大な数の収容というのは新しい通信の仕組みだと言えますが、速度の向上は今までの技術の延長線上にあるので、まったく新しい技術が出てきたという感じではないですね。
石川 ── 第1世代(1G)から第3世代(3G)では、通信規格がガラッと変わりましたよね。それによって新たな基地局を置かなければいけなかったし、出力方式も変えなければいけませんでしたから、各社はだいぶ苦労したはずです。
そこで、第4世代である4Gからは「ロングタームエボリューション」と言って、長い時間をかけてちょっとずつ進化させていきましょうということになりました。
その後に来る通信企画の大きな変化はIoTですが、実はIoTの規格は乱立しています。5Gについて取材していると「ファントムセル」だとか「マッシブマイモ」といった新しい技術の名前がいろいろ出てきますが、もともと4Gと5Gの境目はなくて、なんとなくこのタイミングで5Gと言っちゃおうかというところがあったりするのではないでしょうか?
森川 ── おっしゃるとおりで、5Gはテクノロジー面で言うとインパクトが少ないんです。すごく新しい技術が出てきたという事実は残念ながらありませんから、われわれ技術の側からすれば、あまり面白くはない。しかし、それだけ技術が成熟してきた証だとも言えるでしょう。
 |
多様なニーズに応える通信規格
石川 ── ユーザ側からすれば、大容量というのは大きなメリットだと思います。今のスマートフォンは月末になったら通信速度に制限がかかって、若い人たちが「ギガが足りない!」と困っている状況ですよね。そういったことがなくなり、スマートフォンがストレスなく使えるようになる。もし、YouTubeのような動画を見たいだけ見られるようになれば、新しいサービスも登場するでしょう。
一方で、データ使用量がどんどん増えると電力も使いますから、電池はどうするのかという問題もありますよね。電池の新しい技術はなかなか出ないから、難しいところだと思います。
森川 ── 5Gが今までよりちょっと違ってきそうな感じを受けるのは、ネットワークのソフトウェア化です。有線ネットワークにはSDN(Software Defined Networking)というものが入ると言われているので、有線接続の雰囲気が変わっていくかもしれません。
ユーザ側からするとSDNであろうがなかろうが一緒なのですが、制御が効率よくできるようになります。それによって多様なニーズをうまく収容できるのですね。ニーズのダイバーシティ(多様性)が高まるという表現をしてもいいかもしれません。
例えば、1日に1回だけ少量のデータを送信するIoT端末から、4Kや8Kの膨大なデータをコンテンツとして流すサービスまで、5Gになるとデータの種類が一気に増える。そうした状況をうまく収容するために、ソフトウェアでうまく制御してあげるという感じです。