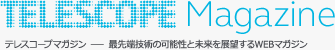第2回
私たちが火星人になる日
実現に向けて動きはじめた有人火星探査計画
- 2016.08.31

太陽系第4惑星の火星。夜空に赤く怪しく輝くこの惑星は、太古の昔から不吉な星として、人々から怖れられていた。しかし20世紀中ごろ、人類はロケットと探査機を使って、この赤い星を探検する力を手に入れ、今では7機もの探査機たちが火星で探査活動に従事している。そして、かつてはSF小説の中の夢物語にすぎなかった有人火星探査も、今やかつてないほど実現に近づきつつある。本連載では、第1回で無人探査機による火星探査の歴史と現在、将来を、第2回で実現に向けて動きはじめつつある有人火星探査について、そして第3回では、日本で検討が進む新たな火星探査計画について紹介したい。
有人火星探査を目指して
無人探査機ではなく、実際に人が火星に行って探査する「有人火星探査」は、古くからSFで描かれてきたテーマの一つである。火星は金星とならんで地球の隣にある惑星であり、かつ熱地獄の金星に比べるとまだ、住むことが可能に思えることから、大宇宙へ漕ぎだした人類が赴く先として描かれてきたのは当然のことだろう。『オデッセイ』や『テラフォーマーズ』といった小説や漫画、映画が記憶に新しいように、火星を舞台に人類が活躍する魅力は、今も色あせていない。
その有人火星探査について、初めて現実的かつ具体的な構想を打ち立てたのは、ドイツ生まれのロケット科学者ヴェルナー・フォン・ブラウン(1912~1977年)だった。フォン・ブラウンは第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの下で世界初の実用的なロケット・ミサイルである「A-4/V-2」を開発し、戦後は米国に渡ってロケット開発を続けていた人物で、彼にとって、人類が月や火星、さらにその先の星々を探検することは個人的な夢であると共に、人類にとっても当然の未来だという確信があった。
フォン・ブラウンは1952年、つまり第二次大戦が終わり、彼が米国へ移住してからわずか7年後の、まだ人工衛星すら飛んでいないころに、『The Mars Project』という本を発表している。この中で、人が火星に行って帰ってくることが実現可能であること、そしてそのために何が必要か、ということを論じ、有人火星探査が夢物語ではないことを説いた。
彼はその後、米国のロケット開発の中心人物としてキャリアを積み、やがて米国が立ち上げた有人月探査計画「アポロ計画」のメンバーの一人として、人を月へ送り届けるための史上最大のロケット「サターンV」の開発を手がけた。そして1969年、そのサターンVによって打ち上げられた「アポロ11」によって、人類はついに月に降り立った。
人類が月に立った。次は火星だ――。フォン・ブラウンはそう考え、『The Mars Project』からさらに進んだ有人火星探査の構想を描いた。しかし、米国はアポロ11の成功後、宇宙開発への熱を徐々に失い、アポロ計画は「アポロ17」で終了。フォン・ブラウンが構想していた有人火星探査も実行に移されることはなかった。
その後も有人火星探査は、ときにはNASAで、ときには大学や民間団体、一個人で検討されたが、やはり実現することはなかった。
有人火星探査を行う際に何よりも障害となるのは、火星の環境が人間が生きるのには適していないことだろう。大気の主成分は二酸化炭素で、宇宙船の中に閉じこもるか、宇宙服を着こむしか生きる方法はない。また、火星で暮らすための酸素や水、さらに地球に帰還するためのロケット燃料なども地球から持っていかなければならず、宇宙船は途方も無いほど肥大化。とても地球から打ち上げられない規模になり、予算も天文学的な数字に膨れ上がってしまう。
ただ、それを解決する方法は、これまでの研究の中でいくつか提案されている。たとえば1990年に米国の科学者ロバート・ズブリンらが発表した「マーズ・ダイレクト」構想では、火星の大気の大部分を占める二酸化炭素を、地球からロケットで持ち込んだ水素と反応させてメタンと酸素を生成。火星で人間が暮らすのに必要な空気と、地球帰還に必要な燃料の両方を現地で作り出すことで、地球から打ち上げなければならない物資の量を大きく抑えるアイディアが示された。このアイディアは現在でも、実際に有人火星探査を行う際の有力な方法の一つとして、検討が続いている。
 |
しかし、人が火星に赴く際の問題はそれだけにとどまらない。火星までは片道でも半年、火星での滞在と、帰還に適したタイミングを待つ時間を加味すれば、行って帰ってくるのに2年から3年はかかる。この間に宇宙船が故障したり、宇宙飛行士が病気になったりしたらどうなるのか。そもそもそれほどの長期の宇宙滞在に飛行士の体が耐えられるのか――。こうしたさまざまな問題が解決する目処が立たず、人類は長く地球で足止めを食らうことになった。