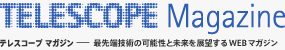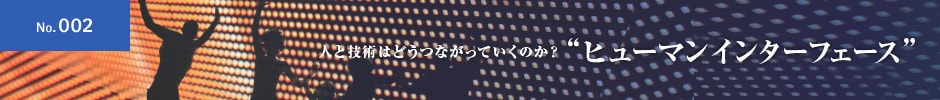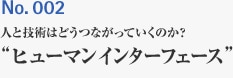身体に訴えるものにこそ、
これからのフロンティアがある。
──お二人の最新のプロジェクトや研究を教えてください。
真鍋 ── インターフェースは間接的に関わってくる内容ですが、Perfumeのグローバルサイト*17を作る際に、3軸加速度センサと3軸角速度センサ、3軸地磁気センサを使ったモーションキャプチャ技術を利用しました。そのダンスのモーションキャプチャデータと音源を無償配布して、ユーザーにエグザンプルコードを提供したんです。GitHub*18の環境なども使ったプログラマー向けの企画でしたね。
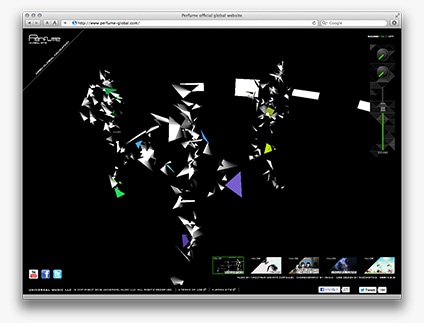 |
暦本── 何百という動画は、全てユーザーが作ったのですか?
真鍋 ── オフィシャルサイトに上がっている動画はこちらから声をかけたものですが、それ以外は全てユーザーが作ったものです。一般の方だと、「初音ミク」との相性が良かったので、初音ミクを使った作品も多かったですね。面白いものではロボットやレーザーを動かしているものもありましたよ。
暦本── うちの研究室でもモーションキャプチャーを導入したばかりなんです。これまでのインターフェースというのは、ワープロなり、検索エンジンなり、人間を賢くする役目が基本でした。その一方で、人間の身体の動きを良くするというオーグメンテッド・ヒューマン的な方向性に、特に注目しています。
私は、ユーザー・インターフェースの大きな変革は、知能よりもむしろ身体をエンハンス(強化、向上)する研究から起こると考えています。例えば、ダンスが踊れるようなインターフェースとか、自転車に乗れるようになるインターフェースなどですね。身体や健康といったテーマにITが入ることに可能性を見ています。
真鍋 ── 僕は今、スタートアップのビジネス界隈で行われていることにすごく興味があって、いろいろとチェックしているのですが、メディカルの事例で面白いものが多いですね。FacebookやTwitterみたいなウェブサービスよりも、生体センサーとiPhoneをセットにしてサービスを作るようなところが面白いと感じます。
暦本── 確かに医療センサーをiPhoneにつなげる動きは顕著です。超音波内視鏡などもありますし、それをさらにソーシャルネットにつなげると発展しそうです。 私はiPhoneなどの次のステージを考えた場合、スポーツウェアなどにコンピュータが入って、新しいスポーツがデザインできないものかと思います。例えば、中京大でハンマー投げの室伏選手が取り入れているのは、ハンマーの加速度をセンシングしてどのぐらいのスピードが理想的か、オーディオ・フィードバックで聴く練習法だそうです。コーチがダメとかいいと言うのではなく、科学的に理想の動き方を計算して、それで今の自分の動きの差分を何らかのフィードバックで戻すといったトレーニング手法が注目されているんですね。
トップアスリートもそうなんですが、普通の子どもがうまく逆上がりできるようになるといった研究を含めて、こうしたインターフェースはもっと進化させられそうです。例えば、本当のPerfumeのダンスと、自分のダンスにどのくらい誤差があるかがフィードバックで分かったら、それでダンスが上達できるかもしれませんよ。
真鍋 ── なるほど。
暦本── Googleやアップルは、情報通信の世界で優れたユーザー・インターフェースを生み出していますが、それは普通の生活としての実空間のインターフェースではないですよね。家の窓がどうなったらいいかとか、もしかすると、食べ物がどうなったらいいかとか、そちらの方がインターフェースの研究と呼ぶべきものじゃないかと感じています。
そうなると、まだいろいろと発展性が残されています。椅子やベッドは長い年月の間ずっと変化していませんよね。コンピュータが画期的になったのと同じようには、画期的になっていないものが世の中にいっぱい残っている気がするんです。
真鍋 ── そういうところにコンピュータ的な要素を入れていく訳ですね。
暦本── そうですね。うちの研究室では、キネクトを使ったちょっとしたネタがあります。私はずっと猫背だって言われていたんですね。なので、オフィスの上にキネクトを吊って、頭上から見て自分が猫背かどうかを判定するプログラムを走らせて、自分が猫背にならないようにというシステムを作りました。
キネクトを使った「Squama*19」という建築の研究もしています。壁を構成しているのは、1個1個のプログラマブルな液晶モジュールで、透明度を電圧で変化させられるパネルです。建物のファサードをロボットのように変化させる研究ですね。
真鍋 ── ウムガラス*20みたいな?
暦本── まさにそうです。ウムガラスをできるだけ細かくしようという発想で作っています。何ができるかというと、ここはプライバシーを守りたいというときに、その住人のいるところだけ部分的に半透明にして隠せる。外から覗き込むとキネクトでトラッキングして、ちょうど絶妙に覗き込めないようにできるんです。あとは、家から外を見るとちょうど絶妙な位置に嫌な看板があるのでそこだけ見たくない、でもカーテンは全部下ろすと嫌だ、というときに視線の先だけ隠すとか、部屋の中の特定の場所だけ「ここは暗くしておきたい」と指定すると、太陽の位置を逆算していつもそこが影になるように窓が変化する「プログラマブルな影」みたいなことができます。
こういう透明な窓が部分的には透明ではなくなるというのをプログラムできるようになると、窓と壁が共存する、新しい建築材料が作れるだろうという研究です。
──実用化されたら、将来の家の形がまるで変わりそうで、デザインの想像がつかないです。
暦本── ケータイとかスマートフォンを30年前の人が見ても、何をやっているか分からないと思うんですよ。Twitterだって全然理解できないだろうし、30年前にSF映画を作っても「小さなガラスの板みたいなものをみんなが電車の中で触っている」といった演出はしないはずです。
そういった意味で、生活の中ですごく変化するみたいなものがないかな、と考えたとき辿り着いたのが、普段暮らしている環境としての家だったんですね。