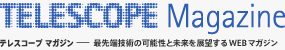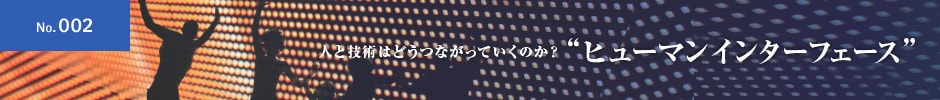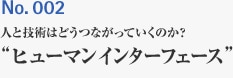消えるスイッチ、残るスイッチ
たくさんのスイッチがあることがイコール、機械が高機能であることの証明だった時代があった。少し前の飛行機の操縦席や、発電所の操作盤。あるいはたくさんのスイッチとツマミが一面に並んでいるシンセサイザー。スイッチやツマミの数が多ければ多いほど、操作できる世界が広がる。インターフェイスが複雑であればあるほど凄いことができる。そんな時代もあったが、いつの頃からか、スイッチやボタンの数は減少傾向にある。
大きな理由は、操作のインターフェイスが、コンピュータのディスプレイ上に実現するようになったからである。Apple社のiPhoneなどは、側面の電源と音量の+-のスイッチ、それに本体下部にあるたった一つの凹みボタンのほかは、すべてディスプレイ上で操作を行なうようになっている。物質としてのスイッチの多くは、これから画面の中へうつっていくことになるのだろう。インターフェイスとしてのスイッチは、モノからデータの領域に入っていく。究極的にはBMI(ブレイン・マシン・インターフェイス)(*1)など、身体を介さないスイッチへと進化していくはずだ。
しかし、どんなにモノとしてのスイッチが見えなくなっても、人間の脳、そしてこころの中にある、オフとオン、0と1、いないといる、の構造は変わらない。だとするなら、そこにスイッチというインターフェイスは残り続けるはずだ。これから先も、子どもたちはスイッチを押し続けるだろう。
取材協力:日本開閉器工業株式会社
参考資料:日本開閉器工業株式会社のスイッチ分類資料:
https://www.nikkai.co.jp/pdf/sw-kiso_ver01.pdf
[ 脚注 ]
- *1
- BMI:ブレイン・マシン・インターフェイス。脳とコンピューターなどの機械を直接つなげて操作を行うインターフェイス技術。
Writer
淵上周平
1974年神奈川県生まれ。中央大学総合政策学部にて宗教人類学を専攻。
編集/ウェブ・プロデュースを主要業務とする株式会社シンコ代表取締役。