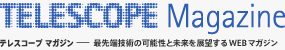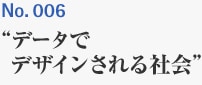RFIDタグへの熱狂と失望
90年代末から2000年代初頭にかけて、ユビキタスコンピューティングは世界的に注目されたが、その中心にあったのがRFIDタグ(Radio Frequency Identifier:無線タグともいう)だった。RFIDタグは数mm程度の小さな電子回路を搭載しており、その中に記録された情報を非接触で読み書きできる情報媒体。Suicaに使われているFelicaなどの非接触ICカードもRFID技術の1つだ。こうした非接触ICカードは、読み取り機(Suicaの場合は自動改札機)からの電波を電力に変換して利用するため、電池を搭載する必要がなく、パッシブ型(受動型) と呼ばれる。
当初RFIDタグは、物流や医療分野での利用が想定されていた。例えば、病院などで患者が服用する薬を入れた容器にRFIDタグを貼って一元管理することにより、薬の飲み間違いや飲み忘れの防止に使える。物流分野に導入すれば、在庫状況をリアルタイムに把握でき、盗難防止や自動レジにも応用できる。
スーパーマーケットチェーンのウォルマートは、2003年にRFIDタグの導入実験に踏み切った。しかし、その後2009年にはRFIDタグ導入を事実上諦め、あとに続く企業の事例はほとんどない。現在のところ、RFIDタグの利用分野はごく限られている。
普及が進んでいない最大の理由はRFIDタグならではの用途を強くアピールできなかったことだろう。例えば、10年前に日立が開発したミューチップは0.4mm四方で厚さは0.1mm以下と、紙に埋め込めるほど小さくて薄い。量産できればチップの単価は数円になると言われていたが、安価な商品の管理に使うにはまだ高く、情報の読み書き、管理するためのシステムも一から構築する必要があった。結局、RFIDタグを想定していた用途のほとんどが、QRコードを使って低コストに構築できることがわかり、RFIDの普及に至らなかったのである。
ただ、空港での荷物管理や商品単価が比較的高いアパレル業界での商品管理などのように、RFIDタグを効果的に活用している分野もある。また、フランスのベンチャー企業、Primo1DからはRFIDタグを糸に埋め込んだ「E-Thread」という技術も発表された。今後IoTが盛り上がるにつれ、RFIDタグが改めて注目されるようになる可能性は高そうだ。
 |