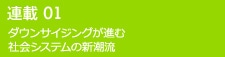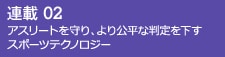理科室でも作れる! ホタルの発光物質を簡単合成
2016.6.13
 |
日本では夏の風物詩となっているホタル。実は1億年前に登場した、(生物進化の上では)比較的新しい生物種だ。
ホタルの発光は、発光物質であるルシフェリンと、酵素のルシフェラーゼ、それにATP(アデノシン三リン酸。生物がエネルギーを貯蔵・放出するために使う化合物)が反応することで行われる。エネルギーの4割程度が光に変わり、あまり熱を出さないのが特徴。生物発光の中で、ホタルは最も発光効率がよいと言われている。
これほど、効率のよい発光システムを備えた生物が、どうやって進化してきたのか? 酵素のルシフェラーゼについて、進化の過程はほぼ解明されているが、発光物質のルシフェリンは非常に複雑な構造の物質であり、それが生物体内で合成される過程は謎だった。
中部大学応用生物学部の大場裕一准教授らの研究チームらは、この複雑なルシフェリンを非常に簡単な方法で合成できることを発見した。その方法は、ベンゾキノンとシステインという2つの化学物質を、中性の水に入れ、室温で3時間かき混ぜるというもの。このプロセスで微量のルシフェリンが合成される。それこそ小中学校の理科室でも、発光物質を作れてしまう。
1億年前、ホタルの先祖の体内でも同じような化学反応が起こってルシフェリンが合成されるようになったと推測される。
ルシフェリンによる発光は、検査用の試薬でも使われている。他の蛍光物質と違い、ルシフェリンはATPさえあれば光源なしでも発光するという特徴がある。簡単な合成手法が発見されたことで、検査用の試薬が低コストになるだけでなく、まったく新しい応用が登場してくることも考えられる。