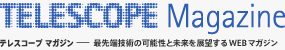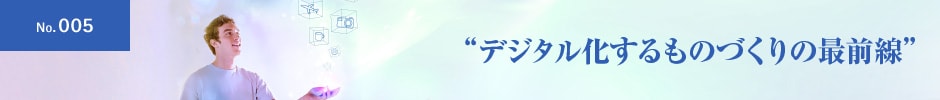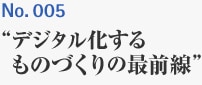創造性を高めるのは、
変わった人が集まる場だ。
──猪子さんのチームラボでは、大学と共同研究したりしていますか。
猪子 ── していますけど、結構難しいよね。大学の趣旨と会社の間には、乖離があるから。ただ、東北大学の先生とはすごい仲が良くて、うちのエンジニアが彼らの研究室で何か月も住み込みで共同研究して、キネクト*21と同じようなものを作ったんですよ。でも、その数か月後にマイクロソフトからキネクトが出てきてしまい、この1年ぐらいの苦労は何だったのかと思いました。
田中 ── 僕らの場合、5年から10年後ぐらいのことを考えてプロトタイプを作っています。すぐにビジネスに結び付かないから、それをマーケットインするのはさらに難しい面もありますが、大学と企業の健全な形って本来はそうじゃないのかな。
猪子 ── 僕らは大阪大学とも「チームラボボディ*22」というものを開発しました。大阪大学の先生が10数年間MRIで人体をコマ撮りした膨大な3Dデータがあったんです。そこから世界で初めて分かったのが、生きている人体の骨の動きなんです。
その先生も現場に出て、外科手術をしている人です。マーケットに半分いながら、研究としても第一人者の人ですね。彼が十何年間、自分がそういうのがあったら便利だと思って撮りためたデータが膨大にあって、それをサービスに落としたという理想形です。
 |
田中 ── 日本ではこうしたビジネスに結び付く例は珍しいですよ。アメリカには大学が作ったわけの分からないプロトタイプを商品まで落とすベンチャーが山ほどあるのに。
研究者が論文を書いて楽しそうにやっている世界とビジネスの世界が、日本では分断されているじゃない。それが問題だと思う。
猪子 ── アメリカだと大学の人たちも比較的マーケットに興味があるし、マーケットの人たちも研究に関心を持つよね、特にシリコンバレーあたりだと。
田中 ── だから、僕らはいろんな意味で大学をもっと破壊して社会につなげようとしています。1つはマーケットの話です。もう1つは、何と言うか、変わった人が集まる場が大学にはなくなってきたんだね、残念ながら。
猪子 ── 確かにね。
田中 ── 悲しいけど、変わった人が集まる場所を無理矢理にでも作る必要があったんですね。それでファブラボ鎌倉を作ったんです。
それでも、日本でワークショップをやると、似た人々が集まってしまうんですよね。チームの創造性が出るのは本来だと、一人ひとりが違う場合に限るんです。異質な人とチームを組むことが、メイカー・カルチャーには必要だと思うな。
猪子 ── 僕自身、エンジニアなどいろんな人たちとディスカッションしてプランニングする時、ある人がプロジェクトに入ると、なぜか自分のいいバリュー(価値)が出せることに気づいたんですね。
その人はグッドアイデアもないし、専門職的なサポートもしてくれないのだけれど、彼が入るとなぜかいいものが引き出されるんです。それこそがこれからのマネジメントなのではないかな、と自分の体験から思います。
田中 ── ちなみに僕はジャズバンドをやっていてサックスを吹いていたんです。音楽をやっていた頃からチームの創造性を感じるのは好きで、5人ぐらい違うスキルを持った人が集まる感じというのは分かる。そういう創造性が高められる場があるといいなと思うんですよね。
[ 注釈 ]
- *21
- キネクト(Kinect):マイクロソフトが2010年に発売したゲームコントロールデバイス。同社のゲーム機「Xbox 360」で音声やジェスチャーによるプレイを実現する。RGBカメラ、各種センサー、プロセッサーを内蔵した高性能に比して安価なため、同種システムの研究者に衝撃を与えた。12年にはWindowsにも対応。13年に次世代機「Xbox One」向けの新設計キネクトが発表された。
- *22
- チームラボボディ:大阪大学と共同開発した3D人体解剖アプリ。20〜30名の研究協力者を募り、生きている人間で10年以上にわたりすべての関節の形態や動きをCTやMRIで撮影。静止イメージ画像をコンピュータプログラミングによって解析した上で、人体の全身の筋肉・神経・血管・骨・関節をビジュアル化した。(c)菅本一臣(整形外科医師, 大阪大学教授) + チームラボ, 2013, アプリケーション。
http://www.teamlabbody.com/
http://www.youtube.com/watch?v=UjZo8U5YEVs