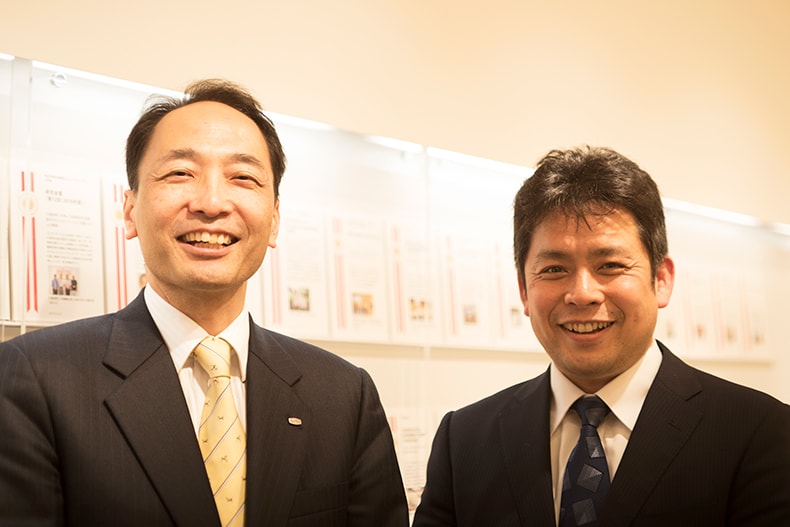Expert Interviewエキスパートインタビュー
── D-Waveなどは、すでに量子コンピュータをクラウド経由で企業が利用できるようにしていると聞きますが、ここにも量子インターネットの関わる技術が用いられているのでしょうか。
いえ、普通のインターネットです。実は、QuTechはいわゆる「生きた量子もつれ」においては、その距離で1.3キロの世界記録*5を持っています。一方、「死んだ量子もつれ」では、中国が世界記録を持っています。彼らは、2017年に量子科学実験衛星から光子を放出し、その光子が地上の最終ステーションで検知されたのですが、その時には光子はすでに消滅して(死んで)いました。
| 2015年にQuTechが行なった「量子のもつれ」現象の実験 |
── ロードマップの最後にある「トポロジカル量子コンピューティング」とはどのようなものですか。
これは、マイクロソフトと共同研究しているテーマでもあります。ここでは、通常の量子ビットではなく、特殊な性質を持つトポロジカル量子ビット*6を利用します。これは作るのが難しいのですが、ロバスト(堅牢)でノイズが防げるのでエラー訂正がそれほど必要ではありません。通常のケースでは、量子ビットを作るやいなやエラー訂正を開始しなければならないわけですが、トポロジカル量子ビットはそれをせずに使えます。どこかの時点でエラー訂正は必要になるものの、最初の負担がないのです。
── エラー訂正というのは、情報を安定させるということでしょうか。
既存の技術においては、フラッシュメモリなどで情報の劣化を防ぎ安定させています。それでも多くの電子機器は何らかのエラー訂正機能を備えており、多くはリダンダンシー(冗長性)を利用することでそれを実現しています。情報を一度で保存するのではなく、例えば3回行い、一定の時間の後にその3つがまだ同じかを確認します。もし一つが異なっていれば、それがエラーだということになり、多数決で残りの二つを本物だとするわけです。これが最も単純なエラー訂正の方法です。量子システムでも同様の方法を採りますが、ノイズの影響を受けやすいため、訂正はより頻繁に行わなければなりません。量子情報をいくつもの量子ビットに入れて確認するわけですが、基本的には常時エラー訂正をやっているようなものです。
 |
── ご説明いただいた3つのロードマップにおける研究成果を、どのように評価されていますか。
QuTechはミッションを掲げた研究組織ですから、具体的なマイルストーンを設定することが必要です。それを5年ゴールという形で定めています。5年後に達成していたいことを決め、研究の全てをそれに貢献するように位置付けています。たいていの大学では、それぞれの専門分野で個別に研究をするのが一般的ですが、QuTechはそうではありません。組織としてゴールを設定し、関わっている研究グループの間で相乗効果が出るようオープン・プランを設定しています。現在は、スタートしてから4〜5年の時点にあり、次のゴールを設定しようとしているところです。次の5年は、大学の外にも技術をオープンに提供して、潜在的ユーザーに使ってもらったり、企業との提携を広げたりすることも考えています。
── より実用化に向けた動きですね。
実際、すでに昨年から、コンセプトをデモとして見せるプロジェクトを3つ進めています。外部の人々がクラウドで利用したり、貢献したりできるようにし、ここで協力関係を築いていきたいと考えています。QuTechは国から資金を得て研究を行なっていますが、世界中の機関や企業とも共有できる技術として開発したいのです。最終的に人々が使いたいものが作れなければ何もなりませんから。
── デモのプロジェクトには、どのようなものがありますか。
量子インターネットでは、2020年にオランダの4都市を量子もつれのリンク*7で結ぶ予定です。それぞれの都市間は50〜100kmの距離があります。それに先立って、今年末にはデルフトと30km先のハーグを結びます。そのために、オランダ・テレコムのファイバーと施設を利用しており、さらにそれをライデン、アムステルダムへと広げる計画です。
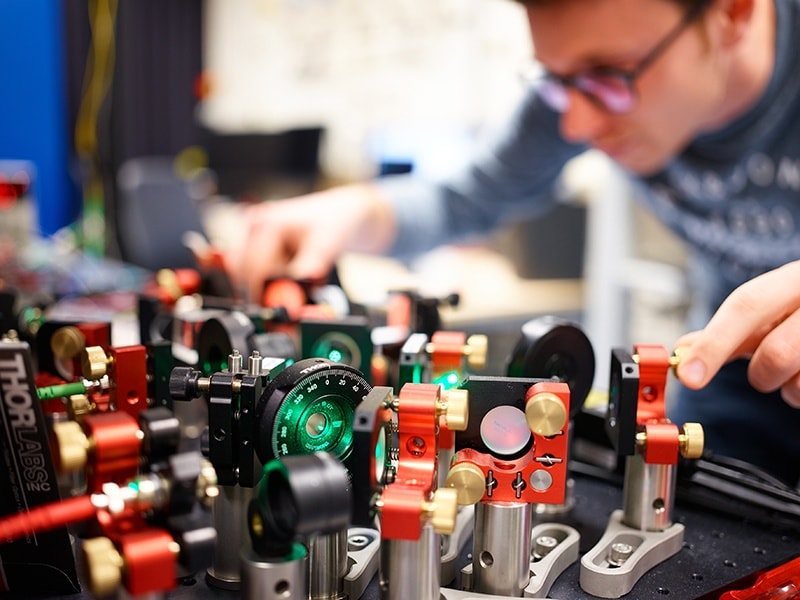 |
[ 脚注 ]
- *5
- 2015年にQuTechが行なった実験では、離れた一対の量子粒子が瞬時に影響を与え合う「量子のもつれ」現象を1.3キロの距離で電子を利用して証明した。その時、電子の存在も確認できた。
- *6
- トポロジカル量子ビット: 電子がシステム内に細分化されて散在するトポロジカルな状態を利用して、安定性を高めた量子ビット。
- *7
- 量子もつれのリンク: 量子もつれを利用した通信ネットワーク。