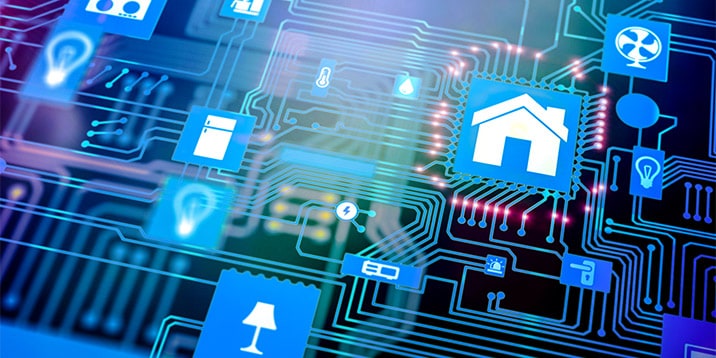連載01
半導体チップの再生可能エネルギーへの応用
Series Report
第2回
パワー半導体がエネルギーを制御する
2018.09.28
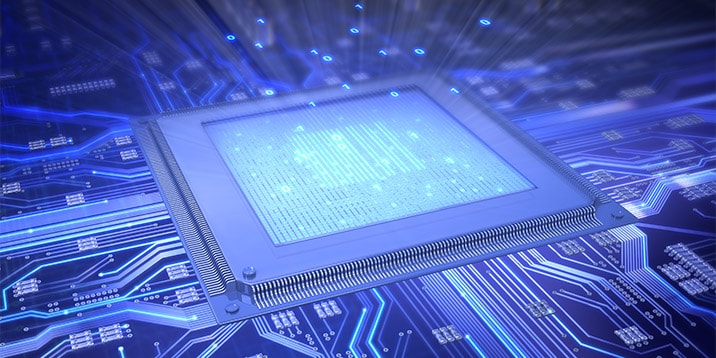
ソーラー発電のような直流電力であれ、風力や水力発電の交流電力であれ、生み出した電力を送電線に戻すためには、電力を商用電源(日本なら100Vで50Hzあるいは60Hz)の周波数に変換しなければならない。ここに、半導体が使われることになる。半導体エレクトロニクスを使わなければ、精度よく制御できないからだ。制御できなければ電力の流れが不安定になり、最悪の場合は停電に至る。ここでは、風力やソーラー発電で使われている半導体を見ていこう。
モーターとは、交流によるN極/S極同士の反発をうまく利用して回転運動に変える装置であり、長い間使われてきた歴史あるデバイスだ。回転させるアクチュエータとしてモーターほど効率よく動かせるデバイスはないため、この先も使われ続けるだろう。そして、電気を加えると回転力を生み出すモーターとは逆の働きをするのが、発電機である。発電機は回転力を使い、交流電力を生み出すが、その多くはモーターの原理に基づいている。これまでは回転数を変えるために、ギアという機械部品が大きな役割を果たしてきた。
ところが近年、電力量が増加してきたことにより、電力量のちょっとした変化でも、最悪の場合、停電を引き起こしかねなくなってきた。そこで、わずかな電力量の変化も検出し、過度な電力の流れが生じないように制御する必要が出てきた。もはやギアだけでは、精密な制御は難しくなってきたのだ。このため、精密制御が可能な半導体が使われるようになり、半導体側で数百アンペアという大電流を制御できるデバイスも登場してきた。これがIGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)と呼ばれるパワー半導体である。
かつて、サイリスタと呼ばれるパワー半導体が1000A(アンペア)という大電流を流す半導体デバイスとして使われていた。サイリスタは、入力にパルス電流を流せば、大電流がどっと流れっぱなしになるデバイスである。パルスを止めても電流は流れ続けるので、電流を止めるためには、転流回路と呼ばれるプラス、マイナスが逆になるような回路を付けなければならなかった。ところが、近年IGBTが登場したため、面倒な転流回路は必要なくなった。入力に電圧パルスを加えれば、一定の時間しか出力電流が流れないからだ。おかげで回路は簡単になり、非常に使いやすくなった。
効率の良いモーター、制御性の良いIGBT半導体といったデバイスの登場により、風力発電や太陽光発電を100V/200Vの商用電源に組み込むことができるようになった。しかし、半導体のメリットはそれだけではない。大電力の制御以外に、精密な制御も半導体ならできる。さらに、高速用・大電流用・高電圧用・高周波用など様々な用途に対して、IGBTのほかに、パワーMOSFET、パワーICなども使われるようになった。また、それらはシリコンだけではない。もっと高温でも使えるSiC(シリコンカーバイド*1)やGaN(窒化ガリウム*2)といった化合物半導体も商用化されている。ただし、シリコンの10倍の価格であるため、まだ限られた用途でしか使われていない。
[ 脚注 ]
- *1
- SiC(シリコンカーバイド): シリコン(Si)と炭素(C)を1対1で混合した半導体で、エネルギーバンドギャップが広い。このため、耐圧がシリコンの10倍もあり、200度を超える高温にも耐えられる。また、シリコンだとIGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)と呼ばれる構造にしなければ、耐圧と電流値を得ることができないが、IGBTは高速動作ができないため、周辺に使うコイルとコンデンサを大きくしなければならないという欠点がある。ここをSiCのMOSトランジスタに置き換えれば高速動作が可能になるためコイルとコンデンサを小さくでき、システム全体を小型化できる。ただし、製造しにくく、価格はシリコンの10倍もする。
- *2
- GaN(窒化ガリウム): これもSiCと同様にエネルギーバンドギャップが広い半導体で、青色LEDの原材料でもある。SiCと同様のメリットがあるが、製造上、ウェーハをまだ大きくできない。このため、MOSトランジスタを横型で使う必要があり、十分な耐圧をとるためには面積を大きくせざるをえない。そこでコスト的に見合う横型構造のトランジスタを使っている。それでもシリコンより数倍価格が高い。ただ、集積化しやすいため、普及はSiCよりも早い。