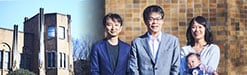Cross Talkクロストーク
医療ビッグデータを活用する上での課題
 |
── 最後に、今後医療ビッグデータを実際の診療に活用していく上での課題などをお話ください。
中山 ── まず医療者へのメッセージとしては、目の前の患者さんに対して、限られたデータだけで判断する時代ではないことを理解してほしいと思います。その患者さんのこれまでのデータを知ることが必要であり、その患者さんと同じような状況にある他の患者さんたちのデータと比較して、目の前の患者さんがどのような状態にあるのかを考えなければなりません。そのためには、まず同じような状態にある患者さんのデータが揃っていることが前提となります。つまり医師がカルテにきちんと記録を残すことが出発点となるわけです。カルテに意図的に書き残さないと伝わらないデータがあることを意識してほしい。
一方で国民に対しては、データを共有することから生まれる強さを理解していただきたいと願っています。個人情報の保護は改めて言うまでもなく大切であり、その上でビッグデータとして多くの人々の診療情報を蓄積して活用することにより、新たな医療が可能になるのです。
── 喜連川先生のメッセージをお聞かせください。
喜連川 ── 今日のお話では、データといえば画像を中心としてある種無機質なものであり、そこにいま中山先生がおっしゃった医師の判断もデータとして必要だということでした。更にそれに加えて僕は、患者のボイスをぜひ取り入れてほしいと思います。
中山 ── 医療ビッグデータに患者の声というのは、私も以前から考えていました
喜連川 ── 僕は少し前にちょっと大病を患ったのですが、そのときにつくづく思ったのが、いくら医師に喋ってもなかなか通じないということです。言葉でどのように表現すればよいのかわからないことも山ほどある。とにかく以前のような状況でない違和感があるのですが、その表出と医師との相互理解は容易ではありません。僕は医療の目的を変えて頂く必要があると思っています。つまり、医者が治せるカテゴリーの疾病を治す医療から、患者が困っていることを治す医療への変革です。実はこれは我々の理工系でも同じ側面があります。研究者は解きたい問題に向かって努力するということそのものを否定するわけではありませんが、解かなくてはいけない課題への挑戦も同時に必要です。もちろんすぐに変えられないとしても、徐々にでも変えていって頂けないかと。その意味ではカルテの中に、患者が抱えている悩みを書き込めるスペースを用意して頂けないかと思います。患者が自分が抱える悩みをもっと直接的に言える仕組みがあると良いと思います。
中山 ── 介護の現場などでも、同じことが言えそうです。
喜連川 ── そのとおりです。介護の現場で最も困っているのは、声を出せない被介護者です。レポートは介護をしている介護士からのもので、被介護者の声を拾い上げるメディアを用意することで、中山先生が最初におっしゃった「人を診る」医療が、ビッグデータを活用しながら実現するのではないか。今日のお話で、そんな希望を持ちました。
Profile

中山 健夫(なかやま たけお)
京都大学大学院医学研究科副研究科長・社会健康医学系専攻長・健康情報学分野教授。
1987年東京医科歯科大学医学部卒、米UCLA fellow、国立がんセンター研究所室長を経て2000年京都大学大学院助教授、2006年同教授。日本疫学会、日本臨床知識学会等の理事、日本医療機能評価機構Minds運営委員長、社会医学系専門医・指導医

喜連川 優(きつれがわ まさる)
国立情報学研究所所長、東京大学生産技術研究所教授。
1983年東大工学系研究科情報工学専攻博士課程修了。工学博士。翌年、東大生産技術研究所講師、現在教授。情報処理学会会長、日本データベース学会会長。紫綬褒章、レジオン・ドヌール勲章シュバリエを始め多数受賞。
Writer
竹林 篤実(たけばやし あつみ)
1960年生まれ。ライター(理系・医系・マーケティング系)。
京都大学文学部哲学科卒業後、広告代理店にてプランナーを務めた後に独立。以降、BtoBに特化したマーケティングプランナー、インタビュワーとしてキャリアを重ねる。2011年、理系ライターズ「チーム・パスカル」結成、代表を務める。BtoB企業オウンドメディアのコンテンツライティングを多く手がける。