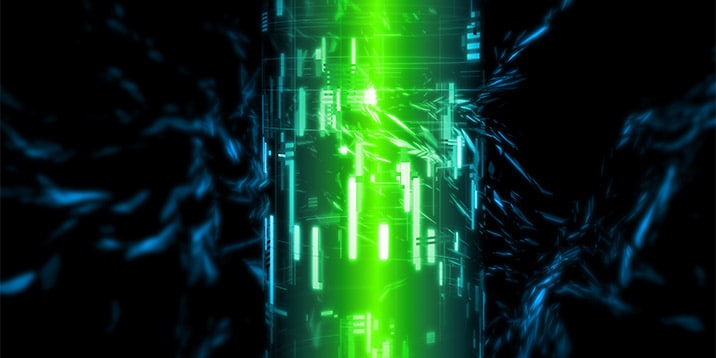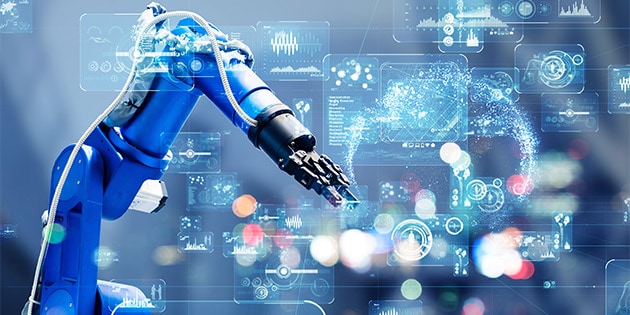Expert Interviewエキスパートインタビュー
最初の機体を自分で製作
── ドローン無人配送のニュースを見て、具体的に行動をしたのですか。
当時、日本ではまだドローンがあまり認知されておらず、私自身、「これは何だろう」と思いながら、インターネットで検索しました。ニュースで使っていたのは、たくさんのプロペラによって飛行するマルチコプタータイプのドローンでした。その頃、日本でマルチコプターのドローンをつくることができる会社はとても少なかったのを覚えています。とにかく、それらの会社に電話をするのですが、どこも門前払いでした。
その中で、唯一、話を聞いて頂けたのが、愛知県名古屋市の会社でした。この会社でも、はじめは門前払いされていたのですが、何回も電話をかけているうちに、社長から電話がかかってきて、材料費として100万円あればドローンをつくることができるという話をされました。そこで、クラウドファンディングを実施したところ、募集開始から2か月で80名以上から支援して頂き、100万円を集めることができました。
100万円はあくまでも材料費です。組み立ては名古屋の会社まで行き、自分自身の手でやりました。2か月という短期間で、ドローンの組み立て技術を一から教わりながら、組み立てたのです。この2か月間はとてもハードな日々でしたが、この経験は今でも役立っています。
── できたドローンを使って、どんなことをしたのですか。
2015年1月18日にこのドローンを使って、物資を運ぶ輸送実験を実施しました。この実験では、ドローンに1kgの荷物を載せて、高松市の高松東港から男木島の男木漁港まで約8kmの海上を飛ばすことに成功しました。さらに、この年の8月には香川県観音寺市において、往復20kmの実験にも成功し、実績を重ねていきました。
この頃の航空法には、ドローンの規程がまだ盛りこまれてなかったので、私たちは長距離の海上輸送実験をおこなうことができました。しかし、2015年9月に航空法が改正されたことによって、ドローンの飛行は基本的に目視による常時監視が必要になりました。ドローンの目視外飛行をするには、航空法に定められた基準を満たし、国土交通大臣の承認を受けることが必要になりました。
法改正でインフラ整備に着手
── 航空法にドローンの規制が加わったので、無人ドローンで遠くまで荷物を運ぶには、基準を満たす必要が出てきたわけですね。
そうです。目視外飛行を実施するためには、ドローンの針路、姿勢、高度、速度、周辺の気象状況、さらにはドローンに搭載されたカメラから送られてくる映像などを地上で把握できるようにする必要があります。そこで、様々な場所の気象情報を把握するための観測装置を配置し、それらの装置やドローンの機体からの情報を取りまとめ、複数のドローンの運行を一括して管理するシステムの開発に着手しました。
人による目視での監視をせずにドローンを運用しようとすると、そのためのインフラを整備しなければいけません。私はもともとICT(情報通信技術)のインフラ側のエンジニアをしていたので、その経験を活かしつつ、整備を進めていきました。
気象観測装置などのハードウエアは、すべて私がプロトタイプをつくっています。この装置は太陽電池で駆動しているのですが、最初のうちは発電量が足りなくなったり、ソフトウェアの不具合が起こったりして、機器が止まってしまうこともしばしばありました。これらの不具合に1つ1つ対応していき、1年半ほどの時間をかけて改良を重ね、完成度を高めています。また、気象観測装置との通信、ドローンから管制設備への画像伝送などのソフト面は、パートナー企業と一緒に開発を進めました。
 |
 |