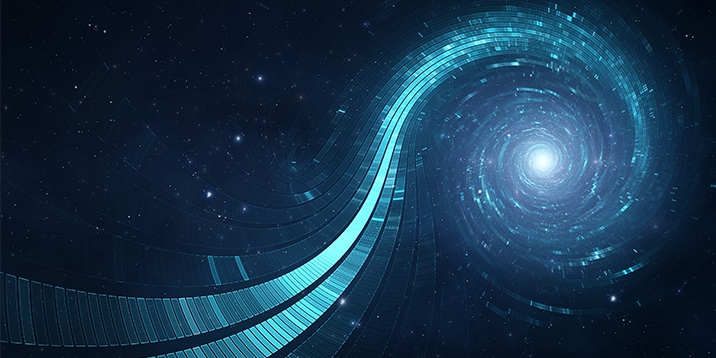Expert Interviewエキスパートインタビュー
日本の強みを活かせる食のビジネス
 |
── 宇宙での食料生産や供給とは、どのようなイメージなのでしょうか。宇宙食とは違うのでしょうか。
宇宙食は、食事そのものだけを指しますが、Space Food Xでは、食料生産から加工調理、そして食事する環境までをスコープとし、昨今注目されているフードテック*2やスマートキッチン*3など、食を取りまく新しい技術にも注目しています。宇宙食は時代の変化や技術の進歩と共に、バリエーションが豊富になってきました。宇宙食が登場したのは、1960年代で、当初はチューブ入りの離乳食のようなもので、味は二の次でした。時代を経るごとに、フリーズドライ、レトルトと技術が進み、宇宙食の質や味が向上してきました。そして、スペースシャトルの時代には、地上の食事のようなメニュー開発も進んだのです。
現在、ISSではアメリカ、ロシアの提供する標準食といわれるレギュラーメニューが300種類ほどあります。宇宙飛行士はそれらのメニューの中から、自分の好みに合わせて宇宙に持っていくものを選びます。Space Food Xでは、その先の技術として、3Dフードプリンター*4を使って、宇宙基地内で料理そのものを作ってしまうことや、宇宙での食料生産などを考えています。
参加しているパートナーの中には、調味料を自動生成して、卵かけご飯用のしょう油を約1500種類出せる技術を持っている方もいます。現在発売されている家電は調味料までコントロールできません。調味料をコントロールする技術を組み合わせると、地上のレストランの味を再現することもできるかもしれません。
── JAXAを含めて、日本で食に関する技術開発を行うことには、どのような利点があるのでしょうか。
日本人宇宙飛行士が宇宙に行くときは、アメリカ、ロシアが用意したレギュラーメニューの他に、自分たちが食べ慣れた食事をボーナス食として持ちこむことができます。JAXAは、宇宙日本食という枠組みで、日本の食事を持ちこめる仕組みを作り、現在この宇宙日本食には、ラーメン、カレー、ご飯など、20の企業から36品目が認証されています。
宇宙食は、宇宙での栄養補給源としてとても重要なものですが、ただ栄養が取れさえすればいいというものではありません。宇宙日本食は、宇宙で食べたときに、地上の味をなるべく再現できるように、味にもこだわっています。そのため、海外の宇宙飛行士にも人気があります。日本人宇宙飛行士が搭乗するときは、一緒に過ごす海外の飛行士と宇宙食を交換することもあるといいます。この日本の食へのこだわりや食品メーカーの強みは、将来の月や火星での食事を考えていく上でも重要になってくると思っています。
宇宙の技術を日常に
 |
── Space Food XはJAXAだけでなく、リアルテックファンド*5、シグマクシス*6と共同で運営となっていますが、なぜ、この3者で行うことになったのでしょうか。
リアルテックファンド、シグマクシス、JAXAは、それぞれ違う部分に強みを持っています。テクノロジー系のベンチャー企業を支援するリアルテックファンドは、宇宙分野だけでなく、バイオ分野からロボティクス関係まで様々な企業に投資しており、幅広い技術の目利きができます。シグマクシスは国内外のフードテック企業との幅広いネットワークに加え、世界の最新情報も常にリサーチされています。JAXAはこれからの月・火星探査に向けたシナリオの中で、宇宙開発と産業界との橋渡し役をしていきます。
ただ、このプロジェクトは運営の3者だけで行うわけではありません。2020年1月現在、企業、大学、研究機関、有識者など、50ほどのパートナーが参加しています。宇宙での食料マーケットは、具体的にはまだ存在していません。それぞれの強みを持つパートナーの皆さんと協力しながら、新たな市場を開拓していきます。議論や検討をして終わりではなく、共に汗をかきながら新たな市場を作っていく覚悟をもった方々と一緒にやっています。
[ 脚注 ]
- *2
- フードテック:フードとテクノロジーを掛けあわせた言葉。ICT(情報通信技術)を初めとする新しい技術を駆使することで、食の分野でイノベーションを起こす取り組みを指す。その範囲は、農業、食品生産、流通、外食、調理、小売りなど幅広く、700兆円の市場規模があるとみられている。
- *3
- スマートキッチン:ICTの発展によって、様々な電化製品がインターネットとつながり、外出先からスマートフォンで操作したり、インターネット経由で情報を得たりすることができるスマート家電が登場した。スマートキッチンは、キッチンにある様々な機器がインターネットとつながり、外出先から冷蔵庫の中身が確認できたり、レシピを映像で投影したりと、これまでにない機能を備えるようになったもの。
- *4
- 3Dフードプリンター:3Dプリンターは積層造形術という手法で、プラスチックや金属などを1層ずつ重ねていき、3次元の造形物をつくる技術。この技術を食品に応用したものが3Dフードプリンター。現在、ピザや和菓子を立体的に出力したり、チョコレートやスコーンをカップ型に出力したりする機器が試作されている。
- *5
- リアルテックファンド:ユーグレナ、リバリス、SMBC日興證券の3社が運営する投資ファンド。革新的な技術を生みだす研究開発型のベンチャー企業に投資し、育成、支援をする。
- *6
- シグマクシス:2008年に発足したコンサルティング企業。コンサルティング、新規事業開発、事業投資、運営などを手がける。