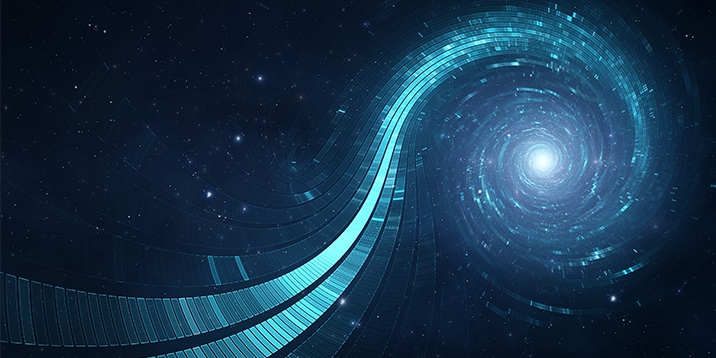連載02
ブラックホール研究の先にある、超光速航法とタイムマシンの夢
Series Report
その後、20世紀になり、同様の天体のアイディアがふたたび提唱されることになる。そのきっかけとなったのは、かの有名な物理学者のアルベルト・アインシュタイン(1879~1955)だった。
アインシュタインが「一般相対性理論」を発表した直後の1915年、ドイツの天文学者カール・シュヴァルツシルト(1873~1916)は、一般相対性理論の基礎となるアインシュタイン方程式を研究したところ、ある空間にきわめて高い質量の天体が存在する場合、その空間自体が重力で歪み、「シュヴァルツシルト半径」と呼ばれる特殊な球形の領域が発生。そして、それに近い場所ではその重力で光が吸い寄せられ、さらに領域の内側では光が抜け出せなくなることを示す結果が得られた。これを「シュヴァルツシルト解」と呼び、ブラックホールの存在を示唆する、最初の理論的な研究となった。
この研究が発表された当時もまだ、そのような天体は数式の上にだけ存在する、いわば”机上の空論”であり、実際には存在しないのではないか、という見方が根強かった。
ところがその後、星がどのように生まれ、進化し、そして終焉を迎えるのかといった研究が進んだことを背景に、もしかしたらそのような天体が存在するのかもしれないという可能性が芽生え、徐々に天文学者に受け入れられていった。
たとえば1930年、インド出身の天文学者スブラマニアン・チャンドラセカール(1910~1995)は、白色矮星*1(図2)の質量には上限があることを導き出し、ある一定の質量(チャンドラセカール質量)よりも大きな恒星は白色矮星として存在することができず、そのうちとくに大質量の恒星は、自らの重力で押しつぶされ、ブラックホールになりうると発表した。
 |
また1939年には、米国の物理学者ロバート・オッペンハイマー(1904~1967)などが、質量がきわめて大きな恒星は、白色矮星はもちろん、当時提唱されていた「中性子星*2」にもならず、ある上限を超えると、自らの重力で収縮(重力崩壊)する状態が続き、ブラックホールになると発表した。
ちなみに、こうした重力崩壊し続ける天体がブラックホールと呼ばれるようになったのは1967年ごろのことで、アインシュタインの友人であり、中性子星や重力崩壊の研究で名を馳せた米国の物理学者ジョン・ホイーラー(1911~2008)が、便宜的にそう呼び出したのが最初だといわれている。
ブラックホールという天体がどうやらありそうだということはわかった。しかし、ブラックホールは非常に大量の物質が、極限まで狭い領域に押し込められた天体、すなわち、きわめて小さいことから、望遠鏡などで直接見ることは難しかった。ブラックホールがあるとしたらどのような天体なのか、どのようなメカニズムで生まれて存在しているのか、その周囲や内部はどうなっているかなどを、物理学や数学の数式のうえでこねくり回す、理論的な研究の対象でしかなかったのである。
[ 脚注 ]
- *1
- 白色矮星:恒星が終焉を迎える際に取る形態のひとつ。質量が太陽の3倍以内の恒星がなりうる。太陽も約50億年後には白色矮星になると予測されている。
- *2
- 中性子星:質量の大きな恒星が終焉を迎える際に取る形態のひとつ。中性子星として存在できる質量には、「トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界」と呼ばれる上限値があり、それを超えるとブラックホールになるとされる。