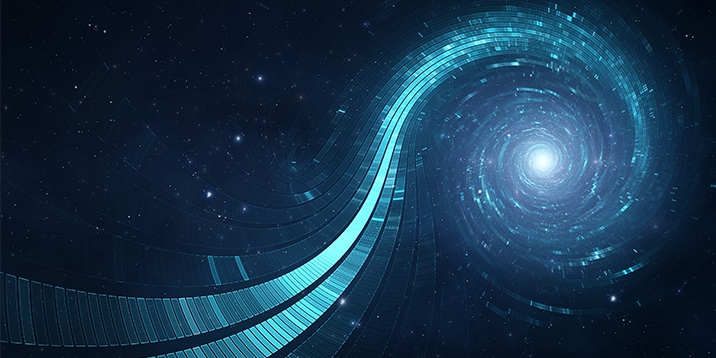連載02
ブラックホール研究の先にある、超光速航法とタイムマシンの夢
Series Report
ちなみに余談だが、光速と同じ約30万kmで進めると考えられているものに「重力波」がある。そもそもアインシュタインは、光のみが光速を出せると言ったわけではなく、自然界最速かつ最も身近にあるのが光だったことから、光を例にとって相対性理論を組み上げたにすぎない。アインシュタインは質量がゼロのものであれば自然界の最高速度、すなわち光速で進めるとしている。
重力波はアインシュタインが発表した一般相対性理論のなかで提唱されたもので、「時空のさざなみ」とも呼ばれ、質量をもった物質やエネルギーが存在すると、そのまわりの時空が歪み、そしてこの物質が加速度運動をすると、時空の歪みが光の速度で伝わる波として伝播していくとされた。長年多くの科学者がその検出に挑み、2015年9月14日、米国にある重力波望遠鏡「LIGO」が重力波を検出することに成功している。
この重力波の素粒子、すなわち重力を伝達する素粒子として、「重力子」という存在が提唱されている。この重力子も光の素粒子(光子)と同じく質量はゼロと考えられており、そのため重力波は光速で伝播するとされている。ただ、現時点でまだ重力子の発見や、その質量の特定には至っていない。
 |
ワームホールを使って光速は超えられるか?
では、本当に光速を超えることはできないのだろうか?
その鍵のひとつを握るのが、本連載の第1回でも触れた「ワームホール」である。ワームホールとは、ある時空にある一点と、別のある一点とを結んだトンネルのような構造のことで、あるいは別の場所にある2つのブラックホール同士、またブラックホールとホワイトホールを結んだトンネルとも説明される。
その理論の発端となったのは、アインシュタインと物理学者ネイサン・ローゼン(1909~1995)が1936年に共同で発表した論文で、このときは「アインシュタイン-ローゼン橋」と呼ばれた。
その後、この論文に触発された物理学者のジョン・ホイーラー(1911~2008)と、同じく物理学者のチャールズ・マイスナー氏(1932 ~)とが1957年に発表した共同論文の中で、その概念を確立させた。ちなみに、この概念にワームホールという名前がつけられたのもこのときだった。ホイーラーは時空をリンゴに見立て、虫(ワーム)がリンゴの表面のある一点から裏側に行こうとした際、表面を延々と移動するのではなく、穴(ホール)を掘って内部を進んで行けば短い距離でたどり着ける、という例え話からきている。
 |
第1回でも触れたように、ワームホールはまだその存在が確認されたことはないが、多くの物理学者によってさまざまな角度から研究が行われてきた。
なかでも有名なのは、2017年にノーベル物理学賞を受賞したことでも知られる米国の物理学者キップ・ソーン氏(1940~)で、天文学者のカール・セーガン(1934~1996)の小説・映画『コンタクト』においては、こと座のヴェガにある惑星にまで行けるワームホールの理論的な裏付けを考案。さらに、製作にも参加した映画『インターステラー』では、土星の近くに発生したワームホールを使い、人類が移住可能な惑星を探しに別の銀河に行くというストーリーが描かれた。いずれの場合も、光の速さよりも速く遠くの場所に行くための手段としてワームホールが使われた。
ただ、これらはあくまで映画の話であり、いまのところ実現は不可能である。たしかにワームホールを通ると、別の場所に瞬時に移動できる可能性はあるものの、あくまで通ることができればの話であり、実際には、ワームホールの中は潮汐力が非常に大きく、その中を通過する物体はばらばらに引き裂かれ、 素粒子レベルにまで粉砕されてしまうと考えられている。
また、ワームホールは安定的に存在できないとも言われており、宇宙船など物質が通れるようなワームホールの構造を維持するには膨大なエネルギーが必要であるとか、あるいは「エキゾチック物質」と呼ばれるもののひとつである、“負の質量”をもった物質が必要であるといった説が出されている。そして、前者は宇宙を創り出すのと同じくらいのエネルギー量が必要であったり、後者はそもそもそのような物質が見つかっていないなどといった理由で、ワームホールを近道のトンネルとして利用することは不可能であるというのが、現在の科学の定説となっている。
 |